![]()
2015年 12月 31日
気が付くとハロプロのことしか書いていない1年だったわけですが
12月30日 「第57回日本レコード大賞」 こぶしファクトリーが最優秀新人賞を受賞

こぶしファクトリー 日本レコード大賞最優秀新人賞 良かったですね!
このグループの特徴は、ハロプロとナイスガールトレイニーという研修生の叩き上げの集団というところです。
デビューまでに3年以上費やしているようなメンバーが多い。
しかもデビュー出来るかどうかが全く保証のない状況下で不安と背中合わせでやってきた子たちです
(アップフロントの研修生って、エリートといえばエリートですが、本当に何も約束されたものはなく、自ら去り際を考えて去っていく子も多いのです)。
自分もたまたまですが、Berryzのツアーに帯同している様子とか見ていたので、最優秀の受賞には感動しました。
パフォーマンスを見た人も受賞文句なし!と感じたと思います。
楽曲『うまれてきてくれてありがとう』(歌唱:クミコ)で作曲賞を受賞したつんく♂の前でパフォーマンス出来たというのもこぶしファクトリーにはひと際のうれしさだったんじゃないでしょうか。
 ハロプロ研修生 「1
Let's say “Hello!”」 (2015)
ハロプロ研修生 「1
Let's say “Hello!”」 (2015)
2012年から2014年の研修生の集大成的アルバム。全曲つんく♂作曲の狂った傑作ぞろいという優れものアルバム
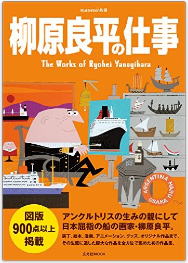 『柳原良平の仕事』 (玄光社MOOK)
『柳原良平の仕事』 (玄光社MOOK)
“図版900点以上掲載”という、柳原良平ファンにはたまらない本が出ていました。
山口 瞳の本の表紙カバーがずらっと載ってますし、筒井康隆の『あるいは酒でいっぱいの海』なども。
中には自身の漫画作品もあります(マンガも描いていたのですね)。
レコード・ジャケットの仕事は少なかったのか、数点(アイ・ジョージ、いずみたくとマリーン・オーケストラなど)しかなかったのは、ちょっと残念でしたが、アイ・ジョージの「トリスでドドンパ」はもし見つけたら購入したいと思いました。
まだ読んでない本
 デイヴィッド・グラブス 『レコードは風景をだいなしにする
ジョン・ケージと録音物たち』 (フィルムアート社)
デイヴィッド・グラブス 『レコードは風景をだいなしにする
ジョン・ケージと録音物たち』 (フィルムアート社)
ヘンリー・フリントの名まで登場するとあっては、読まねばなりますまい。デヴィッド・グラブスのCDは最近のは購入していないのですが、本は買いました。
 スージー鈴木 『1979年の歌謡曲』 (彩流社)
スージー鈴木 『1979年の歌謡曲』 (彩流社)
私は個人的には1978年の歌謡曲に非常に思い入れがあるのですが、たぶん松田聖子の1980年でいったんリセットが掛かるまでの1977〜1979年は調べるとけっこう現在につながるものが出てくるんじゃないかと思います。楽しみ。
 倉田 徹 、張
彧暋(チョウ イクマン) 『香港 中国と向き合う自由都市』 (岩波新書)
倉田 徹 、張
彧暋(チョウ イクマン) 『香港 中国と向き合う自由都市』 (岩波新書)
今の日本はアメリカ、中国、欧州(フランス、ドイツなど)を意識して揺れていますが、例えばカナダのすること(結局はアメリカの傘の下ということで評価に繋がっていないきらいはありますが)、そして香港の“気概”について、日本は参考にするところがあるんじゃないかという気がします。
 宇野誠一郎 (著)、濱田高志 (編集) 『宇野誠一郎の世界(月刊てりとりぃ)』
(888ブックス)
宇野誠一郎 (著)、濱田高志 (編集) 『宇野誠一郎の世界(月刊てりとりぃ)』
(888ブックス)
この本はかなり値がはりましたが、宇野誠一郎ならば仕方あるまいと思い切りました。もう少しメジャーなところへ出てきてもおかしくない作曲家だと思いますが。(2011年没)
![]()
2015年 12月 27日
あらためて言うが℃-uteは日本一だ
℃-uteのNew アルバム「℃maj9」は、やっぱり買って良かったです。つんく♂作曲の曲が無くなったことについて、℃-uteにはあまり影響が無いんじゃないかと私は考えていたのですが、それはちょっとハロプロの中でも比較的異色なタイプのグループで、あまりつんくイズムにこだわらないイメージでやっていたからと思ったからだったのですが、私が間違っていました。
確かにアルバムの前半に並ぶ、非つんく曲は、ある意味オーソドックスなJ-POP調(湘南の風節や安室系、邦Rock風など)で、曲だけ取り上げたなら自分にはあまり響かないメロディでも、℃-uteが歌えば伝統のハロプロの粘り声が曲を自分たちの方向へ引き寄せるのを感じ取ることが出来、それもけっこう乙なものという気持ちにはなったのですが、8曲目の「都会の一人り暮らし」からつんく♂作曲シングルの怒涛の連打が始まると、「いやいや、℃-uteってめっちゃつんくやん」と、どれだけ℃-uteがつんく楽曲を体現していたかを思い知って、思わず泣きました。
「心の叫びを歌にしてみた」なんて、絶対℃-uteでなければあの味は出せないと思う。つんくの“粘り”の部分ってモーニング娘。にも少しありますが、Berryzには殆ど無いものだし、一番つんくらしい粘りを表現出来ているのは実は℃-uteなんですよね。そういうのが「心の叫び-」みたいな爽やかな感じの曲の時にむしろ強調されて出てきているように感じます。これはもう℃-uteでなければ聴けないものだから。
あとやはりまとめて聴くとよくわかるのですが、このグループって、変な声の人が多い! なっきぃ(中島早貴)とまいまい(萩原 舞)の存在意義ってすごいなと思う。それに唯一無二の岡井ちゃんの声に、これに部分的には似ている声でもある愛理と舞美が両者補い合いながらある意味ツイン・ヴォーカルのように℃-uteのアイデンティティを形成している、残るべくして残った5人ということなのかもしれないと、つんく♂楽曲を表現するのに最高の個性が集まったんだなと、“℃-uteはつんくでなくともいい”などと言った自分を後悔いたしました。
℃-uteにつんく♂が必要だ、というより、つんく♂には℃-uteが必要なのです。
それにしても、アルバムとして聴くとはっきりとわかる。なっきぃとまいまいが居るから℃-uteは日本一の歌謡曲なんだなと。
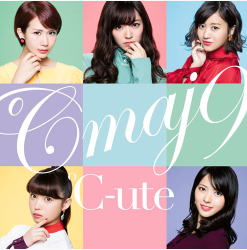 ℃-ute 「℃maj9」(シーメジャー・ナインス) (2015)
℃-ute 「℃maj9」(シーメジャー・ナインス) (2015)
「The Girls Live」でアルバムの新曲「アイアン・ハート」のスタジオ・ライヴがありましたが、今、これだけの突き抜けた歌謡パフォーマンスを出来る歌手が他にいるのか?といいたくなるぐらいに℃-uteはトップ・ギアに入った状態だと思います。
実は2015年のハロプロで一番良かったのは℃-uteだったと私は思うんですよね。

「The Girls Live」より ℃-ute 「アイアンハート」 (YouTubeで探してみてください)
というわけで、今週のワン・ショットは℃-uteから

12月23日 『天皇杯』全日本レスリング選手大会を観戦した℃-uteさん
(隣りはアップフロント会長? という話です) 矢島舞美さんは何故世間に見つからないのか?
矢島さんがまだ世間一般に見つからずにいることを、ハロヲタは内心喜んでいる節が見られます。
![]()
2015年 12月 25日
日本Rockの分岐点について思う 2015年の10枚 その②
カントリー・ガールズ 「ためらいサマータイム」 (2015)
12月20日 いつも応援してくれているファンのみなさんへ。田村芽実ですっ。
http://ameblo.jp/angerme-amerika/entry-12108597517.html

めいめい、来春卒業か。 それにしてもハロプロDDやってると気の休まる日が無いんだな。
”もう少し、アンジュルムに居れないのか、、と。” http://ameblo.jp/angerme-ayakawada/ 「あや著」和田彩花オフィシャルブログ
(あやちょって本当に面白いな)
『ミュージックマガジン』誌1月号の「ベスト・アルバム2015」、歌謡曲/Jポップ部門の順位が
1位.水曜日のカンパネラ「ジパング」
2位.negicco「Rice&Snow」
3位.一十三十一「THE MEMORY HOTEL」
4位.清 竜人25「PROPOSE」 と、
何かイヤ〜な並びだなと思いました。
5位にJuice=Juiceの「First Squeez!」が入っていて、どうもすっきり喜べないという..
図らずもこの並びで5位に選ばれてしまったことで、このアルバムの性格がミュージック・マガジン誌に見破られてしまったみたいな、複雑な気分になりました。
8位に入っているTweedees(元シンバルズの沖井礼二が組んでるユニット)も聴いたことがあるのですが、悪くはないとはいうものの、こういうことでいいのか? とは思う。精度的に上がっていくというのはわかるのですけども、この先にある音楽の楽しさって何なのか?という疑問があります。
 『ミュージック・マガジン 2016年1月号』 (ミュージック・マガジン社)
『ミュージック・マガジン 2016年1月号』 (ミュージック・マガジン社)
今年はとにかくカントリー・ガールズがすごかった、という印象です。
オールディーズや昭和アイドル・ポップスを基調にしていると、一言で片づけられるような単純な構造ではないと思っています。
「The Girls Live」スタジオ Liveより

カントリー・ガールズ 「ためらいサマータイム」(2015) (YouTubeで探してみてください)
例えば、例に出して申し訳ないですが、というかポップス通にはむしろこちらが評価の高い位置にいるのではないかと思われる星野みちると小西康陽や高浪慶太郎のコラボ作品と比べてみたとします。


↑Click 星野みちる 「夏なんだし」(2015) ↑Click 星野みちる「坂道の途中」(2015)
散りばめてあるものがいろいろな符号を持っているのが、こうした過去のPOPSをベースに持っている楽曲の特徴ですが、シンプルなアイデアである程度最小限の要素で仕上げながら、構造が斬新でなおかつ新しい実験が行われているのはカントリー・ガールズの楽曲の方だと思います。
オリジナルをオリジナルなままの符号として提示するのは、オリジナルをリスペクトする姿勢として正統であるし、フェアだし、教養とはその正確さだとも言えると思いますが、その正確さが不満というか、”不確定部分の要素を持ち込む隙間”の無さが息苦しくもあります。
そしてその教養とは何なのか?ということも気になるのです。「坂道の途中」ではフィル・スペクターのサウンドを大滝詠一を介して提示するというディテイルの正確さにはっぴいえんど(細野)の要素を取り込むなどのパズル的な構築アイデアを入れながら、モータウンへとなだれ込むという、ある意味ジャパニーズ・ポップスの流れを意志を持って(つまりこの構造に意味があるという主張を持って)継承していることを明確に打ち出しています。小西康陽がプロデュースした「夏なんだし」も構造の正確さにおいては「坂道の途中」と同じで、こちらはピチカート・サウンドともいうべきオリジナルな部分を自ら正確に継承するというフェアな姿勢を崩さず(例えば若手がピチカートを引用するならば求められるべきフェアなルールを、本人にも自ら課している)、“不正解のない”音楽に仕上がっています。

↑ Click カントリー・ガールズ 「愛おしくってごめんね」 (2015)
それに対して、カントリー・ガールズの音楽は、同じく“不正解”の少ない、教養というバックボーンもしっかりしているアレンジではありながら、その構築の仕方が野性味があるというぐらい荒々しい。それは露骨な部分や一歩引いて抑えているところなどがごつごつとした肌合いで配列されているからです。制作者がコントロールできない不確定要素を生み出し取り込む実験性がここにあらわれていて、私は、この部分に非常にスラップ・ハッピーやXTCらに通じる暴力的なPOPSの雑食性が、基本的な構築の上に乗っかるところに、曲作りの目的を持っているように感じて、カントリー・ガールズとスラップ・ハッピーには共通項があると思ったのです。
POPSの本質は間違いなく此処にある、と私は考えます。

↑ Click カントリー・ガールズ 「浮気なハニーパイ」
(2006年 カントリー娘。に紺野と藤本 で発表したシングルのカバー)
そもそも原曲が屈指の名曲ですが、アレンジは現在のカントリー・ガールズ用にアップデイトされており、
斬新なアレンジというか、ただのカバーにはもったいないぐらいにカッコイイ。
カントリー・ガールズは思いのほかメンバーの声の個性が有機的に機能しているように感じます。
特に森戸知沙希さんの一聴無臭なモノトーンを感じる声が非常に効いていると思います。

↑ Click カントリー・ガールズ 「わかっているのにごめんね」
2015年幕開けにおいて、カントリー・ガールズはBerryz工房の活動を残す嗣永桃子を除く、残りの5人でスタートし、ハロプロ・ファンの間にセンセーションを巻き起こします。
研修生経験もない新人メンバーの島村嬉唄(うた)の初々しいパフォーマンスに注目が集まったわけですが、その後超ベテランのももちが合流して6人となっても最初の衝撃の感触が失われない(違和感なく溶け込んでしまった)という、けっこう驚きの結果、そのまま勢いがついて期間を置かずにメジャー・デビューを果たし、展開の速さが影響があったかわかりませんが、人気の中心にいた島村嬉唄が半年たたずに脱退してしまいます(家族の意向? このあたりの理由は不明)。
メンバーが5人になりますが、個人活動も多いももち(プレイング・マネージャー)抜きで4人でパフォーマンスする機会も多く、このグループは人数が安定しない状況が偶然にも発生しながら、実際には4人でもその構成なりの面白さが発揮できており、ユニークなユニット構成が出来上がりつつある、と思いましたら、少し前に新たに2人メンバーの追加が発表され、果たして7人の時には、またももち抜きの6人の時にはどうなるのか?という、通常あまりない事態に対する興味が生まれています。

カントリー・ガールズ 「渡良瀬橋」 (YouTubeで探してみてください)
(1993年 事務所の先輩 森高千里が発表したシングルのカバー)
 カントリー・ガールズ 「ためらいサマータイム」イベントV (2015)
カントリー・ガールズ 「ためらいサマータイム」イベントV (2015)
(ジャケットもいいですね。このイベントVは私は入手していませんが)
![]()
2015年 12月 20日
日本Rockの分岐点について思う 2015年の10枚 その①
トワ・エ・モワ 「雨が降る日」 (1972)
12月8日のモーニング娘。‘15 武道館の映像(「ハロ!ステ#148」)での新曲「ENDRESS SKY」はヤバ過ぎてボロ泣きしました。
鞘師の歌声が自分は本当に好きだったので、クライマックスの一拍置いたところから鞘師のソロが入るところはたまらない思いで聴きました。
私は少々キツイ声域と思っても声を出していく歌手が好きで、鞘師のちょっと不器用なんだけど、そこだけは曲げない歌い切るのがずっと好きだったんです。
なかなか上手く声が出ない頃が一時期彼女はあって、苦しいことも多かったと思います。
でもとうとう最後まで誤魔化さずに自分を通して押し切った。 良い歌手だった!
まだまだ彼女の成長期は、本当はこれから来るんだと思っています。私は歌手として戻ってきてほしい。
鞘師がこういう形で去る(正式な卒業公演が無い)のって、いろいろな意味でハロプロの歴史(違ったドラマが生まれる)を感じるとともに、鞘師里保への愛おしさが募って止みません。

↑ Click 「ハロ!ステ #148」 (曲は18:10 くらいから)
さて、私は1979年頃から洋楽を聴くようになった(中3)、比較的洋楽に入るのが遅かった人間(勿論、中3になるまで全く聴いたことがなかった、っていうことではないですよ)ですが、それから様々な海外の音楽も聴いて、過去へもさかのぼっていくという音楽鑑賞の遍歴をたどりながらも、思うのは、結局“リアルタイムの感覚”というのは後追いではなかなかつかめない、ということです。
過去へさかのぼるというのも、実際にはその時の現在進行形の時間の上に乗っている。現在を全く無視して過去へさかのぼるのは案外簡単ではないと感じているのです。
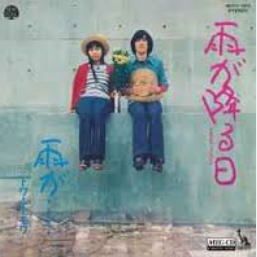
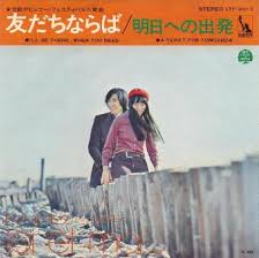

トワ・エ・モワ 「雨が降る日」(1972)、トワ・エ・モワ 「友だちならば」(1972)、モコ・ビーバー・オリーブ 「海の底でうたう唄」(1969)
今になって、そうした“さかのぼらなかった”過去の空白を埋めようとするような行為を自分が始めようとしているのを、今年1年を振り返っても感じるのですが、実はこれも現在進行形の流れの中でさかのぼっているのだ....たぶんそうなのではないかと思います。
その例の一つとしてあげたいのが、メリー・ホプキンです。前にも書きましたが、メリー・ホプキンは70年代の前半に活躍した歌手で、日本でも洋楽ファンの間では人気があったことは歴史として認識しているのですが、79年から洋楽を意識して聴くようになった中学生からすると、さかのぼって掘り起こす対象になかなかあがらなかった。30年以上も振り返ることなく過去に葬ってきたままの存在でした。
実は今でも彼女のアルバム1枚すらまともに聴いていません。

ジ・オフ・コース 「夜明けを告げに」1971)、オフ・コース 「おさらば」(1972)
ここからちょっと長くなりそうですが、ここ数年、昔のシングル盤を中古で買うようになったのですが、その中で、トワ・エ・モアのシングル盤「雨が降る日」というのを、ジャケット写真に惹かれて購入したのです。すると、何かロゴが印刷されている。“NEW
FOLK”と書かれたロゴです。70年前後、日本でもアメリカからの影響でフォークが流行り、カレッジ・フォークやニュー・フォークなる動きはあったことは認識していました。当然、トワ・エ・モワがその代表的な存在の一つだったのも知っています。しかし、ジャケットにロゴを付けるほど、ムーブメントとして“何かPOPな展開をしている”という想像はありませんでした。正直このロゴ・デザインは意外だったのです。
調べてみたら、オフ・コースのシングル盤にもありました。赤い鳥にも。
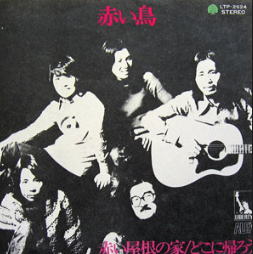
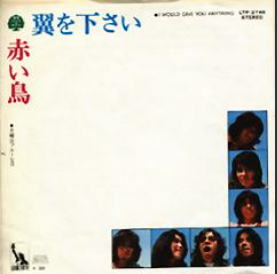
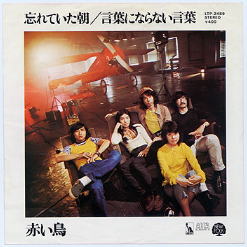
赤い鳥 「赤い屋根の家」(1972)、赤い鳥 「翼を下さい(英語)」(1972)、赤い鳥 「忘れていた朝」(1971)
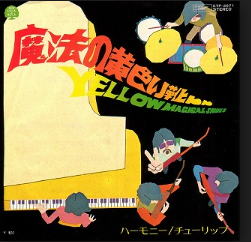
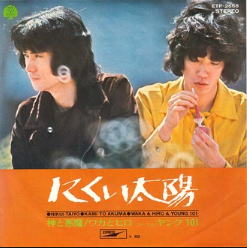

チューリップ 「魔法の黄色い靴」(1972)、ワカとヒロ(後の芹沢廣明) 「にくい太陽」(1972)、ロック・キャンディーズ(谷村新司在籍)
「春は静かに通りすぎてゆく」(1971)
さらに調べていたら“NEW
FOLK”の他に“COLLEGE POPS”というロゴのあるシングルにも出くわしたのです。「まあ、あるわな」という気もしますが、結局カレッジ・フォークとして有名なフォー・セインツの「小さな日記」やリガニーズのジャケットに当然のようにそのロゴはあったのですが、そこで広川あけみという人に出会い、「悲しき天使」のシングル盤を出していたことを知りました。
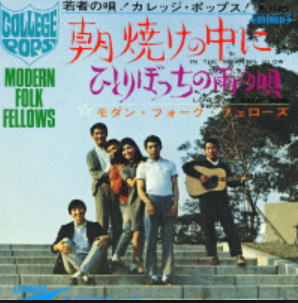
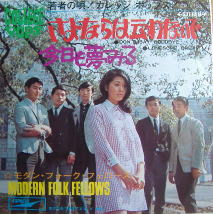
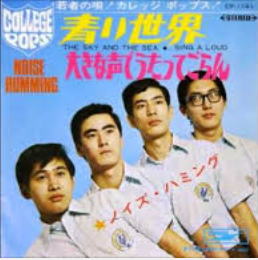
モダン・フォーク・フェローズ (景山民夫が一時在籍)「朝焼けの中に」(1968)「さよならは云わないで」(1969)、ノイズ・ハミング 「青い世界」(1968)


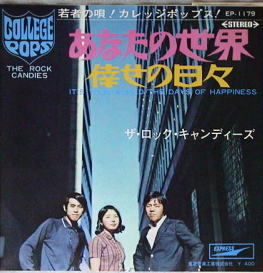
キャッスル&ゲイツ(町田義人在籍) 「おはなし」(1969)、広川あけみ 「5×7=35)(1968)、ロック・キャンディーズ 「あなたの世界」(1968)
そこで、“自分だけかもしれない”発見なのですが、「悲しき天使」がメアリー・ホプキンのヒット曲カバーだということに気付くまではまあ当たり前のこととして、実は、私は「悲しき天使」が有名な“あの曲”だったということを知らなかったのです!
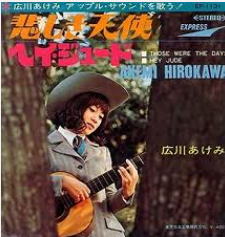
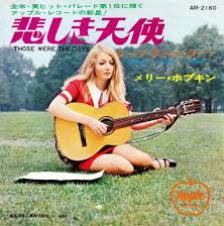
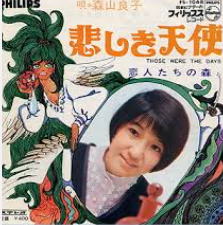
広川あけみ 「悲しき天使」(1969)、メリー・ホプキン 「悲しき天使」(1968)、森山良子 「悲しき天使」(1969)
いや、むしろ洋楽聴いてる人はけっこう知ってることだろ!とは思いました。自分だけが無知だったのです。
「悲しき天使」ってあのロシヤ民謡みたいなあの曲です。曲は当然知っています。しかも曲の方はかなり馴染みある。
昔、ウェディング・プレゼント(イギリスのバンド)から派生したウクレイニアンズがこの曲をカバーしていた時も、「ああ。あの曲だ」とか思っていたのです。
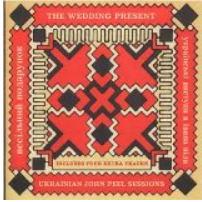
Wedding Present 「Ukrainian John Peel Sessions」(1989) ↑ Click Ukrainians 「A History of Rock Music」(2015)
(実はウクレイニアンズは現在も活動中。新作も発表し、モーター・ヘッドやスミスのカバー曲も入っています。決して有名曲を単純にパンキッシュにやるだけ、みたいなものといっしょにするべからず。もっと正統的なRockバンドです)
自分にとってショックだったのは、その時に、ウクレイニアンズがメリー・ホプキンをカバーしていたのだ!ということを認識できていなかった事。今から思えば、これは大きなことだったのです。
広川あけみからウクレイニアンズまで、ポンと飛んでしまいましたが、これがどのように大きな事なのかというと、日本では、ニュー・フォークとかカレッジ・ポップスというのは、まさにメリー・ホプキンが顧みられなくなるのと同じように忘れ去られて来た存在で、トワ・エ・モワとか、オフ・コース、赤い鳥、リガニーズ、ロック・キャンディーズなんてのはRockの文脈で語られることなど一切無かったグループです。日本のRockの歴史には無かったものとして扱われています。
ですが、メリー・ホプキンの「悲しき天使」は当時、世界を席巻し、世界中のポップスの歴史の血肉になっているのは間違いない。それをRockの側から歴史認識としてとらえていた、というのは“イギリスではやっていた”ということがウクレイニアンズのカバーからわかる、ということになるのです。
日本は何かを簡単に切り捨て過ぎている。特に日本のRockは切り捨ててしまったものが今になって深刻な症状をあらわしている。
そんな気がしている中で、トワ・エ・モワのシングル盤のロゴから、「悲しき天使」とウクレイニアンズの関係にたどり着いたのは、自分にとっては発見だったと思っています。
ワン・ショットはこちら。 ひとつ前の「ハロ!ステ #147」の回で、カントリー・ガールズ
PM(プレイング・マネージャー)嗣永桃子さんと、新加入メンバーの梁川(やながわ)奈々美さん、船木 結(むすぶ)さんのMCで、めんどくさい先輩につきあいきれず、笑ってしのいでる新人二人の様子です。困り果ててふなっきさんが謎のふなっきポーズを連発して面白い回になりました。

12月9日 「ハロ!ステ #147」 ふなっきポーズ
![]()
2015年 12月 13日
小林信彦氏のいうマニアック

トワ・エ・モワってちょいちょい気になるジャケットのレコードがあります。
70年前後の感覚で、ソフト・ロックやサイケ(最近でいうアシッドな感覚)、カレッジ・フォークが混ざり合ってる状態が割とナチュラルに出ている雰囲気。私の大好きなウィ・ファイヴの「ユー・ワー・オン・マイ・マインド」(1965)に近いものを感じるのです。
トワ・エ・モアには「初恋の人に似ている」(1970)という曲を加藤和彦が書いたりしているのですけど、以前、加藤和彦のことを「フォークの人でしょ」と誰だったかが書いてる記事を読んで、その言い方は馬鹿にしてるのかって腹が立って来たりして、事実そういう意味で書かれていたのだと思いますが、最近ではもう、「フォークの人」で全然かまわないという気になってきました。
それで加藤和彦の価値が下がる、なんてことは全くない、ということがわかってしまいましたので。
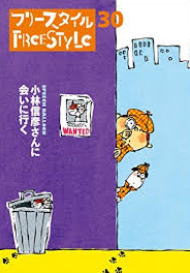 『フリースタイル30 小林信彦さんに会いに行く』 (フリースタイル)
『フリースタイル30 小林信彦さんに会いに行く』 (フリースタイル) 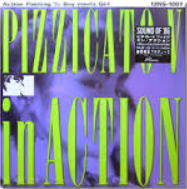
雑誌『フリースタイル』では特集が二つ。亀和田武が小林信彦にインタビューした記事と、小西康陽が和田博巳にインタビューした記事。
小林信彦氏は筒井康隆よりも年上の83歳ですけど、記事の写真を拝見したところでは年齢を感じさせない、変わらないなぁという印象でした。野坂昭如氏から小林氏に「先日、本が送られてきた」という話が出てきて、びくっとしましたが、野坂氏は先日亡くなられた(12月9日 85歳)ばかりで、小林氏も驚かれただろうと思いますが、安倍内閣の話をしていたところに野坂昭如の話が出てきてそこから三木鶏郎の話へ繋がっていくというあたりが面白かったです。
その後で女優の話へと移っていき、若尾文子や香川京子の話から吉永小百合への話へと変わってゆく。二人して吉永小百合のどこがいいのかわからないという話になっていきます。
春日太一氏も『市川崑と「犬神家の一族」』で吉永小百合を監督クラッシャーと書いてかなり辛辣な評価でしたが、どうもこういうのが私はよくわからない。単純に良い悪いで判別できるものなのかなと感じています。
むしろ吉永小百合をどう評価するのかというところを書いてくる人の方に期待感があります。
小林信彦の面白いところは、前田敦子を評価する時に「もらとりあむタマ子」で、こたつに入って寝ながら「日本は駄目だな」って言ったところが良かった、というそういうところ。小島瑠璃子はそんなに買ってないとか。やはりマニアック(蓮實重彦氏のことはマニアックと評価している)の度合いがこのレベルぐらいにはいかないと、と思います。こういう人がなかなかいない。
小西×和田の対談では、やはりどうしても「佐々木麻美子ちゃんが抜けることになって・・・・」のあたりが非常に気になりました。その前の「アクション・ペインティング」録音時の話がけっこうスリリングでもあったので、和田氏が「フィル・スペクターがストーンズを予算無限大で作ったらどういうサウンドになるんだろうみたいなイメージ」を志向していたと、自分の見解を示した時に小西氏は「いや、僕の話はいいんですよ」とお茶を濁しましたが、ピチカートが当時、「姿勢はむしろパンク」と自分たちを形容していたのは、こういうことではなかったのか?とも思ったのです。個人的にはピチカート・ファイヴの分岐点となる部分(それが佐々木麻美子の脱退と戸川京子でなく野宮真樹だったという部分なのですが)が、非常に大きな意味があるという風に思っています。
12月9日
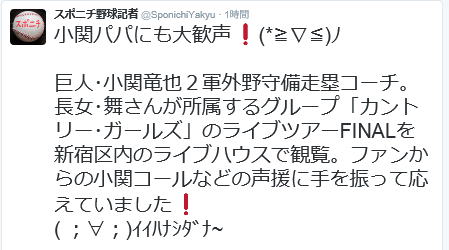
https://twitter.com/sponichiyakyu
では、最近のワン・ショットには、これ。 カントリー・ガールズ。

http://ameblo.jp/countrygirls/entry-12104872378.html?frm_src=thumb_module
Liveで披露された未発表曲2発目の「妄想リハーサル」も洋楽ポップスをアレンジしたというより最早、初期のBerryz工房をアップデートした、と形容したくなるような画期的な楽曲で、しかも、ももちパートはももち的に進化して次のステージに進んでいる「妄想だけが膨らむばかりです」の歌唱が超―カッコイイ。
カントリー・ガールズはアルバム出したらたぶん名盤間違いなしだと思う。(「愛おしくってごめんね」を外すといういわくつきになるだろうことも含めて)
12月11日
 お姉さんズ
お姉さんズ
http://ameblo.jp/shimizu--saki/entry-12104584326.html?frm_src=thumb_module
ヤーバイね。これ見てニヤニヤしちゃってる自分が。
![]()
2015年 12月 8日
Berryz工房と書いてバカと読む
「わが最高傑作にして、おそらくは最後の長編」
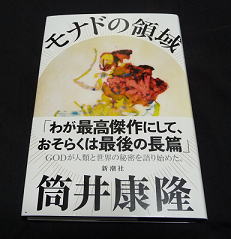 筒井康隆 『モナドの領域』 (新潮社)
筒井康隆 『モナドの領域』 (新潮社)
私はやっぱり大作家には、未完長編にて絶筆、をめざしてほしい。
12月7日
モーニング娘。'15 コンサートツアー秋 ~PRISM~ ツアーファイナル 武道館2DAYS 初日
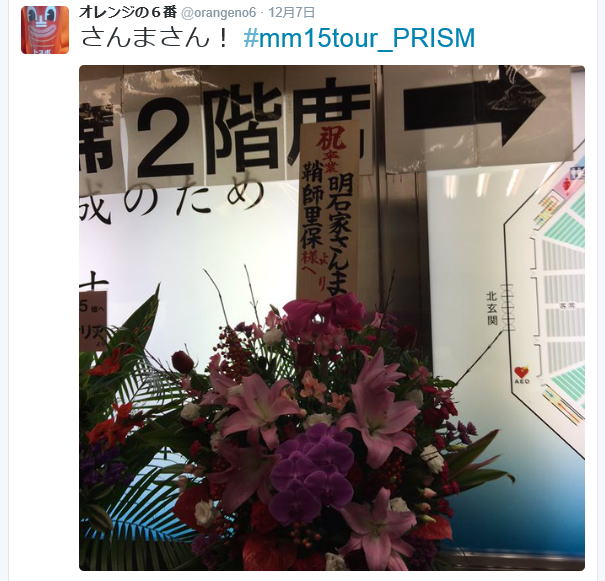

さんま師匠、ほんっとにやさしい。 やっぱり鞘師が心配なんでしょうね。
大阪から戻っての駆けつけで、どれぐらい見ることが出来たかわかりませんが、
でもきっと、娘。のLIVEを見て、安心できたんじゃないでしょうか。
12月6日 さて、こちらはベリヲタ歓喜
https://twitter.com/maasa_0703
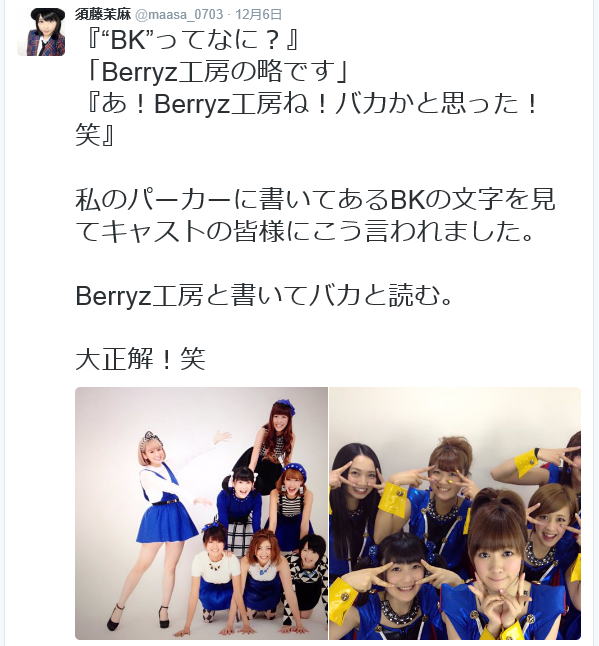
スピリット 健在! 
あさっては 徳永千奈美さん出演最後となる「GREEN ROOM」配信です。
まさか、あの人がゲストで出演?![]() なんてことがあるのか。
なんてことがあるのか。
まあ、ないでしょうが、ちょっとだけ期待しています。
![]()

![]()
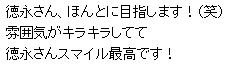
http://ameblo.jp/kobushi-factory/entry-12099192962.html
![]()
2015年 12月 6日
ANGERMEのアルバム ヤバイ サイコー ヴォーカル・アルバム!
12月4日 櫻井孝昌さん死亡、西日暮里駅から転落-京浜東北線の人身事故
http://daily-news.jp/2015/12/04/takamasa-sakurai-death-fell-from-nishinippori-station/
TwitterやNETのコラム記事などは時々読んでいて、名前は知っていたのですが、こんなにもすごい仕事していた人だったのかと驚いています。
ハロプロでも、あのイベント、あの企画に携わっていたのか! と、次々出てきて、どえらい人を失ってしまったんだなと...
ご冥福をお祈りいたします。
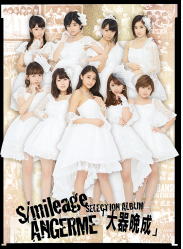


S/mileage
/ ANGERME SELECTION ALBUM「大器晩成」 (初回限定A、B。通常盤 2015)
今週はPhewの新譜もビートニクスのBOXも小島麻由美のカバーアルバムもILL BONE「死者」も買って、聴きもの盛りだくさんの筈なのですが、とても聴いてる時間がありません。
アンジュルムの新譜 Best Album「大器晩成」を聴き始めたら完全に止まらなくなりました。
正直ここまでとんでもないヴォーカル・グループになっているとは、相当期待値を上げていた状態で臨んだのですが、それでも想像を越されてしまいました。福田花音も居る9人でのANGERME集大成、このヴォーカルの完成度の高さは驚異です。
アルバムは3タイプありまして、それぞれに2曲づつ新曲がボーナスとして入ってます。悪どい商売と毒づくことも、まま、意見としては真っ当とは思いますが、「もう、しょうがない」。要は、聴かずに済ませられますか? ということです。
聴かないと、確実に損をします。
今まで、ANGERMEの9人になって、声のバランスが非常に良くなったと感じてきていましたが、この1年、シングル曲をその都度聴いてきて、そして今回、アルバムとしてまとめて聴くことによって、あらためて福田花音の技量に他のメンバーが追いついてきてるということを実感しましたし、いや、メンバーが福田花音のレベルに追いつくってすごいことなんですけど、そもそもが一人一人が全く異なるキャラクターを持った声で、そのまとめ方において難しい部分があったのを、克服して制御しながら表現力はぐっと上げてきているクオリティの高さにびっくりしました。そしてやはり、室田瑞希さんのヴォーカルは本当に素晴らしいなと、ソロでも映えるし、あやちょ、タケちゃん、めいめいのような極めて個性的な声とも親和性があり、全部馴染んでる。
無敵な声ではないでしょうか。この声があるのでユニゾンのパワーがとてつもないことになっている。
「友よ」という曲のユニゾンの凄さ! ぶったまげました。
ANGERMEはちょっと化け物的に伸びてきてますね。はぁ〜、むろたんの声をもっと聴きたい!
まろ(福田花音)が居なくなっても、次はさらに楽しみしかないですね。

![]()
2015年 12月 5日
何かが上手くいってない。にも関わらず無類に高揚する
「炎のごとく」(1981年 日)加藤 泰 (録画)
歌舞伎や無残絵の影響が出ているのか、加藤泰といえば、リアリティのない絵の具然とした赤の血糊、溢れ出る血、噴水のごとき血が非常に特徴的で、あれを見ると、芸術映画とは本質的に異なるところに居る映画作家なのだなぁと思ってしまいますが、確かに本作における、出過ぎる血と、口から明らかにずれた位置から噴き出している鉄砲水のどこかに、娯楽のいい加減さ、はったりを肯定する強い思いがあり、芸術志向に対する反骨、反抗があるように思います。
「炎のごとく」はとりわけその執着がすごく、完成度をわざと放棄している気さえするのです。

菅原文太追悼ということで恐らく企画され、今回「炎のごとく」がBSTV放送されました。何しろビデオ化もされず、DVDも出ていない最早幻と化していた本作をついに見ることが出来、感無量です。
まあ、とはいえ、これ以外にも未見の加藤泰作品は、私にはまだまだ幾らでもあるのですが、実際には「ざ・鬼太鼓座」(1981)よりも後にクランク・アップし、映画撮影として最後となったのは「炎のごとく」の方であり、実質遺作と呼べるのはこちらの方かもしれない。
加藤泰が自分を開放したようなやりたい放題ぶりが横溢しているのではないでしょうか?


特に印象に残るシーンが、弟分が殺され、復讐のため命を狙っている男(汐路 章)と仙吉(菅原文太)の対決の場面で、この場面では仙吉が可愛がっていた近所の娘のあぐりちゃん(豊田充里)と恋人の佐々木(国広富之)が新選組の芹沢鴨の懸想から謀略にあい、脱走の罪をかけられ殺されてしまった場所で、怒りに狂った仙吉が、駆け付けた土方歳三に斬りつける非常に緊迫したところで、横から汐路が仙吉を銃で狙っているという構図となり、見せ場ではあるのだけど、正直なところ土方と仙吉の斬り合いの場面だけでシーンとしては成り立っている筈であり、場面をややこしくゴタゴタにしているようにしか思えない。
芸術映画(エンターテイメントをも包括する)ならば、シンプルに整理したいところではないかと思うのだが、たぶん加藤泰はここに汐路章の横槍をいれるところに、自分のやりたい本分があったのではないか?

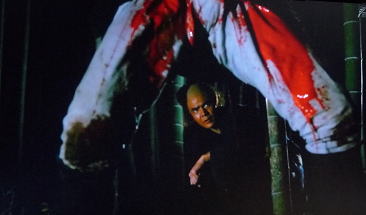
土方対仙吉、名刀小鉄同士の戦いで二人が相打ちすれすれで斬り合っているところに、汐路の銃声が轟き、仙吉を射止め損ね、焦って刀で襲い掛かると、仙吉の全身の怒りが乗った小鉄が一刀し、汐路が異常過ぎる血を腹からごぼごぼ噴出させて、どっと倒れる、何かわけのわからぬ方向へシーンの重心が飛んで行ってしまったような、「下手くそか?」という混乱した演出、しかし、その仙吉の狂った怒りが沈着冷静な小鉄の一閃とともに土方から男(汐路)に軌道を移す。
“激しい感情”の目に映るかと思うほどの衝動を“移動”として魅せるところに加藤泰の真骨頂はあるのではないか。その男(汐路)の下半身がみるみる赤に染まる様は、当然のごとくのローアングル(加藤印)でとらえられる。
汐路章という邪魔な存在、完成度を崩すことこそ、一番やりたいことなのだと。「炎のごとく」を見て、私が一番感じたのはそこでした。

あぐりちゃん役の豊田充里
この映画には4人の女性が出てきます。仙吉の窮地を救った瞽女のおりん(倍賞美津子)、近所の娘あぐり(豊田充里)、実家から勧められている許嫁のお富(きたむらあきこ)、仙吉を襲い返り討ちにあった浪人和多田の娘なか(桜町弘子)。1981年という時点において、倍賞を除けばあまり知名度のない女優陣(桜町弘子は有名ですが、81年では一歩引いた位置での女優だったと思います。少し変わった闘士という桜町さんとしても異色の配役で、任田順好のような怪演を好んだ加藤泰の意外性ある抜擢でした)でしたが、ある意味、この映画は監督が描きたい女性を総出演させたような絢爛な組み合わせとなったと思います。


ほぼ新人のような状況で重要な役を演じているあぐりちゃん役(菅原文太が「あぐりちゃん」と呼ぶときの愛くるしさにまいっちゃってる感じに「トラック野郎」の文太が出ていて面白い)の豊田充里という子は、その後数本TVの時代劇とかに出たぐらいで消えてしまったような情報しか出てこないのですが、非常に清冽な印象を残して、恋人役の国広富之がその後人気俳優になっていくのと同じぐらいのスター性をこの映画で発揮していたと思いました。
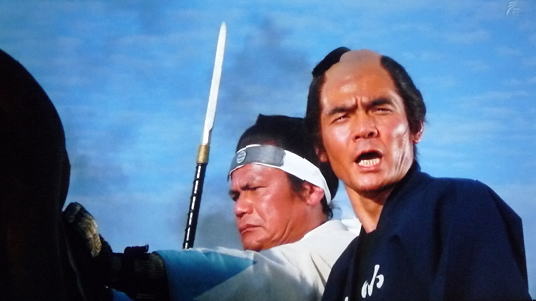
それにしても、俳優がみんな懐かしい。汐路 章、谷村昌彦、川合伸旺...岡八郎が味のある役で出ている(新選組の一人
山崎 烝)のが最高で、「あかん! 余計あかん!」とか、土方・仙吉の斬り合いでは、唾を飲んで「もうちょっとで相討ちや」とつぶやくところなど、涙が出てきそうになるほどいい!
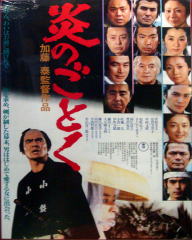

![]()
2015年 11月29日
アンジュルム ファーストコンサートツアー 2015秋 『百花繚乱』 〜福田花音卒業スペシャル〜
ハロプロのLiveをTV生中継で見ることが出来るって、スゴいね。
福田花音さんの卒業コンサートは、花音さん自身のアイデアにより、非常にハロプロの本質的な部分及び歴史を突いて構成されており、画期的なものになっていました。
卒業するメンバーが自らのコンサートを演出するという、ハロプロはパイオニアを続々生んでいて、そのブレずに前に進む姿勢に驚かされます。
メンバー一人一人とデュエット・リレーをしていくアイデアも唸りましたが、その選曲に福田花音のハロプロの歴史に対する造詣の深さが詰め込まれており、ハロプロ史上の名曲を持ってきたわけではなく、あくまでもスマイレージのアルバム曲やシングルB面曲などを交えて構成したのでしたけれども、全ての楽曲がフラットにセットリストに組み込まれるところに福田花音のハロプロ楽曲への思いの深さがにじみ出ているなと思いました。盟友である和田彩花さんとは、久住小春・萩原舞コンビのきら☆ぴかの「ふたりはNS」を持って来たり(和田・福田は過去にもこの曲をLiveで披露したことがあるのですね)、スマイレージがカヴァーしたことのある「カントリー娘。に石川梨華」の「恋人は心の応援団」をチョイスしたりというマニアックぶりは、そのマニアックさが筋金入りであることの証明であるとともに、最小の選択で最大の効果を生み出す職人ワザとして最高にクールにキマッているところがまろ(福田花音)のハロプロ愛の凄みとして伝わってきました。(スマートでコテコテにしないところがまろらしい)
これ、他のアーティストでは出来ない、ハロプロだけに生まれる存在だったと思いますね。福田花音という人は。
 ファンクラブ イベントでの映像
ファンクラブ イベントでの映像
和田彩花&福田花音 「ふたりはNS」 (You Tubeで探してください)
時間が短かった。 個人的には最後の「ショート・カット」を見たかった。
![]()
2015年 11月27日
11月25日 徳永千奈美 留学のお知らせ
おぉ!
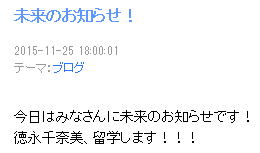
http://ameblo.jp/tokunaga-chinami-blog/entry-12099383902.html

11月26日 【GREEN ROOM#31】
思いがけないほどの辛さ・寂しさに見舞われた。
今まで毎週「Green Room」で千奈美を見ることが出来たのが幸せ過ぎだったのだ。
留学先で「1分劇場」やってくんないかな。
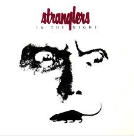
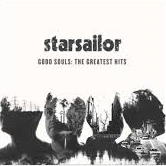
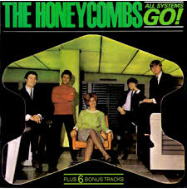
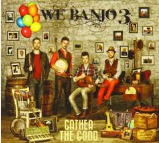
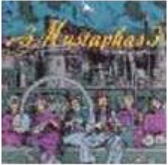
The Stranglers 「Stranglers In The Night」(1993)
ストラングラーズについては、私はあまり熱心なファンではありませんが、中古で安いアルバムをこつこつ買い集めたりして、なんだかんだでけっこう持っています。初期のパンクの時期はリアルタイムではないので、私が一番最初にストラングラーズの音楽を認知したのは1981年の「メニンブラック」が最初。感覚的には後追いのB級ニューウェイヴの感覚に近かった。勿論英国パンクの雄という知識は当時から持っていましたが、結局過去曲も聴くようになってからも、私が一番好きなのは「メニンブラック」から「オーラル・スカルプチャー」(「スペイン」! 1984)の時期。
多作のイメージがありましたが(Live盤やコンピレーションがやたら多い)、案外アルバムは少なくて、40年近くやってて18枚ぐらいのようですね。
680円で買ったこの中古盤は、ヒュー・コーンウェルが脱退して、Voにポール・ロバーツが加わった最初のアルバム。ストラングラーズって楽曲のピントがどこかずれてる感じで、いわゆるジャンル音楽を下敷きにしながら「こんないじくりかたしたらおかしくなっちゃうでしょ?」と思うようなことを仕出かして、何を好んでこんな風にしちゃってるのか謎、という曲が多い。このアルバムも奇妙なロマンチシズムに憑りつかれて、変てこなことになっているのだけど、こんなに不可解な構築が出来るのはストラングラーズだけだという気がする。イギリス人らしい狂い方をしている。
Starsailor 「Good Souls:The Greatest Hits」 (2015)
スターセイラーが2009年以来、活動を再開したということで、そのタイミングでベスト・アルバムが発表された。レア曲などを盛り込むというような編集盤に近い装いみたいな事はせず、ごく通常のBESTアルバムで(新曲が2曲追加されているが)、ファンがわざわざ買うほどのこともないCDではありますが、スターセイラーについては私は熱心なファンと言ってよく、新曲2曲と、リマスターされているという事実だけで購入する動機としては十分でした。
このバンドの最大の特長ということでは、「曲が良い」。これに尽きる!ということではないかと思います。
それ故にBESTアルバムの存在の意味は、実は大きい。とにかく何の衒いもない“Best AlbumらしいBest Album”という体裁がバンドの自信でもあると思います。
曲が書けている。まざまざとその作曲能力を見せつける堂々の作品です。
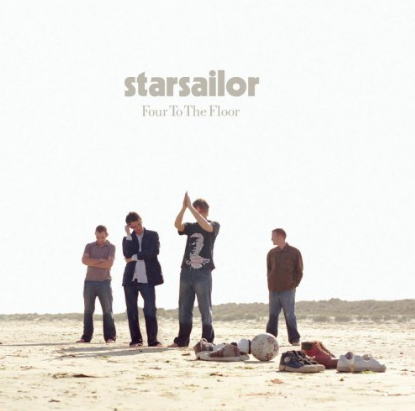

↑ Click Starsailor 「Four To The Floor」 (2003)
活動を再開したというからには、オリジナル新作アルバムの制作の準備にも入っているだろうことが予想されますが、待ち遠しいです。新曲2曲の出来も素晴らしいし、期待しています。
The Honeycomes 「All Systems GO!」 (1965)
ザ・ハニーカムズはちゃんと聴いたのは初めてで、そもそもオリジナル・アルバムのCD化自体殆どなく、古(いにしえ)の洋楽ポップスとして認知されていただけだったように記憶するが、ジョー・ミークが関わっていたことで、実は簡単に見過ごすわけにはいかないバンドです。今回「POP ROCK MASTERPIECE Complete Collection」として全オリジナル2枚が発売されたのは嬉しい企画でした。
このバンドの制作陣で注目なのは、プロデュースのジョー・ミークと、作曲チームのケン・ハワード&アラン・ブレイクリー(デイヴ・ディー・グループやザ・ハードなどを手掛ける)。バンドの末期に後のハニーバスのVo、コリン・ヘア(ハニーカムズではコリン・ボイド名義)が参加しているのも興味深い。 ジョー・ミークのフィル・スペクター、ビーチ・ボーイズ趣味はけっこうエクスペリメンタルなタッチでアンダーグラウンド臭いのが特徴。それでも当時は大ヒットしてるんですけど。
モンドな味わいがあるとはいえ、アメリカのラスベガス的トラッシュなイメージではなく、純粋に実験音楽の斬新さを持っているのが、まさかハニーカムズから伺えるとは思っていませんでした。確実にモノクローム・セットに繋がっている。この辺を切り捨ててパンク以降のブリティッシュ・オルタナティヴを解釈しようとするのが大きな間違いだった(まあ、日本ではとにかくメインストリームのRockと、ヒットチャート・ポップスを完全に切り分ける人が、Rockについて語ってきたところに捻じれが発生していたように思う)。
We Banjo 3 「Gather The Good」 (2014)
今年国内盤が出たウィ・バンジョー3の2014年発表のセカンドアルバムを愛聴しています。ライナーノーツの資料によると、このバンドはアイルランドのバンドで、ブリティッシュ・トラッドではバンジョーを中心に据えるのは珍しいとのことです。
ただ近年では、音楽を現代的にアップデイトしていく中にバンジョーは選択肢に入っていると考えてもおかしくない状況にあると思います。アメリカの歴史の延長線上にこの楽器を用いるか、ある意味全く新しい楽器として取り入れるか、30年前ならちょっとした論争になったかもしれませんが、今では軽々しくバンジョーを使うな、という論理はさほど説得力を持たないだろうと思います。
古くは30年以上前に、ペンギン・カフェ・オーケストラが使ったようなやり方が既にあったわけですし、まあでも元はといえば、ザ・バンドがオルタナティヴとして出現した(ヴァン・ダイク・パークスもいましたね)時点で、バンジョーという楽器はテクノ・ミュージック的な歴史から切断された無機質感を纏ってもいます。
ウィ・バンジョー3も、アイルランドの有名なトラッド継承者が歴史上の楽器バンジョーを取り込んでいる(つまり歴史を取り込んでいる)というよりは、アメリカのオルタナティブ・カントリー系のバンドが出現した頃や、イギリスのネオ・フォーク(マムフォード&サンズやローラ・マーリングなど)が立ち上がった頃と同じように、歴史をたどると同時にスチームパンクさながら過去と現代の往復・横断が自由になった感覚を思わせます。 依然として、是非の問題が消えて無くなってはいないのも間違いないとは思いますが。
新しい楽器としてとらえながら、歴史認識を間違えないようにするというのは条件として重要だとは思っています。
3 Mustaphas 3 「Heart Of Uncle」 (1989)
今年に入って3ムスタファズ3の名前を雑誌に見つけて、実に珍しいことだ、と思ったら、メンバーのサバ・ハバス・ムスタファが12年ぶりにソロ・アルバムを発表したという。
まだ活動していた人がいたのかというのが驚きでしたが、記事を読んだら、このサバ・ハバス・ムスタファという人、本名をコリン・バスといい、元々キャメルのメンバー(現在も)だというのを今更に知って、あの謎のグループのメンバーがキャメル!?と、不思議な気分になったわけですけども、3ムスタファズ3が活動していた80年代に、私が無知だっただけで、キャメルのメンバーが居るということは恐らく周知の事実だったのだと思います。
たまたま持ってるCDを引っ張り出して聴き始めたのですけど、当時変態音楽扱いしていたのが、今聴くとかなりしっかりワールド・ミュージックを整理して提示していたのだなということがわかり、感心するやら、ちょっと失望するやら... でも、整理されてはいるけれど、ニュー・ウェイヴの影響が大きいのはやっぱりはっきり出ている。30年たっても古びていない諧謔精神を聴きとることができます。
コリン・バスのソロ新作は未入手ですが、You Tubeにある断片を聴くと、The Lodgeに似た感じがあって、不思議なPOP感覚があるんですよ、ピーター・ブレグヴァッドなんかに近い。 すごく聴きたくなってきました。でも、もう何か紙一重で、あとちょっとでエイジア?みたいな危うさもあります。そういえばキャメルもけっこうそういう危ないギリギリの線をうろついてるプログレ・バンドだよなぁと思ったり。
(私はキャメル、けっこう好きなんですけど)
つばきファクトリーの新曲「気高く咲き誇れ!」、NETでLIVE録音を聴くことが出来ましたが、「青春まんまんなか」と同じテクノ(青春エレポップ)路線で良かったです。この路線で攻めてほしい!


![]()
2015年 11月23日
POPの評価
「女王蜂」(1978年 日)市川 崑 (録画)
今、スカパーなどで市川崑の特集をやっていて、金田一耕助シリーズがほうそうされており、このタイミングで春日太一氏の『市川崑と『犬神家の一族』』という新書本も出ていますが、特集を一気録画して、チャプターで適当に飛ばし見みたいにしていたのですけど(まあ、昔、どれも2,3回は見ているので、内容はけっこう覚えています)、およそ30年ほどを経ているということを考えると、実に感慨深いものがあります。特に小林昭二や辻萬長、冷泉公裕といった当時の非常に顔馴染みだった脇役の人たちとか、とりわけ坂口良子とか見てしまうと、否応なく懐かしさに誘われます。
市川崑監督は、言わずと知れた大監督として評価は定まった人ですが、実は80年代以降、ある種のシネフィル的評論の界隈では著しく評価を低く見積もられた監督で、割と2流扱いすることが映画に詳しい人間の常識とされている風潮があり、映画にうるさい人ほど、市川崑を軽く見るという流れが続いています。
春日太一氏は、門外漢のような立ち位置から、時代劇などに切り込んでいる人で、五社英雄や仲代達矢など、上記のような流れで低評価に陥っていた名前をあえて取り上げたりもしており、挑発的な人物だなと、感じています。新書本の方はまだ読んでいないのですが、市川崑に対してどのような切り込み方をしているのか非常に気になるところです。この本は読んでみようと思います。

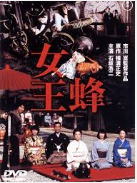

春日太一 『市川崑と『犬神家の一族』』 (新潮新書)
金田一シリーズをざっと見直して、私はもともとシリーズの中では「女王蜂」が好きで、これだけはDVDも買って持っているぐらいですが、あまり真剣に、何故これが一番好きなのかについて考えてみたことはなかったのですけど(今でもこの時の中井貴恵が超絶に美しい、とは思いますが)、今回チャプターで飛ばし見していて、何となくわかった気がしました。飛ばして出てくる画面に毛糸編みの画面がたくさん出て来たんですね。その色があからさまにPOP(ポップ)な色をしていた事に気付いたのです。というか、昔見た当時からたぶん気付いていた筈で、そこに本能的に惹かれていたのだと思います。
そういう視点で見ると「女王蜂」というのはPOPで彩られたぐらいに華やかだったのですね。例えば最初の時計台での殺人。歯車がぎりぎり回り、死体を切断していくショッキングなシーンがありますが、その後にも寄木パズル構造の壁で塞がれた密室であるとか、清楚な婦人(岸 恵子。この時の岸 恵子の美しさというのは、トリュフォー「隣の女」のファニー・アルダンに匹敵する)の持つ拳銃から容赦なく撃ち出される2発の銃弾、毛糸編みの記号で書かれた暗号など、まあ、市川崑に否定的な映画通の人などは、あざといとか言い出しそうな仕掛けの応酬ともなっているのです。


事件が連続する間、実は精神的には動揺で揺れていた神尾さん(岸 恵子)は、画面上ではのんびり毛糸の刺繍を編んでいる風でもある。非常に落ち着き払っているようでありながら、最後になって、心の中がどんな状態であったかが知れるのです。しかし、それを映し出す画面には、原色ともちょっと違う、POPな色合いの毛糸がポツンポツンとフレームの中に置かれる。

“POP”というのは、こういう、非常に意味合いのある状況(穏やかならざる心中と毛糸編みののんびりした風景という対比)にあって、全くの無意味に存在するもの(なんでこの色なのか? と不可解に感じざるを得ないことをあえて存在させること)なのだなと、「女王蜂」を見直して、あらためて強く印象付けられました。
市川崑は、でも、どの作品においてもこの一面を持っていたんじゃないかなと思います。
私は、これをあざとさとか媚という言葉で表現してしまうのはおかしいんじゃないかと思っていて、何かそこに、市川崑の低評価につながる争点のようなものがある気がします。
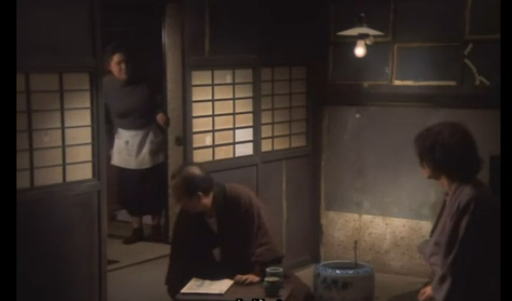
「何ちゅう口の聞きようかっ!! お客がいるのに」 伴淳三郎のこのセリフ。前後との呼吸においてPOPだと思う
リチャード・レスターや大林宜彦などの低い評価(市川崑を低く見る人は、こういう傾向があるのです)に対し、私は一度、では、POPな映画として上位になる作品とは何なのか?を問いただしてみたいと思っているのですが、いわゆる俗にPOPと言われる映画とは到底つながらないジャンル外の映画を挙げてくるか、そもそもPOPな映画自体を全否定してくるか... けっこう興味深い気がします。
市川崑について、語るべき視点はいろいろあると思うんですよね。
なにしろ、市川崑作品のたいていが低評価に陥ってる現状(あくまで一般的には巨匠ですけどね)ですから、個人的には覆す市川崑論が出てくるのが楽しみなんです。
あと、シリーズを見ていて、加藤 武はやっぱり良かったなぁ。岸恵子が自らを撃って倒れた時の加藤武の無念な表情。すっごく良かった。今年亡くなってしまったんですよね。つい最近まで、変わらない感じでやってましたもんね。寂しいな。


11月21日〜11月23日
遊ぶ。暮らす。育てる。SATOYAMA & SATOUMIへ行こう 2015 with 勇気の翼 秋フェス
くまとツーショット!
その1
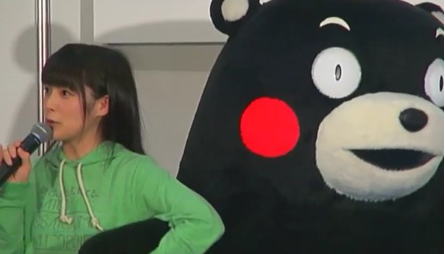
その2

それにしても Berryz 仲良すぎるよね。

矢口っちとカントリー・ガールズ http://ameblo.jp/mari-yaguchi/entry-12098754499.html
ところで、カントリー・ガールズがLIVEで発表した新曲(シングルではない?)「キスより先にできること」が信じられないくらいの傑作曲だったのですが、カントリー・ガールズ、凄すぎるんですけど。
このクオリティの高さはなんなんでしょうか?
ももちが関係するグループ、良曲100%の確率。(ももちってとんでもないな)
32:07より
https://www.youtube.com/watch?v=x9g1jsajLhY
![]()
2015年 11月20日
ベリメンのセットリスト
サム・プレコップのCDは初めて買いました。私はアーチャー・プレヴィットのファンで、彼のアルバムは欠かさず買って聴いていますが、実はそのアーチャーとサムが参加しているユニット、シー・アンド・ケイクは、最初に1枚聴いただけで、その後は聴いたことがないんです。トータスやトランズ・アムなどを聴いていた頃、シー・アンド・ケイクは一番ソフトでイージー・リスニングを批評的にではなく、むしろ積極的に志向しているようにすら感じる内向性が印象として強くて、あまり積極的に聴く気が起きませんでした。現在のシー・アンド・ケイクがどのように変化しているかもわからないのですが、アーチャー・プレヴィットがソロ制作から遠ざかっていることもあり、渇望感があって気になってはいるのです。ただ、グループの中にいるアーチャー・プレヴィットに触れるのが怖いという感じもあるのですね。シー・アンド・ケイクに対する先入観が非常に悪い印象なので。だから、シー・アンド・ケイクの新作には手が出なかったのです。
そこで、どういうわけか、グループの一人、サム・プレコップの最新作の方を入手して聴いている次第でして。 ちょっと探りを入れる、というところでしょうか。
しかし、これがかなり面白かった。モジュラー・シンセサイザーを使ったインスト・アルバムですけど、表現が細かく、年輪も感じさせるもので、初期のパンソニックにも通ずるような手作り感覚のノイズがけっこう攻撃的に挿入されていて、テクノ・ジャンクぽい粗削りな表情を持っていました。モジュラー・シンセサイザーというのは手を加えて楽器をカスタマイズしていくことで変化を楽しむのがミュージシャンの間で流行っているらしいとのことですが、確かにプレイヤーの個性が非常に細かいニュアンスとして出そうだな、という気がします。サム・プレコップが面白かったので、本当は本命であるシー・アンド・ケイクを試してみようという気持ちが出てきました。これならシー・アンド・ケイクを聴いて、失望することはないだろうと..
まあ、そもそもそこを確かめたくて、サム・プレコップの新作に手を出したのです。
何より、アーチャー・プレヴィットがソロ作を出してくれれば、ここまで回りくどい手順を踏む必要もなかったのですが。
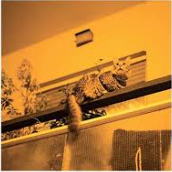
Sam・Prekop 「The・Republic」 (2015)
先日、熊井友理奈さんのカジュアル・ディナー・ショーが行われたとのことですが、そのセット・リストがNetで公開されていて、凄いセット・リストだったので、ここに挙げずにいられなくなりました。
11月15日

1 ハピネス~幸福歓迎!
2 秘密のウ・タ・ヒ・メ
3 君の友達
4 さぼり
5 恋愛模様
6 真っ白いあの雲
7 ROCKエロティック
8 恋の呪縛
9 なんちゅう恋をやってるぅYOU KNOW?
10 ライバル
E1 笑っちゃおうよBOYFRIEND
E2 ガールズタイムス
バンド演奏もついていて。
ベリーズって、鉄板曲が無いんですね、いい意味で。これは外せない、という曲がないわけではないんですけど、メンバー自身がけっこう無頓着だったりする。というか、Berryzの特徴として、いつでも全曲が候補曲になっているというのがなかなか他のグループにない独創的なスタイルで。
「恋愛模様」、「真っ白いあの雲」とか、どこから飛び出してくるかわからない自由な選曲。
逆に熊井ちゃんの鉄板である「安心感」は無かったりするんですけど、すごく自然体に好き勝手なところが、やっぱりBerryz工房のメンバーだなって、思います。
「さぼり」(小学生のたこ焼き屋さんデートの歌!)を今でも歌える無邪気さ。
あと、「笑っちゃおうよBOYFRIEND」は、きっと熊井ちゃん、個人的に好きな曲なんだね。
11月18日 https://twitter.com/maasa_0703

もう駄目だ。 ベリメンの幸せそうな映像見るだけで涙が出てくる。
今週のワン・ショットはこれで。
ついに「GREEN
ROOM」にたぐっち先輩がゲストで登場!
けっこうリラックスして受け答えしてました。 千奈美の方が緊張してたね。

11月19日 【GREEN ROOM#30】
℃-ute Newシングルのアナログ盤(12inch)届きましたー。
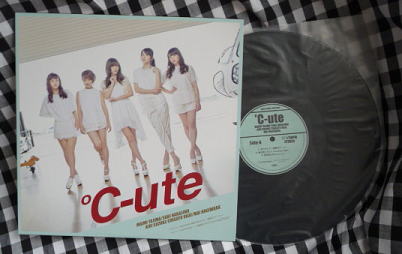 (表)
(表) 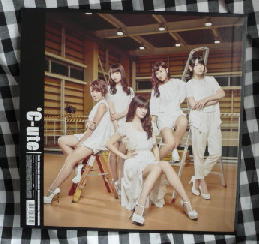 (裏)
(裏)
℃-ute「ありがとう~無限のエール~/嵐を起こすんだ Exciting Fight!」アナログ盤
7inchがほしいでーす!
まーちゃんしかない
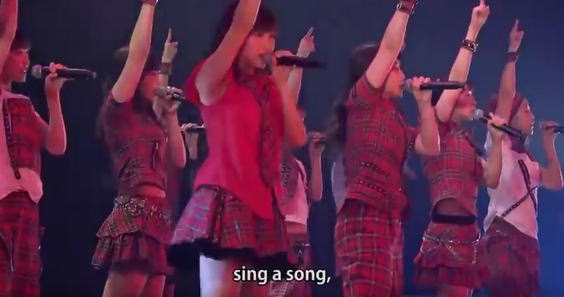
↑ Click モーニング娘。'15 『スカッと My Heart 』『私のなんにもわかっちゃない』 『One And Only 』
それから、モーニング娘。‘15の新曲「One And Only」 (全文英語歌詞)ですが、超――カッコイイです。新種のグラムか!?と思うような、ディスコ・ブギー感が出てます。このつんく♂の神がかったモーニング娘楽曲の連打は何なんでしょうか? 「TIKIBUN」を聴いた時に、もう絶対、一生ついていける、と思いましたが、「スカッとMy
Heart」のようなド傑作の後に、立て続けに「One And Only」て、凄すぎるでしょ。
来月出るNewシングルが怖いです。 またさらに衝撃を受けるよりも、ここは一息入れて、凡曲でホッとしたい、とすら思います。
来年、モーニング娘。は、モーニング娘。‘16となって、鞘師がいない新体制で臨むことになるわけですが、いやもうほんと、会社はどうするんだろうなぁと思いますけども、鞘師が居ないというのはモーニング娘。の根幹を揺るがす大問題ですから、英断を迫られる大きな転換期なのじゃないかと思います。
英断ということで言えば、私個人の思いとしては、完全10期体制に移行するぐらいが必要じゃないかと想像しています。エースに置くのは佐藤まーちゃんです。これを飯窪、石田の二人がバックアップして、天才まーちゃんと世間との距離感をコントロールしていかねばなりません。パフォーマンス面ではくどぅー(工藤)とズッキ(鈴木)が両脇を支え、さくら(小田)がツートップやソロ、多様な曲への対応など、裏で殆どを支えるような存在になると思います。9期は一歩ひく形。あとは牧野、野中を飛び道具的にぶち込む。
勝手な妄想ではありますが、佐藤優樹ぐらいはみ出した才能でないと、モーニング娘。としては物足りない、という気がします。
あと、「私のなんにもわかっちゃない」、大好きです!
これ聴くと、段原さん(研究生)が要るな。と思います。
この際、段原瑠々(14歳)さんと橋本渚(18歳 ダンスで映える)さんをモーニング娘。に入れて、14人になってもいいと思います。
![]()
2015年 11月13日
まろ(福田花音)の「わたし」が、スマイレージ讃歌としてあまりにも偉大な曲だった件

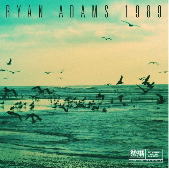
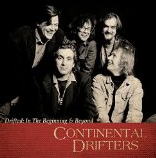
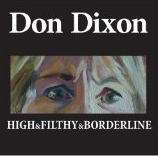
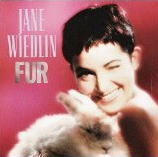
ジョー・ストラマー
with ザ・メスカレロスの3枚目(ラスト・アルバム)は聴いていませんでした。CDショップで、どう聴いてもジョー・ストラマーな声が聴こえてきて、「メッセージ・トゥー・ユー、ルーディー」だったので、調べてみたらラスト・アルバム「ストリート・コア」(2003)のボーナスに入ってました。3枚目にして何故かクラッシュ寄りの内容。ガレージィなRockにレゲエ、ダブが折り重なるように畳みかけてくる。
クラッシュって今や名盤としては必ず挙がってくるぐらい評価は確立されているのですが、正直、今「サンディニスタ」をちゃんと聴き続けている人ってどれだけいるのだろうか?と思う。Rockとダブ、という手法が最早手垢がついた感じで、もう誰も「サンディニスタ」のようにシンプルにやるだけでは面白くならないと考えているのではないかと思いますが、Sleaford・Modsのように必ずしも手法だけではないのですよ、Rockは。メスカレロスはそれを教えてくれたバンドだったわけで、ただ、あれから時代はたいして動いていないように感じる。「サンディニスタ」やメスカレロスを聴き続けるしかないのだろうか?
ライアン・アダムスの新譜。ライアン・アダムスはかなり久し振りに買いました。アメリカでソロで大ブレイクして、その後も多作家で、新作を出すたびに話題にはなっていましたが、日本ではそれほど評価を受けるジャンルではないという印象だと思いますね。Wilcoよりもブルース・スプリングスティーンに近いところで活動しているようにも感じてしまう。どちらのファン層からも距離が出来てしまっている気がします。私にとってもライアン・アダムスはいつまでたっても結局“ウィスキータウン”のライアン・アダムスというイメージが残っていました。しかし、そもそもWilcoとスプリングスティーンを分けて考えること自体、本来ナンセンスな筈。
そして新譜「1989」(2015)は、ライアン・アダムスによるテイラー・スウィフトのアルバム「1989」(2014)の全曲カヴァー・アルバムなわけです。
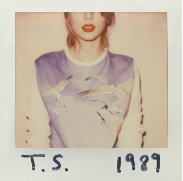 テイラー・スウィフト 「1989」
テイラー・スウィフト 「1989」
私は別にライアン・アダムスとスプリングスティーンとテイラー・スウィフトを同じエリアに置きたいとか思っているのではありませんが、“それは有りうる”ということです。有りうるということを忘れたくない。
コンチネンタル・ドリフターズは恐らく日本では殆ど無名のバンドです。元dB‘Sのピーター・ホルサップルや元ドリーム・シンジケート、元バングルズ、元カウシルズのメンバーらも参加した、ちょっとしたスーパー・グループではあるのですが。新譜が出れば必ず聴いていました。2003年頃には解散状態にあったようです。今年に入ってお蔵入りになっていた曲やLive音源を集めた2枚組のアルバム「Drifted: In The Beginning & Beyond」(2015)が出まして、コンサートも行っていました。フェアポート・コンベンションのカヴァー・アルバムを出す一方でホリーズのカヴァー・アルバムもあるという。いや。“出す一方で”なんて言い方はおかしいですね。でも、日本において(日本に限らないかもしれません)ホリーズって、ぶっちゃけ“対象外”とされる対象ですよね。コンチネンタル・ドリフターズとはそういう批評性を持ったバンドです。
懐かしいところで、Don・Dixonを最近聴き直したりしています。全くノーマークでしたが、ずっと活動は続けていたようです。アルバムも何枚も出している。今のところの最新作である「High&Filthy&Borderline」(2013)は意外やコンセプト・アルバム的なけっこうノン・コマーシャルな内容でした。1985年に「Girls L.T.D.」というアルバムで一躍人気。REMのプロデューサーとしても有名になりました。あの当時のアメリカのティーンズ・ムーヴィー(ジョン・ヒューズの「すてきな片想い」が1984年)が背景に浮かんでくるような音楽、「かまきり」、「サウスサイド・ガール」とか本当に好きでした。
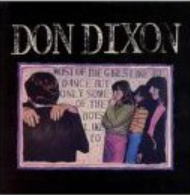 ドン・ディクソン 「Girls L.T.D.」
ドン・ディクソン 「Girls L.T.D.」
今、「80‘sに夢中 80‘s
BEST COLLECTION 1200」なるCD廉価のフェアが行われていて、定番のカルチャー・クラブやデキシーズ、GO-GO’S、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」サントラなどのCDがTOWERの店頭などに並んでいるのですが、ちょいマイナー(中途半端に売れ線みたいな)なCDも出ていて嬉しいです。既に持ってはいるのですが、元GO-GO‘Sのジェーン・ウィードリン「FUR」(1988)などは長年手に入りにくかったCDなので、今では知らない人が多いと思います。この人は、当時イギリスにおけるトレイシー・ウルマンやカースティ・マッコールのようなオールディーズの古き良きメロディーを当時において“現代風に”提示出来た優れたソング・ライターで、アルバムの内容も非常に良いので、今の人に、新たに発見してもらういい機会だなと思います。音が良くなってるんじゃないかと思って私も買いました。1200円ですし。「Rush
Hour」,最高なんだよな。
 ジョー・ジャクソン 「ナイト・アンド・デイ」
ジョー・ジャクソン 「ナイト・アンド・デイ」
他にもジョー・ジャクソンの「ナイト・アンド・デイ」(1982)も買ったのですが、まぁー、「ステッピン・アウト」の懐かしいこと懐かしいこと。感涙に近いくらい感動がありました。思わず「いい時代だったなぁ〜」とか口走りそうになりました。

↑ Click ANGERME 福田花音ソロ「わたし」 (作詞:福田花音 2015)
ANGERMEの最新シングルに入っている福田花音のソロ曲「わたし」が、凄い傑作曲だったので、尚更に花音さんの卒業は残念だなと思いました。ソロでデビューして十分にいける優れた歌手であることを再認識しました。
2004年4月ハロプロエッグの1期生。福田花音、9歳から既に11年。同期に初期スマイレージメンバーや、後のTHE ポッシボー(現チャオベッラチンクェッティ)、アップアップガールズ(仮)がいますが、やはりその中でも逸材だったんだなぁと、むしろここまでずっと、なかばハロプロの集団に埋もれてしまうような形で来てしまったのが、果たして許されることだったのだろうか? これもひとつの巡り合わせというものなのだろうかと、ちょっと溜息が出てしまう感じがありました。
スマイレージって不思議なグループだったんだなと思いました。言わば消費されることを拒んできたグループというか、幾多の障壁、失速が、実は自分たちが選んできた道だったのではないかと、雪崩うつようなグループ危機の連続に、怒りで耐えてきたあやちょ、花音、2期メンバーの振る舞いを思い出す(あ、偉そうなこと言ってますが、リアルタイムでは知りません。後付け理論です)に付け、結局それがこの「わたし」という曲の動機づけになっているのだと、思い至りました。正にスマイレージ(=ANGERME)の歴史を表すような歌詞の内容になっている。聴けば聴くほど、“わたし”が“スマイレージ(=ANGERME)”のことだとわかってくる上に、スマイレージとは、あやちょ、花音、2期のアイデンティティそのもの、彼女たちの人格であるという思いを強く感じました。
スマイレージの本当の凄みってそこにあったのか。まろ(花音)卒業を控えた最後の一手でやっと気づきました。スマイレージが闘ってきたことを、まろがこういう形で歌詞に表現してくるとは...
ますます日本のロックってここだけだな、の意を強くしました。
まさかの「ラララのピピピ」に匹敵するロックの傑作、ANGERME 福田花音ソロ「わたし」。
11月11日 https://twitter.com/motomotohide
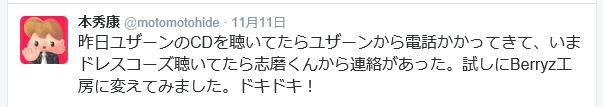
こぶし らっこ(和田桜子)とたぐっち(田口夏実)

https://twitter.com/airi_yukachan
たぐっちのブレイクが待ちきれない。





たぐっち「麺が こしこし してる」 れなこ「え? も もちもちでしょ?」
![]()
2015年 11月 6日
ももち復活祭 そして、カントリー・ガールズに新メンバー加入
11月6日 https://twitter.com/kayamayama
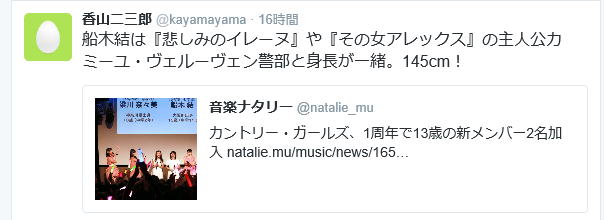
香山氏 さすが。 あぁ、どうせなら、このぐらい書ける、(君のような)根性がほしいよぉー!
そして、ハロプロ・アドヴァイザーの徳永千奈美さんからもブログにコメントが..
11月6日 http://ameblo.jp/tokunaga-chinami-blog/entry-12092564038.html?frm_src=thumb_module

これ読んで、けっこうマジ泣きした。
ちーちゃん、ほんとに可愛い過ぎる!!
さらにさらに、おぱよキャプテンからも
11月5日 http://ameblo.jp/shimizu--saki/entry-12092195951.html?frm_src=thumb_module

「見守る」って言葉があるけど、やっぱり佐紀ちゃんからすると、ももちは妹みたいな感じがあるよね。
今週のワン・ショットは、清水佐紀さんとみつばちまき先生

11月 5日 【GREEN ROOM#28】
なにか、蜜月になりそうで、難しそうな二人というか。 ベリメンの自由人気質を実は色濃くメンタルに秘めているのが清水キャプテンなわけで。 この距離感の壁が溶ける時がくるのかな〜と思いながら見ています。 “そこまでいかない”のがベリ、というのがあるとも思うんですよね。 キャプテンが本気を出すのを心の底では勿論願っているのですけども。
![]()
2015年 11月 1日
竹内・田村 × 室田 体制の序章

↑ Click ANGERME 「ドンデンガエシ」 (11月11日 発売)
ハロプロCDラッシュの時期で、次はANGERMEのシングルが出ます。「出すぎた杭は打たれない/ドンデンガエシ/わたし」のトリプルA面。ANGERMEも、現在では原則つんく♂曲は無し。今回は卒業する福田花音の作詞曲「わたし」が入っています。
他の2曲はどちらもハードなロック調の曲で、「ドンデンガエシ」はアニソンぽいとか言われ、「出すぎた杭〜」は所謂邦ロック(昨今流行りのフェス映えするパターン化したノリのロック)寄りとされ、どちらもまあ褒め言葉ではないわけですが、ファンの間では、上記のように例えながら、感想的には好意的に受け止めるというような反応が多いようです。
私も実は同じような反応なのですが、曲として必ずしも支持とはいかないタイプの曲なのですが、もはやANGERMEの持つ潜在的破壊力に応え得るには、真っ向勝負の単純な速さと激しさが必要なんだろうなとも思うのです。
なにしろANGERMEの持つ最大の武器が、竹内朱莉と田村芽実という二人の大砲のごとき声です。実際この二人をどのように生かすかがANGERMEの生命線になると思います。この二人を前面に出すようになるには、どうしても二人に拮抗しうる正攻法のヴォーカリストが必要だったわけですが、室田瑞希という理想的なヴォーカリストを得ることによって、可能になりました。それまで、個性的ながらバラバラな声を、まろ(福田花音)が一人で支えてきたところに若干苦しさがあった(福田さん自体、本来下支えするようなベーシックな声の資質の人ではないのですが、実際のところ福田さんの技量がズバ抜けていたために彼女に頼り切ることになっていたのが6人時代だったのではないかと思います)。
今回のシングルで福田さんが去るとなると、いよいよ竹内・田村×室田の壮絶なバトルが始まるという期待感があります。
私の感想としては、今回の曲は次の本格的バトルをひかえての序章のようなものととらえています。
というか、竹内・田村体制をとらないとしたら、ハロプロ・スタッフのセンスを疑います。二人の破壊力に対する認識が無さすぎるということになります。 ま、そもそもスマイレージ4人時代からこのグループは能力を全く生かし切れずに不遇をかこってきたのですが...
私も注目しているLoVendoЯの魚住有希さん作曲の「出すぎた杭は打たれない」も良いのですが、「ドンデンガエシ」が意外にいいです(アニソンみたいなのに 笑 っていう言い回し)。 竹内、田村の歌割りでスタートし、福田、室田で迎え撃つスタイルが打ち出されていて、ANGERMEの一つの到達点を示すものだと思います。で、私の予想では、恐らく室田さんなら、まろが居なくなっても一人で竹内・田村に渡り合えると思う。正にANGERMEのヴォーカル・バトル時代の幕開けを予感させるのが「ドンデンガエシ」なのだと。
一方で可愛い曲なんかでは佐々木莉佳子さんを思い切りフィーチャーすればドンピシャだと思う。
ANGERMEが9人になってバランスが良くなったと思うのは、こうして必要な声が出揃った感があるからなんですよね。オーデションのメンバーを加える必要はないんじゃないでしょうか。竹内・田村・室田でガーン!と行けば。
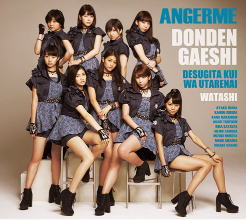
今度こそ、放っておいても死ぬほど売れちゃうんじゃないかなという気がするんですが..
![]()
2015年 10月 31日
Muse

↑ Click ℃-ute 「嵐を起こすんだ Exciting Fight!」 (2015年10月28日 発売)
書くのが遅くなってしまいましたが、℃-uteの新曲「ありがとう 〜無限のエール〜/嵐を起こすんだ Exciting Fight!」が10月28日より既に発売中です。
安定の℃-uteで(安定の℃-uteとは、安定の高難度という意味です)、間違い無しにエキサイト出来る楽曲です。
配信で曲のプロモーション・ビデオを見ることが出来ますが、そちらは日本レスリング協会の映像(オリンピック強化選手の練習風景など)が曲中に入っており、ままま、それはそれで全然良いのですが、やはりDVD付きのCDを買って、Dance Shot Versionを見ていただくと、そちらのミュージック・ビデオは、がっつり℃-uteだけの映像が見られるので、ここは、お金払ってでも、CD買う価値があり過ぎるほどにある、と宣言しておきます。
いやもう何たって℃-uteはかっちょ良いの一言。
気付いている人は気づいていますけれども、矢島舞美さんという、この人をどう言葉に表せば、表現しえたことになるのか.. こんな人、この世に存在するんだな、と思うぐらい、Muse(ミューズ)って言ってしまうと、昨今ではありふれた安っぽい表現になってしまうかもしれませんが、本来の幻想的な神の領域としての.... いやもう書けば書くだけ恥ずかしい文章になるだけのような気がしますが、とにかくもうその領域に近い方ですよほんとに。特に「嵐を起こすんだ Exciting Fight!」のDance Shot Verは、永遠に見続けられるほど美しい。そして彼女のシャウトは全て衝撃的にエモーショナルなのです。
今回2曲とも撮影のロケ場所が良く、「嵐を〜」の飛行場の倉庫でヘリをバックに置いたのって、曲のアレンジでプロペラの重低音的な音がするのとシンクロしてたりするんですけど、何かあのコロンボのテーマみたいな、やけに70年代アメリカ映画音楽のテイストが下に流れている感じがムチャクチャ面白いです。
偶然だとは思いますけど。
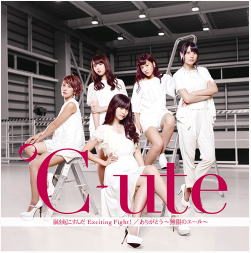 (℃-uteに馴染みのない方、矢島さんは右端の人です)
(℃-uteに馴染みのない方、矢島さんは右端の人です)
あとですね。最近のワン・ショットはこれ。
「GREEN ROOM」がどんどん楽しくなってきているので、千奈美さんには是非長寿番組をめざしてもらいたい。この空気感が楽しみで仕方がないです。

10月29日 【GREEN ROOM#27】(カントリー・ガールズ 小関 舞さんゲスト)
![]()
2015年 10月 30日
鞘師

鞘師里保&小田さくら 「大好きだから絶対に許さない」2014 小田さくらバースデイ・イヴェント
今年、いろいろけっこうあったから
ファンとして、口から出かかりそうになる言葉は幾つかあるのだけど、
結局、何も言うことは無い。
あれだけモーニング娘。が好きな鞘師が悩みぬいた末に出した結論だから
支持するのみ。
(31日、「ヤンタン土曜日」聞きました。 さんまさんの鞘師の送り出し方は本当に優しくて温かい。ハロメンにはありがたいなと思いました)
![]()
2015年 10月 29日
ご報告 鞘師里保
http://ameblo.jp/morningmusume-9ki/entry-12089659596.html
う〜ん。
がっくり肩が落ちるぐらい悲しい。
鞘師の居ないモーニング娘。って、あり得ない。
はぁ___________
鞘師がいないというのを想像できない。 全く浮かばない。
http://ameblo.jp/c-ute-official/entry-12089611470.html
![]()
2015年 10月 24日
日本人が知らない?
ミーコンズ、すごっ! 今年に入っても「Memphis、Egypt」やってる。

↑ Click The Mekons - Memphis Egypt LIVE @ Square Roots Fest Chicago
2015
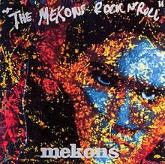 日本人が知らないRock名盤
日本人が知らないRock名盤 
Mekons 「The Mekons Rock'n Roll」 (1989)
クリス・ステイミーも今年の映像がありました。

↑ Click Chris Stamey - "Universe-sized Arms"
この顔を見た瞬間に、もう好きっ。
今年出た新作アルバムは今まで以上に恐るべきレイドバックぶりで、完全にビートルズやキンクスを始めからやり直しているぐらいの勢いでしたが、それが何故か最新型に聴こえる、というか、最新型とはこれなのだ!ということをクリス・ステイミーが宣言し、定義している。
それがこの映像見てもよくわかる。つまりはクリス・ステイミーだけがずっと前を進んできたのだということを、この易しさも難解さも全く同じレベルで1曲の中に表現しきることによって、証明している。
アメリカで最も正確に正しい方向を向いているアーティストだと思う。
そして、2015年に演奏する「It‘s
All Too Much」 。この境地。ある部分の歌い方においてはあるまじきほどに忠実なところに震える。

↑ Click Chris Stamey - "It's All Too Much" (Cover)
本家の曲はこちら。ビートルズ最重要曲のひとつ。
https://www.youtube.com/watch?v=uq_WwAHRwoc 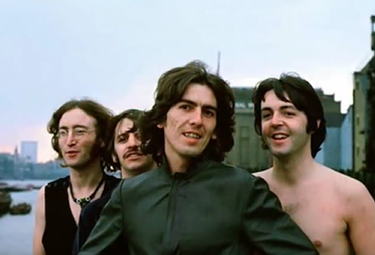
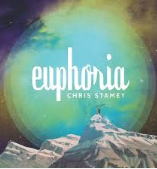 日本人が知らないRock名盤
日本人が知らないRock名盤
Chris Stamey 「Euphoria」 (2015)
さらには、イレヴンス・ドリーム・デイの今年のLive映像も見つけました。

↑ Click "Orange Moon," Eleventh Dream Day Mercury Lounge, NYC. Aug. 21, 2015
イレヴンス・ドリーム・デイは割とコンスタントにアルバムを出しているのですが、殆ど話題になることもなく、たぶんひっそりと国内盤CDも出されているんでは?と思いますが、イレヴンス・ドリーム・デイのCDを国内盤で買っている人ってどれだけいるんだ?って話ですよ。
今年も新作アルバム出ましたが、何と、国内盤出てるんです。知ってましたか? いや、驚いた。
ここはメンバーのジャネット・ビーンがFreakwaterというバンドもやっていて、こちらのバンドもかなりアメリカのオルタナ・シーンでは重要なバンドで、Califoneとも繋がり、さらにそれがRed Red Meatへという感じで厚いコネクションを持っているのにろくに日本で紹介されてこなかった、日本では極めて不遇だった存在です。(日本ではヨ・ラ・テンゴで全て事足りるみたいになってる)
音を聴けば、ジャンクやグランジの強靭なノイズを今に再現できる(実際、今のシーンには本物のグランジ?音を出せるバンドなど殆どいない)数少ないバンドであるのがわかる。(当時のグランジ・シーンにあって、なかなか突き抜けないもどかしさを内包していたバンドであったのも確かですが。それ故にスリル・ジョーキーの面々やジョーン・オブ・アークのような奇天烈なバンドとの交流も可能で、芯を残しながら現在までの変化を恐れない20年以上のキャリアをかけての進化が出来たのだと思う)
TOPではなく3番手あたりを走り続けて来たからこその、ぶれない眼差しには、もっと注目すべき。目先ばかり追って、アメリカのかなりの部分を日本の音楽シーンは取りこぼしてるように思う。
 日本人が知らない国内発売盤
日本人が知らない国内発売盤 
Eleventh Dream Day 「works for tomorrow」 (2015)
あとは、毎度のハロプロStory。
10月22日 【GREEN ROOM#26】「大好きだから絶対に許さない」ハロプロ研修生オーディション編

合格したふなっき(船木 結)といっちゃん(一岡怜奈)
「大好きだから絶対に許さない」(モーニング娘。 鞘師里保・小田さくらのデュエット曲)をカヴァー。
Live披露3回のうち2回を一岡怜奈さんが歌うチャンスGET! ハラハラする。
https://www.youtube.com/watch?v=OktM7wLShOQ
10月24日 大阪医科大学大学祭 嗣永桃子(カントリー・ガールズ)トークショー

ももち まずはトーク・ショーで復帰
![]()
2015年 10月 18日
千秋楽 見たかったなぁ

オレもうほんと、見に行きたいと思ったぐらいつばきが好きだわ

↑ Click 絶対欲しい! このサントラ

演出 茉麻 18公演お疲れさまでした


![]()
2015年 10月 18日
日本は忘れるのが早い!
佐々木敦氏と川崎大助氏の対談の映像を見ました。川崎氏は先だって新書で『日本のロック名盤BEST100』というのを出した人で、私は書店でパラパラとめくりましたが読んでいません。「ロッキング・オン」に書いていた人ということで、川崎という名のライターが居たのは覚えているのですが、ちょっと下の名前までは記憶がありませんでした。

↑Click 佐々木敦×川﨑大助「日本のロックを語り尽くそうぜ!」スペシャル対談
本を買わなかったのは、正直、ハイ・スタンダードとかが入っていたのと、はっぴいえんどが1位だったこと、それから佐々木氏が指摘していましたが、ムーン・ライダーズの順位が異常に低かったことには私も気づいていて、評価基準が、取っ掛かりが無いと思うほどにつかめなかったこと等の理由によります。
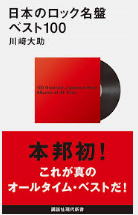 川崎大助 『日本のロック名盤ベスト100』(講談社新書)
川崎大助 『日本のロック名盤ベスト100』(講談社新書)
およそ2時間にも及ぶ対談(映像を流していた時間をカットした上で約2時間ありました)は、しかし非常に面白かったし、興味深いものでした。何しろ、二人とも1964、1965年初めの生まれで、学年で言えば私と同学年であり、聴いてきた音楽もほぼ同じような経歴をたどっていて、言ってる内容がもう完全にわかる。同世代の音楽好きが持ってる視点ということで共感する部分が多々ありました。
それにしても、初めて聞いた佐々木敦氏の音楽好き遍歴が、さだまさしとオフ・コースから、しかも当時けっこうどっぷりだった(その後、いきなりビーフハートへ飛ぶとのことですが)というのが意外でしたが、自分の中で妙に納得している部分もあります。川崎氏はクラッシュだそうですが。
いろいろ語ったうちで、やはりこの書物を出すきっかけ(佐々木氏は『ニッポンの音楽』を今年出しています)に、今の若者が洋楽を聴かないことへの危惧があるように感じました。これは非常にいいにくいこと(洋楽原理主義者のように思われる)ではあるのですが、結局本音はここなのだと思います。
伊藤銀次氏が川崎氏に「日本は開国と鎖国を繰り返す」というような言葉で日本の音楽を表現したのが印象に残っていると言っていましたが、洋楽を取り込んだらもう自分のものにしたと思い込んで、忘れるという批判をしているわけです。
忘れるのが早いだろ! この批判が動機になっているのではないかと思いました。
本音として、はっぴいえんどを1位や最重要としているが、客観的に考えるとそうなるのだけれども、個人的にはそうではない、と二人とも言っており、こうして公(おおやけ)の前で言いたくなってしまうというところに、二人にとって“日本のロック史”の公式的なものが、実は“面白くはない”ものなのではないかと勘ぐってしまいました。こういう風潮が90年代から始まると佐々木氏がはっきり言っていたのも興味深かったです。
“日本人が洋楽を聴かない”と暗に示した批判は、世界がストリーミングの時代にとっくに入って、若者が聴き放題で過去のアーカイブを享受しまくっているのに対し、日本の、自分の国の音楽しか聴かず、決定的にストリーミングの波に乗り遅れたことにより、音楽の教養において、相当差がつくという予言めいた発言まで出ました。
以前書いた。山下達郎を神とあがめるNEWシティ・ポップス・ムーブメントの旗手に「アイズレー・ブラザーズが」と言ったら、「何ですか。それ?」と帰ってきたというエピソード。
それじゃ、いかんのか? と言われれば、別に駄目じゃないよ駄目じゃ...と、はっきり反論しにくいところはあるのですが、何だかなぁ、という。
川崎氏の意見は非常に面白かったです。イギリスのロックは不良のロックだが、アメリカはそうじゃない、という意見も面白かった。佐々木氏もそれに乗って、アメリカは意外に学究の徒が多いと言っていました。
これって、一般的にはどういう認識なんでしょうか?
私も、これはけっこう重要なキーだと思っているのですが...
![]()
2015年 10月 17日
Souvenir
Dean
Wareham & Britta Phillipsが担当した映画音楽のサントラが発売されているのですが、この映画は日本で公開されるのでしょうか?
「Mistress America」というタイトルで今年の作品です。監督は「イカとクジラ」(2005)、「マーゴット・ウェディング」(2007)でけっこう有名なノア・バームバックで、この人はウェス・アンダーソン作品の脚本もやってる、というところで、ちょっとアート系のようなので、ベン・スティラーが主演しているのに日本未公開なんていう映画(「ベン・スティラー 人生は最悪だ!」(2010))もあり、公開されるかDVDスルーになるか微妙な位置にいるようです。
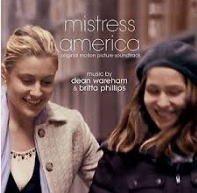

Dean Eareham & Britta Phillips 「Mistress America OST」 (2015)
ま、そういう人だからディーン・ウェアハム&ブリッタ・フィリップスに音楽を依頼するレア・ケースも出てくるのでしょうが。
こういうアメリカ映画の面白いところ - 挿入曲にオーケストラル・マヌヴァーズ・イン・ザ・ダークの「スーヴェニール」とポール・マッカートニーの「ノーモア・ロンリーナイツ」、スーサイドの「ドリーム・ベイビー・ドリーム」、Hot Chocolateの「You Could‘ve Been a Lady」が入っているところ。
こういうバランスの選曲が出てくるところがアメリカやイギリスの凄いところで、日本だとどうしてもこのバランスが出ない。どれかになる。結局どれだけ音楽と一緒に生きてきたか、ということなんでしょうね。

 ←Click 「Souvenir」
←Click 「Souvenir」
Orchestral Manoeuvres in the Dark 「Architecture & Morality」 (1981)
主にBrittaが作曲している映画のインスト曲は、どこかOMD(オーケストラル・・・)にひきづられている雰囲気があり、オマージュを捧げているかのようです。これは映画制作側と話し合った結果からかもしれませんが、確かにサントラを聴いていて、「スーヴェニール」が出てきた時の何ともいえぬ高揚は不思議な感じで、Brittaの音楽が前後にあるから“ああ「スーヴェニール」なんだという、この曲を主役に押し出している感じが出ているようです。5曲目の「Mom‘s」という曲はOMDの「Of All the Things We've Made」のカヴァーか?と思うほど(因みにこの曲は石井聰互が「逆噴射家族」のエンディングに、同じくカヴァーか?と思うほどそっくりな曲を使っています)です。他にもNew
Order意識したのではないかと思うアレンジの曲があったり、スーサイドの曲が入っていたりで(しかもこの曲はブルース・スプリングスティーンがカヴァーしたことのある曲でもあるという実にアメリカ的に入り組んだ構造が出来上がっているところが、やはりノア・バームバックらしい仕掛けっぷり)70年代末から80年代前半の空気感をまとっているように思います。
アメリカってやっぱりすごい考えている人がいるんだな、と安心するところがありますよね。
それがOMDだというのが、何かもう、これだからアメリカはやめられん! という気になるのですが。
![]()
2015年 10月 16日
ハロー!
10月13日 http://ameblo.jp/shimizu--saki/entry-12083494720.html

ハロプロ研修生とハロプロ・アドヴァイザーと、みつばち先生?
(駄目だなオレもう。 これ見ただけで幸せを感じる。)
「ビジュルム」
アンジュルム和田彩花さんが美術について語るラジオ番組「アンジュルム和田彩花のビジュルム」が、10月3日より、東海ラジオ土曜夕方6時から6時30分の放送で始まっています。
https://twitter.com/bijurum1332
1回目はマネの「死せる闘牛士」と広隆寺 弥勒菩薩半跏像の話。
2回目はマグリットとマネ「オランピア」の話でした。
あやちょの話は本当に好きだという気持ちがあふれていて、ほとばしるように言葉が出てくるのですが、非常にわかりやすい! 描写が上手い。 声質が軽くてはねるようなリズムが心地よく、すんなり頭に入ってきます。めっちゃ面白いです。

牧野真莉愛、「パ・リーグ激動の昭和48年」を読みびっくりマリア
モーニング娘。‘15の牧野真莉愛さんは相当ガチなプロ野球好き(日ハムファン)で知られていますが、この本を読むって、かなり、ですよ。
昭和48年(1973年)て、巨人V9の年。私でもこの頃のプロ野球はまだ見ていませんでした(私が意識的に見た初めてのTV中継は昭和49年 長嶋引退試合。)
私も書店でこの本は見かけて、面白そうだなと思って一度手に取りましたが(買いませんでした)、なかなか年季の入った野球ファンでもハードルの高い書物ですよ(40年以上前の話を書いている本なわけで)。
この子は、時間の都合がつけば7回からでも試合を見に行くらしい(年間のパスを持っているのかな?)と、何かで読みましたが、筋金入りだなと恐れ入りました。
しかし、確かにこの本は面白そうだ。
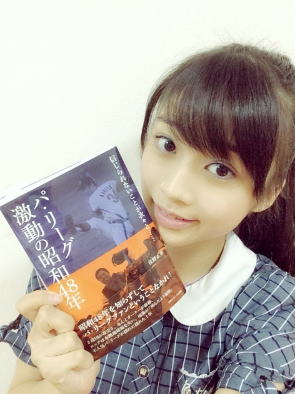 佐野正幸 『パ・リーグ 激動の昭和48年』 (日刊スポーツ出版社)
佐野正幸 『パ・リーグ 激動の昭和48年』 (日刊スポーツ出版社)
牧野真莉愛さんは2001年生まれの中学3年生
10月8日 http://ameblo.jp/mm-12ki/entry-12082079287.html
「J-MELO」のMOOK本に小室哲哉とつんく♂の対談が載っていて、けっこうな分量 があったので資料(?)として購入しました。
 『J-MELO』が教えてくれた世界でウケる「日本音楽」 (ぴあMOOK)
『J-MELO』が教えてくれた世界でウケる「日本音楽」 (ぴあMOOK)
最近はもうハロプロについて調べるのが、フィル・スペクターや大滝詠一のスタジオ仕事について調べたりするのと同じなぐらい趣味になってきまして、実際ハロプロ自体が数年前から、スタジオ・ワークや研修生システムなど内部を一般に情報公開するようになってきていることもあり、けっこう面白いんですよね。
しかも考えてみればUP FRONTの中でハロプロだけでも18年ぐらいの歴史が既にあるわけで、フィレスや福生、モータウンやマッスルショールズなんかに比べてもそれなりにけっこうな年月です。何でも手掛ける大手のレコーディングスタジオやレーベルとは違い、明らかにハロプロはある種の特徴的な音楽を量産してきているので、内部を知ることで、興味のわくポイントが次々引っ掛かってきます。
まだメディア関係で、ハロプロを深く取材している人はいないみたいですが、本気でやってみたら面白いんじゃないかと思います。
対談で興味深かったのは、小室氏が自分や秋元康氏をプロデューサーの第1世代と考えていたことで、村井邦彦とか、それまでの人たちのことはどうなるんだ?と思ったのですが、たぶん秋元氏の名前は出してるものの、本当はそれほどでもなくて、小室→つんく♂→中田ヤスタカのラインのことを考えていたんじゃないかと思います。
作詞・作曲から録音までやってしまう全面プロデュースとしては自分が第1世代だと考えたのですね。
その流れの中で小室氏からトッド・ラングレンの名前が出てきて、ちょっとプロデューサーの規模としては箱庭的な解釈でいるんだなと思ったりしたのですが、小室氏の音楽作りというのは本人の中では案外そういうスケール感でいるのかもしれないなと思いました。
つんくが著作(『だから、生きる』)で全て自分が把握しないと気が済まないぐらいの勢いで語っていたのと共通するし、中田ヤスタカ氏もそういう傾向がある気がします。これって確実にフィル・スペクターの流れの上にあるし、ミュージシャンの立場でこじんまりとやっていた大滝詠一とも通じていると思います。
つんく♂をこの流れの中でとらえるという考え方は今まであまりなかったのではないでしょうか? 私は小室氏がトッド・ラングレンの名前を出すというのは、けっこう重要なキーワードだったんじゃないかという気がしています。
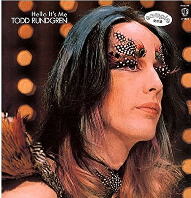 トッド・ラングレン 「ハロー・イッツ・ミー」 (1974)
トッド・ラングレン 「ハロー・イッツ・ミー」 (1974)
1972年発表の名盤「Something/Anything?」(25曲入り)の日本独自編集盤(10曲入り)がCD復刻された。1300円
トッドは「Something/Anything?」まで日本盤は発売されていなかったそうです。
安かったので買ってしまいました。トッドは以前に一通り聴いていますが、今、手元にはオリジナル・アルバムがありません。でも何だかんだでずっと聴き続けています。聴かずにいるのは無理、ってなぐらいの存在です。
![]()
2015年 10月 11日
J-Rock好き
プププランド、Keytalk、androp、UNION
SQUARE GARDEN、Mrs.Green Apple、ONIGAWARA、Shiggy Jr.、Czecho no Republic、夜の本気ダンス、東京カランコロン、SAKANAMON、アルカラ、死んだ僕の彼女、Homecomings..etc どいだけあるんだよっていうぐらい沢山のバンドがいて、人気もあったりするんでしょうが、さすがに全体を見渡すなんて面倒くさいことしている好事家(Japanese
Rock好き)なんてのもいないでしょうね。いるのかな?
割と好きなバンドとかもいたりします。ONIGAWARAとかプププランドとか八十八ケ所巡礼、Saloversとか嫌いじゃない。たまーに流れてれば「おっ」とか思うかも。

↑Click go!go!vanillas - カウンターアクション
go!go!vanillasは新曲が出ましたね。「カウンターアクション」。やっぱり良いなとか思いながら聴いています。次のアルバムが出たらまた買おうと思います。このバンドも今のモードからするとちょっと外れた位置にいるのかもしれませんが、意外とアメリカンな感じ(dB‘sやGame
Theory、plimsoulsみたいなギターの音色)も出せるんだなと感じました。Kinksがアメリカへ出てった時の感触? ちょいルーズなところが。
ブリティッシュ・ビートのパキパキのところにちょっと緩みが加わった感じがすごく面白い。

[Alexandros] - ワタリドリ ttps://www.youtube.com/watch?v=O_DLtVuiqhI
世間的には、というか、ジャパンというか、「J-MERO」などでフィーチャーされるアレキサンドロス(Alexsandros)なんて、むちゃくちゃ売れているんでしょうが、この“流れ”が主流を成したとしてどこへ日本の音楽を運んでいくんだろうな?と、まあ自分は遠くから眺めるばかりで、本当に何と言っていいかわかりませんが、認める?認めない?認めたらお終い? でも私はやっぱり長い時間で見ていきたいと思っています。プレスリーからだって60年やって来てるわけじゃないですか。全ては、無駄ということはないんだろう、とか考えながら、何かに“抵抗”はしていきたい。 だから私は“認めたらお終い”と思ってる。
でもね、Alexsandrosは実はそんなに嫌いじゃない。

Silent Siren 「女子校戦争」 ttps://www.youtube.com/watch?v=QvpEQ2jrUP0
無条件に好きになれるってのは、Silent Sirenだなあ。今、日本で一番好きなギター・POPバンドです。
清々しい。正々堂々としている。潔い。ものすごく簡単に難しいことをやってる。
「女子校戦争」なんて、キーボード聴いてるだけでも惚れ惚れする。
何なんだろうね。これをカッコいい!と思わない人が、音楽雑誌とかで書いてるんだよね。そういう人がスリーター・キニーの復活とかタルーラ・ゴッシュがどうだったとか、少年ナイフがどうだったとか書いて、チャット・モンチーやミドリを絶賛してきたんじゃないかと、私は勝手に思い込んだりしているわけですが。
今週のOne Shotは嗣永桃子さんで。研修生のいっちゃん(一岡怜奈さん)と出演の「UP-FRONT
CHANNEL Recommend #22」の一場面。

「UP-FRONT CHANNEL Recommend 」 10月9日配信 MC:嗣永桃子、一岡怜奈
ももち、10日に「声帯ポリープ」診断により、しばらく治療に専念の発表ありましたが、本人も会社も治療は慎重に対処するよう気を付けてほしいなと、私が心配したところでどうなるものでもないのですが、とにかく出来る限りのことはしてあげてほしいと思います。今年の初めにも高熱出した事があり、正直12年ろくに休み無しみたいな人なので、いろいろ蓄積している部分あるんじゃないかと気にかかります。
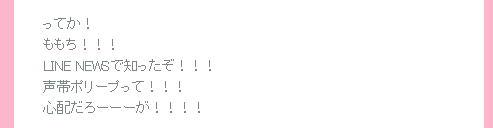
清水CAPがBlogでコメントしています。Berryzのお姉さん二人の関係は、この距離感が良いんですよね。
キャプテンの心遣いがうれしい。お互いがわかってるというのが伝わってきます。
![]()
2015年 10月 9日
赤裸赤裸赤裸的 KISS
何しろ今、ハロプロはめまぐるしく「物語」が動いていますので、ファンをやっていると、とにかく忙しいのですが、まずは一番の直近のNEWSとして、Juice=JuiceのTVドラマ「武道館」主演!は取り上げねばなりますまい。どれぐらいのスケールになるのか不明なので、まあ「ラーメン大好き小泉さん」規模(同じ時間枠?)になるというラインも範疇内に考えておかねばならないでしょうが、つんく♂が楽曲及びプロデュース担当をすることも決まり、話題性としてはけっこう期待できます。ヴォーカル・グループとしてのJuice=Juiceは最早申し分のない実力を備えており、本人たちも、広く一般に披露してあっと言わせて見せるぐらいの自信は既に持っていると思います。
フジテレビ系 2016年「土ドラ」枠にて放送予定
http://www.fujitv.co.jp/fujitv/news/pub_2015/i/151008-i183.html
クライマックス、武道館LIVEでフィクションと現実が重なる瞬間が訪れるのか..今からゾクゾクします。
楽しみです。
 朝井リョウ 『武道館』 (文藝春秋)
朝井リョウ 『武道館』 (文藝春秋)
突然Big Newsが入ってきて、早くも過去へ記憶は霞んでいってしまいそうですが、Juice=Juiceは先日、台湾・香港の初海外公演を敢行してきたばかりです。
当地で熱狂的ファンを迎え、香港では「暴君」団扇を振る(「暴君」とはメンバーの金澤朋子さんの“愛称(?)”の一つです。他にkntm、ローズクォーツなどの愛称があります。あくまでも2チャン界隈での話ですが)女子ヲタもいたりして、笑いに貪欲で、実にハロプロの現場らしいなぁという空気感が伝わってきて良かったです。

↑ Click Juice=Juice 香港公演の模様
Juice=Juiceのパフォーマンスの実力の高さに関してはこちらを見るだけでも容易にうかがい知れます。

↑Click Juice=Juice 「生まれたてのBabyLove」
このグループ自身、様々な物語を経てきており、(長い挫折期間を乗り越えてきた一人の少女、研修生たちの未来を背負わされてきた責任の重圧、メジャー・デビュー直前のメンバーの脱退など) 小説「武道館」のドラマ化に抜擢されるにこれほどふさわしいグループも無いと思います。
かつて「革命を起こさなければならない(自分たちが成功しないと後輩の研修生たちが続けてデビューできない)」という言葉を発して、悲愴感すら感じさせる空気感の中で泣いていた宮本佳林ちゃんにとっても、これは飛躍となる大きなチャンスなんじゃないかと思います。

↑ Click ハロプロ研修生内新ユニット、メンバーへ発表の瞬間。(2013年)
〈重苦しい空気の中での新ユニット発表。「革命」という言葉を放った
(時々ドキっとする言葉を使う佳林ちゃんさんです。カクメンとか、
言えてなかったりしてるし)宮本佳林さんは、14歳ながらハロプロの
オーディションに幾つも落選した経験を持ち、研修生の中では先輩的存在)

 Juice=Juice 「First Squeeze!」 (2015)
Juice=Juice 「First Squeeze!」 (2015)
アルバム新曲は、つんく♂作曲が無く、外部依頼作で構成されています。聴いた当初はハロプロらしさは薄めでJ-POPに寄せた?と個人的には思ったりもしましたが、Liveでこなしているうちに自分たちでハロプロらしい楽曲に引き寄せてしまっている感が出てきています。
リーダーの宮崎由加さんが、久し振りにつんくさんプロデユースで活動が出来ると知り、メンバーみんなで大喜びしたと語っていますが、ハロプロの子ってみんな、心底つんく♂が好きだなと、本気で思う。
![]()
2015年 10月 3日
さらに つばき!
ttps://www.youtube.com/watch?v=LZNsW4ffB5c

いやもう なにしろ とにかく、名曲! 名盤過ぎる! この仕上がり 信じられない!
ニュー・オーダーの心髄(抒情性、本当は違うのだが、むしろあえてベタにメランコリーと呼びたい。メランコリーではないのだがメランコリーと呼びたい)が完全に乗り移った楽曲。
「Blue Monday」に震えたあの衝撃を思い出しました。(ちなみに私、80年代の1曲を選べと言われたら、答えるのは「Blue Monday」です)
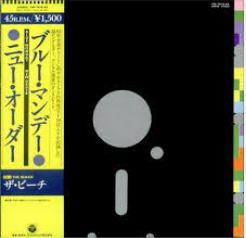

↑Click New Order 「Blue Monday」 (1983)
1点の曇りもない丁寧な作り。しかも歌謡曲としても完璧。
最後に「まんまんなかー」のリフレインが入るのですが、これを考案したのが誰なのかが気になります。
これ、ハロプロ的な決め手になっているので、私の想像では2015年の今にこのワザを繰り出せるのはハロプロしかいないと思う。一方、これが最初のアレンジの段階で出来ていたのだとすれば、恐らくハロプロとニュー・オーダー、ソフト・セルの根元(ロックンロールからブリティッシュ・ポップスの流れと日本歌謡曲の同時性)は同じだということなのだと思います。
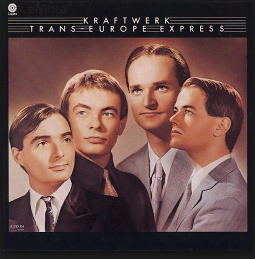

↑ Click Kraftwerk 「Trans-Europe Express] (1977)
あとは、さらに個人的な感想ですが、
このデビュー曲を聴いて、つばきファクトリーの特色というのは、浅倉樹々さんを中心に据えることで明確に出ると確信しました。6人が全く異なる役割を担っているという点で、つばきはBerryzに強烈に似ていますが、ベリの中心的存在である夏焼 雅さんに対し、浅倉さんが性格的には全然似ていなさそうなところが楽しみです。たぶん浅倉さんはどちらかといえば℃-ute的存在(矢島舞美的)なのではないかと思いますが、℃-uteが矢島さんに寄り添っていく方向で固まったのだとすれば、つばきは浅倉さんに無い部分を他のメンバーが埋めるというBerryz形式になると思います。
(ニコ動のつぶやきでヨーロッパ特急の名があがっていたこと以上に立花理佐の名があがっていたことに興奮しました。立花理佐はニュー・オーダー歌ってますからね。)
 ←Click 立花理佐 「リサの妖精伝説」 (1988)
←Click 立花理佐 「リサの妖精伝説」 (1988)
今週のワン・ショットはこちら。カントリー・ガールズの山木梨沙さんと「Green Room」 MCの徳永千奈美さん、夏焼 雅さんです。
いつか、嗣永桃子さんがゲストに来る日もやってくるのでしょうか?

10月1日 【GREEN ROOM#23】
![]()
2015年 9月 25日
研ぎ澄ます


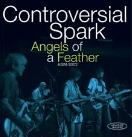
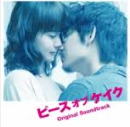
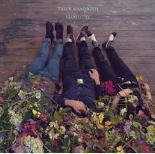
Flying
Saucer Attackの新譜(「instrumentals 2015」)が出る!というので驚きましたが、多少今風に打ち込みががんがん入ってくるのかなと思ったら、変わっていないどころかむしろ中期ぐらいの厳格な音響勝負に徹してきていて、さすがだと思いました。自分の中では95年の「Chorus」から97年の「New Lands」の頃が一番聴いた時期で、2000年に「Mirror」が出た時はちょっとリズムの方に興味が移り、ネオ?サイケデリア的な方向へ向かってしまうのかな?と、若干不満もあったのですが、アメリカのネオ・アシッド・フォークやネオ・ヒッピー的なシーンが収束するに従い、やっぱりあの流れはあまり実りがなかったんじゃないかなと思いましたし、帰ってきたなという感じで、私にとってはこの新譜はFlying Saucer Attackの前進だという判断です。余計な色付けが無くなり、理論とか考えずに、研ぎ澄ますことに集中していることが一番だなと思います。ジム・オルークやローレン・マザケイン・コナーズらがネオ・ヒッピー的なものとの間に1線を引いていたのも、研ぎ澄ます感覚の方が重要であり困難であると考えたからだと思うので。
結局、LOW(「One And Sixes」(2015))もそこに音楽の目的があったので、ある意味、理論の方向へ走る変化を拒み、自分たちの領域にとどまることを選んだバンドですが、それで現在まで継続しているというのは、メジャーなレコード会社(Sub Popをメジャーと言ってしまってはいけないかもしれませんが、世界レベルで展開出来ているレーベルとしてそれなりにセールスのプレッシャーは大きいと思います)に所属することを選択し、かつ生き残るという極めて困難な道のり(本人たちが折れてしまう可能性も含めて)をしのいできた音楽に対する思いの強さあればこそで、ファンとして敬服します。私はLunaが折れて失速していった現実を見たのが、こういうちょこちょこ書きたい事を書いているきっかけにもなっているので、本当に折れずにサバイバルするのってスゴイことだと思います。(実際、「Drums & Guns」(2007)の時にけっこう精神的な危機はあったし)
LOWも一貫して日本では大して評価されず、“良質なオルタナティヴ・バンドで平均以上”程度にしか扱われてきていないバンドだが、結局そういうのが今の日本の音楽シーンの在り方を形づくっている。
何しろバンドメンバーが5世代(年齢が、20代、30代、40代、50代、60代に分かれている)にまたがっているというControversial Spark(「Angels of a Feather」(2015)は、研ぎ澄ますというよりむしろ混沌をめざしているようなバンドかもしれない。今度出た新作のミニ・アルバムも5曲を5人のメンバー夫々が1曲づつ作曲しており、振り幅の大きさを意図的に望んで音楽づくりをしているのだけど、結果としては鈴木慶一本人の許容幅が大き過ぎるせいで、年齢ギャップを乗り越えて、研ぎ澄まされてしまっている。20代の女性が作った曲に対して、他のメンバーは容易に同じ地点まで降りていける。全然面白がっていっしょにやれるというのがあるので、アイデアが鈴木慶一本人にとっても自分から出てくるのが不思議だと思えるようなものが飛び出しているのではないかと想像される。例えば4曲目のKonoreさんが作曲した曲「キャスケット」など、konoreの世代で思いつかないリズムで出来上がったんじゃないかと思うし、鈴木慶一ら年上組もこのギターフレーズやコーラスをこのリズムに乗せようというアイデアは、自分たちだけでやっていたら出なかったのではないかと、聴いていて勝手に思ったりしました。世代間で研ぎ澄ました結果生まれた感覚で作り出されていると思います。
映画「ピース・オブ・ケイク」のサウンドトラック盤。音楽担当は大友良英で、高田 漣、近藤達郎、芳垣安洋、峯田和伸らが録音に参加しています。田口トモロヲ作品の音楽は大友良英がずっと担当しているようで、これで3作目らしいですが、私は田口作品のサントラを買ったのは初めてです。「あまちゃん」をやってからの大友良英は以前とは少し変わったというか、それまでは山下毅雄や伊福部昭、中村八大など、日本の音楽のジャイアント達を追いかける作業をしていたのが、いよいよ後を引き継ぐ段階に入ったという感じで、音楽的な幅が今まで以上に大きくなってきているのに注目していて、商業音楽にも余裕を持って関わってきているところが、俄然面白くなってきたと思っています。このサントラもアコースティック・ギターなどの少ない音数のシンプルな構成に、大胆にノイズすれすれ(というより、ノイズ!)のシンセ音を、曲構成としては異常な比重で組み込んでいて、それでいて雑食的な大衆音楽を匂わせるという、まさに「あまちゃん」以降のビッグ・バンド・サウンド(内容はシンプルなのに、何故かコンボ感が出る)が出現していて、大友良英自身の歴史を感じさせる長いスパンで構築されたアルバムになっていました。しかし、近藤達郎、芳垣安洋がいれば、何でも可能。不可能なことがないってくらい最強ですね。
あと、多部ちゃんが1曲、鼻歌を歌っています。
Trick Mammmothのアルバム「FLORISTRY」(2013)で驚くのは、どう聴いても出身が直ぐニュージーランドだとわかるくらい、どうしようもなくニュージーランドのサウンドであることです。
キウィーポップと称されるだんご化したジャングリーなビートと、自然に備わるとしか思えないアノラック的なアマチュアリズム。伝統としか考えようがない。普通ここまで徹底してニュージーランドからしか出てこないなんて有り得ないんですけど、他の国がやりたいと思わないからか? これってニュージーランドしかやっていない。その意味においてTrick Mammothは全く濁りがなく、研ぎ澄まされている。
良いのは、これが単にBatsやVerlaines、Chills、Cleanらのエピゴーネンにはなっていないこと。
このままで十分The
Batsの後継者として推せます。
 ←Click Trick Mammoth - "Baltimore" (Live in Dunedin)
←Click Trick Mammoth - "Baltimore" (Live in Dunedin)
最近の One
Shotはこちらです。
つばきファクトリーの新沼希空さん、撮影は須藤茉麻さんです。
さけるチーズを食べながら、ただ茉麻さんをガン見していたらしいのですが。
本当にもう、今、つばきがツボ。

9月20日 ttp://ameblo.jp/sudou-maasa-blog/entry-12075334108.html?frm_src=thumb_module
![]()
2015年 9月 20日
映画を探せ
少し前の記事ですが。『映画論叢 38号』に西村 潔監督のお蔵入りした映画、「夕映えに明日は消えた」(1973年制作)のことが載っていました。(許されざる者 「夕映えに明日は消えた」覚書 /小関太一)
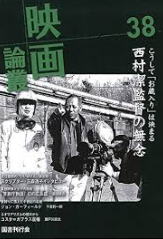 『映画論叢 38号』 (国書刊行会)
『映画論叢 38号』 (国書刊行会)
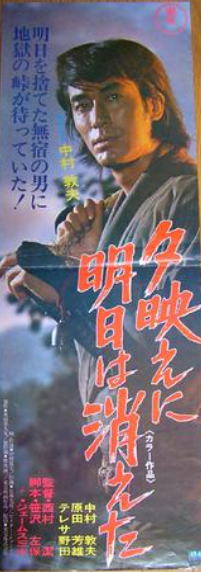
なぜお蔵入りになったのか? 放送コードに引っ掛かるような部分があったからというわけではないようなので、可能性としては今後、陽の目を見るチャンスも有りうるみたいですが、このお蔵入りがきっかけで西村監督が映画界から距離を置くようになったのかもしれないと考えると残念です。
1973年からTV版「日本沈没」の演出をし、TVの方が仕事の中心になっていきます。
1977年に「青年の樹」という三浦友和主演の作品で映画復帰していますが、実際のところ、西村監督はあまりちゃんとした評価を受けたことが無いように見受けられ、そのあたりが「夕映えは明日に消えた」がわけのわからない映画とプロデューサーに一刀両断されたという噂もあり、評価の無さから軽んじられたんじゃないかと疑いたくもなってくるのです。
西村監督の評価の分水嶺として決定的な役割を持つ作品だったのではないか?
そんな気もしてくるのですが...
ただ、「ヘアピン・サーカス」も「薔薇の標的」もそれなりにしか話題とならなかったことを考えれば、あの時代ではそもそも理解のしようがなかったということなのかもしれません。
ただ、今ならばむしろ、西村作品の特異さは明らかに際立っていることに気付いた人が出てきている状況にあると思われるため、発掘上映する価値は大いにあるのではないか?
映画界に新しい波が起こるのを私は期待しています!
![]()
2015年 9月 19日
英国音楽の王道 歩いてる?
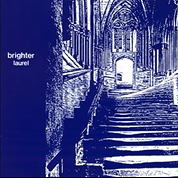
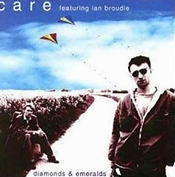


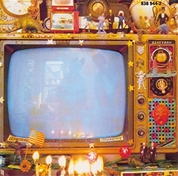
ちょっと新人のCDを買ってみたりもしたのですが、わざと外れになりそうなところを狙う癖(へき)が災いしてか、まあ、悪くはないんですけども、“これは拾い物”というところまではいかない、自分が悪いんですが、他に聴くものあっただろう? と、反省もしつつ、しかしまあ、昔からこういうことはやってるんで。
いいんですよ。 たまには聴くこともあるかもしれませんよ。決して駄目じゃないんですから。
いや、けっこう気に入ってます。
 Hooten Tennis Club 「Highest Point In Cliff Town」 (2015)
Hooten Tennis Club 「Highest Point In Cliff Town」 (2015) 
↑ Click
Borde Auxxx 「Only Fiction」 (2015) 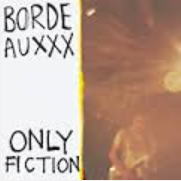
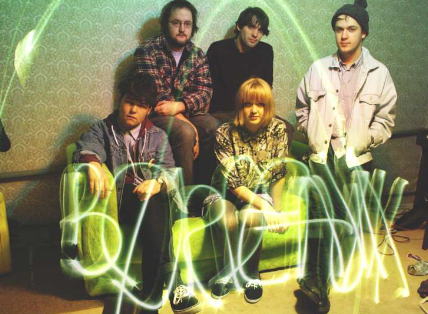
↑ Click
新しいものも聴きながら、それでふと思い出したように、というか、昔聴いてたものをYou Tubeで探したりして、聴いたりもします。
Brighter 「Laurel」 (1991) Brighter - "Summer Becomes Winter"
昔、私はSarah Recordsとかクリエイション・レーベルとかが嫌いで、殆どスルーしていましたが、Sarahの中では唯一、Brighterというバンドは好きで、CDも買いました。今聴くとSt. ChristopherやThe Field Mice、The Orchids、The Sea Urchins、The Wake、etc...それらに比べてBrighterだけが特別だったかというと、どれもそれなりに、だったかという気もしますが、当時はBrighterだけは違う!とか思って聴いていました。
Sarahの良さって、7inchのシングルを買い集める楽しさだったのかな?と、今頃しみじみ考えてみたりしますが、当時は自分の場合、7inchに特別思い入れをもなかったので、あまり楽しみ方がピンと来ていなかったのですね。 ただ、Brighterは、今聴いてもやっぱり良い。
Care 「Diamonds& Emeralds」 (コンピ 1997) Care - Whatever Possessed You (1984)
Ian
Broudieは好きなんですよ。Lightning Seedsでアルバム出した時も本当に良い曲ばかりだと思いました。作曲家としても好きだし、アレンジャーとしても打ち込みが中心だということが自分にはマイナスでも何でもなくて、天才だと思ってました。感覚としては紛れもなくネオ・アコだと認識していました。今聴いても私は古いとは思わないですね。今の若い人が聴いてどう思うかわかりませんが。
アコースティックという感覚が伝わるかなぁ?という気が... 生楽器をゴージャスに使う。ヴィンテージぽく芳醇な香りを放つ、良い音で鳴る...そういうのがアコースティック、というわけではないというのがポスト・パンクから発生するネオ・アコの定義なんです。
Max Eider 「The Best Kisser In The World」 (1987) Max Eider 'My Other Life'
マッカーシーとかジャズ・ブッチャーとかは今ひとつのめり込めませんでした。私からすればジャズ・ブッチャーは物足りなかった。何か、匂いがしない、という感じがありました。ジャズ・ブッチャーとかTV・パーソナリティーズなんかはかなり曲者のイメージでとらえられていましたが、私はそれほどのものかなぁ?と思っていました。ジャズ・ブッチャーのギタリストだったマックス・エイダーがソロ・アルバムを出して、評判になった時も、褒めすぎだろ?なんて気持ちでいて。モノクローム・セットの足元にも及ばぬ...なんて心情だったのかもしれません。
その後、カクテルズとかそれからアーチャー・プレヴィット、シー・アンド・ケイクなどアメリカ勢の“上手さが加わるアコースティック”(そう。意外とアメリカの方がアカデミックになるんですよね)に出会って、その頃にマックス・エイダーの感覚(ガボール・ザボを知ったのも大きかったかも)がやっと理解できるようになりました。
Blue Aeroplanes 「Swagger」 (1990) The Blue Aeroplanes - ... And Stones
また、ちょっと天邪鬼なんですが、私はジェイムスって苦手で、ブルー・エアロプレインズを聴いてました。「その違いは、何なんだ?」と聴かれると返事に窮するところもありますが、その後のイギリスのロック、ポップスの流れを考えると、ジェイムスが人気を博していったことは、やっぱり自分のイギリス離れにつながっています。これはやはり、“やってはいけないことをやる”の感覚の違いだと思う。ブルー・エアロプレインズやロドニー・アレンがもっと売れていれば....とは考えることがあります。
ただ、ビリー・ブラッグが居続けてくれたこともあって、ローラ・マーリングなんかが出てくる。ブルー・エアロプレインズの流れも生き続けているのは感じています。
何の事言ってるのかわからないかな? 全然説明にも何もなっていないかもしれませんが..
EAT 「Sell Me A God」 (1989) Eat-Tombstone
マンチェ・ブームの頃。これも私はマンチェ勢が好きではなくて。ストーン・ローゼスだけ聴いてました。ハッピー・マンデーズとか、インスパイラル・カーペッツとか嫌で嫌で。ハウス・オブ・ラヴとかもどこがいいのかわからなかった。私が注目していたのはEATでした。デヴューはけっこう華々しくて、大物の予感があった。アメリカのジャンクやグランジに拮抗する価値を持ったバンドはウェディング・プレゼントやスナップ・ドラゴンズやこのEATのようなバンドだと思っていました。当時はマイ・ブラッディ・バレンタインもかなり批判的にとらえていました。イギリスのインディーとしてとらえられるバンドよりも、むしろメジャー側から現れたみたいなとらえらえ方をしたジーザス・ジョーンズの方が何倍もマシぐらいに思っていました。
ところがEATはあっという間にしぼんでいく。結局イギリスの嫌な流れに飲み込まれてしまった。
そんな気もしています。
個人的には、EATは再発見する価値があるバンドなんじゃないかなと思っています。
![]()
2015年 9月 18日
ちゃま!
やたーっ やっと抹茶―ずのCDが買える。


http://www.ujimiyage.com/products/detail.php?product_id=1032
![]()
2015年 9月 18日
「迷ったら”ドスコイ!”に戻ればいいっていう」発想で作られたハロプロ楽曲
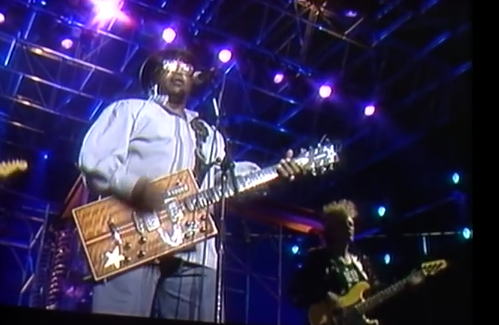
↑ Click Bo Diddley - 「Bo Diddley 」 どすさまじい格好よさ!
先週のハロー!プロジェクトの配信番組「MUSIC+」で、ディレクターの橋本 慎氏が編曲の菊谷知樹氏と、こぶしファクトリーの曲「ドスコイ! ケンキョにダイタン」について語っており、曲の取っ掛かりが“ドスコイ!”と“ボ・ディドリー”だったことが判明したわけですが、曲を作るときに「“ドスコイ!”と“ボ・ディドリー”で何が作れる?」というところから始まるという、相変わらずのハロプロの狂った発想で、最高だなっ!と思ったものの、「ドスコイ! ケンキョにダイタン」は実はそれほどボ・ディドリーを直接に引用したサウンドというわけではない。制作する側が、ボ・ディドリーから何を汲み取り、自分たちにどう取り込むのか。結局それはボ・ディドリーをどこまで理解しているかという教養が試されることにもなります。
それを考えながら、この曲をあらためて聴いてみると、“いや、まさに、本質的な部分のボ・ディドリーがちゃんと生きている”ということがわかります。

↑ Click こぶしファクトリー 「ドスコイ! ケンキョにダイタン」
(このグループにおけるノムさんのポジションが なにか絶妙な感じで好きです)
それでいて思い切り異化している部分もあるのです。オリジナルへの理解と、一気に飛躍する異化の狂気。
これも必ずしもボ・ディドリーのサウンドに極似してもおらず、むしろぱっと聴いたところでは気づかなかったりもしますが、紛れもなくボ・ディドリーでもあるというニック・ロウの「I Love The Sound Of Breaking Glass」をふと思い出したりしました。POPへと異化する、これがニック・ロウの最も異常な才能なのであって、元からかけ離れているとともに本質はがっちりつかんでいるところに感動します。
「ドスコイ! ケンキョにダイタン」は考え方としてはニック・ロウと同じだと思うのです。

↑ Click Nick Lowe 「Breaking Glass」 (1978)
![]()
2015年 9月 14日
「僕のロック哲学から外れた音楽的な妥協は許さない」の発想で作られてきたハロプロ楽曲
つんくの「ロックやで」のこだわりの部分においては、さておき、として。
105ページからある、ハロプロで作る音楽に対して、
「しかし、どんな状態になってもサウンド面に関しては、一切妥協をしなかった。詞、曲、アレンジ、レコーディングにオーバーダビング、トラックダウン、マスタリングなど全てに、こだわり続けてきた。
それはロックの基本である。
コードがぶつかっても、かっこよければOKするが、僕のロック哲学から外れた音楽的な妥協は許さない。
だかtら、僕はアイドルは作らない(結果、それを世間で言うアイドルが歌うんだとしても)。
それだけは徹底してやってきた。
(中略)
そして、このこだわりを邪魔することは誰であっても許さない。
そういう気持ちで音楽と向き合っている」
と、語っている語気の荒さは注目だと思いました。
つんくにとってのロックの定義とは何なのか? というのはありますが、音楽を作るうえで自分がおかしいと思った部分を徹底して排除する決意というのは、実際ハロプロの楽曲に通底しているものです。
つんくがそこに一番こだわっている(いろいろ足していく発想以上に、やってはいけないことに対して厳しいということ)のが、今回の手記で、はっきりと明記されているのを見ることが出来たのは、ハロプロを聴いている人間にとっては、大きい収穫でした。
NHKの番組(「NEXT 未来のために “一回生”つんく♂ 絶望からの再出発」)も見ましたが、今年に入っての仕事で、湯川れい子さんからの希望で、子守歌を作曲することになり、事務所で湯川さん(作詞)と、歌うクミコさん、つんく♂の3人が一同に会して、打ち合わせを行っているシーンを興味深く見ました。
作曲作業がシステマティックになっている歌謡曲の産業界隈では、案外作詞家と作曲家が顔を合わせることもなく作業が進んでいくみたいな想像をしていたので、一瞬、珍しい光景だな、なんて勝手に思ってしまいましたが、湯川さん(最近何かとメッセージ的な発言があって、ロックしてんなぁという感じの湯川さんです)とつんく♂が曲の打ち合わせをしている場の空気感が、「いいな」と思いました。

つんく♂ 『だから、生きる』 (新潮社)
![]()
2015年 9月 11日
ベリメン 近況

「GREEN ROOM #19」 9月3日配信 MC:徳永千奈美、夏焼 雅
ついにハロプロ・アドヴァイザー 清水佐紀さんがハロプロ研修生の楽曲を振付け&指導か。 (前田こころさんを指導するCAP)
ダンスの実力はハロプロ歴代でトップと言われる清水CAPの直接指導なんて、研修生は嬉しいだろうなぁ。
(それにしてもCAPは可愛い過ぎる)


「GREEN ROOM #16」 8月13日配信 MC:徳永千奈美、夏焼 雅
ちょっと前になりますが、
研修生が可愛い過ぎて、大ウケしている、千奈美とみやびん。
そして,須藤茉麻さんは、

つばきファクトリーの面々が可愛いくてしかたないらしい。

「UP-FRONT CHANNEL Recommend 」 9月11日配信 MC:嗣永桃子、加賀 楓
一方、嗣永桃子さんは、研修生のかえでぃを相手に、得意の微妙な空気をかまして威嚇。
しかし後輩はベスト・リアクションでももち先輩をいなした。
ももち先輩は微妙な空気の中にいるのが実に居心地良さそう。

「The Girls Live」 8月24日放送(東海地方)
夏焼先輩はこぶしファクトリーのステージ衣装をコーディネイト。
気配りの出来る優しい先輩。 ただ、とにかく自由。
では、熊井ちゃんはといえば、

熊井ちゃんなのでした。
![]()
2015年 9月 5日
ポリフォニー
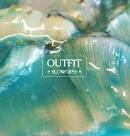
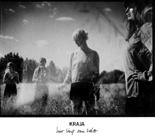
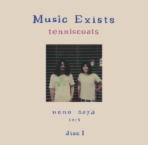

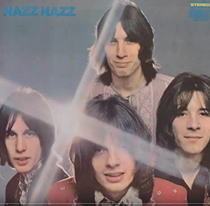
またけっこういろいろなタイプの音楽を聴きたいなと思うような時期が自分の中でやってきまして、やっぱり、音楽っていいなぁと思います。
前にも書いたことがあるんですけど、継続って、重要だなと思う。私は音楽を点(その時その時の最新)よりも線(歴史のつながり)で感じて聴いているのですが、それを続けてきて考えたことが随分あります。聴いてるだけの人間でもそれは決して楽なばかりではなくて、飽きることだってあるんです。それを無理して聴き続けることもある。だけどそれは後で案外無駄ではなかったことがわかるんです。
OUTFITの新譜「SLOWNESS」(2015)は楽しみにしていたアルバムでした。このリヴァプール出身の5人組。日本では殆ど話題になっていませんが、確かに人気沸騰するようなタイプの音楽ではありませんけども、このグループに気付いている筈のタイプの音楽好きの人達の耳にも届いていないという印象を受けます。不幸にして売れない実力あるミュージシャンは勿論過去にも幾らでもいましたが、こと洋楽に関して言うと、現在の日本の音楽ジャーナリズムは取りこぼしが多過ぎます!
厳しい言い方をさせてもらえば、今の音楽ジャーナリズムでは例えば過去にジャーナリズムや少数のリスナーによって成しえた“プリファヴ・スプラウトを救いきるような役割”を果たすことは出来ないと思う。
残念ながらしつこくOUTFITの新譜が良い!と、少数派が何しろ頑張って粘るしかない。
そういうことをしっかりやっているライターの方が少ない。「30年たったけど、まだ聴いているよ」という音楽について、もっと考えてもらいたい。

↑ Click Outfit "New Air"(2015)
KRAJA(クラヤ)はスウェーデン出身、4人組のアカペラ・コーラス・グループ。新譜の「離れていても(HUR LANGT SOM HELST)」(2015)は4枚目のアルバムだそうです。二十歳前の頃からもう10年に渡って活動しているそうですが初めて聴きました。ポリフォニー形式という多声音楽で、さらに不協和音やズレも音楽として有効にしていく。私たちの世代だとブルガリアン・ヴォイスを4ADのレーベルから出ていたのに誘われて、聴いてこの形式にはまった人がけっこういたと思います。新しいスタイルというわけではなくて、私なんかにはフリー・デザインを聴いた時の衝撃(知ったのはブルガリアン・ヴォイスよりも後でしたが)も同様な、多層的ではみ出した部分すら包括する刺激的な音楽でした。
Tennis Coatsも新譜です。「Music Exists (disc1)」(2015)は久し振りに二人だけで録音したアルバム。残響音に対して意識的なバンドなので、案外、音は厚いです。どんどんシンプルな方向へ枯れていく(?)のかと思いきや、そのへんは裏切ってきてくれます。ある意味、ビーチ・ボーイズ的。日本にいてくれて本当に有り難いバンド(二人だけど)。ビーチ・ボーイズって本当はこういうことだよ、と言いたくなりますが、“モンド”の感覚を掴めないと、この理屈はちょっとわからないかもしれない。
「海のトリトン オリジナル・サウンドトラック」(2015)は、何と1979年にLPで発表(録音は1972年!)されてから未CD化だったという36年ぶりにしての初CDである。というより、自分には「トリトン」が1972年の放送だったことが驚きだった。勿論リアルタイムで見ているが(その後も夏休みなどにそれこそ飽きるほど再放送にもつきあった)、小学校2年生で見ていたのか。音楽は鈴木宏昌が担当。演奏していたのは、鈴木宏昌、江藤 勲、杉本喜代志、日野元彦、石川 昌などJAZZ界の錚々たる面々だが、音楽的にはJAZZにとどまらない幅広さで、時にはフランク・ザッパみたいな、突き抜けたJAZZロックみたいな曲もある。めちゃくちゃ面白い。挿入曲にはかぐや姫(須藤リカ、南こうせつとかぐや姫)の曲もある。「神田川」(1973)の前でした。
You TubeのFull Albumシリーズでは、これは有名なバンドですが、とトッド・ラングレンの在籍したNAZZのアルバム「NAZZ NAZZ」(1969)を久し振りに聴いてます。昔ひととおりLP買って聴きましたが、今は手元にありません(そういえばトッド・ラングレンも殆ど手離し、今はBESTとユートピアの「Oblivion」しか持ってません。またいずれ買い直したりすることにはなるでしょうが...)。
NAZZみたいなPOPロックの形態は、時代時代に存在して、今もそれこそたくさんいるし、それぞれ時代のビートやリフやメロディがあって、今の人からすればNAZZは割と比較しやすくて、なおかつ容易に古臭いで片づけてしまえる音楽かもしれませんが、もう自分の場合、そういう時代のモードみたいなものは評価基準からは消えてしまいまして、むしろNAZZみたいな音は、“今出せるバンドがいないんだから、今も有効”という考え方をするようになりました。で、当時聴いても最高だったろうし、今聴いても最高!
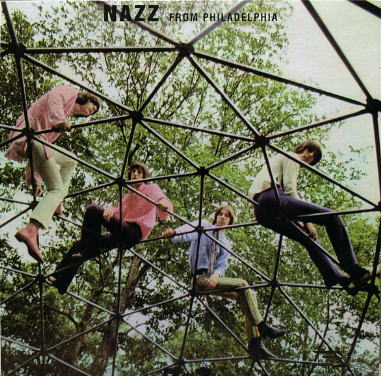 「NAZZ FROM PHILADELPHIA 」
「NAZZ FROM PHILADELPHIA 」
このジャケット・デザイン好き NAZZのOut Take集2枚組
![]()
2015年 8月 29日
つばき
あやちょがあやちょすぎる件 8月25日
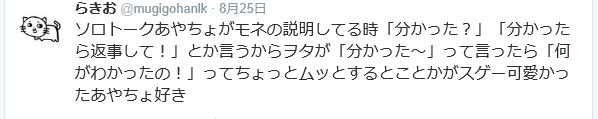
って、おかしいだろ! 8月20日
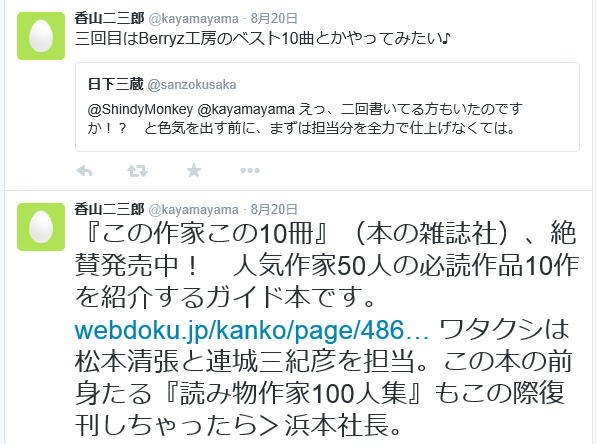
やっぱソフト・セル良いな、ていうか、当時聴いてたより今聴いた方がより深みが増しているように感じる。
つばきファクトリーはこの路線進めてほしいなぁ。歌謡曲で絶対やれると思うし、今、ここを攻めるのって意味があることのような気がする。つばきがやったら恰好いいだろうな。
この反復の感覚。 ハロプロは得意の筈。

↑Click Soft Cell - Soul Inside (1983)

つばきファクトリー
 つばきファクトリー 「青春まんまんなか!」9月6日 生タマゴShow!にて会場限定販売
つばきファクトリー 「青春まんまんなか!」9月6日 生タマゴShow!にて会場限定販売
(当分は会場限定でしか購入できませんが、インディー・デビュー・シングル出ます)
おっとその前に、水曜日にこぶしのメジャー・デビュー・シングルが出ます。ただ、こちらは曲も期待ながら、とにかく早いとこコントとかクイズ、ゲームをやる番組作ってほしい。(俺の心の中の)ハーポ・チコのマルクス兄弟(たぐれなコンビ)の開花が見たい。

こぶしファクトリー 「ドスコイ! ケンキョにダイタン/ラーメン大好き小泉さんの唄/念には念(念入りVer.)」 9月2日発売
(そうそう、「ドスコイ!・・・」の録音にはたいせいさんに加えて、Berryz工房を担当していた山尾正人さんも参加してましたね!)


![]()
2015年 8月 28日
はぁ〜 HAPPINESS 幸福歓迎!

2015-08-22 あなたに出会えた♡ 茉麻
ttp://ameblo.jp/sudou-maasa-blog/entry-12064669862.html?frm_src=thumb_module

2015-08-27 hello! 佐紀
ttp://ameblo.jp/shimizu--saki/entry-12064965721.html


![]()
2015年 8月 23日
つばき
今週は One Shot のみ とりあえず

ハロプロ・アドヴァイザー 清水佐紀さんと、つばきファクトリーの面々。
もう今や、つばきに完全にはまってます。
パフォーマンスはdailymotionさんに動画がUPされてますので、ぜひ一見を。「青春まんまんなか」の衝撃に打たれていただきたい。「17才」、「ジリリキテル」のカヴァーも素晴らしい。
とにかく「青春まんまんなか」のアレンジは今年最高の完成度だと思う。ア・サーティン・レイシオや808 stateeを聴いた時の感動に近いものがありました。さらにはソフト・セルのデカダンと打ち込みの狂気が加わって振り切れているところに女性Voが乗ってアコースティック感が出るという最高の仕上がり。
![]()
2015年 8月 22日
ガレージィ〜
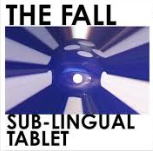
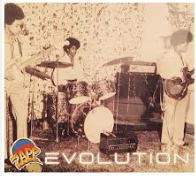
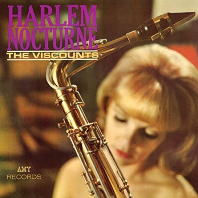
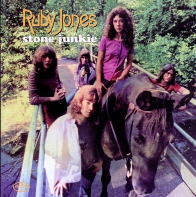
The
Fallの新譜「SUB-LINGUAL TABLET」(2015)は国内盤も出たのですが、輸入盤に帯が付いただけで歌詞カードもライナーも無しという、何の意味があると思ってこういうことをしているのか(ろくに商売になると思えないし、思い入れも無いって事ですよね)、謎です。 ただ実際店頭では輸入盤が並ばなくなっており、国内盤にしないと流通しなくなっているのか? まあ、CD自体、買ってる時代じゃないと言われればそうなんでしょうが... アメリカのAmazonなんかもうCDよりMP3の方が上位で表示されてくるし。
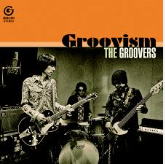 The Groovers 「Groovism」 (2015) ちょっと期待してた音と違ってた
The Groovers 「Groovism」 (2015) ちょっと期待してた音と違ってた
今のスタジオ録音技術ではツルツルキラキラでラウド感も十分なRockサウンドを作るのは比較的簡単なのではないか?と、この前買ったGROOVERSの新作アルバム「Groovism」(2015)(Groovers初めて買いました)を聴いて、けっこう違和感を感じましたが(あ、Grooversって意外と2000年代のRockバンド然とした音出せるのねとか思いました)、逆にFallは先端の機材の音(打ち込みなども)を使用しているのに、この“ささくれだった、落ち着きとまとまりのなさ”は何なのかと、どうやったらこういう音で録音が出来るのかと不思議になります。ツルツルという表現を一切受け付けないサウンド。 Fallを聴けば原点に戻れます。マーク・E・スミスのVoもコンディションが上がっている気がする。
ZAPPは変な新作(「EVOLUTION」(2015))が出たんですよ。イントロで日本語のアナウンスが流れるという。このアルバムを作るのに50年近くの歳月が掛かっている(50年前の録音が使用されている?)と言ってるのですが、どうやらロジャー・トラウトマン(1951-1999)15歳の時の録音曲がボーナスで付いているということで、ZAPP自体13年ぶりの新作で、まだ止めてなかったんだぐらいの感覚ですが、聴けばやっぱり、トーキングBOX健在で、唯一無二なんだなと感慨深く思いました。しかもそのトーキングBOXの声が、ちょっと、やっぱり、イカレ具合がとび抜けてる。ブーツィ・コリンズも1曲参加。
「ハーレム・ノクターン」というと、私は初めて演奏者を意識して聴いたのはラウンジ・リザーズが最初なのですが、けっこう好きで、この曲が入っているアルバムを見つけると、つい買ってしまったりすることがあります。このヴィスカウンツ「ハーレム・ノクターン」(1965)も最近見つけて、買ってみたら当たりでした。
あとはYou TubeでFull Albumで音源がUPされているのをちょこちょこと聴いています。Ruby Jonesというバンドも全く知らないバンドで、1971年に唯一のアルバム「Ruby Jones」を発表しています。アメリカのバンド。女性Vo:Ruby Starrをフューチャーしていて、この人はジャニス・ジョプリンばりのシャウト系の歌手で、その後ソロや他のバンドで活躍したようです。Ruby Jonesはかなりブラス演奏を多用していて、ブラッド・スウェット&ティアーズやシカゴが流行った頃の影響で出てきたバンドだったのかもしれません。アメリカの泡沫バンドの一つということになってしまうのかもしれませんが、クォリティーはめっちゃ高いっス。類型的ってこともなく、ちゃんと個性もあって、面白い。 例えば日本では名盤発掘隊企画なんかでコールド・ブラッドみたいなジャニス系歌手を擁したバンドで、復刻されて知名度あげたケースなどありましたが、コールド・ブラッド同様にRuby Jonesを発掘紹介したとしても、十分話題性のあるバンドだと思います。フルートも効果的に鳴ってて、この組み合わせにはちょっと時代も感じるけど、私は好きです。
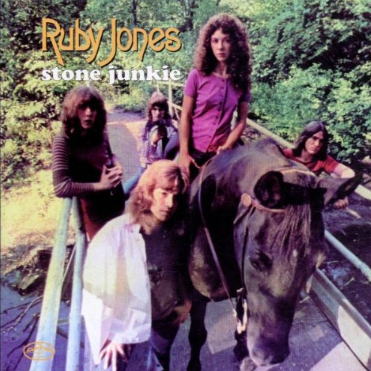 Ruby Jones 「Ruby Jones」 (1971)
Ruby Jones 「Ruby Jones」 (1971)
(かなりブラス隊が強力です)
![]()
2015年 8月 15日
うん、やっぱりソフト・セルでアコースティック感 出せると思う。 つばきに合う
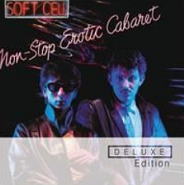
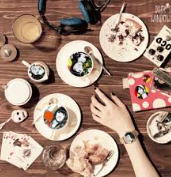
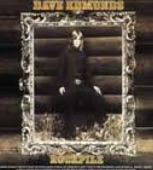
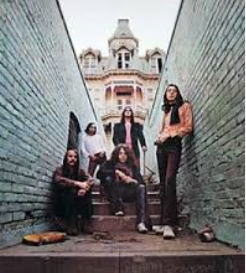
棚からソフト・セル引っ張り出してきて聴いてます。「Non-Stop Erotic Cabaret」(81)だけ何故か持ってました。たぶん「Chips on My Shoulder」が気紛れに聴きたくなったからじゃないかと思うのですが。やっぱり良いですね。「Memorabilia」みたいな曲を聴くと全然古びていないというか、ソウルを感じるという点で本物をつかんでいる音楽は違う、いつまでも本物のままだというのを感じました。流行り廃(すた)りとかにソフト・セルは関係ないんだなということがわかりました。
学生の頃、こんな曲を聴いて喜んでいたんだから、ハロプロをすんなり受け入れてしまった現在の状態もむべなるかな。
 Drop’s Vo、Gの中野ミホさん
Drop’s Vo、Gの中野ミホさん
日本のではDROP’Sの新譜「WINDOW」(2015)をよく聴いています。他にもいろいろ聴いていますが、また機会があれば書いていきたいと思います。DROP’Sは少し生真面目な感じがきのこ帝国と通じるものを感じますね。結局その生真面目さが自分は好きなんじゃないかと思いますが..
で、どういうわけかまたふらっとデイヴ・エドモンズが聴きたくなり、「Rockpile」(72)を。デイヴ・エドモンズは10年に1回ぐらい、妙に聴きたくなる時期が来るんですよね。この「Rockpile」はエドモンズのファースト・ソロアルバムで、ボブ・ディランの曲をカヴァーしたり、スライド・ギターをフューチャー(B.J.コール)したりとややザ・バンドあたりのサウンドも意識していた時期なのかな?と思う、この人の作品の中では異色な方なのですが、やっぱり「The Promised Land」なんかが聴こえてくると気分があがります。ギターで元エーメン・コーナーのアンディ・フェアウェザーロウが参加。
あと、これはCDは持っていないのですが、偶然目にしてYou Tubeで聴いてます。 Crabby Appleton。
元ミレニアムのMichael Fennellyが在籍していたバンドということで気になってしまいました。全く知らなかったバンドですが、70、71年に2枚のアルバムを発表しています。ひょっとしてBig Starみたいな音楽をじゃないかと期待したりもしました。ま、実際にはキーボードをけっこう多様したグルーヴィーなサイケ・ロックといった風でしたが、嫌いじゃないです。60年代後半から70年頃にかけて、アメリカにはこういう無名なサイケ・ロック・バンドがわんさかいるんだろうなと思うし、事実You Tubeには関連で同傾向の知らないバンドが次々出てきましたが、ちょろちょろ聴いてみたら、どれも悪くなかったです。アルバム1枚分まるごとUPされてたりするんで、その気になれば聴き邦題。レコードがうん万円するなんてバンドも音だけならば簡単に見つかるかもしれません。
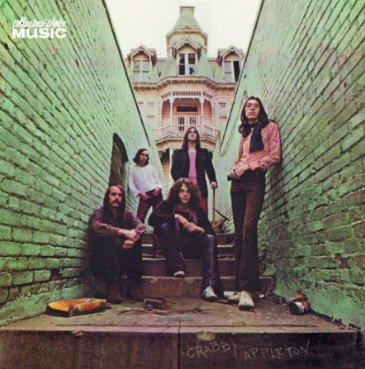 Crabby Appleton「Crabby Appleton」(1970)
Crabby Appleton「Crabby Appleton」(1970)
(ジャケットがけっこうそそる)
![]()
2015年 8月 14日
つばきファクトリー スゴイ!ヤバイ

ハロ☆トラ店長 『道重さゆみという生き方 モーニング娘。史上最強のリーダーと呼ばれるまで』(メトロポリタン新書)
名著。
新書というスケールにここまで余すところなく道重モーニング娘。の必要な部分すべてを盛り込む技術、上手さに唸りました。自分でもそれなりに“道重伝説”について語りたい言葉はたくさん持っていたのですが、ここまで読み物として完成度の高いものとして形に出来るかと考えると到底不可能です。
筆者の方は年齢も自分とほぼ同じだし、ファンとしての関わり具合(プラチナ期でのブランクがあった後の、9期デビュー直前での再会)も近く(しかも、お顔もマツコの番組で確認済み)、必ずしもモーニング娘。の何もかもを知るという古参者でもなくて、執筆するにはハンデがなかったわけではないと思うのですが、結果として、道重さゆみを語るのに最適な接し方を出来たんじゃないかなという気もします。道重の12年間を全てリアルタイムで知っているとかえって整理しにくくなる部分もあったのではないかという気がするのです。例えば、道重にとって方向を決めるのに決定的な影響を及ぼした高橋 愛については、もっとヴォリュームのある単行本のレベルで突き詰めていくということでもいいのではないか? この新書では適度に割愛するという選択も絶妙に行われていたと思いました。それもやはり、ハロプロへの愛の深さ故の的確な読解・判断力が成せる業だったのかもしれません。
道重さゆみが、自分の内面を存分にさらけ出してきた人だったという指摘は読むまで考えたことのないフレーズだったのでハッとしました。言われてみれば確かに。それがファンへの“絶対的な信頼感”から来ているという言葉には大納得ですし、あらためて感動しました。道重さゆみほどファンを無条件に愛したアイドルは稀れだと思います。
道重さゆみの卒業LIVEについては、残念ながら記録として残ったDVD作品には十分ドクメンタリーな部分が活写されているとは言いがたい。作品としてはそれで正しいとは思うのですが、恐らく映像作品としてならば、有料放送で生中継された番組映像の方が優れたものになっているでしょう。現場にいた人でないとなかなかわかりづらい道重の足の故障と後輩たちの対応部分について、他の章よりも長めで詳細に書いてくれているところも、かなり重要な部分なのでありがたいと思いました。譜久村 聖が高橋 愛の時代にあった似たような経験を思い出したという後の発表は私も読みましたが、あらためて需要なポイントである高橋 愛からのバトンという“物語の肝”となる部分を最上の形で表現されているのに共感いたします。
(そうやって考えると、ミキティーの離脱(笑)って、モーニング娘。の最大の幸運を呼び込んだミラクルだったのかもしれない)
高橋 愛からのバトンという大きな軸とともに忘れてはならないのは、道重さゆみの決意の部分だと思います。バラエティー番組に出演して、モーニング娘。が想像以上に世間から忘れ去られている事実に直面して愕然とし、それ以後、「全てをモーニング娘。にささげる」と決意するに至るこの過程の部分。この本に書かれていない部分で、唯一付け足しておいて欲しいと思うのが、新垣里沙の卒業が決まり、次期リーダーが誰になるかが話題となる中で、「自分をリーダーにしてくれるのなら、できるだけ早い段階で言って欲しい。いろいろ準備しなければならないので」と語っていたことです(ラジオで言っていたと思う)。私はそれがもう道重のラストスパートが始まる決意だったというような気がして仕方がありません。幾らなんでも“全てを捧げる”のをいつまでも続けられるものではない。彼女はもうこの時点でスパートを掛けていたんじゃないかなという気がします。
私も当時見て、一番衝撃を受けた番組「黄金伝説」での道重さゆみの一万円生活は、その境地に至る、彼女にとっても重要なやり遂げた仕事で、この番組について見出しを上げて書いているのにも深く共感いたします。あのプログラムは道重さゆみの魅力が全て出ていて圧巻でした。私もあの番組を見て、道重さゆみってこんな人だったのかと驚き、しかもその時点のモーニング娘。を初めて見て、知らん子ばっかりになっとるやん!?と気づいた一人です。
8月14日 Juice=Juice 高木紗友希
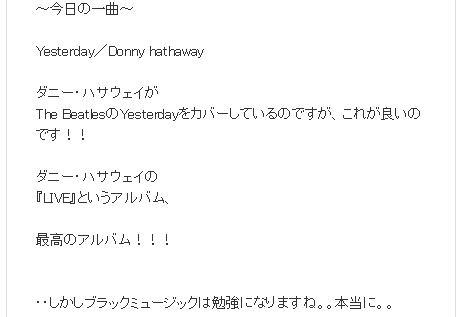
アイドルがダニー・ハサウェイまで行っちゃうのはどうなのか?とか思ったりもしつつ、紗友希ちゃんは楽しみだなと思う。
Juice=Juiceは今までのハロプロに無いグループになれそう。スタッフとしてもここは伸ばすべきでしょう。



ベリメン 清水佐紀さんの近況。研修生のダンス・レッスン見たり、イベントの選抜選考に加わったりと若手育成に頑張ってます。
左は吉澤ひとみさんのblogで報告されてましたし、右は「Green Room」の映像。ハロプロって繋がっていくんだよねぇ。

つばきファクトリーの「青春まんまんなか!」が完全にツボに入ってしまい、もうこればっかり!見てます。
どこがいいのか?といったら、とにかくヤバイ匂いがぷんぷんする。いろんな意味で、これはたいへんそうだぞと思いました。(80年代B級アイドル・グループの霊が憑りついている感もあり)
正直ここまで一人一人のカラーが立って出てくるとは思いませんでした。ハロプロの中でもおとなしめの子が集まったと思われていたし、本人たちも自覚していたぐらいだったのですが、おとなしいにはおとなしいなりの個性がある。浅倉さんのきっとした表情を見た時に打たれました。谷本さんはそこに立っていることの違和感とともにそこに立つ決意を感じましたし、山岸さんと希空は既に何かをしょって立っている。まばたき一つしないんじゃないかという秘めているものの怖さを感じました。(ビジュアル的にこの二人は対照的な面があるのですが、出てくる雰囲気は非常に似ている) 次にきしもん(ゆめの)と小片さんが並んで立った時、いや、なんかこれ、すごいメンツになってるじゃん!と思いました。ずっと笑っていても許されるであろうきしもんと、対極的に表情の硬さから美しさが出る小片さんが並んだのを見た時に、つばきファクトリーが本気で好きになりました。
このグループはテクノばっきばきで通して欲しいです。おそらくテクノを突き詰めるほどにアコースティック感が出てくるグループだと思います。ソフト・セルやアソシエイツの名前を出したくなったのはそういう印象から。さわやかな柔らかいテクノを作ってもチャイナ・クライシスやイレイジャーになるような感覚。
小片さんがこれほど必要不可欠的に生きてくるグループが出来たというのが嬉しかったですし、とにかくパフォーマンスする時の浅倉さんは要注目。きしもんのハロプロらしい笑顔ににんまりしますし、谷本さんをできるだけ自由にしてあげたい。これをきっと山岸・新沼二人でコントロールしながら支えてくれるのではないかなという気がします。
今週のSHOTは、これかな 真野恵里菜さんと嗣永桃子さん (真野ちゃんはタイでLIVEするそうです!)

8月15日、タイで放送される情報番組「Japan in Motion」(TBS新広島制作)に出演する二人
(仲良しの真野ちゃんと一緒にいるときのももちは表情もちょっと違うよね。 小指は安定の小指)
![]()
2015年 8月 13日
近江八幡 水郷めぐり
「十兵衛暗殺剣」(1964年 日)倉田 準二 (録画)
先日、会社の仲間とちょっと日帰り旅行に行きまして、滋賀県近江の方に行ったのですが、琵琶湖の水郷巡りをするというので、ふと、少し前に見た時代劇の「十兵衛暗殺剣」を思い出したのですが、本当に偶然で、少し前に見たばかりだなぁと思ったわけですが、あの映画に出てきた葦のしげった沼地のような風景を見ることがもしかしたらできるかもしれないと思ったのが、がっつりと葦で挟まれた水路を縫っていくような水郷めぐりで、間近にあの映画のロケ地を見たような気分になって、けっこう気分があがりました。


その後、サイトで時代劇についていろいろ著作も出している春日太一氏(ベリヲタです)が「十兵衛暗殺剣」の解説をしている動画を発見して見ていたら、この人も実際にロケ地が見たくて水郷巡りしたことがあるそうで(春日氏は偶然ではなく意志をもって行かれてるわけですが)、で、近江八幡と言っているので、えっ、まさに自分の行ったところじゃんと思い、そういえば映画で「近江八幡」と言っていた気もするなぁと今更に思い出し、ぼんやり見てんなあ自分、とか反省したりも致しました。
しかし、「十兵衛暗殺剣」に魅せられた人ならば、本当に実際に見たくなる風景だと思います。この映画はロケ地を存分に生かして、ここでしか作ることが出来ないと思うほどロケーションがまず圧倒的なんですね。

この「十兵衛暗殺剣」は集団抗争時代劇(「十一人の侍」、「十三人の刺客」など)の傑作の1本とされ、時代劇ファンの間では有名な作品なのですが、監督がいわゆる映画批評などで語られる巨匠(たとえば工藤栄一や三隅研次、森 一生、池広一夫など)ではなく、主演も近衛十四郎ですから、知識から過去の作品を辿って行こうとすると見落としてしまいがちな面があると思います。倉田準二は時代劇監督としては一定の評価を持っている監督ですし、近衛十四郎は十分大スターなんですけど、今の若い人ではなかなかここに行き着くのは簡単ではないという気がします。 ただ、一方で、今むしろ、30年前よりも出会い易いのではとも思うのです。時代劇に対する評価自体が以前とは変わってきているという気がしていて、案外、監督にこだわるという考え方がやや無効化してきているのではないかと思っているのです。たとえば春日太一氏が五社英雄を取り上げるような作業が現在行われているのは、30年前、人気の五社英雄をこき下ろす空気が映画批評のある部分でけっこう大きな影響力を持っていた時代なんかと比べ、明らかに見方が変わってきていると思うのです。
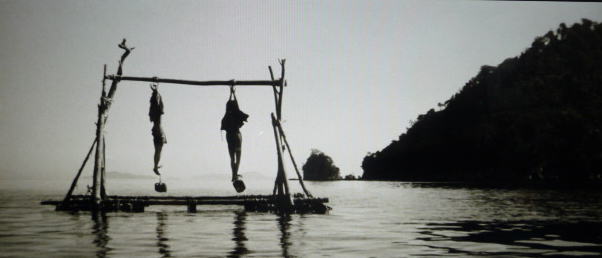

まず、近衛十四郎について。実はこの俳優については、今まであまり語られてこなかったと私は思います。ただ非常に独特なポジション(何となくですが、西部劇におけるランドルフ・スコット、オーディ・マーフィのような有名は有名なんですが、いわゆる名画にあまり出演していないスター)で、印象の強いキャラクターを演じており、本来ならばもっと注目をあびていてしかるべき存在なんじゃないかと思います。その意味で、柳生十兵衛だというのに、剣も折られ、武器を失い、素手でかまえて情けない形相で悲鳴まであげてしまう、そんな十兵衛ありえないというような役柄もこなしながら、画的にはやはりびしっと時代劇役者の魅せる姿勢と型、色気を出して見せてくれるところが、さすがです。


相手は大友柳太朗で、この映画では普通の定寸刀より短い「小太刀」を操り、柳生の門下を次々と斬り倒します。この刀の短さを強調するため、両腕を広げて構える姿勢が幕屋大休(大友)のスタイルです。刀が長いと様にならないポーズですが、通常の刀で対峙する相手に対し、短い剣で向かう幕屋大休が両腕を広げると、刀の短さがハンデキャップ感を与えながらも大友柳太朗だからこその姿勢の美しさで、むしろ剣の達人らしさが立ち上がってくるのです。こういう時代劇ならではの魅力を役者の動きから引き出す演出が見事です。たとえば相手を斬った時に大量の血が大休の足に掛かり、血のぬめりで滑るのを避けるために下駄を脱ぐシーンなども全く理由説明的なカットをはさまず、状況として当然の所作として動作をおさめるだけという編集の仕方などもかっこいい。
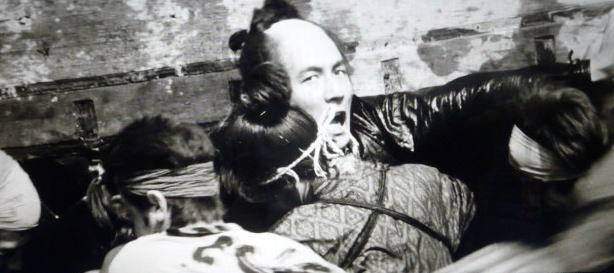

予算はそれほど掛かっていないと思われますが、幕屋大休の本拠である近江の屋敷を、琵琶湖の湖賊(湖における海賊、山賊)の女首領(なぜか女で若い)が訪れるシーンなど、廊下を歩いてくるシーンだけでけっこうスケール感を出しており、美術も素晴らしい。この湖賊という設定(実在したらしい)を存分に生かしていて、集団で柳生十兵衛以下、柳生一門の先鋭部隊に水面下から一気に襲い掛かるシーンはまさに名場面で、絶望的におぞましい(ジョン・フォードの「アパッチ砦」でヘンリー・フォンダが襲撃されるシーンのような)。
見どころ満載です。
シリアスなシーンばかりかというと、意外にちょっとユーモラスな場面もあって、河原崎長一郎が柳生門下の出来の悪い坊ちゃんあがりみたいな若造として出ていて、何の役にも立たない存在のようでいて、残念な結果ばかりを残しながら、最後にそれなりに貢献するんですけど、すごく河原崎長一郎らしく(ちょっと鈴木慶一に似ている)役割をふられているのも、良い演出だなと、ここだけは少しなごみました。

 ←Click
←Click
ttp://st.wowow.co.jp/detail/6072
![]()
2015年 8月 12日
つばきファクトリーのデビュー曲がとてつもなく恐ろしい曲だった! 怖い!
ヤバイ。 ハロステでつばきファクトリーのデビュー曲「青春まんまんなか!」を見たんですけど、完全に自分のツボ、というか、これ、あぶないヤツです。 いろいろな意味で、軽く感想を書くわけにもいかない、ちょっと全貌が見えてくるまで黙ってようかな、とか思います。
 ←Click 「ハロステ #130」
←Click 「ハロステ #130」
つばきファクトリー 「青春まんまんなか」は9:50くらいから
70年代というよりは80年代のテイストだと思うのですが、確かにメロディーには70年代的なメランコリーも入っているかもしれませんが、CMJKさんのアレンジが極めて危険なやつじゃないですか! この曲にこのアレンジ持ってくるか?という。 アップフロントの会社側がこの組み合わせを目論んでいたのだとしたら、またまた久し振りにハロプロに舞い降りた“狂ってる”パターンの楽曲です。
本当にこれでいいのかなぁ。マイナー突き抜けてB級の一番怖いところへ行ってしまってる気がします(わぁ、結局感想書いちゃってる)。メンバーも、こぶしファクトリーはかなり一体感(バランスが良い)のあるグループとなったのですが、こちらのつばきはバラバラ感が半端ない。一人一人の持っているテイストが全く融合しないタイプ。これをグループとしてまとめるのは無理があるのでは...いや、そこが面白過ぎて興奮しました。
浅倉樹々さんのアイドルに徹したきりっと締まった佇まいと谷本安美さんの初々しさとのギャップが大き過ぎる。きしもんと小片さんはBerryzのメンバーと将棋番組のアシスタントさんが並んでいるかのような交わりようのない違和感があり、山岸さんと希空は最早普通過ぎてこんなテクノの渦の中に放り込まれていることの場違いさがくっきりと浮き出ている感があります。真剣に歌ったら、ここのメンバー、こんなに変わってる(意外と強烈にキャラ立ちしてる)人たちばかりだったんだと気付きました。 これ、ついてこれるファンいるんだろうか? と非常に心配になってきました。
面白過ぎです。 でも、デビュー曲らしい、メンバーがこの1曲に全てを賭けた、捨身な勢いも突き刺さりました。
で、この曲、アレンジを割とありがちなテクノと思う人いるかもしれませんけども、相当ヤバイです。CMJKさんが本気で作ったんじゃないかと思うほど怖い。一番イギリスの深い“気の狂ったテクノ”の寒々しさとロマンチシズムが入り込んでいます。ソフト・セルやアソシエイツなんかのレベルです。それをあくまでもニュー・オーダー的に展開させようという強引ワザ。
これら全部合わせて、崩れたバランス。 久々に凄いもの見た。
つばきはKOUGAとCMJKのコンビ専属でお願いします。 電気グルーヴと共演してほしい。
最高でした。

今度、「サンク・ユー・ベリー・ベリー」を再演する茉麻とつばきファクトリー。茉麻は演出もする(!)
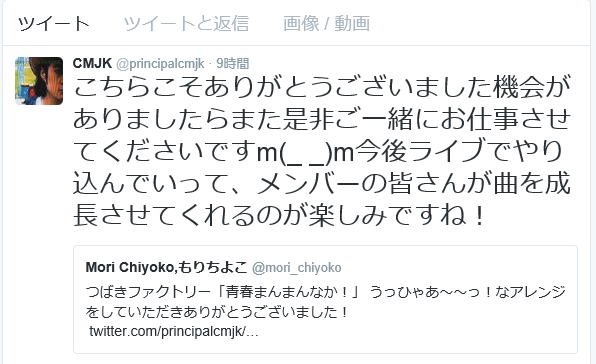
ttps://twitter.com/principalcmjk
![]()
2015年 8月 11日
British Popsの系譜 「Seasons in the Sun」 The Fortunes
中古盤屋で1971年の「雨のフィーリング」というシングル盤をよく見かけるフォーチュンズはイギリスで60年代後半に出てきたスウィンギング・ロンドン以降のPOP系のロック・バンド(エジソン・ライトハウスやフライング・マシーン、ラヴ・アフェアーなどの)だと思っていたのですが、調べてみると1965年にはヒット曲を出しているいわゆるブリティッシュ・インヴェイジョン時期のバンドだったようです。
私はまだまだこの辺りまでは掘り下げていないのですが。
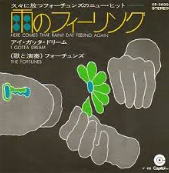 フォーチュンズ 「雨のフィーリング」(1971)
フォーチュンズ 「雨のフィーリング」(1971)
このバンドに「Seasons in the Sun」という曲があり、これは1969年にリリースされています。

↑ Click The Fortunes 「Seasons in the Sun」 (1969)
実はこの曲は1974年にカナダ出身のシンガ・ソング・ライターであるテリー・ジャックスという人が全米および世界で大ヒットを飛ばしており、こちらが有名なのです。日本でも邦題「そよ風のバラード」で発表されるもそれほどのヒットにはならなかったらしいですが、元々はフランスのジャック・ブレルの1961年の曲で、これをアメリカでキングストン・トリオの人などが取り上げた流れからフォーチュンズやテリー・ジャックスのカヴァーに至っているとのことで、1974年のビルボード年間2位になったというほど有名(らしい。いやもうこういう昔の事はわかんないですよねぇ)なため、その後もこの曲を取り上げる人は多く、実はニルヴァーナもカヴァーしているのです。
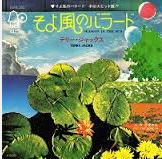
 ← Click
← Click
テリー・ジャックス 「そよ風のバラード」 (1974)
ただ、面白いのは、このテリー・ジャックスのヒットの前に、1970年、ビーチ・ボーイズがテリー・ジャックスのプロデュースで録音を行っており、結局ボツになったのですが、これがまた素晴らしいバージョンなんですね。当時ビーチ・ボーイズの人気はどん底(まさに「Sun
Flower」 ビルボード最高151位!の頃)なのですが、完全に音楽の評価軸がとち狂ってる時で、ビーチ・ボーイズが最高に良い(ブライアンは苦しんでましたけど)状態の作品が全く無視された時代。まあ、Rock多様化の進化を迎える時代で、取り残されてしまったのはあるかもしれませんが、PopsとRockの関係性、分離というか、差別意識というか、少し誤ってしまった部分があったんじゃないかなぁという気がします。


↑ Beach Boys (1970) ↑ Nirvana (1993)
ニルヴァーナが、1993年にこの曲をカヴァーした記録があります。子供の頃のヒット曲をカヴァーしたつもりだったのか、彼らの事ですからビーチ・ボーイズの暗黒史に興味を持っていた可能性もあると思うので、ブートなどで流布していたビーチ・ボーイズVersionを知っていたかもしれないという仮定もあり得る気がします。個人的にこういうPopsとRockの価値観がひっくり返った時期(私はパンク/New WaveはPopsへの回帰という側面も重要と考えているので)に興味があります。(ニルヴァーナがヴァセリンズを評価した、という評価軸です)
一方で、イギリスではBlack Box Recorderがこの「Seasons in the Sun」をカヴァーしています。(1998年)
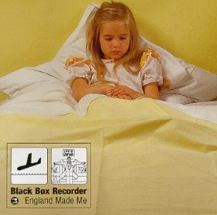
 ←Click
←Click
Black Box Recorder 「England Made Me」 (1998)
Black Box
Recorderは、ジーザス&メリーチェインのドラマーだったジョン・ムーアが在籍したバンドで、あまり成功には至りませんでしたが、こちらは果たしてテリー・ジャックスの大ヒット曲として意識していたのか、それともやはりビーチ・ボーイズのアン・オフィシャルな記録を知っていたのか(何たって、ジーザスはビーチ・ボーイズのフリークなのは間違いない)、又はニルヴァーナを経由してこの曲を知るに至ったのか。そして、もう一つ、このバンドならばあり得るというのが、フォーチュンズの曲をカヴァーしたという可能性です。
イギリスの人だからこそ、子供時代に聴いた自国のPopsが否応なく自分の中に取り込まれてしまっている(ジョン・ムーアは1969年では5歳であり、リアルタイムで聴いていたとは思えませんが..)、そういう感性があるということが、最近、非常に気になるのです。(アンディ・パートリッジがフライング・マシーンやハニー・バスについて語るというのが、自分としてはけっこう衝撃があったし、そこで合点のいったところが多かったので)
ニルヴァーナはビーチ・ボーイズ版を知っていたのか、はたまたテリー・ジャックス版を子供時代から好んでいたのか、Black
Box Recorderはフォーチュンズ版を知っていたのか、それともやはりテリー。ジャックスのを聴いていたのか? 気になります。
(ニルヴァーナのはテリー・ジャックスを下敷きにしているように聴こえる気がしますが)

↑ Click The Fortunes-Here Comes That Rainy Day Feeling Again(雨のフィーリング)
![]()
2015年 8月 8日
新曲「今すぐ飛び込む勇気」を見ると、モーニング娘。’15の潜在能力のとんでもなさがわかる
Queen of Girls POP BERRYZ 工房

↑Click Berryz工房 「すっちゃかめっちゃか〜」
今後、このグループを超えるGIRLS POPに出会うことは無かろうと思うので、残された映像を見続けるしかありません。
(ももちって、ZYX、Berryz工房、Buono!、カントリー・ガールズと、10年余りで200曲を超える楽曲に関わってきていると思うのですが、曲の多さもさることながら、その楽曲の良曲の確率は異常といえる高さに達しているのではないでしょうか? 実際のところほぼ全曲、名曲・良曲だし。個人としては案外“記録”の領域に達している気がする)
8月8日 つばきファクトリー デビュー曲決定
 (写真は結成発表時)
(写真は結成発表時)
つばきファクトリーのデビュー曲が決まりました。「青春まんまんなか!」。作詞は「海岸清掃男子」のもりちよこさん。作曲は「我武者LIFE」のKOUGAさん,編曲はアンジュルム、Juice=Juiceやチームしゃちほこを手掛けたりしてるCMJKさんとのこと。カントリー、こぶし、つばきにつんく♂曲が無いのはちょっとさみしいですが、ハロプロらしさの継承は期待できそうです。曲調はちょっとレトロっぽい70年代の感じという噂で、まあ流行りには乗っかりにくいかもしれませんが、上手く折り合いをつけながら頑張っていってほしいなと思います。 私は、小片リサさん推しでいきまーす。 このグループはけっこう気掛かりで放っておけないグループです。
8月6日 「GREEN ROOM ♯15」

申し訳ありませんが、毎週、雅ちゃんと千奈美を「GREEN ROOM」で見ることが出来て、幸せです。
そして、今週のショットはこれ、ですね。

8月4日 NHK「いのちのうた」 モーニング娘。’15 「雨の降らない星では愛せないだろう?」
モーニング娘。‘15 8月19日発売の新曲「oh
my wish!/スカッとMy Heart/今すぐ飛び込む勇気」は、3曲とも気に入っています。中でも特に「スカッとMy
Heart」は、まあ安定のディスコファンク楽曲で、割と地味に正攻法なのですが、ほんとーに、しみじみと良い曲です。
実際のところ、このジャンルって、もうモーニング娘。は伝統的に血肉化しちゃってて、メンバー入れ替わってても最早自然体で歌えてしまうというのが、この曲でわかりますよね。
あと「今すぐ飛び込む勇気」のMV見てもらいたいのですが、野中チェルさんのポテンシャルの高さがじわじわ露出し始めてまして、この子すごいゾの気配が来てます。 このグループのとんでもないところは、今もっておそらく潜在能力の半分ぐらいしか出ていないだろうと思えるところで、最近になってようやく佐藤まーちゃんやズッキが片鱗をお披露目し始めましたが(能力の高さは既に知ってるのですが、ここはシングルでなかなか見せずに出し惜しみしてるんですよね)、ふくちゃんと飯窪さんの声の良さはまだまだ隠してる状態ですし、12期、実はみんなまだ全然持ってるもの出してないですからね。 真莉愛と朱音ちんのパフォーマンス力の高さはひなフェスで確認済みですし、はーちんのひょっとして道重の後継か?と思えるほどのぞくぞくしてくる妖しさも、まだ今出し切るのはもったいないという感じでわざと小出しにしていますよね。
ただ何しろ野中さんにはちょっと驚いてます。
いやぁー、野中さんを見つけることが出来るハロプロのスタッフ凄ぇ〜。
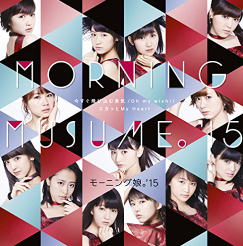 モーニング娘。’15 「Oh
my wish!/スカッと My Heart/今すぐ飛び込む勇気」 8月19日発売
モーニング娘。’15 「Oh
my wish!/スカッと My Heart/今すぐ飛び込む勇気」 8月19日発売
まーちゃんの天才が楽しみで仕方がない!
![]()
2015年 8月 4日
ジミー・ペイジ
7月30日 ジミー・ペイジ、1971年以来、44年ぶりに広島を再び訪ねる。

![]()
2015年 7月 30日
最近はこんなんばっかり! 見てます

みて!みて!みーて! 見つけた瞬間、きゃー!でした笑❤
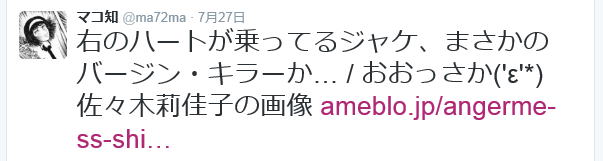
ttps://twitter.com/ma72ma
ハートマークはマネージャーさんの細かい目配りでしょうが、見る人が見ればしっかりわかるようにしてるあたりにハロプロの「ロジャー・ラビット」的笑いの性(笑いのためなら敵の銃の前にも飛び出すバックス・バニーの業)を見る。
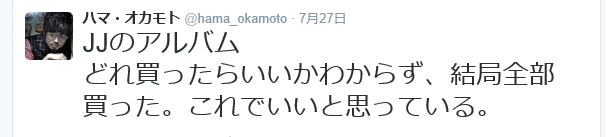
ttps://twitter.com/hama_okamoto
ハマ・オカモトは1991年3月の生まれ。つまりベリキューのキャプ、舞美、桃より学年は1つ上でした。
Juice=Juiceのアルバム。私は通常盤しか買ってませんが、限定盤B買おうか迷ってる。
佳林ちゃん、紗友希の素晴らしさが勿論前提にあってのことですが、私は結局かなとも(金澤さん)に持ってかれた。まさかかなともさんがハロー!のハロー!たる所以を担っていたのだとは、気付いていませんでした。(あと、「天まで登れ!」は恐らくオリジナルVer.のままだと思う。つまり6人バージョンが1曲だけですが、アルバムに収録されたことになるのでは...)
7月29日
Juice=Juice 高木紗友希さん、『医師により「右声帯出血および両側声帯炎」と診断されました。
それに伴い、本日の「Juice=Juke BOX」は欠席とさせていただきます。大変、申し訳ございません。』
もう、ほんとうに鞘師も小関も紗友希も、本気で心配になってしまったりします。
7月29日 「ナカイの窓」

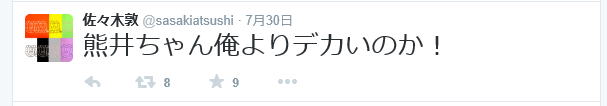
ttps://twitter.com/sasakiatsushi
あれっ、なにげに佐々木 敦氏も熊井ちゃんのことつぶやいてた。
あと最近のONE SHOTではやっぱりあやちょのこれ

7月22日 アンジュルム 和田彩花 ホール・ツアー決定報告で涙
「なんか、今、みんな(お客さん)が知ってる?とか聞いたら、みんな知っててうれしそうだなって思って。やっとできたね。よかったね。」(あやちょ)
みんな、あやちょが嬉しそうだからなんだけどね。
竹内「これで冷たいお弁当ともおさらばですよ。これからはもう温ったかいケータリングですから」
![]()
2015年 7月 25日
The Lodge と COUNTRY GIRLS
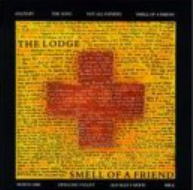

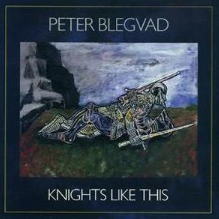
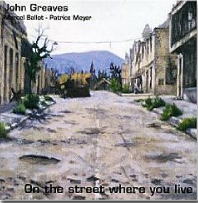

この1週間は毎日欠かさずカントリー・ガールズの「ためらいサマータイム」を聴いております(見ております)。この曲を聴いてXTCやSlapp Happyを想起する人がどれぐらいいるだろうか?と考えたりして、そもそもSlapp Happyとカントリー・ガールズ両方聴く人間がどれだけいるっちゅうねん!?という話ですが、「ためらいサマータイム」の、メロディをひとつひとつ丁寧に置きにいってる感じが、いわゆる商業音楽としては不自然でしかも妙に機械的に捻りを加えており、単なる親しみ易さを避けているようにも聴こえます(私には)。
でありながら、音楽的には紛れもなくPOPなところが、どうもXTCやピーター・ブレグヴァッドの作り出す音楽(時には箱庭的と、その内向性と実験的要素ゆえに決して褒め言葉とは言えないような表現をされてしまうこともある)に通じている気がしています。
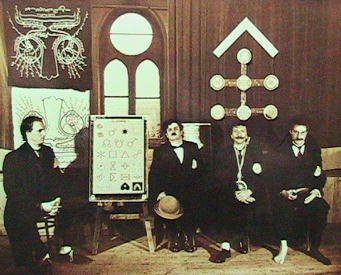 ←Click The Lodge 「Solitary」
←Click The Lodge 「Solitary」
ジョン・グリーブズ、ピーター・ブレグヴァッド、ジャッコ・ジャクジグ、アントン・フィア、リサ・ハーマン、クリストファー・ブレグヴァッドらからなるユニット
このレベルのポップスに捻りを入れることが必要なのか? それはむしろ曲を殺す選択となってしまうんじゃないかと思うような念の入れ方で、楽(でしかも自然)な方向を避けることによって、別種のポップ・ミュージックが出来てしまう。私が昔からつくづく“このアルバムはおかしい”と思っているThe Lodgeの「Smell of a Friend」というアルバムはまさにそれで、装い自体はAORやPOPに舵をきったASIAやジェネシスのように人当たりのいいメロディなのに、何とも言えない居心地の悪さがまとわりついていて、どこかで遺伝子組替のような決定的な転換が行われているとしか思えなくなってきて、その異形のいわば紛い物的な要素に惹かれていくようになる。
とか。 (自分、大丈夫かな...)

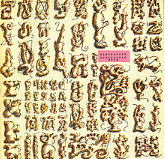
↑ Click Slapp Happy 「Charlie 'n Charlie」(1973)
Slapp
Happyは、最近になって「Acnalbasac Noom」が紙ジャケで再発され、正規?のジャケット・デザイン、S-HMCDでしたので、かつてレコメンデッドから出ていたジャケット・デザインの盤(私が最初に買ったSlapp Happy)を持ってはいるのですが、また買ってしまいました。
このSlapp Happyの「Charlie’n Charlie」など、聴きようによってはこれも「Baby It‘s You」の変奏に聴こえなくもない(?)

↑ Click 「Special Delivery Live - Peter Blegvad and Golden Palominos」

↑ Click 「LA LUNE BLANCHE - JOHN GREAVES, JEANNE ADDED & MARCEL BALLOT」
ピーター・ブレグヴァッド(Slapp Happy)、元Henry CowのJohn Greaves、Chris Cuttlerなどは、少々小難しい音楽をやるような印象を持たれていますが、実際にはブレグヴァッドの曲などは非常にPOPで親しみやすいものですし、ジョン・グリーヴスも「Fry
Me to The Moon」などのスタンダードをカヴァーしたアルバムを出すなど、ポピュラー・ミュージックとの接点を大切にしているアーティストです。決して彼らとカントリー・ガールズが距離を隔てた存在だとは思わないんですがね。

↑ Click 「Andy Partridge and Peter Blegvad Beetle」
![]()
2015年 7月 20日
COUNTRY GIRLS 「ためらいサマータイム」 衝撃的な楽曲美!
 ←Click
←Click
ヤバイ。 前にエディット・バージョンで聴いて割と平凡だなと思った(Baby It’s You)「ためらいサマータイム」が、Fullで聴いたらとてつもない名曲だった!
なぜか自分の中ではXTCの「Glass」がフラッシュ・バックしつつ、これ確信犯的「恋するフォーチュン・クッキー」に対するブリティッシュ・ポップスからの回答?
”「恋チュン」の二番煎じ”的な阿保なコメント出現が予想されるのがちょっと不安ですが、曲の前衛性(スラップ・ハッピー、The Lodgeの前衛POP性)も含めて、こちらの方がはるかに上。(あまりこういう比較の仕方で言いたくないけど、容易に感想として大したことないというような意見が出てくるのが予想されるため、あえて言っておきたい)
ドラムのドコドコドコなだんご状のエコー薄めな生々しさが特に前衛的カンタベリー・サウンドのPOP性を彷彿とさせるぐらい、ウォール・オブ・サウンドの革新性を実証してしまっている。ハロプロ特有のベースの厚めの音入れも効いています。カントリー・ガールズの特徴は、“新人にしてはVoがこなれている”のではなくて、“まだ技巧が追い付いてなくて初期衝動の部分で歌っている子が多い”(それなりにキャリアのある稲場、山木さんでもその傾向がある)のが強みで、勿論そこにアクセントで入っているベテランももちもスパイス的に効果があり、ただこの人のかすかなナチュラル・ビブラートが実は重要。この曲は特に、もし嬉唄ちゃんが残っていたら、よりとんでもなくヤバイ傑作になっていただろうと思われ、そこが惜しまれる。
私はもうこの1曲が生まれたことで、この1年は満足です。例によって10連続リピート やってしまいました。
それにしても、このグループに山木さんが入ったの、本当に大きい。
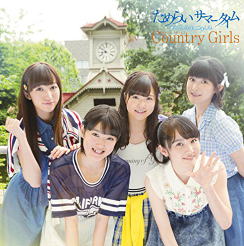 カントリー・ガールズ 「わかっているのにごめんね/ためらいサマータイム」8月5日発売
カントリー・ガールズ 「わかっているのにごめんね/ためらいサマータイム」8月5日発売
![]()
2015年 7月 19日
なぜはっぴいえんどなのかがわからない
never young
Beachっていうバンドを見てみようと思ってYou Tubeでチェック始めたら、次から次へと今の日本のバンドやアイドルのクリップが出てきまして、本当にいっぱい居てカオスですね。Yogee
New Waves、Lucky Tapes,ミツメ、Sugar“s Campaign,フレデリック、アカシック、バンドじゃないもん!、平賀さち枝とホームカミングス、BISH、Billy
Idle、片想い、Cero、あだち麗三郎、、、、、
けっこうノン・コマーシャルな音楽だったりはするんですよね。オルタナティヴな。

 「paradise lost, it begins」 (2015)
「paradise lost, it begins」 (2015)
↑ 吉田ヨウヘイGroup 「間違って欲しくない」
吉田ヨウヘイGroupはセカンド、サードを買って持ってます。そんなに熱心には聴いていないんですが、ちょっと気になってはいる。ネルス・クラインと対談したんでしたっけ? ややとっつきにくい感じはあります。ちょっと要素的に抱え過ぎてしまっている気がして、ジャム・バンドの感覚まで混じってきてしまうと違うんじゃないかという気がしてしまうのですが、このバンドはそこへ踏み込んでしまいそうな危うさを感じます。
あれやこれやと聴いてたのですが、だんだんめんどくさくなってきまして。
Silent Siren 「八月の夜」 ttps://www.youtube.com/watch?v=TuRm1JzAsVg
私はやっぱりSilent
Sirenが好きで、「これでいいじゃん!」と思う。無駄が無いし、間違ったことをしそうにない。冒険しないということではなくて、自分たちがやっている音楽として、これはやったら方向としておかしいということがわかるんだと思う。

↑ ペロペロしてやりたいわズ。 「High Wave」
他に面白いと思ったのが、ペロペロしてやりたいわズ。このバンドのグルーヴ感、うねりが好き。本来の70年代というか、知識で塗り固めた70年代ってはっぴいえんどや渋谷系(つまり渋谷系が描こうとした70年代)じゃないですか。このバンドはそこのところをうまく回避している気がする。(回避することが良いことだと言っちゃってますけど)
何しろ、私の聴いてきた70年代は、はっぴいえんどではなかったので..はっぴいえんどが主流かのように跋扈する日本のRockというのがいまひとつ馴染めないのです。
あとはやっぱりA.B.C-Zだな。このグループ、メンバー5人の顔が全部イイ!
A.B.C-Z 「Summer 上々!!」 ttps://www.youtube.com/watch?v=pRk3nz8IUHU
![]()
2015年 7月 18日
Sweet Land of Liberty (toda-yっ)
超アメリカ讃歌なニール・ダイアモンドの「America」を聴いたのは1980年だったと思います。これは映画「JAZZ
SINGER」(1980)のサウンドトラック盤として発売されたアルバムの中に入っていましたが、当時、映画を見ることはなく(随分たってから、ニール・ダイアモンドの、というよりリチャード・フライシャーの映画だと思って、VIDEOで見ました)、何だかよく知らないがアメリカの大御所の新作アルバムだと思って聴いていました。何しろ映像を見てもらえばわかるように、エルヴィス並みにキラキラの衣装を着て大物オーラを発していて、あの頃、私の考えるアメリカの大物って、ニール・ダイアモンドとかバリー・マニロウのことだと思ってました。
自分はこういうのを“虚飾の”と考えて辟易する、というタイプではありませんでした。だからといってアメリカ讃歌に思い切り乗っかるというわけでもなかったのですが、ニール・ダイアモンドは好きだった。

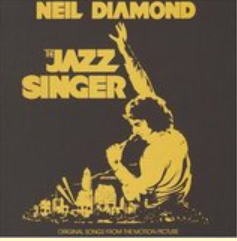
↑ Neil・Diamond 「America」 (1980)
小林信彦の『本音を申せば 女優で観るか、監督を追うか』を読んで、イーストウッドの「アメリカン・スナイパー」に対し、「イーストウッドの映画をいつも楽しんで観るぼくが、そうもいかなかったのは珍しい」と書かれているのを見て、ついに小林信彦氏もイーストウッドから降りたのか...と思った時、自分の中ではいまだにニール・ダイアモンドの「America」が鳴りやんでいないのだなと、ふいに思いました。
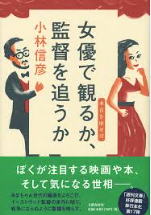 小林信彦 『女優で観るか、監督を追うか』(本音を申せば)(文藝春秋)
小林信彦 『女優で観るか、監督を追うか』(本音を申せば)(文藝春秋)
(「ハート・ロッカー」も良い映画だったが..と氏は書いているので、「アメリカン・スナイパー」も悪い作品ではないと見做してはいるかもしれない)
![]()
2015年 7月 16日
ぼくらの
 高橋源一郎 『ぼくらの民主主義なんだぜ』 (朝日新書)
高橋源一郎 『ぼくらの民主主義なんだぜ』 (朝日新書)
高橋源一郎 『ぼくらの民主主義なんだぜ』読了。
まあ、二週間ぐらい前に読み終わってはいたんですが...
最近はこんなのばっかり! 見てます。
 ttps://twitter.com/motomotohide
ttps://twitter.com/motomotohide
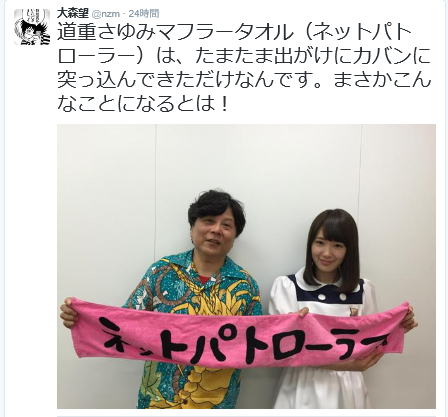 ttps://twitter.com/nzm
ttps://twitter.com/nzm
乃木坂活字部の高山一実部長と
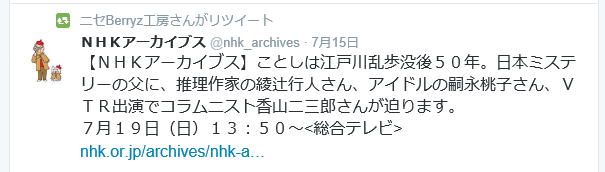 ttps://twitter.com/niseberryz_kobo 香山二三郎氏、まさかももちと同じ番組に出られる日が来るだろうとは、夢にも思わなかったでしょうね
ttps://twitter.com/niseberryz_kobo 香山二三郎氏、まさかももちと同じ番組に出られる日が来るだろうとは、夢にも思わなかったでしょうね
そしてこれが最高の癒しSHOT

![]()
2015年 7月 11日
Music +
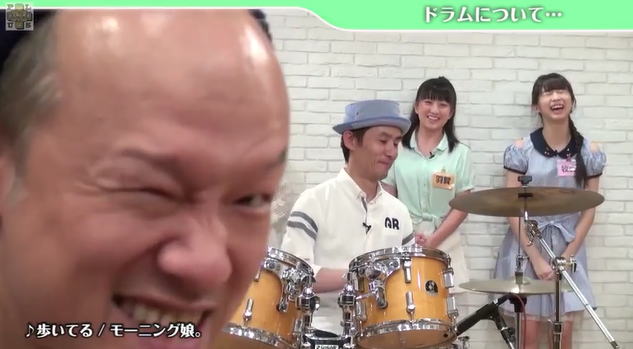
なんか、やっぱり ハロプロってええな
 「First Squeeze!」 Juice=Juice 2015/07/15発売
「First Squeeze!」 Juice=Juice 2015/07/15発売
いよいよJuice=Juiceのファースト・アルバム「First Squeeze!」が来週発売になりますが、リーダーの宮崎由加さんが、初回限定盤A、Bと通常盤、それぞれ違うので3つとも買わないと揃わないのでよろしくお願いしますとか言っていてすごかったです。私は通常盤を予約しましたが、CD3枚組、4000円(税抜き)です。
今までのシングル(9枚)の曲が全部入っている上に、アルバム新曲も9曲。「Magic
of Love」などのハロプロ・カヴァー曲も6曲入って、ファースト・アルバムにして全29曲というありえないヴォリュームです。
(乃木坂46のファーストも29曲入りだったようです)
現在、Juice=Juiceは、6月より、220公演(!!)LiveツアーがStart。
![]()
2015年 7月 5日
90年頃
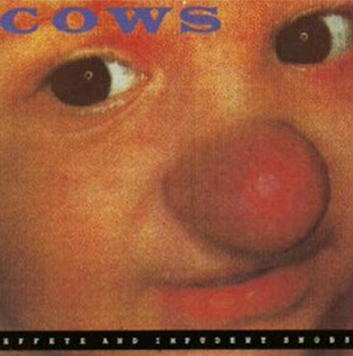
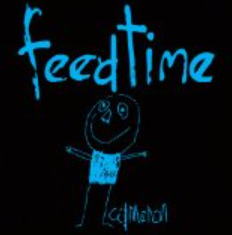
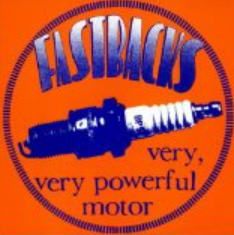
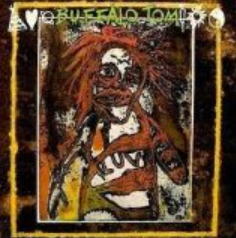
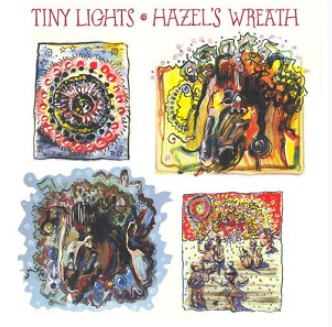
↑ Click ↑ Click ↑ Click ↑ Click
ここのとことは、ちょっと懐かしいのを聴いてました。COWS 「Effete and Impudent Snobs」(1990)、Feedtime 「Feedtime」 (1985)、Buffalo Tom 「Buffalo Tom」(1988)、Fastbacks 「Very, Very
Powerful Motor」 (1990)、Tiny Lights 「Hazel's Wreath」 (1988)。5枚あげてみましたが、実はこの中でCDで今も持っているのはCOWS 「Effete and Impudent Snobs」(1990)だけ。FastbacksとTiny
LightsはCDは持っていますが、ここに挙げたアルバムはもう手元にありません。Baffalo Tomなんかは当時、このデビュー・アルバムを本当によく聴きましたが、ダイナソア Jr.の弟分というような音で、ちょっと二番手的に見られてしまったのかあまり話題にならなかったのですが、そのあとでグランジ・ブームの流れでしょうか、どかんと売れてしまいまして、もうその頃はあんまり聴いていませんで、このバンドに関しては1枚目と2枚目ばっかりです。
COWSはもう全部好きで、全部持ってます。ずーっと、ちょくちょく発作的に聴きたくなります。
Feedtimeはオーストラリアのバンドだったと思います。私はジャンク/グランジの80年代後半のタイミングで知りましたが、結成は79年でけっこう古かったらしい。Go-Betweensと変わらないぐらいの古参だったのですね。
Fastbacksはあまりアルバム単位でどうこうというバンドではないかもしれません。意外にアルバム出してないし。当時、こういうバンドがアメリカの良心と言われていたように思います。演奏はそれほど上手いってわけじゃないんですが、ティーンエイジ・ロックをどこまで(いつまで)引っ張れるかというところの、ある意味卒業しないヲタクのだらしなさみたいなものをアメリカは昔っから体現してきたわけで、その強度が日本なんかに比べてはるかに別格だった。当時はね。
Tiny Lightsは、今聴くとヴァイオリンがコクシネルっぽく聴こえたりね。初めて聴いたときはクリムゾンみたいだなと思ってました。このバンドは音が割と洗練されているので、かえってアメリカのインディー・ロックを聴く人からは敬遠されちゃったところがあったかもしれない。私は、このバンド、けっこう理想で、昔のイッツ・ア・ビューティフル・デイ(ってバンドがいるんですけど)みたいな男女混成の、アメリカに出現したジプシー?みたいな佇まいの、あてどないヒッピーのファミリーみたいな感じを勝手に投影したりしてました。
 ← Click Tiny Lights - The Bridge
← Click Tiny Lights - The Bridge
![]()
2015年 6月 29日
あのぅ、すみません。 「臥薪嘗胆」が、 最高でした。
 ← Click
← Click
死ぬほど 売れちゃってください!
![]()
2015年 6月 28日
「ラーメン大好き小泉さん」面白かった
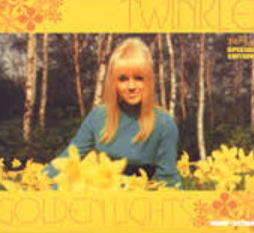
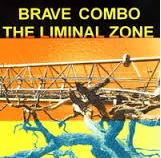
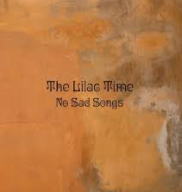

トゥインクルが亡くなっていたことを先日「ミュージック・マガジン」誌 7月号を読んで知りました。5月21日、66歳だったそうです。ご冥福をお祈りします。ヒット曲として知られる「Terry」は1964年の曲だそうですから、当時16歳だったのですね。私の年齢では完全に後追いなので、当時、日本でどれぐらい知名度があったのかもわかりません。彼女が亡くなったことは日本では殆どNEWSになっていないと思います。
スミスが彼女の曲「Golden Lights」をカヴァーしています。
どちらかというとワンヒットの方の人だったのかもしれませんが、このアイドルの存在を忘れていないのは当然といえば当然ながら自国のイギリス人であり、イギリスのRockをやってる人たちがアイドル、つまりイギリスの歌謡曲で育ったことを公言するのが(スミスしかり。ラヴ・アフェアーをカヴァーしたアズテック・カメラしかり)、80年代に台頭してくるポスト・パンクの世代だった(60年代後半に子供だった世代)というのを記憶しておきたいと思う。
他に、最近聴いていたのは、ブレイヴ・コンボの新作「The Liminal Zone」(2015)。ライラック・タイムの久し振りのアルバム「No Sad Songs」(2015)。ソウル・サヴァイヴァーズのセカンド・アルバム「テイク・アナザー・ルック」(1969)。
ソウル・サヴァイヴァーズは、ニール・ラーセンがまだ加入していない時期の作品でした。マッスル・ショールズのフェイム・スタジオで録音されており、演奏はフェイム・ギャングの一派と思われる。デュエイン・オールマンが弾いている可能性が高いとのこと。
ブレイヴ・コンボとライラック・タイムの新作は、いつもの音、といえばまあ確かにそうで、新味はそれほどありませんが、相変わらず良いです。新しくなることもなく、ルーツを辿っていくわけでもない。むしろスタート地点である80年代のサウンドを、年輪とともにひたすら磨き上げていってるところに貴重さを感じる。彼らにとっては80年代の音は一過性のものではなく、交換の効かないオリジナルな音楽なのだ。私も完全に賛同する。
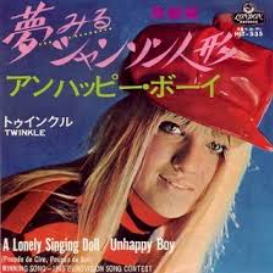 ←Click 勿論、フランス・ギャルのあの曲です。
←Click 勿論、フランス・ギャルのあの曲です。
A Lonely Singing Doll (1965)- Twinkle
土曜日深夜に放送が始まった「ラーメン大好き小泉さん」面白かったです。 元ももいろクローバーZの早見あかりさん主演ですが、ラーメン食べた後の恍惚の表情が最高。
主題歌は、こぶしファクトリー「ラーメン大好き小泉さんの唄」で、これは元々はシャ乱Qの曲だった「ラーメン大好き小池さんの唄」(91年)をアレンジしたもの。ドラマ中ではあまり聴けなかったので、早くFull Versionを公開してほしいものです。
こぶしファクトリー、完璧に推せる。
そのあと、「音楽の日 朝までライブ COUNT DOWN TV」は℃-uteが出るので録画。
℃-ute、いまいち反応ないお客さんを前に、好調!
他にもゴールデン・ボンバー、気志團、ABC-Zを堪能。OKAMOTO’sは何だかしらないけど、見てると20年ほど前のアメリカのバンド Make Upを思い出す。 グリム・スパンキーというバンドがけっこう良かったんですけど、サイケデリコやsuperfry的な洋楽志向に向かっていきそうな気配もあって、やや警戒心がわく。
それにしても℃-ute、めっちゃ良かったなぁ。
 ← Click
← Click
こぶしファクトリー 「念には念」 (2015)
![]()
2015年 6月 26日
まさかの期待超え カントリー・ガールズのセカンド・シングル「わかっているのにごめんね」
ANGERMEの新曲、「魔法使いサリー」がかなり良いんですけど。ちょっと予想外な仕上がりで。
どちらかといえば抑え気味というか、外部のコンテスト企画の主題曲ということもあって、ハロプロらしさを押し出すみたいな感じで何かを仕掛けてくるということもなかったのですが、素直にこのアレンジは好きだなぁと思いました。勿論、同時新曲の「七転び八起き」も「臥薪嘗胆」も、死ぬほど売れてほしい!と思える素晴らしい曲ですが、今、自分の中で来ているのは「魔法使いサリー」です。
 ←Click
←Click
(3期の3人の声、全部ANGERMEに必要な声。正解だった!)
それと、先日TV東京で放送された「テレ東音楽祭」でいきなり初披露となったカントリー・ガールズの新曲「わかっているのにごめんね」は、期待よりも不安の方が大きかった(実はいろいろありまして)状況下で、想像を軽々と超える良曲が登場し、唖然としました。
良曲と書きましたが、小品ながらとんでもなく名曲だと思います。作曲の加藤祐介氏はハロプロではHI-FINの「海岸清掃男子」、カントリー・ガールズの「愛おしくってごめんね」に続く驚異的クオリティの連打ですが、ハロプロ以外で手掛けているジャニーズ系や水樹奈々での作曲なども気になってきました。
ハロプロらしい小芝居の野暮ったさとユーモアと音楽的教養あったればこそながら、この曲の構成が天才的としか言いようがありません。小品を構成力で聴かせるってめったにない。センスにも品性が問われるし。

You Tubeで テレ東音楽祭 カントリー・ガールズ わかっているのにごめんね で検索すれば見ることが出来ると思います
総合としてもメンバーのパーソナリティーから声質、アレンジ(相変わらず、ハロプロは細部にわたって音の芸が細かく、マニアック)まで全部、セカンド・シングルに寄せる期待、そして不安から想像していたレベルを超えてきました。 トイピアノ(?)の音が入ってますよね。ああいう使い方にポップマエストロの狂気を感じる。
1回見始めると止められなくなってつい10回ぐらい繰り返して見てしまうのですが、このテレ東音楽祭での出来が、ステージ美術も司会の緩いMCも含めてあまりに完璧なので、これを上回るパフォーマンスが今後可能なのかどうかが心配になってくるぐらいです。
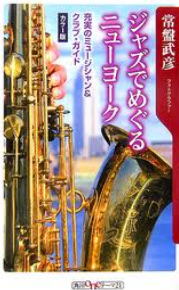 常盤武彦 『ジャズでめぐるニューヨーク』 (角川oneテーマ21)
常盤武彦 『ジャズでめぐるニューヨーク』 (角川oneテーマ21)
常盤武彦 『ジャズでめぐるニューヨーク』読了。2006年に出た新書本。本人は80年代後半からニューヨークのジャズ・クラブをめぐるようになり、ウィントン・マルサリスの演奏に感銘を受けたのを皮切りに、ニッティング・ファクトリー系のオルタナティヴなジャズや、90年代以降に隆盛をみるジャム・バンド・シーンなどの現場にも足を運び、リアルタイムのニューヨーク・ジャズ・シーンを知る人。ウィントン・マルサリスからジョン・ゾーン、アート・リンゼイまで横断するジャズ・ライターって実はそんなに多くはないだろうと思う。
何たって80年代後半からのジャズ・シーンなので、ジャズの本でありながら、いわゆるジャズ・ジャイアンツよりも、ジャンル崩壊のごとき変化をとげる現在のジャズに大幅に文章を割いている貴重なルポルタージュだと思いました。
今までありそうでなかなか無かったのがパット・メセニーやジョン・スコフィールド、ビル・フリゼール、ブラッド・メルドーらの世代の活動変遷をきっちり追って書いてくれている点で、セックス・モブやマリア・シュナイダーまでに多くの言及があるのが嬉しい。ウェザー・リポートよりもザヴィヌル・シンジケートに関する文章のが多いとかね。
アフリカ、カメルーン出身のベーシスト、リチャード・ボナがジョー・ザヴィヌルの発見により、フランスを経てアメリカに上陸し、ザヴィヌル・シンジケートからパット・メセニー・グループへと活動を繋げていく様子を読んでいると、やっぱりアメリカのなにものにも替えがたい自由を感じる。アメリカってやっぱり面白い。
ものすごく久し振りに、スティーヴ・コールマンが聴きたくなりました。昔はCD持ってたんだけどなぁ。
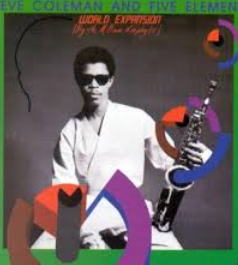
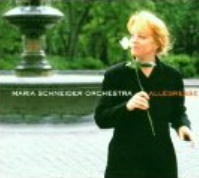
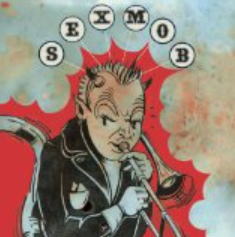
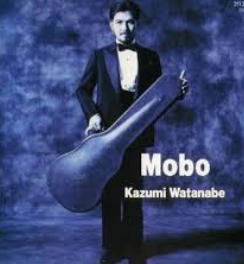
(渡辺香津美は本書には登場しませんが、「Mobo」でのマーカス・ミラーがめっちゃ好きでした。83年かぁ。)
![]()
2015年 6月 21日
XTC VS Berryz工房
曲がはっきりと似ている、ということは別に無いのですが。
Berryz工房が持っているXTC気質......あると思います。

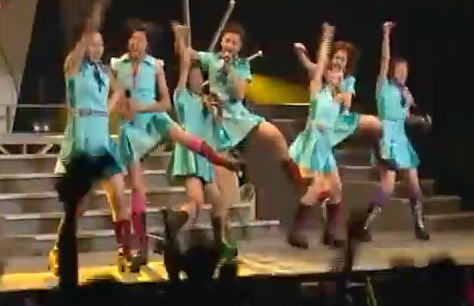
All You Pretty Girls (1984) かっちょええ! (2004)
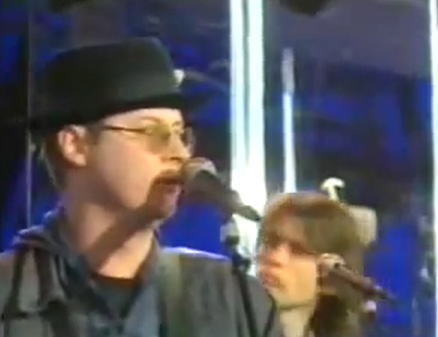

Mayor of Simpleton (1989) 永久の歌 (2014)


Living Through Another Cuba (1980) 素肌ピチピチ (2006)
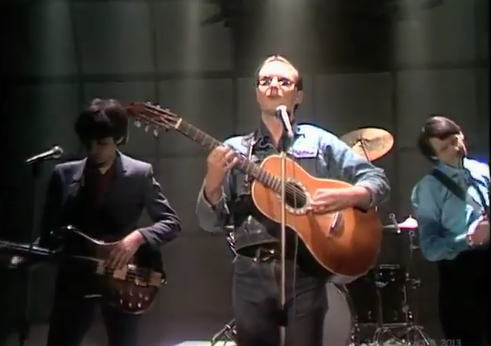
Senses Working Overtime (1982)

普通、アイドル10年やってらんないでしょ!? (2014)
(それにしても、この最高過ぎるヴォーカル集団 なんなんだ!?)
![]()
2015年 6月 20日
国の思想をユートピア思想呼ばわりするのは学者としていかがなものかとは思いましたが、成程ねとも思いました。
まあ、シャングリラってことだよね。(「ブリガドーン」の国か)
佐伯啓思の『従属国家論 日米戦後史の欺瞞』を読みました。すこぶる面白かった。賛同できる部分は多くはなかったですが、あらためて言われて気づく、ということがけっこうありました。
アメリカが、自由な民主主義の普遍性、人権思想の普遍性、市場経済の普遍性を国家の根幹にすえており、それを世界化するという一種のメシア的ユートピア思想を持っている。その背後にはユダヤ・キリスト教的世界観があることは疑い得ない。
と、言い切って書いているところに少し驚きましたが、さらにはそんな思想を持っているのはアメリカだけと言っていて、民主主義に普遍性があるなどと考える国は世界のどこにもなく、日本もそうではないと書いているのですが、なるほどと思いました。
何となく絶対視しがちな民主主義や平和主義が、アメリカのユートピア思想に過ぎないと考えるのは、気持ちよく賛同はしにくい意見ですが、確かにそれは考え方として有るという気がします。
しかも、民主主義と平和主義が繋がっているかのように思っているリベラル左翼的な平和主義者を佐伯氏はやや感情的に否定しており、民主主義と平和主義は全く別物であり、むしろ逆な時すらある、ということで、民主主義の民の意向は、自立する民として自ら戦争を選ぶ場合がある筈であり、戦争放棄を掲げる絶対平和主義は、民主主義に反する思想という論すら打ち出しています。(これはあくまでも私の読後の感想ですので、佐伯氏はそんなことは言ってないという反論もあるかもしれません。それは各々読んで判断してもらうしかありませんが、逆に言えば、私の読み方は間違っていない可能性もあると思います)
佐伯氏は、安倍政権を支持しているというわけではないようですが、少なくとも憲法改正は必要だと考えており、戦争放棄の文言は消すべきだと考えているように思えます。つまり、アメリカの民主主義のような絶対視とは違いますが、どこの国にもその国なりの民主主義というのはあり、勿論日本にもそれはあって、その場合、他国に従属しない真の自立した国の民主主義において、自国のために闘うという体制を放棄する国など、まともな国とは言えないということを言いたいのではないかと思いますが、まあ、考え方として真っ当だなとは思いました。
そのあとで『永遠の0(ゼロ)』(百田尚樹 著)での特攻隊の話が出てきて、美化するのはどうかとは思うが、世間の一部にある『永遠の0』バッシングの論調が、国のために死ぬという思想を否定しているみたいなのはおかしいのではないかと、佐伯氏は考えているように思いました。
私は必ずしも戦争放棄を掲げるリベラル左翼的な平和主義者の人たちが、国のために死ぬという発想を持っていないとは言い切れないんじゃないかと思っていますが、ただ、「殺られる前に殺れ」の発想には乏しいのではないかと感じてます。それが自立した国(民)として生命力に乏し過ぎると言われれば、確かにそうかもしれないとも思う。
ただ、佐伯氏が一番言いたかったはずの“戦後レジウムのねじれ”が、日本の元凶であると重要視する考えが、重要だとは確かに思っても、要は「ねじれがなかったら」、日本はどのように判断して、現在どのような国家になっていたと思われるか?」を仮説としてでも提示してみることの方が、やっぱり関心としては大きい。そこで結論が、正式に軍備をせず、イスラム国からも逃げを打つ不参加居直りでは世界から信用されないというものになるのは、「結局そこへ来るのか」となるわけで、個人的には、そこまで日本の従属国家ぶりが最優先課題だという考えに乗れませんでした。
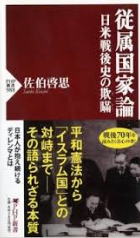 佐伯啓思 『従属国家論 日本戦後史の欺瞞』 (PHP新書)
佐伯啓思 『従属国家論 日本戦後史の欺瞞』 (PHP新書)
![]()
2015年 6月 14日
密かに熱い
聴きながら笑えて来ちゃって涙が出てきた。スゴ過ぎて ひくレベル。
ちゃんさん、さゆべえ、信じられへん。
←Click Juice=Juice 「Magic of Love '15」
![]()
2015年 6月 13日
最近聴いてる4枚
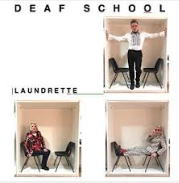

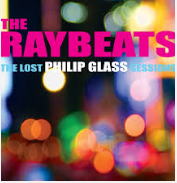
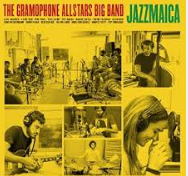
このところ聴いているのは、デフ・スクールの37年ぶりのオリジナル・アルバム新譜! 「ランドレット」(2015)。
活動していた頃のデフ・スクールは私は知らないんですよ。
活動は78年ぐらいまでで、その後日本で殆ど紹介されることもなかったし。1988年に一時的な再結成Liveアルバム「Second Coming」が出た時は、プロデューサーで有名なクライヴ・ランガーが昔やってたリヴァプールの伝説のバンド、という触れ込みで、聴いて良過ぎてビックリしました。
まさかここで新譜が出るとはまたしても驚きですが、Live音源(14年11月)なども絡めながら巧妙に雑然としているのが素晴らしい。
パンク以前からのキャリアを持ちながらも現時点のサウンドが十分にパンキッシュ。ザリザリしていて心地いい、イギリスだなぁって嬉しくなるアルバムです。
スカパーに入ってしまって、時代劇のチャンネルなんか見ていて、勝新太郎の「痛快!河内山宗俊」(‘75〜’76)を見ているのですが、このドラマの主題歌を歌っているヒデ(出門 英)の「いつの日か人に語ろう」が聴きたくてヒデとロザンナのBEST CD「ゴールデン・ベスト 真夜中のボサノバ」を買ってしまいました。
俳優としての出門 英が好きで、まだまだこれからって時に亡くなってしまった(90年 47歳)のが残念でした。いい声だなと思う。
レイビーツ 「The Lost PHILIP GLASS Sessions」(2013)も最近買いました。
レイビーツはCDが長い間殆ど出回ってなくて、中古もすごく高くて手が出なかった(まあ、アナログ盤は持っているのでいいのですが)ので、たまにAmazonでチェックするくらいだったのですが、知らない間にCDが出ていたのに気づき、タイトルにフィリップ・グラスの名があって謎だったんですが「Jack The Ripper」が入っていたので購入しました。
Liveバージョン(82年の録音)になってるんですけども、やっぱり最高です! レイビーツ好きな人は安心して買ってください。
内容も録音状態も文句なしです。フィリップ・グラスがどのように絡んでいるのかは謎?のままですけども。
オリジナル・アルバムも再発してほしいです。
スペイン マドリードでレゲエ、ロックステディ/スカを中心に紹介しているリキデイター・ミュージックというレーベルから発売されたバロセロナのビッグ・バンド、ザ・グラモフォン・オールスターズ・ビッグ・バンド
「JAZZMAICA」(2015)は、モータウンの名曲やオリジナル曲をスカ・アレンジで聴かせるJAZZコンボ。
パーティー・ミュージック的なリラックスしたサウンドですがかなり面白い。お勧めです。
ちょっと「いつの時代?」と感じさせるような古き70年代のJAZZの響きながらマジにスカ。
しかも単になぞるという感じではなくて相当のめり込んでいる熱気が感じられるかる〜くクレイジーな人たちです。
女性ヴォーカルは今風な感じの歌い方でキュート。
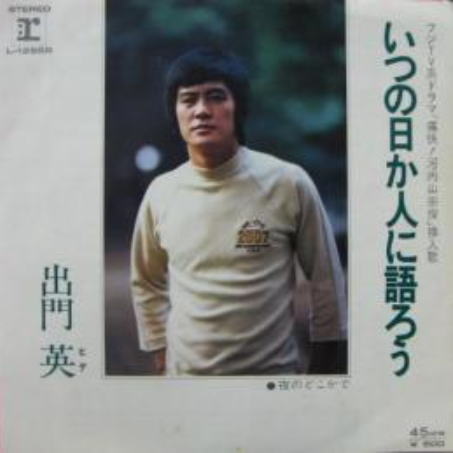
![]()
2015年 6月 12日
「ミュージック・ステーション」 ℃-ute
今日、「ミュージック・ステーション」で℃-uteを見た方に、断言しよう。
これが、℃-uteです。
ちょっとばかり肩すかしをくった、と思われた方。
実は、℃-uteをずっと見てきた古参のファンでさえ、そう思った人が多かったかもしれない。
ファンであればあるほど、℃-uteはこんなもんじゃない!と言いたくなったかもしれない。
しかし、迷う必要は全くない。
今日の℃-uteは最高だったじゃないか! ファンであるあなたの好きな℃-uteは、まさに℃-uteの全てを見せてくれた。
愛理はもうちょっと上手く歌えたはずだ。千聖は何とか水準レベルを出してきた。舞美、まいまいは少し上手くいかなかった。なっきいのダンスが生かせたとは言いがたい。
こんな歯がゆさがこみ上げてきたかもしれない。(勝手な私の感想です。℃-ute人気が爆発してほしいと思う欲求が、こんな苦い感想を引き出してしまう)
でも、そんなあなたは、℃-uteのことをちゃんとわかっている筈だ。
愛理が完璧ではないことも、舞美の音程が必ずしもパーフェクトではないことも。なっきいやまいまいの声質が、歌手の声としてはやや本流から外れるタイプの特徴ある声だということも。
それを好んで編成してグループを作り上げてくるのがハロプロであり、だから℃-uteを愛してきたのだ、という人が℃-uteのファンだと思う。
無敵な時の愛理をあなたは知っているし、舞美の声がどれほど掛け替えのない美しい声であるかを知っているし、なっきいのダンスやまいまいのおきゃんな声がどれだけ“たまらん”ものかを知っている。千聖がどれだけ℃-uteのベースを支えているか、千聖の貢献度の大きさを知っている。
誰をも納得させるような説得力を、今回℃-uteは見せつけることは出来なかったかもしれない。
だけど、℃-uteの良さって、そこに舞美という女神の声があること。まいまいのたまらん声があること。愛理が最高に未完の大器であること、千聖がああ見えてクールに支え続けていてくれること。なっきいがこんなにも無理して頑張ってくれていること(彼女は本当に大変なんだから。なっきいの美しさを本人が一番気づいてないから)。そういうところじゃないですか。
ハロプロって、そういうところを重視しているわけじゃないですか。
だから、これでいいんです! 今回もきっと、誰かが舞美やまいまいの魅力に気づいたはずです。
(ああ、やっぱりハロプロ好きって、ちょっと斜めな嗜好を持った体質の人間たちなんじゃないかな、と私は思います。 今回、マツコ・デラックスが本当に恥をしのんでという感じで、がらにもない宣伝を無理してやってくれましたが。「ハロプロは、ずっと密かに熱い」と、マイナーへ逃げを打っちゃうところも、いかにもハロプロ好きだな。やっぱりマツコ、本物だな、と思いました。 サイコーッ。


コラブロは℃-ute好き

う〜ん。これは確かに言葉失うわ。
![]()
2015年 6月 5日
6月12日 「ミュージック・ステーション」に℃-uteが7年ぶりに出演
来週、なんと7年ぶりだそうですが、℃-uteが「ミュージック・ステーション」に出演するとのことで。
本人たち的には、やっぱりここは勝負の時、だと思います。
ただもう、大一番での℃-uteってけっこう心配で..
ちょっと祈るような気持ちになってきます。

↑ Click とにかく圧巻だったひなフェスの映像
![]()
2015年 6月 5日
Juice=Juice First Albumのタイトルは「Juice=Juice First Squeeze!」 スクィーズ?!
ハロプロはサブカルか!?
ユトリロとヴァラドンについて語る和田彩花(ANGERME)さん
(私もユトリロ好きです。本持ってます。)
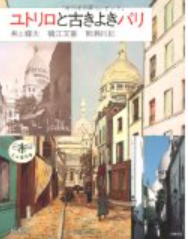 井上輝夫 『ユトリロと古きよきパリ(とんぼの本)』 (新潮社)
井上輝夫 『ユトリロと古きよきパリ(とんぼの本)』 (新潮社)
スティーヴィー・レイボーン、アルバート・キングについて、ハマ・オカモトと意気投合してブルース談義を繰り広げる高木紗友希(Juice=Juice)さん
(今はメイシオ・パーカー 聴いてるそう)
丸尾末広読んでた、小田さくら(モーニング娘。’15)さん
『ドグラ・マグラ』を中学時代に読破した広瀬彩海(こぶしファクトリー)さん
(近頃の子は夢野久作や丸尾末広の名を出してしまうことに抵抗がないのでしょうか?)
ウェス・アンダーソンの映画を、ウェス・アンダーソンの映画だからと見に行く菅谷梨沙子(ex.Berryz工房)さん
(シネフィルか!?)
カラオケに行って、山口百恵「ひと夏の経験」を3回歌った田村芽実(ANGERME)さん
(考えてみれば40年も前の曲)
一方、
「三丁目の夕日」を知らないことがバレて、自称“映画オタク”に疑いが掛かった前田敦子さん。
吉田 豪氏がNETニュースの見出しを見て、「三丁目の夕日を観ていない時点で、底が知れた」って、いいフレーズ! とツィート。
「ミュージック・マガジン」誌 6月号のCeroを中心とした新しいシティ・ポップの特集で、「山下達郎は神」みたいに言ってる若手バンドに話しかけたら「アイズレー・ブラザーズって何ですか?」と言われたという、シーンをよく知る人が語ったインタビュー記事。シーンの盛り上がりを喜んでいるんだか、嘆いているんだかわからないような内容。
サブ・カルが通用しないって感じが、いややっぱり80年代とは随分変わった、という気がします。
(ちなみに先日のANGERMEの武道館コンサートでは開演前のBGMにアイズレー・ブラザーズが掛かっていたそうです。)
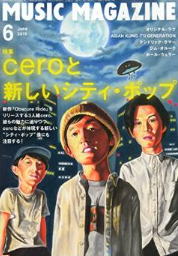
ここで、もちろんJuice=Juiceとは何の関係もないのですが、と言いつつ、Squeezeの曲を1曲

↑ Click Squeeze 「Up The Junction」
![]()
2015年 5月 23日
完全にXTCな「あすはデートなのに、今すぐ声が聞きたい」
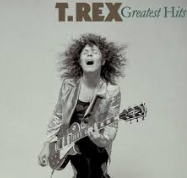



最近聴いているのは、T.Rex 「Greatest Hits」、こぶしファクトリーの限定シングル「念には念/サバイバー」、XTC 「Wasp
Star」(2000)、スマイレージ 「悪ガキ!」 (2010)あたり。
こぶしの「念には念」を聴けばT.Rexの「20センチュリー・ボーイ」あたりが浮かんでくるのは道理、というか意図されたものであるのは明明白白ですが、実際に比べてみるとイメージとしては強い割に曲調は随分違うんだなと思いました。「念には念」の方がドライヴが掛かっていて重量載せてる感じが出てる部分もあるんですよね。5月に入ってからのLiveの映像なんか見ると、こぶしファクトリーの体の重心の乗せ方が良くて(重心がかなり低い!)、全体にパワフルなパフォーマンスに磨きが掛かっているのを感じました。このグループ、やっぱりコミカル路線いけそうだなと、Berryz工房の後継として期待感高まってきました。
T.Rexの曲中のコールや煽りの声がハロプロのパターンに酷似しているのも発見。ハロプロの「イエーイ!」はもしかしたらマーク・ボランから来ているのかもしれない(?)
私はスマイレージって殆ど聴いてきていない(まともに聴いたのは「ええか!?!(2013)」が最初というぐらいかも)ので、今頃になって過去の曲を聴く作業を始めているわけですが、マツコ・デラックスが「スマイレージは最初からかなり出来上がったものを出してきた」といっていた意味がよーくわかった次第です。全員声は子供ですが歌は上手い(若干あやちょに不安があるぐらい)。ただ、当時有望視されていた前田憂佳さん(モベキマス「ブスにならない哲学」での声は衝撃だった)は、スマイレージでは十分発揮されているというところまでは行っていなかった気がします。このあたりがバランスの問題になるのですが、割と全員の声質が似通っていた点で前田さんの声を際立たせることが出来なかったのは惜しかったなという気がする。それよりも安定感のあるメンバーの声の中で、歌割り的には割り当てが少ない方である和田彩花(あやちょ)さんの鼻にかかったまま語尾でころころとひっくり返る特徴的な声の方が際立ちます。素質では前田さんの声が圧倒的であるのははっきりしているのですが、それがグループの中で生きるかどうかは別問題なのですね。
ところで、スマイレージの曲って、ひじょーにXTCな曲が紛れ込んでいると思うのですが、いかがでしょうか? (これも今更かもしれませんが)
「○○がんばらなくてもええねんで!!」も強烈に匂いますが、「あすはデートなのに、今すぐ声が聞きたい」は完璧なまでにXTCじゃないですか! こ、これはちょっと、スゴ過ぎる! 絶句のナンバーなんですけど。
ttps://www.youtube.com/watch?v=CYMW2EBjb8c
![]()
2015年 5月 16日
道重の「根性」
実は今週に入るまで、南波一海氏が元□□□(クチロロ)のメンバーだったとは知りませんでした!
そんなの調べれば直ぐ分かることだった筈ですが、何故かそこへ発想が向かいませんでしたね。
まあ□□□(クチロロ)をそんなに知っているわけでもなかった、というのもありますが。
その南波一海氏の使う言葉に「アイドル好きに“楽曲派”は存在しない!」というのがありますが、至言だなと思います。
今月の『ダ・ヴィンチ 6月号』に石田衣良、朝井リョウ、柚木麻子の座談会が載っています。ハロプロの魅力やアイドルについて語っている内容ですが、さすがに55歳の石田氏は冷静に見ているなと思いました。
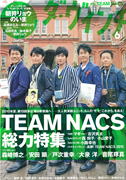 『ダ・ヴィンチ 2015年6月号』(KADOKAWA)
『ダ・ヴィンチ 2015年6月号』(KADOKAWA)
朝井「僕、鞘師とおださくには“星”を感じるんですよ・・・・・・。」
石田「“闇”ってことでしょ? なんか分かるなぁ。」
相当冷静に見ているし、相当ハロプロが好きですよね。
朝井「歌詞だとどの曲がぐっと来ますか?」
石田「ぱっと思い浮かんだのは『彼と一緒にお店がしたい!』」
石田「あとつんく♂さんの歌詞で感心するのはさ、僕も作詞するんですけど・・・・・・。」
朝井&柚木「『REAL YOU』だ!! (山田 優のデビュー曲)」
石田「1行目にね、どうしても力が入っちゃうものなの。でもつんく♂さんって、例えば『スッペシャル ジェネレ~ション』の1行目は、「どうたら こうたら」。あれは書けないよ。』
石田「基礎体力が十分にある人が、だんだんと自由に変態になっていった結果が、今のハロプロじゃないかな。」
石田「生涯未婚率の上昇とともにね。でもそれって恐ろしい価値観でしょ。僕たちはそういう人のほんとの辛いところを分からないけれど、応援される側のアイドルの女の子たちのためにもね、なんとか抜け出してほしいなあ。」
また、アイドル(特に女性アイドル)について、朝井リョウとの対談で、AKB48の高橋みなみさんが言っていた言葉が突き刺さります。
朝井「男性アイドルは40歳になっても、結婚して子供がいても、アイドルでいていいですよね。」
高橋「初期メンバーの間で「いつかSMAPさんみたいになりたいね」と話していたんです。でも、今や初期メンバーは3人になって、じきに私も卒業する。結局、そうはなれなかった。」
何か問題が生じている、というのは、アイドルもファンも感じているとは思います。
ただ、感じてはいるけど、その解決は簡単ではない。それは高橋みなみさんも言っていたように「珠理奈は別にいいんですって。「恋愛は大人になればいつでもできるけど、アイドルは今しかできないんで」」
という考え方も一方にあるわけで。
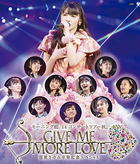
「モーニング娘。'14 コンサートツアー2014秋 GIVE ME MORE LOVE ~道重さゆみ卒業記念スペシャル~」
道重さゆみのラスト・コンサートに観客として来ていた朝井、柚木の両氏は、道重の最後の挨拶に「なんでこの子は全員の欲望に百点満点で打ち返さないといけないんだって気持ちになっちゃって・・・・・・。」「あの挨拶の間中、実はずっと辛かったんですよ。こんなにもアイドルとしての欲望を、つまり人間としての欲望の無さみたいなのを体現されたら、つんく♂さんがこんなに歌詞の中で人間の欲望を出してきたのに、道重さんの根性がそれを上回ったんだなと思っちゃったんです。」
これに対しては、しかし、鞘師が週刊マンガ雑誌のインタビューで興味深い意見を口にしています。(済みません。これはNETから拾ってきたんで、実際にマンガ雑誌で読んだのではないのですが)
「アイドルとは、ただの人間です。自分ひとりでは、何もできません。アーティストのように、自分で曲や詞も作れないし、仕事も見つけてこれないし、応援してくれる人がいなければ、ステージに立つこともできません。スタッフさん、ファンのみなさんが、輝く場所を用意してくれるから、アイドルはそこで育つことができるんです。だから、アイドルは全ての人に感謝だなって思います。」
この意見を良い意見だなと言ってしまっていいのか、ためらうところはあるのですが、たぶんこの意見は道重の考え方と近いと思う。
これを「道重さんの根性」という言葉で朝井、柚木両氏が表現したのも、至言だと思います。
物事が簡単ではない、というのは、朝井リョウ氏がメッセージとして考えていることはアイドルのためにもファンにとっても良かれと思って考えていること。つんく♂が考えていることにも「アイドルだって人間」というメッセージはある。(鞘師が言っている「アイドルとは、ただの人間です」は意味合いがちょっと違い、同じではありません) ただ一方で、アイドル自らそれを望まないという「根性」も存在するのだ、ということです。
石田衣良氏の言う「なんとか抜け出してほしいなあ」という言葉のニュアンスが歯切れの悪いものになってしまうのにはこういう難しさもあるから。
私は、個人的には道重の考え方は間違っていないと思うし、かといってアイドルが過酷な条件に耐えている理不尽さが許されるとも思わないし、実際その中で道重が見出そうとしていた答え(例えば、モーニング娘。の中で恋愛スキャンダルを起こす子が現れたとして、道重が排斥するかと考えたら、それはあり得ないと断言できる)を現在のモーニング娘。‘15は現に継承しているわけだから、この先どのようになっていくかは注目だと思います。
ひとつ意見として言わさせてもらうならば、モーニング娘。のDVD Magazineは、もっと一般市場で購入しやすい(もっと一般の目の届きやすいところにも置くこと)状況を作ることを提唱したいです。
アイドルの過酷さをドキュメンタリータッチで見せるのがリアリズム、というのが答えとは限らない。
ハロプロが作り上げた、というより、やはり道重が作り上げたというべきモーニング娘。‘14の、勿論DVD Magazineに映し出されているのは一面、または表面に過ぎないかもしれませんが、これは道重が理想をめざして試行錯誤した状況をおさめた記録であることは間違いないと思います。
無理をせず理想郷を作り上げるのって、すごい野望だと思う。道重の本当の凄さはここに出ていると思うから、必見です。
道重の卒業で一旦終わった、のではなく、この物語は、まだまだ続く。
 「MORNING MUSUME。’15 DVD MAGAZINE .69」
「MORNING MUSUME。’15 DVD MAGAZINE .69」
(道重 卒業発表シーンのあるvol.64~最新71まで、メチャクチャ面白い)
3月末に行われたハロプロのひなフェスの映像が素晴らしすぎて、もう20回近くは見直してる気がしますが、特にANGERMEになってからの9人体制での「夢見る15歳」を是非、紹介したい!と思っても、まだNET上に映像が無いみたいなので、本当に残念です。
スマイレージは勿論オリジナル・メンバー4人での「夢見る15歳」もその年齢ならではの掛け替えの無い感じがあって最高だし、6人になってのバージョンも良いのですが。
何しろこのグループは間違いなく9人になっての今のメンバーが最高の組み合わせだと思います。さらに初期メンバーであるあやちょ(和田彩花)とかにょん(福田花音 まろ)が、Berryz工房や℃-uteのメンバーがそうであったように、今、完成形を迎えつつあるのがはっきりと出ている、見てわかるのです。仕上がってきているというやつです。
まろなんか、今、最高潮だと思う。「夢見る15歳」での「なぜかさみしいよ」の部分の迸(ほとばし)ってる感がすごいことになってる。あやちょはあの声・存在がもうカリスマですから、「イヤホンで」の部分の観客があやちょに“のめり込む”熱狂の高さも初期とは比べ物にならないほどで、鳥肌ものです。
9人になったことで歌割りが新しい3人にも振り分けられている、というわけではないのですが、極めて個性的、下手すると悪目立ちしかねない6人の声に3人が新たに加入して、中和的な作用が加わったことで、6人の声がめりはりとして効果的になったのは非常に大きい。とにかくこのグループにはお姉さん二人の他にも、歌手としてのインパクトが大きいめいめい(田村芽実)とタケちゃん(竹内朱莉)がいるので、声としての面白さはハロプロの歴代の中でも1、2を争うユニークなグループであると思うし、前にも書きましたが、そうした個性的な声質の中に、正攻法ど真ん中のような声の持ち主であるむろたん(室田瑞希)が研修生から入ったことの意味の大きさは計り知れない。
それでいて、9人になったからといって、初期オリジナル時代からの、明るさの中にある哀愁がいまだグループに根付いたままだというのは、いったいどういうことなんだろうと、謎めいたまま、「夢見る15歳」はグレード・アップを果たしているわけです。
ANGERMEほど、過去の自分たち(スマイレージ)の名曲の数々を今のメンバーの声で再録音してほしいと希望せずにはいられなくなる、声が大成長を遂げたグループはないんじゃないか? 9人バージョンの「有頂天LOVE」も正式録音で是非、聴いてみたい。
6人の時の映像がここにありますが、正直、今、こんなレベルじゃないんで、本当に9人での「夢見る15歳」を見てもらいたいんですよねぇ。
ttps://www.youtube.com/watch?v=t0TyOH54mjk
![]()
2015年 5月 9日
最近聴いてる4枚




最近聴いている音楽は。ちょっとランダムな感じですが。
Built To Spillの新作「UNTETHERED MOON」(2015)は何と2009年以来のアルバムだったということに気づいて驚きましたけど。デビューの頃より新譜が出るたび必ず買って聴いているバンドではありながら、ある時期からマンネリというかあるパターンに固執する感じになって、3枚目以降はすぱーっと売っちゃったりして、手元には1枚目、2枚目と前作ぐらいしか無かったりします。新作は大きな変化はないですが、ギターにこだわる思いに初期のささくれだった感触が戻ってきている気がします。J・マスキスのギターを聴いているようなむせ返るような渇きを感じました。続けているというところに凄い意義があると思っています。なんだかんだで消えていってしまうアメリカのオルタナティヴ・バンドに失望していますので、続けるということが非常に重要だと強く思う。
全く毛色の違うサイモン・デュプリー&ザ・ビッグ・サウンド「ウィズアウト・レザヴェーションズ」は、このバンドの1967年の唯一のアルバム。このバンドは後にジェントル・ジャイアントに発展する。XTCのアンディ・パートリッジが、ジェントル・ジャイアントとXTCの音楽性に共通性を感じるというファンの声に対して、ジェントル・ジャイアンツには思い入れは特に無いが、サイモン・デュプリー&ザ・ビッグ・サウンドは好きだったとTwitterで答えていた。ただ、このバンドは当初はアラン・ボウン・セットやズート・マニーのバンドなどと競うブルース、ソウル、JAZZを基礎としてクラブ・サーキットを活動の場とする音楽性のバンドだったのが、サイケ・ポップの「Kite」という曲を会社の意向で発表し、ヒットしてしまったことから方向性が狂ったかのようにCDのライナーノーツには記されており、アンディはもしかしたらこの「Kite」のへんあたりが好きだったのかもしれないという可能性がある。今回聴いた唯一のアルバムは「Kite」は含まれない、初期のモッズ的な音楽が収められている。モータウン・マナーなロックンロールというモッズの奇妙な感じ(悪く言えば歌謡曲チックなロックンロールということです)。完全に私の好みの音です。スペンサー・ディヴィス・グループっていう感じです。分裂気味になってきてからこのバンドには元ナック(当時イギリスにいたバンドです)や元モジョズのメンバーが加入したりしているようです。
白波多カミンという子のサード・アルバム「白波多カミン」(2015)には早川義夫の推薦文が貼り付けてありました。ミドリやあふりらんぽのレーベルに見出されて出てきた子とは後で知って、ちょっと警戒感を抱きましたが、実際、エキセントリックなサウンド使いをするところもあって、それがオルタナティヴ・ロックやニュー・ウェイヴ、アングラ・ロックの優等生的抽出というまさにミドリやあふりらんぽみたいな“襟正しいアングラ・ロック”という行儀のよさが鼻につく、というのはあるのですが、(歌詞もあまり好きではありませんが)、「いますぐ消えたい」という曲のニック・ロウばりなカントリー・ロッキン・ギターに反応して聴いています。Blogのようなものを見たら、アイドルと私は違うと書いてあって、アイドルを下に見ているのとは違うというところはおさえているつもりらしいのですが、“アイドルが歌にこめているもの”“歌が好きだ”という視点がスコンと抜けていたので、駄目だなと思いました。あふりらんぽだって買って聴きましたし、白波多カミンさんのCDを買ったことは後悔しているわけではなく、気になる部分はあるのですが、今の時点では、ちょっとどうだろうか?という疑問があります。
清水靖晃「IQ-179 愛究壹百七拾九究」 (1981)は既にマライアで活動中でのソロ・アルバムですね。私は82年の「案山子」とマライアの83年の「うたかたの日々」は当時本当によく聴きました。「IQ」は初めて聴きましたが、マライアのメンバー総出演ですし、ソロにする必要あるのか?と思いそうなところですけども、さらに渡辺香津美、坂本龍一、吉田美奈子まで加わることで、80年代初頭の、それこそコリン・ニューマン(ワイアー)のいう「パンクでなければ何でもいい」という反意語的な、「・・・でないもの」をめざす相当変てこな領域へ踏み出すのに、こうしたソロ・アルバムは意味があったのだろうと、このアルバムを聴けばよくわかります。その次にはもう「案山子」を経て、マライア自身も「うたかたの日々」のような脱JAZZ、脱ロックな突き抜け方を達成させてしまったのだから、随分とスピードが速かったのだなぁと思う。マライアの流れがあって、WHa-ha-haやムーン・ライダーズ(「MIJ」)、鈴木さえ子のような音楽の流れも出てきたのではないでしょうか?
![]()
2015年 5月 8日
ハロプロ好きをやめられない理由(わけ)
ももち

楽屋で ももち先輩の最近の趣味、クロスステッチ (山木梨沙)
ハロ!ステ#116
「私の中では 舞ちゃんはずっと小学1年生のままで止まってる」(桃子)
小学1年生の時、「10年後、ももちゃんと一緒に暮らしてる」って書いた(萩原 舞)
「(もう)ないもんね、絶対!」
カントリー・ガールズの只今ラジオ放送中!! 5/3 #5
ハロメンの中で好きな声
島村嬉唄(うた)「うたねぇ、ももち先輩の声がずっと好きだったりする。実は」
山木・小関「ええーっ。 実は過ぎる!(笑)」
![]()
2015年 5月 1日
祝! 夏焼 雅さん 歌手活動 始動発表
もうすっかりファン・ブログのようになっているのですが、それでもかまわないかな、と思い始めてます。
夏焼 雅さんが、歌手活動の続行を発表してくださいまして、感涙にむせんでおります。
とにかくひたすらありがたいことです。メンバーを募集するという、グループでの活動を視野にいれているということだと思いますが、私は大賛成です。おこがましいですけど。
“グループを操れる声”だというのが、私が夏焼さんに持っている印象です。この場合、エース級を一人、別に用意するということになります。(例えば、菅谷梨沙子、鈴木愛理といった存在です)
エースを置くのですが、結果的にグループの主役は夏焼さんになると思います。
私が想像しているのはそういうグループです。おこがましいですけど。
理想は3人です。(じゃあ、Buono!でいいじゃねぇかって、そうなっちゃいますか)
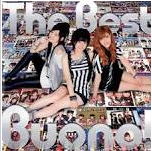 Buono! 「The Best Buono!」(2010)
Buono! 「The Best Buono!」(2010)
どのようなグループになるのか楽しみです。
激動のハロプロ。また動きがあります。
夏焼さんとハロプロ・アドヴァイザー:徳永千奈美さんのMCでYou Tube配信の新しい番組が始まりました。ハロプロの創作の裏側を見せていこうという番組で、ある意味ASAYAN(浅ヤン)への原点回帰的なものを明確に打ち出していこうという動きの一つじゃないかと思います。
 ← Click
← Click
新番組 「GREEN ROOM」 毎週木曜日更新
1回目の放送を見ましたが、番組の構成が「ハロステ」や「Music+」とあまり変わらない作り(机に座ったMCの比較的堅い進行)だったので、せっかく千奈美さんに出ていただくのだから、そこはスタイルを変えて、少し慣れてきたら「BZS1422」のとっくまのノリで進行するなどの方法も有りだと思いました。徳永さんのためにもその方が良いと思います。
[Berryz工房 名場面コレクション]

↑ Click Hello!project winter 歓迎新鮮祭りBっくりライブ(2010)
スマイレージ「スキちゃん」
(スマイレージの特徴は徹底的に明るい曲調の中にある哀愁)
高橋 愛の時代に一度ハロプロの頂点の時代が来ていたんだろうと、これを見るとわかるのですが、この時代はハロプロの難しい時代だった(2010年、AKB48は「ポニーテールとシュシュ」、「ヘビーローテーション」を発表している)のだろうとも推察されます。(私はこの時代のハロプロのことは殆ど知りません。メロン記念日は2010年5月に解散しているし)
この時代の特徴が、言い方は悪いですが目の上のたんこぶ的な先輩グループが全て抜けて、モーニング娘。5期以降で形成される点です。高橋 愛さんの雰囲気というのが、怒らない、仲の良いグループというイメージで、少し油断するとなぁなぁの緩い状態にもなってしまうのですが、一体になった時の多幸感が大きくなって、モベキマスという頂点を作り出すことになった。もう一ついえば、Berryz工房が子供の頃、指導が怖くて毎日のように泣いて、嫌だった、というトラウマから、従来のハロプロの方針に対する反発もあったのではないかと思います。(厳しい指導は人間形成に大切だとも認識しているが、それでも嫌悪感はあったと、私はBerryzの態度から推察します!)
“自分たちの世代がハローのTOPになった時”に対して非常に意識が強かったのがモーニング娘。 6期の道重さゆみです。彼女の理想は、高橋 愛のイズム(高橋 愛がどれだけ意識的だったかはやや不明瞭ですが、道重は、はっきりしていたと思う)を継承することだったのではないでしょうか。
どこかに言葉が明確に記録されていないか、調べてませんが、リーダーになってからの道重の言動を追っていけば、そう解釈してよいのではないかと思います。
これは会社(UP FRONT)は、意図していなかったかもしれません。ハロプロのメンバーがファミリーのようにアットホームな仲の良さをゆるゆると形成していくのを、会社側はどのように見ていたのか?
高橋 愛がいなくなってからのハロメンのTOPは、道重の時代になればもう道重、田中れいな、清水、嗣永、矢島といった6期、キッズ世代の王国になってしまったわけですから、自然とハロメンの“反抗”は水面下を潜航し、ハローの空気をいつしか完全に塗り替えてしまうことになった気がします。
恐らくこれは、道重らハロメンの革命に近い行為。
それが成功か失敗か...ハロー!プロジェクトがかつての栄光を取り戻すなどというとんでもない事態が起きない限り、評価は出ないでしょうが、既に理想の形が本当は2011年初頭には出来ていた!ということを、この「スキちゃん」の映像を見て、思いました。
それにしても、私はスマイレージって全然聴いてきていないので、今更にスマイレージを知る作業をしているのですが(「今さら ℃-uteを知らないなんて」のキャッチコピ-を馬鹿に出来ない)、実は良曲多しと、Berryz工房のように言われている評判だけは知ってましたけど、「スキちゃん」てめちゃくちゃ名曲ですね。
“タルーラ・ゴッシュ、ヘヴンリーを超える名曲”という、自分にとっては最大級の賛辞を送りたいぐらいスピード感、ザクザクしたパンキッシュなタテノリの切れ味、全く無駄の無いシンプルさ、ベースのうねり...さんざん作られてきたビート・ポップの枠にすとんと落としこみながら、これだけの名曲を書いてしまう、天才だな、つんく。
なお、頬っぺたがぷっくりしてた時期の佐紀ちゃん超絶に可愛いです。







ももち結びも未完成の頃。茉麻の髪型、初めて(?)見た。
![]()
2015年 4月 30日
British Popsの系譜 EQUALS
やっぱり そういうことだったのか!
「アンディ・パートリッジの初めて買ったレコードは?」
「イコールズの「ベイビー・カム・バック」か、ストーンズの「ジャンピング・ジャック・フラッシュ」」
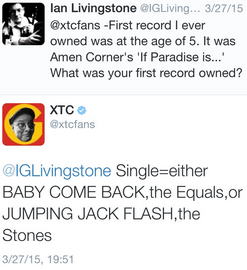
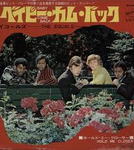
イコールズとかやっぱり聴いてるんだよな。
![]()
2015年 4月 29日
こぶしファクトリーの次は つばきファクトリー
相変わらずハロプロについてしか書く気がしないというか、激動過ぎて毎週何か起きるんで書くことにホント事欠かないんですけど、今日は今日でまたしてもハロプロ研修生から新ユニット結成で吃驚。会社として大丈夫なのか?と、会社経営の攻めか守りかみたいな悩みをこんなところで考えてみたりしちゃったりするんですが..
また、この会社(UP
FRONT)は何を考えているのかわからないようなところがかつてもいろいろ問題になったり(成功もあるが、けっこう失敗もある、というファンの認識は根強い)しているので、この新ユニットも単純に喜んでばかりもいられないという面はありそうです。
 花山十也 『読むモー娘。』 (コア新書)
花山十也 『読むモー娘。』 (コア新書)
読んだの、もう半年以上前になりますが、「ハロマゲドン」や「クソ事務所」など、ファンの立場から会社を痛烈に批判した部分もけっこう客観的に言葉にしようとしており”公平と言える本”だと思います。会社の犯した過ちという点も証拠が無いので黙っている、というわけには、いかない。やっぱりファンとして。
名前が“つばきファクトリー”。 先に結成した“こぶしファクトリー”に被せちゃった。これもいろいろ憶測を呼びながら会社は黙ってるんでしょうが、喜んでばかりいられないということでいえば、“こぶしファクトリー”の面々はBerryz工房を受け継ぐというキーワードを大事にしてきたので、自分たちだけじゃなくなったという扱いは気持ちとして微妙だと思います。まあ、UP
FRONTはそういうところはちゃんと説明しなかったりする。
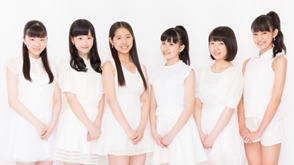
つばきファクトリー
いつの間にかそこそこ研修生の名前まで覚えてしまっていたりする自分は既に世間的にいう“気持ち悪い存在”でしょうが、とりあえず、新沼希空さんがメンバー入り出来たことは目出度い。きしもん(岸本ゆめの)もBerryzのツアーに帯同していたのを知っているので、ほっとしました。個人的には寄り目が私の好きなメアリー・タナー顔の一岡伶奈さんも“つばき”に入れてあげてほしかったなどと、書いてるうちにどんどん危うくなるので切り上げます。
このところ著名人、芸能人がハロプロについて語り出している現象が目立ちます。
と、あまり大袈裟に煽ってもいけませんが、それでも以前には無かったような現象が起きているのは間違いないと思います。実際、著名人が語るということで、ハロプロについては“物語が動き出している”のを感じます。もちろん著名人といっても世間一般に有名でメッセージが訴求力を持つほどの力を起こしているとまでは全然言い難いですが、“物語を語る”のに才のある人がポツポツと出てきているのは、けっこうハロプロにとっては大きいのではないかと思います。
 朝井リョウ 『武道館』 (文藝春秋)
朝井リョウ 『武道館』 (文藝春秋)
先日、作家朝井リョウの新作『武道館』が出版されました。これはアイドルを題材にした小説ですが、あくまでも創作であり明確なモデルは存在していません。ですが、SF翻訳・書評家の大森 望氏が、NETのコラムで、キー・パーソンとして℃-uteを挙げています。指摘が正解かどうかはわかりませんが、まさしく『武道館』はこのコラムのような読み方が望まれている小説であろうと想像されます(私はこれから読みます)。
大森 望氏がハロヲタとして最近いろいろ書き始めるようになったことで、ハロプロの物語が生まれ、動き始めている。その影響力は小さくないと思います。(単行本の帯にはつんく♂が文章を寄せています)
「50代からのアイドル入門 第12回 大森 望」
ttp://www.webdoku.jp/column/ohmori/
℃-uteについては、私はもう、今現在“日本一”だと言い切ってしまいたいという要求を抑えられずにいるのですが、この“日本一”というのは、Girls
Popとして、ということではなくて、現在の日本の音楽全体でという思いもあるのですけど、まあ当然たわ言扱いになるので止めておきますが、しかし、これについてはいろいろ考えているところがあります。(日本の音楽の中で、個人的には歌謡曲の偉大さを感じることが多いため、歌謡曲にこだわった場合の℃-uteについて考察してみたい)
その℃-uteは今年9月に初めてメキシコでLiveを行います。これを知ったのも今週。(本当にいろいろあるわけですよ!)

そう! 歌謡曲って、アメリカじゃないんですよ! アメリカが世界におよぼしたものではあるんですけど、歌謡曲の歌謡曲たる部分って、ディープなのはけっこうアメリカからの影響を受けた結果としてのラテンだったり、ヨーロッパだったり、アジア!だったりする。アジアだとインドネシアとかタイとかカンボシアとかそういう世界の方が濃厚に匂い立つものを放っていたりする。
日本のアイドル歌謡はフランスやメキシコにファンが多いらしいのですが、実際、℃-uteはフランスやメキシコで人気が高く、それが今回のメキシコ公演につながっている。私は、この℃-uteのメキシコ公演については、音楽メディアは大きく取り上げるべきだと思います。いわゆるクール・ジャパンとか、ジャパン・アニメ(とアニメソング、アイドルのタイ・アップ)とは℃-uteの人気は一線を画するものだと考えるべきだと思います。
もっと音楽(歌謡曲史)的に深いものだと思う。
 輪島祐介 『踊る昭和歌謡 リズムからみる大衆音楽』 (NHK出版新書)
輪島祐介 『踊る昭和歌謡 リズムからみる大衆音楽』 (NHK出版新書)
いわゆるメディアで踊る”昭和歌謡”のフレーズとは全くもって一線を画する正統な昭和歌謡論。ドドンパの起源を探ると日本の歌謡曲がみるみる世界に繋がっていくのが見える。
佐々木敦『ニッポンの音楽』と全く被らない音楽史をたどるところが極めてスリリングで面白い!
ハロプロについて物語を語り始めている人たちが現れてきている状況で、UP
FRONTが果敢に動いている様が、今、面白くて仕方ありません。
(意外にスポーツ新聞紙やマンガ週刊誌などのインタビュー記事で、ハロプロ・メンバーの重要なコメントが取れていたりする。専門の音楽雑誌より余っぽど刺激的、かつ笑いもあって収穫多い)
まだ続きます。
これもつい先日。 新人シンガーソングライターの瀧川ありさという子がハロプロ愛をインタビューでえんえん語って話題になりました。(特に℃-uteヲタです)

「Berryz工房の魂を受け継ぐ者になりたい」美人シンガーソングライター瀧川ありさ、ハロヲタ節炸裂インタビュー
ttp://otapol.jp/2015/04/post-2836.html
インタビューの内容自体素晴らしいのが、この子が自分が1991年生まれであることに言及した点です。
2002年、ハロプロでは「ハロー!プロジェクト・キッズ・オーディション」が行われます。彼女は応募するまでの自信が無く、結果の発表をTVの前に正座して見たといいます。91年生まれの彼女にとって、キッズ・オーデション以外に年齢基準の合致するオーディションは殆んどなく、キッズ・オーディションが唯一のチャンスだった。彼女にとってベリキューの15人は、選ばれし15人だったと言うのです。
1991年生まれを、こういう視点で語る人が出てきたというのも面白い。
(1991年生まれでは、例えばAKB系列では、前田敦子、板野友美、高橋みなみ、柏木由紀、松井玲奈、河西智美がいる。彼女らは清水佐紀、矢島舞美、嗣永桃子、真野恵里菜と同学年です)
ベリキューとベリキュー以後のハロプロの歴史について、彼女はほぼ寄り添いながら現在にいたっており、スマイレージの危機(ゆうかりんの卒業)とその後のあやちょの変化についても語っています。スマイレージというのはハロプロの歴史の中でも象徴的な悲劇を幾つも持つ(「スマイレージはいつもこうだ!」という名言がある)グループで、オリジナル・メンバーとして現在も残るあやちょ(和田彩花)、花音(福田花音 まろ)二人は近年のハロプロの物語における、それぞれに重要人物ですが、私も思うのですが、あやちょってかなりカリスマ性のある人物で(意外にも、と前置きしながらなのですが)、特にステージ上での仕草の一つ一つが、どこからこの妖気は出てくるんだ?というぐらいに妙に惹きつけるものがあって、スマイレージ(現アンジュルム)の悲劇性と重なりながらあやちょの変化が一種妖気に満ちた物語を形成していってるわけです。

押しが強くないので目立ちませんが、ハロプロで極めて重要な存在あやちょ
![]()
2015年 4月 24日
想定外の変てこな佳作
「リトル ホスピタル vol.1、2」(2003年 日)安田真奈 (DVD)
3月半ばにはもう見ていたのですが、書くのが遅くなってしまいました。ベリロスによる傷心でBerryzの映像が見れなくなっているファンが多くいるらしい中、ファンになってキャリアの浅い自分はむしろ今から見ることの出来る過去の映像が山のように残っているわけで、あらためて出会いをやり直しているような感じです。

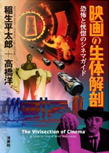
この「リトル ホスピタル」というTVドラマは2003年(つまりBerryz工房結成前)に1話4分、全55話で放送されたドラマで、患者が少ないものすごーくヒマな小児科を舞台に、盲腸で入院した女の子(村上 愛 その後℃-uteに入る)とナンチャッテ看護婦(加藤紀子)のやり取りを脱力系のいわゆる退屈でまったりしたペースで描いているのですけど、見てみたらけっこう見応えのある演出で面白く、堪能しました。


ギプスの中がキノコだらけの図
脚本・監督を安田真奈という人が行っているのですが、全く知りませんでしたけれども自主映画で名を知られていた人らしく、その後メジャーの劇場映画で「幸福のスイッチ」(2006)を撮ったりもして、その後、結婚・出産などで少し活動を控えていたりするものの、また最近活動を始めつつあるようです。ちょっと他の作品も見てみたい監督です。
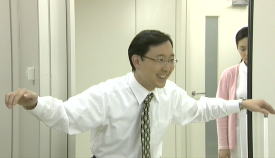
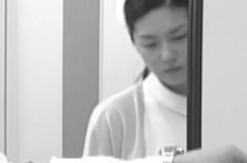
「リトル ホスピタル」は、脚本も本人ということで、どれぐらい自由に権限が与えられていたのかはわかりませんが、製作サイド側の要求だった可能性があるにしても、女の子3人(数話後に夏焼 雅、熊井友理奈 が揃って骨折で入院する)を3つのベッドに並べるというところから、どうもこの監督のホラー趣味のようなものが透けて見える感じはあって、ドラマの冒頭で、盲腸を手術した村上 愛にナンチャッテ看護婦の加藤紀子が「体の悪い部分をバサッ、バサッと切り取って」みたいに大袈裟に刃物を振り回すような仕草を見せて手術の様子を説明し、女の子を泣かすという、何やら物騒な空気感を出していて怪しげな雰囲気はあったのです。


あからさまに手術用具などを画面に入れ込んでくるようなことはありませんでしたが(そもそも脱力コメディが本筋であって、そういう話ではないのです)、ほのかに匂わすところはあって、その趣味っぷりを見て、「手術台」とか「放電」とか隠微な趣味性でテーマを括って映画論を展開した『映画の生体解剖~恐怖と恍惚のシネマガイド』を著した稲生平太郎、高橋 洋両氏あたりが反応しそうな作風だなと思いました。


熊井ちゃんの口(子供のころから変わらんな)
後半にはそのものズバリというようなホラー演出のシーンもあって、唐突過ぎて度肝を抜かれるのですけど、正直本当に怖いシーンで一瞬ゾゾットします。もう一度言いますが、このドラマ自体はだらだらぁーとしたコメディであって、ホラーとは何の関係も無いテーマが本来のものなのです。
まあ、割とアイドルものはガードが緩かったりするので、こそこそっと好きなことをやってしまっても文句を言われない自由なところはあったりするのですが、けっこう大胆に盛り込んできてるなぁという演出でした。

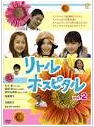

なお、ドラマの中心は加藤紀子と村上 愛で、友達として見舞いに来ていた雅ちゃんと熊井ちゃんが、数話後には揃って骨折で入院するという強引なストーリーで、コメディとしてもすっとぼけていて割合いけます。中では熊井ちゃんが、元太陽とシスコムーンの稲葉貴子と親子関係で、いいコンビで笑わせます。
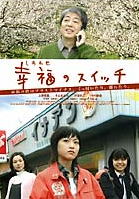
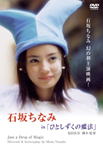
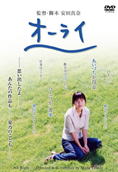

井口 昇監督「猫目小僧」では脚本を担当している
![]()
2015年 4月 21日
床の鳴る音が聞こえた「青春小僧が泣いている」フルコーラス

昨日、BSスカパー!で放送された音楽番組「FULL CHORUS ~音楽は、フルコーラス~」(司会:ベッキー、ハマ・オカモト(OKAMOTO’S))にモーニング娘。‘15が出演していました。
この番組はゲストに曲をフルコーラスで歌ってもらうのを番組の主旨としているのですが、そのため通常のTV番組であればワンコーラスで終わる「青春小僧が泣いている」をフルで歌ったことにより、他の番組では見られない、間奏のダンス場面も披露され、この場面は割合音を少なめに落としてメンバーが軽いステップで踊りながら移動するのですけど、移動するときのステージの床が小さくミシッ、ミシッ と音を立てるのが聞こえてきたのです! これはけっこうインパクトのある放送だったのではないでしょうか。臨場感のある素晴らしいステージになったと思います。
この臨場感が出せるなら、今後も面白い音楽番組になるのではないでしょうか?
来週は、おそらくハマ・オカモトがハロプロの中でも最も気に入っているであろうJuice=Juiceが出演予定なので、司会もテンション上がるんじゃないかと、期待しています。
![]()
2015年 4月 20日
超HAPPY SONG
以前に「超HAPPY SONG」は何だかんだいってもやっぱりベリキューのがいい。と、書いたのですが。
間違ってました。
今、久しぶりにBerryz工房×Berryz工房で聴くと、音楽全体からあふれ出してくるものが「しあわせ」過ぎて、まあ情けないぐらい泣けてきました。あくまでも個人の好みの問題ですが、すべてベリのが良い。訂正します。
このバランスはどう考えても今後二度と現れることはないだろうと思う。何しろこの50年でこれほどの奇跡のバランスは存在しなかったのだから、今後50年も無いに違いない。
[Berryz工房 名場面コレクション]

↑ Click (この映像、Clipがどれを取っても超HAPPY)
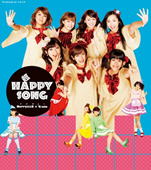 Berryz工房×℃-ute 「超HAPPY SONG」 (2012)初回限定盤C
Berryz工房×℃-ute 「超HAPPY SONG」 (2012)初回限定盤C
(「超HAPPY SONG」とは、Berryz工房の「Because Happiness」と℃-uteの「幸せの途中」の合体曲です。)
Berryz工房Ver.の「幸せの途中」が聴けるのはこのシングルだけ。(初回生産限定盤C)
2ヴァージョンをMixして「超HAPPY SONG」Berryz工房×Berryz工房は完成する。(初回限定盤Dは逆に℃-uteVer.の「Because
Happiness」が入っている。)
℃-ute×℃-ute Ver.の「超HAPPY SONG」はこちらで聴くことが出来ます。勿論、こちらはこちらで魅力的です。
ttps://www.youtube.com/watch?v=nOlWtwXIueY
ただ、℃-uteの魅力というのは、「バランス」とは違う部分にあると思う。Berryz工房の場合は、どう考えても「バランス」というしかない絶妙な構造が存在する。
Berryz工房×Berryz工房
Ver.の「超HAPPY SONG」の音質的にナチュラルにMixされているのはこちらの音がBestかもしれない。
ttps://www.youtube.com/watch?v=ifeF47sE3u8
![]()
2015年 4月 19日
ロックの神様
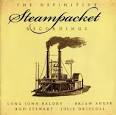
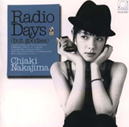
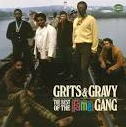

最近聴いてるもの。スティーム・パケットの2枚組CD!(「The Definitive Recordings」)なんて出てるの知らなかったので、見つけて即買いました。やっぱりスウィンギング・ロンドンというか、この時期の音楽が一番自分には馴染む音楽かも。
スティーム・パケットのメンバーといえばロッド・スチュワートと、ブライアン・オーガー、ジュリー・ドリスコールのトリニティーが有名ですが、そのロッドがスティーム・パケットの後に加入したバンド、ショットガン・エキスプレスというのが、後のフリートウッド・マックとなるミック・フリートウッドとピーター・グリーンが在籍していて、そこのバンマス(?)だったピーター・バーデンスはこの後Love・Affairに加入する。しかもこの人、62年頃にはレイ・ディヴィス(Kinks)とバンドを組んでいたというのだから、Kinks、ロッド、フリートウッド・マック、Love・Affairが繫がってしまうという、「何なんだ! この時代」という感じです。ショットガン・エキスプレスも聴いてみたい。さらには何気にドラムのミッキー・ウォーラーという人は一時期ロッドと一緒にジェフ・ベック・グループに加入。ギターのビック・ブリッグスはアニマルズでアンディ・サマーズと同時期に活動している。
中島ちあき(「Radio Days(but goodies)」99年)はたまに思い出したようにCD取り出して聴いています。もっぱら「Chain My Heart」という曲ばっかりなのですが。サウンド的には渋谷系の流れにもあると思うのですが、ちょっと時期的には外れていたのと、Voがウェットなバラードに合うタイプの人で少しコンセプトとしてちぐはぐなところがあったかもしれない。黒沢健一(L⇔R)がプロデュースしたりもしましたが結局1年ほどで活動は終わってしまいました。
ジャケ買いしてしまったのがザ・フェイム・ギャングの「グリッツ&グレイヴィ ザ・ベスト・オブ・ザ・フェイム・ギャング」。
これはマッスル・ショールズ(アラバマ州)のフェイム・スタジオで活躍したスタジオ・ミュージシャンの集団。録音は第3期と呼ばれるメンバー構成で行われたもので3期の活動期間自体はそれほど長くなく2、3年ということのようです。
ただ、いわゆるマッスル・ショールズのサウンドというのはフェイム以外にもあり(スワンパーズと呼ばれる)、ボズ・スキャッグスらの録音はそちらになるのでちょいややこしい、らしい。また、フェイムの録音も3期以前がアレサ・フランクリンやウィルソン・ピケットの録音などで有名らしく、言わばマッスル・ショールズという著名の下に半ば埋もれた状態としてある3期の存在に焦点をあてたもののようですが、キャンディ・ステイトンなどはこの3期フェイム・ギャングと関わりが深いらしい。しかし、ブラス有り、オルガンが最高(過去にスプーナー・オールダムも在籍している)だし、ギターもグルーヴィで、サザン・ソウルってイメージとはちょっと異なっている気もするのですが、全く詳しくないのでわかりません。リズム・セクションとしての強調が私には気持ち良くて好きです。
打って変わって、ありがちながらも「これ、これ」って思わず言いたくなる“間違いない”サウンドを鳴らしているCourtneysというカナダはヴァンクーバーの女性3人組のバンドもリズムがツボ。
ニュージーランド、フライング・ナンのサウンドの影響を受けていると言われ、ジャングリーにビートを転がす特徴が良く出ており、ザリザリ感、もやもや感を内包している生きた音がする。2013年のファースト・アルバム「The
Courtneys」。こういう不安定さを内包したままのバンドっていそうでなかなか居ない。
[Berryz工房 名場面コレクション]
 「Berryz工房 デビュー10周年記念スっぺシャルコンサート2014 Thank You ベリキュー! in 日本武道館 後編」 (DVD
2014)
「Berryz工房 デビュー10周年記念スっぺシャルコンサート2014 Thank You ベリキュー! in 日本武道館 後編」 (DVD
2014)
アイドルがロックを歌うことについて。はなからまともに話をする気にもなれないという人は多いんじゃなかろうかと思いますが。まあ、それはもっともな反応という気もするし..
この武道館LiveではBerryzのLiveの途中にBuono!が出てきて「ロックの神様」という曲を歌います。
あくまでも3人はアイドルとして歌っているのは間違いないのですが、これは“ロックではない”のか..?
歌詞は、文化祭の体育館で衝動メロディをかき鳴らす下手くそトリオバンド。小さなステージでも私たちにはブドーカン、という内容で、メンバーはこれを武道館で歌うのが念願だったという、夢がかなった瞬間です。ロック・アンセム的なメロディ、サウンドでもない。でもこれが衝動にまかせた歌唱であるのは伝わってくるのではないでしょうか(実際、ももちは、まあまあ歌えるようになった時期からは上手く歌おうとするよりも気持ちを優先することに決めたと語ってたりします)。
若干放任主義的で、バラバラなグループといわれたBerryz工房は、重要なところでも個人の勝手を許してきたところがあり(本のインタビューでキャプテンの清水佐紀が、キャプテンだからまとめろとスタッフに言われ、「冗談じゃないですよ」とまとめるつもりなど無かったことを明かした事がある。結局この清水佐紀のある意味強情な意思がBerryz工房をかけがえの無い存在にし、ももち始めメンバーが(いい意味で)勝手し放題となる基礎となった。)、ギリギリまで個人を尊重するという共通認識が強固なグループとなった。彼女たちが尊重した自由、衝動、快感原則がどんなものだったのか。Rockであろうがなかろうが、けっこうここは重要なのではないかと思う。(つまりこの偉大なる佐紀ちゃんがまとめたくないと思った部分こそが肝であり、これはロックが掲げる自由にも関わってくる核心部分でもあると思う)
しかし、Berryz工房って、あれだけ自由なグループのように言われながら、それでもラストコンサートの最後の挨拶でそろいも揃って「辛いことのが多かった」と愚痴たらたらだったのが最高に面白いグループだなと思いました。
 ← Click
← Click
![]()
2015年 4月 11日
モーニング娘。'15 における譜久村 聖の最重要性
モーニング娘。‘15。 道重さゆみはいなくなりましたが、このグループは既に次のステップに進んでいます。
あまり取沙汰されていないようなので、強調しておきたいと思う。
Voの割り振りにも変化が見られます。その大きな特徴として上げたいのが
1. まーちゃん(佐藤優樹)の自由度が増しているということ。
・・・もともと絶対音感を持ち、歌唱力には期待感を抱かせる存在でしたが、今まではどちらかというとPOWER系の役割で割りと一本調子にSHOUTを要求されていたのですが、ここへきてある程度自由に、可愛らしい声なども混じえて表現のバリエーションを持たせる方向に変わってきています。これは13人になってからの新しいモーニング娘。を象徴する特徴です。
2. その表現のバリエーションがモーニング娘。‘15の大きな特徴となってきているのを最も象徴している声がふくちゃん(譜久村 聖)です。成長著しく、ハロプロには珍しいぐらい色艶のある声でなまめかしい。モーニング娘。’15の声が一気にグレードUPした感があります。
3. 鞘師、小田、石田の3人の声が全体のベースとなります。道重卒業後、だーいし(石田亜祐美)の声の比重が増しています。基本的にはまーちゃんの分までPOWER系を背負うという感じで、重要な役目ではありますが、脇役に徹するという意味合いになると思います。
4. ズッキ(鈴木香音)、くどぅー(工藤 遥)は、元々歌唱力は安定していて、歌える子なのですが、歌割りの割合が少ない。それだけ、今、上記の5人を歌唱メンとする体制が、モーニング娘。‘15のカラーを特徴づける基本として重要視されているということなのではないかと思います。
5. 12期はまだ未知数なところがあります。ただ、真莉愛(牧野真莉愛)は、声もよく出ており、既に全体の中でポジションを獲得しつつあるように思います。
個人的には鞘師の強さ、小田のウエットさ、この2本の柱に対し、譜久村、佐藤の表現力が加わった(開放された)のは、モーニング娘。‘15にとって非常に大きな変化だと思います。この二人の台頭によって、さくら(小田さくら)の特徴がより生きる形になっており、今まで負担が大きかった鞘師が、若干役割が小さくなるとはいえ、それはエースとしての鞘師の位置を脅かすものという意味ではなくて、いよいよ今のモーニング娘。’15の理想的な形(バランス)が明確になってきたことをあらわします。

↑ Click 「夕暮れは雨上がり」 4月15日発売
「夕暮れは雨上がり」において、工藤、鈴木のパートが殆んど無いという事実は、たまたまということではなく、極めて機能性が高まり、役割分担が完成度を上げていることの証明だと思います。曲によってはこの二人や生田、飯窪もフューチャーされる場面が出てくると思いますが、この、人を余らせるほどのバリエーションの豊かさは、今、日本のヴォーカル・グループの中でも突出して優れているのではないでしょうか?

↑ Click 「TIKI BUN」
それにしてもつんく♂の楽曲は、今凄いところへ来ている(特にモーニング娘。の楽曲において)気がします。「TIKI BUN」が殆んど無視されましたが、あれは無視していい曲ではなかった。今やこのレベルの楽曲を作曲できている存在は日本にはいないと思う。あの曲が無視される意味が全く理解できない上に、既に次に「青春小僧が泣いている」が来ているわけです。あれだけサイレント部分を連発して挙句に「クラっと来ちゃて青春だね」「Yo!」「誰ぞ」「フォー!!」とくる楽曲です。
この曲を現在の日本の代表曲として提示できないところが、もはや国の不幸かなと「妄言めかして」つぶやきたくなるほど、どこかで方向性が狂っている気がしてなりません。

↑ Click 「青春小僧が泣いている」 4月15日発売
[Berryz工房 名場面コレクション]
声が出ない梨沙子にたまりかねてコールが入ったBerryzの最後の歌唱
https://www.youtube.com/watch?v=mBamlzp2E7g
(すごいねヲタコール。佐紀ちゃんの2度目のコールはちゃんとタイミング微調整が入ってる)
![]()
2015年 4月 10日
イーストウッドに乗りきれないとは...
これから書いてあることは、文芸誌『文學界』5月号の特集「映画狂宴」蓮實重彦x青山真治x阿部和重の鼎談の内容にかなり触れているので、これからそれを読もうと思っている方は、文芸誌の方を先に読んでから、こちらに進んでください。済みませんが、よろしくお願いします。
 『文學界』5月号 (文藝春秋)
『文學界』5月号 (文藝春秋)
文芸誌『文學界』5月号で、「映画の狂宴」という特集が組まれており、蓮實重彦x青山真治x阿部和重の鼎談が載っています。イーストウッドの新作「アメリカン・スナイパー」についてかなりページを割いて語っており、面白いのですが、どうも結局御三方とも語尾をにごした感じで曖昧な評価に終わっていると思いました。第一に、製作に名を連ねた主役のブラッドリー・クーパーの意向(野心でしょうか?)が働いており、イーストウッドが雇われ仕事的に引き受けているという予測めいた意見を述べていますが、「アメリカン・スナイパー」に対してそんなゴシップまがいの意見を批評のまな板に乗せますか?というあきれた感じが、3人の意見から次々出てくるのが失望感ありましたね。面白かったけど。
この映画の謎のポイントといえば、イーストウッドがイラク側を人でなしの殺戮者のように扱い、イラクが悪でアメリカが正義であると言いたげな描き方になっているのは何故か?という点と、スナイパーのクリス・カイルはヒーローなのか、ヒーローではなくただのバカ野郎なのか、イーストウッドはどのようにとらえていたのか?という点です。
これについては蓮實氏が“Savage”という言葉を用いて語っています。訳して“蛮人”としているのですが、クリス・カイルはイラク側を“蛮人”と言い放って憚らない人物で、醜悪な人物と断じています。アメリカ映画は歴史的に“蛮人”と言い放った人物は映画の中で必ず罰せられてきた(「アパッチ砦」のヘンリー・フォンダ演じた中佐など)が、今回、クリス・カイルは映画の中において罰せられなかった(現実において、或る事件で殺されてしまったが、これは映画で罰したのとは違う)。これはアメリカ映画ではかつて無かったことで、イーストウッドが初である、とし、「感服した」と結んじゃうのですが、ただ、結論としてカイルを肯定的に描いているのか、否定しているのかは、どちらともわからないと答えています。
私は蓮實氏と違って、クリス・カイルを醜悪な人物とは考えていません。現実の人物がどうだったかはわかりませんが、イーストウッドが描いたクリス・カイルは、過酷な状況の中でかなり頑張った人物としてとらえているように思います。幾つかのシーンでクリス・カイルは本当に思慮のある判断をしている。イラク人を蛮人としか思っていなかったのが本性であったなら、後半に出てくる子供も撃ったであろうと思います。徐々に変わっていったんだ(戦場で帰国する弟に会ったのを契機に、という意見は青山氏から出てきてはいましたが)というのもあるとは思いますが、つまり、イーストウッドは頑張っているクリス・カイルを描いているということです。帰国したのに、真っ直ぐに家に帰らず、バーで泣いて時間潰ししているクリス・カイルをイーストウッドは描写しましたが、この人物はPTSDと戦っている。PTSDを克服しようとしていた人物として、アメリカ映画に初登場した人物だったのではないでしょうか?
そのあとは、例によってキャサリン・ビグロー「ハート・ロッカー」のこき下ろしに入るのですけど(「アメリカン・スナイパー」には正直乗れないが、「ハート・ロッカー」よりは数段ましという比較論法)、ここへきて、若干迷いがあるのか、阿部氏はビグローの次作「ゼロ・ダーク・サーティ」については、悪くなかったと、少し認める発言をしています。「ハート・ロッカー」については、どうしてこういうことになっているのか、私には全く理解出来ないのですが(どこが駄目なんだかさっぱりわからない。良いところしかない!)、何しろ「ゼロ・ダーク・サーティ」を見ていないので、大きなことは言えない。
「ジャージー・ボーイズ」はもう全然駄目みたいなこと言ってますね。しかし、そうだろうか?
あれはもしかすると、もっと素直に“オフビート”な映画ととらえれば、面白いのではないかな、と思います。
青山氏が、イーストウッドの近年作でのガラスと鏡に注目していましたが、「ジャージー・ボーイズ」は確かにガラスと鏡に意識的だったと思うし、それが冴えなかったのではなくて、むしろ冴えていたんじゃないかと思う。もう一回見て確かめてみたいと思いますが。
あと、「アメリカン・スナイパー」を、世評に反して、さほど西部劇的ではないと評し、西部劇にある高揚する場面がないといっているのですけど、ちょっと天邪鬼にすぎるのでは...
見た人で、エンターテイメントとして面白すぎるのが欠点だ(シリアスな題材なのに)という意見が巷ではけっこうあったのですが、実際、仲間が殺され、引き返すことなど出来ない!とグループの怒りが一気にヒートアップする場面などあって、西部劇的エンターテイメントの高揚は十二分にあったと思います!
![]()
2015年 4月 7日
あーりー急成長で いよいよ面白くなってきたJuice=Juice
Juice=Juiceの新曲「Ça va ? Ça va ?(サヴァサヴァ)」は、殆んど70年代歌謡曲そのものというマニアックなメロディーで、これを両A面シングルにしていいのかなぁ?という気もしますが、上手いこと現代風にアップデイトしてると聴こえなくもないし、今の人がこれを聴いてどう思うかというのは楽しみでもあります。
でもやっぱりこういうB級テイストの曲ははっきり「B面」と割り振ってくれた方が、CDを買った時の密やかな楽しみという感じでうれしいんですけどね。
この曲、聴きようによってはまるでモノクローム・セットでしょ?
一見、優等生っぽいグループなんですけども、歌唱メンの3人がそれぞれ全く異なるテイストを持っていて、本当のところ交わって無いところがJuice=Juiceの奇妙な味になっている気がします。
少し前に、雑誌のインタビューで宮本佳林ちゃんが(父親からの影響で)「プログレが好きです。」と答えていて、アイドルの子が「プログレ」言った、と、あくまでも狭い界隈にて話題になりましたが、それで好きなのが「エイジアだ」と答えて、界隈は「エイジアがプログレ・・・?」と一瞬言葉に詰まりつつ、「エイジアでむしろほっとした」という感情になったと思いますが、いっそヴァンダーグラフ・ジェネレーターとか答えられた日にゃ思いきり引いちゃうでしょ。
ただ、佳林ちゃんのやってたコピンクは少しジャパン・プログレの要素が入ってたと思うし、彼女の雰囲気が、メルヘンゴシック・ファンタジー的要素を実は持ってるところがユニークな歌手だと思います。一方で紗友希(高木)やかなとも(金澤朋子)は声のキャラクターが全然違う。そこへ最近になって急激に伸びてきたあーりーのスーパー・ナチュラルな声と、ある意味貴重さを増してきたリーダー:ゆかにゃ(宮崎由加)の微かに不安定な声が絶妙なバリエーションというメチャクチャ面白いヴォーカル・グループになってきてます。こういうグループには「B面曲」の遊びが凄くお楽しみになってくると思う。
特に奇妙な味で練り上げるB面曲だからこそ、あーりー(植村あかり)の澄んだ声が際立ってくる気がします。

↑ Click 「Ça va ? Ça va ?(サヴァサヴァ)」 4月8日発売
![]()
2015年 4月 5日
「やっぱ、ウチの兄貴は最高!」 メロウクアッドがサイコーな件



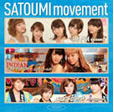
最近聴いてる音楽。いろいろ聴いてはいるんですが、なかなか落ち着いて何か書いてみようというような状態に持っていけてないのですが、まあぼちぼち書いていきます。ポップ・グループとかクラムボンの新作なども近いうちに少し書いてみたい。
The Go! Teamの新作「The Scene Between」は前作から4年振りですか。なんだかんだでこのバンドも新作出るたんびに聴いてます。好きですね。今作はマイ・ブラッディ・ヴァレンタインがフィフス・ディメンションの曲をやっているような感じ?といいますか、けっこうありきたりにPOPな佇まいでヒップ・ホップやミクスチャーをちょこちょこ盛り込んでくるというところは影を潜めてますが、その分、タルーラ・ゴッシュやフラットメイツのようなバブルガム・ポップな味がもろに前面に出た曲が並びました。“ありきたりな”などと書きながら、このアルバムを相当に気に入っているのは、結局根本の部分で“やってはいけないことはやらない”という音楽に対する真摯な姿勢が貫かれていてブレが無いことに尽きる。つまり精神はフラットメイツの強靭さに通じているということです。
モノクローム・セットも元気に新作「Spaces Everywhere」が出ました。とどのつまり、ということでビド、アンディ・ウォーレン、レスター・スクエアーの三人が残っている(他のメンバーはサポート・メンバーということになるのでしょうか?)わけですが、今、見回しても、結局モノクローム・セットのような音楽をやっているバンドが他にいない、という結論に達して驚いてます。この人たちしかこんな音楽やる人いないんだぁと思ったら、何だか泣けてきました。境地に達した部分もあるのか、なんの気兼ねもなく好き放題にやっているので細かいところまでマニアックな小技が仕込まれている精密さがたまりません。ベテランにありがちな一筆書きの境地に至る簡略さとは反対の方向へ舵をきったところが嬉しいです。
モデスト・マウスもかなり久し振りだと思いますが新作「Strangers to Ourselves」を発表しました。確か前作まではジョニー・マーがいましたよね。今作には参加していないようです。
しかし、モデスト・マウスがこんな長きに渡って活動を続けるとは思いませんでしたね。あのちっぽけなUp Recordsから出て来た時は全く評判になりませんでしたし、まさかメジャーで売れるなどとも想像しませんでしたし.. ビルト・トゥ・スピルももう直ぐ新作が出るんですよね。非常に地味な存在だった両者なので、感慨深いです。今作でも無国籍化したアジアン・ブルース的な旋律やサウンドは健在で、このバンドも本当におかしなことをする奇ったいな連中です。お勧め。ジョン・マッキンタイアも絡んでますね。
もう一枚は少し前ので、またかい?というハロプロ関係のですが。これ、ほんの少し前のですけど、もう最近の新規のファンからすれば見たことも聞いたこともないようなものだと思うので、あえて紹介したい。
2013年のSATOUMI movementで企画された3ユニットの曲を集めたDVDです。CDも出ていますが、DVDの方はPVとともにAnother ver.も沢山加えられており、見応えあります。
何といってもHI-FIN(中島早貴、萩原舞、福田花音、生田衣梨奈、石田亜佑美)の「海岸清掃男子」が珠玉なんですが、この曲の作曲者:加藤祐介はカントリー・ガールズの「愛おしくってごめんね」も手掛けた人で、ハロプロ・ファンとしては注目の人ですよね。このHI-FINというユニットは、私の中ではもうこれでデビューしてもらいたいと思うくらい完璧な組み合わせで、各グループのNo.2的存在が集まってる手強い感じが曲調も相俟って非常に格調高いポップ・ミュージック(例えていうならばギャング・ウェイみたいな感じ?)に聴こえたんです。新しいファンの人は知ってる人少ないと思うので、カントリー・ガールズに興味を覚えた人なんかには是非聴いて欲しい。生田もメチャクチャ可愛いし、私はこれで萩原 舞さんを発見しました(遅まきながら)。それからダイヤレディー(鈴木愛理、菅谷梨沙子)の曲は中島卓偉作曲ですから、今こそこのDVDを見直すタイミングなのではないでしょうか?
もう一つのユニット、メロウクアッド(矢島舞美、岡井千聖、徳永千奈美、夏焼雅)はお祭り気分のお遊びSONG(「エイヤサ! ブラザー」)で、当時あまり人気なかったような気がしますが、Berryz工房ファンにはちょっと侮れない曲です。千奈美の代表曲の一つと言ってもいいと思うんですね。ファルセットで歌うところと、歌割りソロで歌う場面が素晴らしい!出来なのです。 これ、ノーマークで見落としがちなので、けっこう驚くと思います。千奈美はホントこの飛び道具があるので、歌が上手いとか下手とかいう価値基準を斜めから超えていくから、どちらかというと「千奈美は、歌、上手いよ」と言いたくなっちゃうんですよね。(実際、ほぼ、そう思っちゃってるしね)
他にも雅ちゃんがDJ雅で一瞬登場するので、お楽しみ満載です。「ぴちぴちのサバやアジ」とか歌うところなども、「もーう、ハロプロ!!」という最高さです。

![]()
2015年 4月 5日
そこに物語があるということ
ハロプロに限りませんが、ももクロでもAKBでもそうでしょうし、何でもそうだと思いますが、ゲームとかもそうでしょうし。
物語が出来てくると面白い。 し、物語を作りますよね、誰かれとなく。
ハロプロは特に歴史も既に20年近くになってきてるし、ファミリー的な活動も多いのでもうサーガめいたものが出来つつあります。去年後半から新加入、新グループ結成が連続して今盛り上がりを見せつつあるのも突然に企画されたわけではなくて、長い物語を経て、ある意味必然によって発生しているわけです。
こういうことは、ある程度、中に踏み込んでのめり込む熱狂もないと見えて来ない部分を含みます。
その物語を知る必要があるのか?と問われれば、どうでもいいことも多々あるのかもしれませんが、そのどうでもいいことすらも紡いでしまうのが物語の最大の魅力なのかもしれないとも思います。
今回、℃-uteの新曲のうち、「次の角を曲がれ」という曲は、アンジュルムの「大器晩成」の作曲者でもある中島卓偉の作品です。既に幾つかハロプロの曲に関わっていますが、つんく♂のテイストに似たものを持っていることはもうある程度ハロプロ・ファンの間で共通認識となっており、信頼できる一人です。
https://www.youtube.com/watch?v=G3tiawRnXIM
「大器晩成」同様、「次の角を曲がれ」でもコーラスで参加しており、要らないと思えばカットしてもらっていいと言いながら、同じパートに何通りもの声を提示して、小さいアイデアでも労を惜しまず提供してくれています。その様子が番組で放送されましたが、ディレクターの橋本 慎がうれしそうに「(それって)ブリティッシュ・ソウルだよな」と言えば、「ありがとうございますっ! 俺にアメリカねぇっス!」と答える中島卓偉に、やはりハロプロのコア(核)の部分を見たと感じざるを得ません。

↑ Click 「次の角を曲がれ」
(スタイル・カウンシルじゃん! というあなたに、 「甘い!」。 これ、ブリティッシュ総力戦だかんね)
PVでは、この曲に限り、℃-uteの5人に加え、ハロプロ研修生から4人がバック・ダンサーで参加しています。最近では少し珍しいかもしれません。しかし、これもハロプロの歴史のひとつです。10代のうちは2年、3年も歳が違えば大先輩ですから、一緒に仕事をしていてもグループのメンバーと研修生が直ぐに馴染むということはなく、一定の距離はありますが、それでも帯同して活動することは研修生にとっては先輩と触れ合う大きな出来事です。
モーニング娘。‘15の牧野真莉愛、アンジュルムの佐々木莉佳子、室田瑞希、カントリー・ガールズの稲場愛香、こぶしファクトリーの浜浦彩乃、田口夏実などなど、新加入で話題になっている子たちの多くは、2、3年前からのモーニング、Berryz、℃-ute等のLIVEツアーのDVDを見れば、いつもそこには誰かしらが参加していて、顔も名前も自然に覚えてしまうくらいです。そんなのは、相当のファンやヲタでなければ知りようもないことですが、今、新人で注目を受けている彼女らは既に様々な物語を持っている。この歴史のスパンの大きさというのは、ハロプロの大きな特徴です。
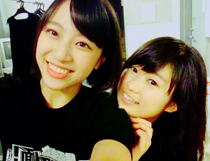
先日、現在演劇「Weekend Survivor」を上演中のこぶしファクトリーの練習風景を切り取った写真では、メンバーの小川麗奈がBerryz工房の「帰ってきたBerryz仮面」のTシャツを着ています。けっこう前のレアなシャツでしょうし、まあ今着られることなど殆んど考えられないTシャツだと思います。先輩に貰ったのかもしれませんが、ハロプロに入ってくる子は、自身ハロプロに対してヲタ気質の子も多く、例えばこの小川麗奈はBerryzの菅谷梨沙子ファンで知られています。Berryz仮面Tシャツひとつがハロプロの連続性を様々に物語っている。彼女にとってそれはおそらく単なるTシャツの一つではない。それを着ることで、彼女はハロプロの歴史の一面を担うことにもなっているのです。
肝はやっぱり、単なるBerryz工房のTシャツではなく、よりによって「帰ってきたBerryz仮面」のTシャツであること。意図的ではないにしろ、そんなわざわざ変な(?)Tシャツを披露してしまうところに、まざまざとハロメンの気質が見て取れる気がします。
![]()
2015年 4月 4日
ギターのことなど
![]()
更新しました。
ロックンロールとギターについて。
連続射殺魔 1976年の記録「SHARL」での17才のギタリスト 和田哲郎(現 琴桃川凛)。
![]()
2015年 4月 2日
℃-uteにとって特別の曲 「我武者LIFE」 こぶし突き上げて 磨き続けた 雨の日も(泣 舞美)
℃-uteの新曲「The Middle Management ~女性中間管理職~/我武者LIFE/次の角を曲がれ」は四月一日に発売されたばかりですが、今度の日曜日深夜(4/6)NHK「MJ」に出演して「我武者LIFE」を歌うみたいです。
「我武者LIFE」はTV番組の企画で選ばれた作曲家の人に湘南乃風の人がサポートする形で出来上がったキャッチーで良い曲で、CMソングにもばっちり合うみたいな感じで、いやもう本当に売れてほしいなと願わずにいられませんが。
ただ、
℃-uteの本領といえば、やっぱり「The Middle Management ~女性中間管理職~」だと思います。
これぞ、“ザ ℃-ute”という圧巻のヴォーカル・パフォーマンスとダンスが炸裂するぶっ飛び曲なので、って、結局つんく♂曲(つんくは作詞だけ担当ですが、この曲がつんくイズムあふれる℃-uteならではの曲であるのは明らか)を支持してしまうところが、ハロプロ・ファン(自分)の独りよがり(ハロヲタよがり)の依怙地さで失笑買うかもわかりませんけども、ちょっとハロプロ追い続けている人間にはそういうマイナー気質がありますかね。ついつい「お前らにわかるか」的態度になりがちなところ、認めます。

↑ Click 「The Middle Management ~女性中間管理職~」
(マイマイが存在することの贅沢すぎる感じ)
それがつまりは“今さら ℃-uteを知らないなんて”などという広告のコピーにも現れる。完全に怒りを含んでますからね、あのコピー。(会社の悪いクセ?)
ああ、駄目だ。どうしても言ってしまう。
「我武者LIFE」で℃-uteを知ってくれていい。でも、いっしょに是非「The Middle Management ~女性中間管理職~」と「次の角を曲がれ」も聴いてほしい。見てほしい。
こんな書き方したら、まともな場所でなら炎上しそうですね。
だから、こんなんじゃいけない。
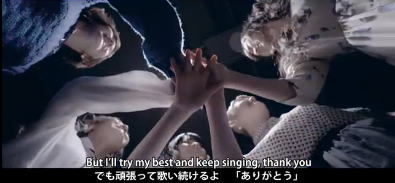
↑ Click 「我武者LIFE」
(℃-uteに感傷はまだまだ早い。Berryzと同じ画でも意味が違う)
この曲は℃-uteへの最高のプレゼント。
「我武者LIFE」、いい曲です! いい曲です! 好きです!
ANGERME、こぶしファクトリーに続いて℃-uteにも「こぶし」が出てきましたね。
SHOCK EYEさんの歌詞も良いんですよね。 私はBerryzファンだから、という立場で聴いてしまうのですが、正直、けっこう切実なる思いで、℃-uteには卒業なんてことを考えてほしくない!
この曲、10周年の℃-uteにとって特別の曲じゃないですか。℃-uteは本当にこれで終わりじゃない。
「僕らはまだ止まれない」 ℃-uteの夢はでかいですよ。
![]()
2015年 3月 29日
British Popsの系譜 HONEYBUS
やっぱりアンディ・パートリッジもこういう音楽聴いてたんだね。
https://twitter.com/xtcfans
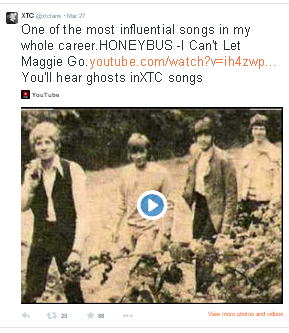
↑ Click
ハニーバスの「I Can’t Let Maggie Go」は日本盤シングルは出なかったんですかね?
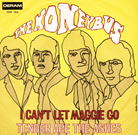

Honeybus 「I Can't Let Maggie Go」(1968)
![]()
2015年 3月 28日
ひなフェス
ハロプロのひなフェスまで中継で見れてしまい、本当にこれはスカパーに入って良かったと噛み締めました。今、見所満載だし。
全部のグループがほぼ新曲引っ提げて、次のステップを見せてくれるという特別なフェスでもありました。
 Juice=Juice (しかもあーりーが急速に上達している)
Juice=Juice (しかもあーりーが急速に上達している)
4/8発売 「Woderful World/Ça va ? Ça va ?(サヴァサヴァ)」
Juice=Juiceがつんく♂以外の作曲で新曲「Wonderful World」、「サヴァ・サヴァ」を披露。このグループはもはやハロプロのトップクラスといえる歌唱メンを複数抱える、歌唱力ではいわゆるアイドルの領域を超えてくるグループですが、そういう意味ではまだまだ幾らでも難曲へ向けてレベルを上げていけるポテンシャルの高さがあるのがはっきりとわかりました。「裸の裸の裸のKISS」のクオリティの高さ! これが埋もれたままという勿体無さ。「良い楽曲が無い」のではなくて「良い楽曲をちゃんと売ってない」という音楽シーンの怠慢さ。今からでも遅くはないから「裸の-」をちゃんと聴きなさいと言いふらしたい感じです。
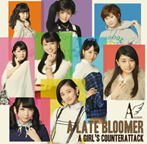 ANGERME(アンジュルム) (莉佳子のHM/HR趣味が完全に自分世代! ”fool for your loving no more”)
ANGERME(アンジュルム) (莉佳子のHM/HR趣味が完全に自分世代! ”fool for your loving no more”)
2/4発売 「大器晩成/乙女の逆襲」
ANGERME(アンジュルム)は「大器晩成」で今、最もHOTなグループです。こういう曲が売れるように“なるべきだ”と個人的には思いますが、まあ、時代を掬い取ることができない、というのであれば仕方がないとも思いますけれども、ハロプロが好きな人たちの中では、もうこれほどアガレる曲は無い!今回のフェスでもやっぱり沸点のピークはこの曲で来ていたと思います。アンジュルムは個々のヴォーカル・ポテンシャルは平均水準の高い(上手い、下手のバラツキが小さく、全員平均以上に歌える)グループなのですが、クセのある声のバランス取りが難しく、声を合わせたときに思ったようにまとまらない傾向があったと思うのですが、あやちょ(和田彩花)が急激に上手くなっているのと、何といっても歌唱メンとして室田瑞希ちゃんが入ったのは大きく、メンバーも9人になって本当に声のバランスが良くなってきたと感じます。
(あと、あやちょがあやちょ過ぎるディパーチャー笑った)
 ハロプロ研修生
ハロプロ研修生
2/18発売 『① Let’s Say ”Hello!”」 (怒涛の傑作揃いアルバム)
ハロプロ研修生もアルバムを出したばっかりで、こちらはけっこう前からの定番曲も入っているアルバムでしたが、つんく♂のメータ-振り切った感のある渾身の楽曲が詰まっているド傑作といわれていて、ある意味、今回のフェスでは一番ハロプロ魂にあふれた曲はここ(ハロプロ研修生)で出た、というパワーがありました。「彼女になりたいっ!!!」は何度聴いても傑作!
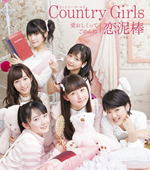 カントリー・ガールズ
カントリー・ガールズ
3/25発売 「愛おしくってごめんね/恋泥棒」 (「海岸清掃男子」の作曲者)
さらに新生カントリー・ガールズが登場。今週出たばかりのデビュー曲「愛おしくってごめんね」、「恋泥棒」を披露。ここはANGERMEとは逆に、歌唱力はいかにも新人でいわゆるアイドルらしい音程の不安定さにあふれた初々しい感じですが、声のバランスは非常に良い。Berryz工房の奇跡の組み合わせのような、いびつな声がパズルのようにピタリとはまった心地よさがあります。山木梨沙、稲場愛香のおねぇさんズ・コンビの声が絶妙に隙間を突いているのがいいコンビネーションになっています。ももちはBerryz工房の頃からそうですが、本能的にバランスを取って、必要なときには声を消すタイプなので、変に目立つことも無く(意図的に一歩引いているところもあると思います)バランス感覚に全く不安はありません。しばらくはこれぐらいの初々しさで引っ張っていいのではないでしょうか。
 モーニング娘。’15 (「青春小僧」「夕暮れ」ちょーカッコいい!)
モーニング娘。’15 (「青春小僧」「夕暮れ」ちょーカッコいい!)
4/15発売 「青春小僧が泣いている/夕暮れは雨上がり/イマココカラ」
モーニング娘。‘15も4月発売の新曲「青春小僧が泣いている」、「夕暮れは雨上がり」を持って参上。これがちょ―カッコよかった。曲中でサイレントが入るのは歌謡曲でも“あり”だとは思いますが、このサイレントのメッセージ的な果敢な姿勢の挑発の匂いにしびれました。13人もいるうち、11期以上9人のメンバーはかなり仕上がってきているので、にも拘らず、多人数のために1曲の中に9人分振り分け切れないという贅沢感があって、くどぅー(工藤 遥)やズッキ(鈴木香音)が歌割が殆ど無かったりする!なんて、4番打者が余っちゃってベンチ座ってる、みたいな豪華ぶりがすごいです。突出したエースに頼るのではなく、全員のポテンシャルが等しく上がっていく感じは、モーニング娘。らしいなと思いました。
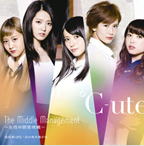 ℃-ute (℃-uteはもうつんく♂曲でなくともOKかもしれない)
℃-ute (℃-uteはもうつんく♂曲でなくともOKかもしれない)
4/1発売 「The Middle Management~女性中間管理職~/我武者LIFE/次の角を曲がれ」
モーニング娘。‘15が文句なくカッコよかったんですけど、しかし、その後に出た℃-uteがあまりにも凄過ぎました! 結成10年を迎えて、℃-uteもBerryz工房みたいに完成してきたなと感じました。それでまた、Berryzとは全然違った内容で凄いですからね。鳥肌がたつぐらい圧倒的なパフォーマンス。“圧倒的”、“圧倒的!”です。
一人一人がチョー格好いい! 萩原 舞さんの、そこにいるだけで“そこにいることがたまらん!”感のわけのわからなさが凄いです。音楽好きな人ならこの素晴らしさがわからないなんてことはないと思いますけどねぇ。音楽のLive空間が作り出す民俗の祝祭的な高揚の中に立つ℃-ute(の美)って、実際それこそ音楽ならばこそと思うのです。℃-uteが歌謡曲史において無視されるのは、もう我慢ならない気がしますね。
この日は「里山 里海」のイベントも行われており、そちらは矢口真里が復帰して司会とかやってました。UP FRONTがちゃんと迎え入れてくれたってのは良かった。先週は「旅ずきんちゃん」で大久保佳代子、益若つばさと共演していて、友人である益若が、ブログに矢口を載せていて、ファンから「そういうことはしない方がいいよ」なんてコメントが送られてきたのに対し、益若が「しるかっ!」と怒ってたの、良かったです。
イベント中には矢口とももちでZYXの話が出たりして和みました。

こぶしファクトリーが演劇を上演中で、フェスには不参加だったのは残念でしたが、個人的にはどうも音楽よりも単にこのグループ自体に興味がある感じです。藤井莉央推しでいきます。出来れば千奈美のセンスをこのグループに注入してもらいたい。
 こぶしファクトリー
こぶしファクトリー
「念には念/サバイバー」 3/26 劇場限定販売
![]()
2015年 3月 22日
Blue Tonic (当時、聴かず嫌いでした)
この前、某BOOK-OFFでブルー・トニックの中古CDが250円で売っていたので2枚買ってきたのですが、それでちょい気になって調べたら、復活するらしいですね。井上富雄さん、いろいろバンドやってみえるらしいので、忙しくて一つに掛かりきりになることは難しそうですが、今後続けていくんでしょうか?
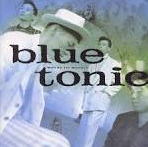

Moods for Modern (1987) GUTS FOR LOVE (1988)
自分の場合、実はブルー・トニックが活動していた当時は殆んどノーマークで。ちょっとお洒落っぽい感じが嫌だったのかな。聴かず嫌いでした。
あの頃、音楽の流れみたいなものが掴めていなかったし、ルースターズが後期のような流れになっていくことも想像していませんでした。ルースターズや花田が向かった方向に対して、案外ブルー・トニックも離れてはいなかったのかもしれないとは、後年になって思うことで、だから、今ならちょっと聴いてみたい、という気はしていたのです。
CDが買えたので聴いてみたら、思ったとおり、青臭いロックンロールの感じはブルー・トニックの中にもちゃんとありました。
ただ、正直、当時聴いていたらどう思っただろうかと考えると、やっぱり駄目だった気はするのですが。例えばブルー・トニックとスタイル・カウンシルやオレンジ・ジュースはどう違うのか? ケイン・ギャングだと思えばどうだったろうか?とか想像してもみたのですが、スタイル・カウンシルにはあって、ブルー・トニックには無い決定的なものが両者の間を切り分けている気がします。そこは結局、音楽と育ちの密接さ、土壌の部分かもしれないけれど。
今度の再結成にあたっては、管楽器は持ち込まないつもりなのでしょうか?ブルー・トニックと言いながら、音楽的にはかなり変わってしまうのかもしれませんが...
名古屋に来たら行ってみたいですね。

![]()
2015年 3月 21日
驚異の 激熱本!
『HELLO!
PROJECT COMPLETE SINGLE BOOK』から1年ほどがたち、ついに『HELLO! PROJECT COMPLETE ALBUM BOOK』も出てしまいました! まさかこんなに順調に出るとは。
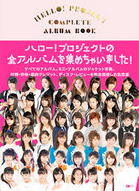 『HELLO! PROJECT COMPLETE ALBUM BOOK』 (CDジャーナル・ムック)
『HELLO! PROJECT COMPLETE ALBUM BOOK』 (CDジャーナル・ムック)
なかなか、こう、やりきるっていうのは難しいもので、情熱というか、本当に狂ってる人にしか出来ないんではないかというぐらいの偉業だと思います。
狂ってる人たちが集合しているだけに、本の内容も素晴らしい。ハロプロのディレクター座談会から、ダンス、ヴォイスのトレーナーへのインタビュー。作曲・編曲家も注目の和田俊輔氏からKAN(真野恵里菜)、小西康陽(松浦亜弥「ね~え?」アレンジ1曲のみ)まで、掘り下げたい隅っこに至るまで目配りが行き届いている。その後のハロヲタたちの楽曲をめぐる座談会にて作家の朝井リョウx柚木麻子対談に至るまでの熱く基地外じみた会話の数々も冷静に考えると一般公開して大丈夫なのか?と思うほどのレベル。
物凄いことになっているなと思うと同時に、これに完全に乗り遅れた音楽評論雑誌の役立たずぶり(何しろこの本を出したのは、音楽評論誌ならぬ音楽広告誌の「CDジャーナル」! ま、CDジャーナルの方が雑誌として最早うわてであるのは周知の事実化してはいますけどね)がさらに際立ったという...
ここまでバカなことがやれるのが、どうして資本のある雑誌で、逆に守りに入っているのが細々やってる貧乏雑誌の方なのか? 貧乏雑誌が「つぶれたくない」という発想でやるのって、理屈だけど、理屈でやってる貧乏雑誌の志ってどういうものなの?
他人から笑われるぐらいの恥を承知でやる! ぐらいの心意気が欲しいと思う。
個人的にこの本の中で一番感動的だったのはディレクター座談会でBerryz工房担当の山尾正人氏が「菅谷は昔から天才肌で。10テイクに1回ぐらい神様が降りてくるんですよ。普通の人はそんなに録らないんだけど、菅谷の場合は次くるかも次くるかもってトラックが増えていくんですよね。神様降り待ちで(笑)。」と語っているところにじわーっと来ました。
つんく♂がBerryz工房ラストLIVEの感想で菅谷梨沙子の最後の歌唱に対し「ニューミュージックの大御所みたいに心に入ってきた」という言い方をしていましたが、私はこれは梨沙子に対する“釣り”だと思っていて、ニューミュージックの大御所とかどうでもいいんですけども、とにかくお前、帰って来いよ、というラヴ・コールだと思うんですね。
それをネクスト・レベルと語った南波一海氏の評も載っていて(3月18日発売のムック本の本文内に3月3日のLIVE評が載っているという!)。熱い!
![]()
2015年 3月 20日
羊 狼 番犬
「アメリカン・スナイパー」(2015年 米)クリント・イーストウッド (劇場)
イーストウッドの「アメリカン・スナイパー」は少し前に見に行ったんですけれども、感想も簡単には書けないなと思って、臆してるうちに日にちもたってしまいましたが、まあ面白いっていえば面白い。ただ、強度的にいうと、「チェンジリング」に負けてるんじゃないかなと思いました、その禍々しさが。

マイケル・ムーアが“安全なところから人を撃つ、スナイパーは卑怯者だ。そんな奴は英雄じゃない”(正確なコメント写しでないので、ニュアンス的に異なる部分があるかもしれませんが、まあ、そんなようなことを言った、というに留めておきますが)と語ったらしいですが、何か忘れてやしませんかね。
イーストウッドは敵を背中から撃つ男だということをね。
このクリス・カイルというイラク戦争で160人以上を狙撃したと伝えられるネイビーシールズの兵士ですが、この男も完全なPTSDだってことで、“英雄であるより、戦争で壊れた男だ”みたいな見方もあり、イーストウッドもその辺りをしっかり描いてますね。
問題にすべきなのは、イラク戦争が実はアメリカ(又は世界)にとって、大儀の無い戦争であったと、イーストウッド自身は個人的な見解を持っているのに、何故かそこは映画の中で語らず、イラク側は単純に悪であり敵であるという態度しか見せていない、そのように描いている、それは何故なのだ?というところなのですけども。
でもまあ、そこは、結局、あんたら皆、そう思ってたことでしょ?ということですよね。誰かが騙している。誰かがそそのかしている、というのはありますが、結局あんたらもそれに乗ったのだ、という。それは“自分はちょっと異なる意見を持っていた”とはいえ、イーストウッド本人にも言えることです。
クリス・カイルというスナイパーが病んでいる、ということを強調する意見もあるようですが、私が映画を見た限りでは、それでもこのクリス・カイルという人はけっこう戦った人だ、と思います。そのように描かれていると思う。
たぶんギリギリの状況下で重要なのは、判断を間違えないことだ、ということだと思う。
クリス・カイルは最初の狙撃で自爆テロを試みる子供を撃ち、母親を撃ちますが、スナイパーとしての判断は正しい。ま、正しいってのは変ですけども、撃たなければどうなる?撃ったらどうなる?という置かれた立場の中で、考え抜いた結果としてギリギリで行動している。
後半になって再び武器を持つ子供を標的にする場面に遭遇しますが、今度はギリギリまで待った結果、子供が武器を放り出す瞬間まで待って狙撃せずに済んでいる。後半になって人情が出てきているなんて事ではなくて、この人は戦争で相当精神的にやられながらも、判断は一貫してコントロール出来ている。
最後、クライマックスで、イラク側の狙撃手と対峙する場面がきます。この場面の怖さというのは、狙撃手が安全であるということは言えなくて、狙撃手もまた標的となってしまうことがあるし、この場合、撃ったが最後、町中の敵がクリス・カイルらが陣取る地点に気づき、一気に押し寄せて、まるで“アラモの砦”のように八方塞がりの絶望的状況に陥ることを示している。チームの一人は「撃たなくていい。やりすごせばいい」とつぶやいているぐらいなのですが、クリス・カイルは敵の狙撃手を見つけ、撃ったら自分が次には丸裸同然になる事を覚悟しながら、やっぱり狙撃します。
これだけの大した男を、PTSDにやられた男、悲劇の男で済ましたくない。イーストウッドならそう思ったのではないか?と私は考えます。
とはいえそこは、イーストウッドも引き裂かれる思いはあったと思う。PTSDに苛まれた事実は疑いようがない。クリス・カイルという実在の人物は、この映画の製作が進行中の時に、戦争後遺症のリハビリを援助する仕事に携わっていて、そのリハビリの相手に射殺されるというショッキングな事件に見舞われるのですが、NEWS映像として挿入される葬儀シーンを深刻に受け止め、今一度、よく考えろよと、締めくくりたくなる気がするものの、そうであるよりは、もっとイーストウッドは怒りをこめて、「敵は誰だ」ということを言っていると思う。先にも言ったように、それはイーストウッド本人も含めてのことです。
ただ、「アメリカン・スナイパー」は表現がちょっと説明的過ぎる気もする。「許されざる者」にある怒りの沸点切れや「チェンジリング」の仲間の子供たちを逃がして自分は暗闇の中で殺人者に見つかり、追い詰められる少年のあの恐怖の場面の禍々しさに匹敵するほどのどうしようもなさが、「アメリカン・スナイパー」には備わっていないように思う。クライマックスでのすさまじい砂塵と暴風音やエンドタイトルからの無音など、今回は技巧に頼った傾向が感じられなくもない。
状況が起きてしまう前によく考えろ(イーストウッドはインタビューで「もっとよく調べろ」と言っています)ということだと思います。
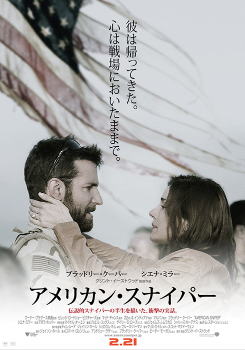
![]()
2015年 3月 8日
British Popsの系譜 HOBBY HORSE
メリー・ホプキンというと、有名であることは認識しているのですが、私の世代(70年代末のパンク以降の時代から洋楽聴き始めた)ぐらいから後の人は殆ど馴染みがないんじゃないでしょうか?
昔、一世を風靡したが故に、後になって省みられることなくきれいさっぱり忘れ去られるというパターンもけっこうありますが、メリー・ホプキンはまさにその典型的なケースのような気がします。実際大ヒットしていたのは68年~71年までで、名前こそ現在に至るまで有名なまま残ってきていますが、おそらく何度となく復刻CDが出ていても、聴いているのは当時のオールド・ファンのみ、といった状況じゃないかという気がします。
そんなメリー・ホプキンが72年にトニー・ヴィスコンティとハーモニー・グループを組んでシングルを1枚出していたなど、これはもう知ってる人、今ではいないんじゃないかと...
渋谷系が好きな人が見たら興味ひかれそうな感じのジャケット(私、まさにジャケ買いしました)で、日本盤のシングルが出ていました。売れなかったようですけど、曲は1958年にアメリカでヒットしたJammiesというグループの曲のカバーで、ドゥーワップ風のティーンエイジポップの佳曲です。
70年代の洋楽ポップス自体、80年代以降懐メロ扱いで軽んじられたので、発掘されることもなく現在に至ってますが、きっかけさえあれば、この曲はリバイバル・ヒットしそうな感じはありますね。トニー・ヴィスコンティがプロデュースでなく実演で参加しているのもレアなケースで面白い。(メリー・ホプキンとトニー・ヴィスコンティが結婚していたことも、今回調べて初めて知りました)
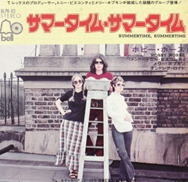
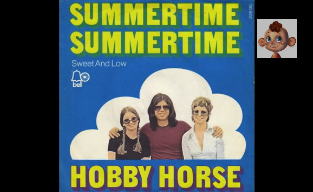
ホビー・ホース 「サマータイム・サマータイム」 (1972) ↑Click
![]()
2015年 3月 8日
SF作家 芦奈野ひとし
芦奈野ひとしの新作が出ました。
一見、黄昏ているような舞台設定で、過疎地や未来の水没が進行した日本などを描いてきましたが、そうした世界でスローライフを楽しんでいるかのごとくのんびりとしている人たちが、しかし非常に生命力にあふれているのが特長で、一種のユートピアとはいえ、ただ逃避の対象になっているのとは違う、時間軸を大きく捉えることが出来るマンガを描き続けている作家です。
きわめてSF的な作家。
『コトノバドライブ』は、小さな怪談噺を聞くようなエピソードが並んでいて、時代設定ははっきりせず、現在が舞台ともとれますが、過去がふっと目の前に現れたりし、時間軸がやはりずれる時があります。昔話にあるような、動物が人間に化けて出てくるような話。超自然現象。。。 言葉にしてしまうとありきたりですが、本当はひとつひとつはやはりありきたりではない。主人公がその現象に出会い、受け入れる行為に時間軸と生命力の大きさを感じ、懐かしさよりも時間がパラレルに自分の中に取り込まれる躍動のような感情の方が強くなると思います。
主人公すーちゃんに、ある日見知らぬ女の子が突然「すーちゃん」と声をかけます。赤毛で大きな黒目の女の子。「なつかしかったから きてみたの」とその女の子は言い、「わたし....こわい?」と聞く。「ん~ そんなことないよ」と答える(内心はぞっとしていた)すーちゃんでしたが、女の子が鳥の群れを見て「帰る」といった瞬間に消えてしまうと、誰もいなくなった周囲を見回して、「ええ~、急だね」とつぶやくすーちゃん。
芦奈野ひとしのマンガを読んでいて感じるのはこの“受け入れる”という行為なのですが、非常にミニマルな場を利用して、大きな時間軸を捉えていることに意味があると思います。過去も未来も繋がっているとは、当たり前のことだとは承知してますが、実感することも受け入れることも実際は難しい。
SFは、この難しさに特に意識的に取り組んでいる分野で、芦奈野ひとしは、この分野に対する貢献度は高いと思います。

芦奈野ひとし 『コトノバドライブ』 (講談社 アフタヌーンKC)
![]()
2015年 3月 7日
市井に降りて 元気だせよ
例年ならば正月の連休の間にたいてい読み終えてしまうのですが、今年は進みませんでした。
中野翠さんの「サンデー毎日」に連載しているコラムを毎年1冊にまとめて出すこのシリーズも恐らく29冊目ぐらいになるのじゃないかと思いますが、長く続いてますねぇ。私も最初は文庫で読むところから始まり、いつしか年末に単行本を買って正月に読むのが習慣となって、何だかんだで20年以上になります。
やはりみんな歳を取っていきますから、どうしても元気は無くなっていきます。
ま、頑張って元気を出して生きていこうとはしているのですが、実際元気に張り切ってやってる部分もあるにしろ、どこか弱まっていくのは避けられない。
そんな気がします。
『晴れた日に永遠が・・・』と題したのは、“何かが遠のいていった感覚”だと思います。特に、今の50歳代、60歳代のような人は、2010年代に入って、こんな世の中になるとは30年ぐらい前には想像していなかったと思うのです。世界は少しづつ良い方向へ向かっているという希望があったと私は思います。
それがすっかり水泡に帰したように、全ては1945年以前に戻っていってしまうかのような失望に見舞われる。
この年代の人は、本当にがっかりしていると思います。
しかし諦めたらやっぱり終わりでしょう。
何か、もう一度やり直す必要がある。ゼロに戻って出発するくらいの徒労感は感じますが、それをやらなければならないのが、この年代の人たちでもあるのです。
中野翠さんが日常で感じる違和感や反論をこつこつと記していくことは、宗教観や無常観に心の平常を求めるようなやり方よりも意味のあることだと個人的には考えているので、出来ればもっと自信を持った態度で世間に毒を撒き散らして欲しい。
最近、どうも文化人が黄昏に逃げている気がして仕方ないです。高橋源一郎の『弱さの思想:たそがれを抱きしめる』とか松本隆の『冬の旅』とか、決して希望を放棄してしまっているわけではないと思いますが、芸術や思想の高みへ向かうことで自分だけの平静を保っているだけのような気がする。
私は高橋源一郎が今の少女漫画のコラムをやるとか、松本隆がアイドルの曲をがんがん書くというような世俗にもう一度まみれるぐらいの、本人的にはレベルの低いところへまた降りるみたいな気分になるかもしれないけれども、そういうサービス精神は要るんじゃないかと思う。
筒井康隆や小林信彦、イーストウッドらは、やっているよ!

中野 翠 『晴れた日に永遠が・・・』 (毎日新聞社)
![]()
2015年 3月 4日
Love Together!

Berryz工房ラストコンサート2015 Berryz工房行くべぇ~! セットリスト
01. スッペシャル ジェネレ~ション
02. ROCKエロティック
VTR(BGM:Berryz工房行進曲)
03. 愛のスキスキ指数 上昇中
04. 付き合ってるのに片思い
05. 勇気をください!
MC
06. 21時までのシンデレラ
07. ロマンスを語って
08. 秘密のウ・タ・ヒ・メ
09. まっすぐな私
10. あなたなしでは生きてゆけない(04-13-15完熟Completion Ver.)
11. 普通、アイドル10年やってらんないでしょ!?
VTR:振り返り映像(BGM:桜→入学式)
12. 行け 行け モンキーダンス
13. I’m so cool!
14. cha cha SING
MC(清水・夏焼・菅谷)→(嗣永・徳永・須藤・熊井)
15. ジリリ キテル
16. なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW?
17. 本気ボンバー!!
18. 世の中薔薇色 ※煽りMC
19. ライバル
20. すっちゃかめっちゃか~
21. 一丁目ロック!
アンコール
22. Bye Bye またね
MC
23. 永久の歌
ダブルアンコール
24. Love together! (ピアノ:上杉洋史)
Berryzのラスト・コンサートについて、つんく♂がblogにコメントしてくれました。
11年の活動が長かったのか短かったのか・・・
今日のステージを見てそう思いました。
彼女達がまだまだすべき事はたくさんあったとも思うし。
でも、そう言いながらもやるべき事はきちんとやった。
多分、作るべき曲は作って来た、
けど、まだまだ歌わせたい曲はある
という気持なんだと思う。
僕のプロデュースしたグループの中で一番いろんな事にチャレンジさせて
くれたのが彼女達。
そう思うのは、それだけいろんな種類の曲があるから。
それだけ真剣に作って来たから。
シングルの量なんかで言うとシャ乱Qなんかより全然多いし。
子供だった時からこうやって成人するまで曲と共に成長出来た事は
類を見ない経験値であり、そんなグループだと思う。
なんせ、辞めてったメンバーが居たものの
アイドルとして、こんな長く一つのグループが継続したのは無いと思うしね。
約二時間半のステージ。
今日のステージはメンバーのセルフプロデュース。
曲順からセット、衣装にも本人達が拘って完成させました。
最後まで100点じゃないのがBerryz工房ってやっぱり思ったよ。
良い場面で人間味がめちゃ出る。ズコって。
そういう所が癖になって味になって個性となってたんだなって改めて思いました。
ありがとう!
そしておつかれ!
少しはゆっくり出来るんかな・・。
最高のコメントの数々、ファンとしても嬉しく思いました。
「最後まで100点じゃないのがBerryz工房」
この賛辞もうれしいです。
「まだまだ歌わせたい曲はある」
これ以上の言葉はありません。

ありがとう Berryz工房
![]()
2015年 3月 3日
ラスト・コンサート Berryz工房 行くべぇ~ エンジョーイ!
今、終了しました。以下、感想。
茉麻には ビックリ だわ ! (笑)
梨沙子、頑張れて良かった。最後の1曲沁みた。
千奈美、ヤバかった。マジ可愛い過ぎた。
熊井ちゃん、やっぱりアルバム1枚出したほうがいい。
みやちゃん、一番自由だったのね。今、一番やる気じゃん。
キャプテン、「永久に不滅」が出ちゃったね。裏声、耳に焼き付けました。
ももち。さすがでした。今後ともよろしくお願いいたします。
ベリヲタの皆様、お疲れ様でした。 そしてありがとうございました。
スカパー様。感謝です。ベリヲタ・コールの最後まで、いい放送でした。
3月3日、日本史上最高峰のGirls POPグループ Berryz工房の青春劇場 ここに閉幕。
またいつか、再会の日を期待して待ってます。
しっかし、茉麻。ウソでしょー?
![]()
2015年 3月 2日
Berryz工房 全曲名曲コレクション
とうとう来てしまいました。
いよいよ明日は「ラスト・コンサート 2015 Berryz工房 行くべぇ~」日本武道館です。
もう今はとにかくラスト・コンサートが無事に終わり、彼女たちが悔いが残らないよう思う存分にパフォーマンス出来ることを祈るばかりです。
1日の有明で喉の調子が良くなかったことを悔しがっていた梨沙子が万全のコンディションで臨むことができることを願っています。
名曲コレクションも今回が最終回です。Berryzの楽曲は、私の数えでは142曲ということになりました。カバー曲や企画ものも入っていますので、どのようにカウントするかは人それぞれということになるでしょうが、やっぱりこうして全て聴いてきて、どれもが良い曲であったのには驚きを禁じえません。さすがにここまで名曲が揃っているグループは過去にも殆ど例がないと思います。
しかもこれは恐らく、曲自体の力に加え、Berryz工房だからこそ成しえた快挙のような気がしてなりません。このグループでなければ、これらの曲は生まれなかった可能性が高い。
私はそう思うのです。

↑Click 「すっちゃかめっちゃか~」~(138) 「世の中薔薇色」(2012年 8thアルバム収録)
“楽しい”しかない黄金のナンバー「すっちゃかめっちゃか~」と「世の中薔薇色」は2曲とも有明では歌われていません。少なくともどちらか一方は明日披露されるに違いありませんが、勿論メドレーでぶちかまされてもファンは臨むところでしょう。こんな幸福にはちきれたナンバーが2曲も持ち歌にあるというのもBerryzならばこそ。
[ Berryz工房 全曲名曲コレクション](完)
 ← Click
← Click
(139) 「Hello!のテーマ」(2004年 1stアルバム収録)
「ハロー!のテーマ」もBerryzのバージョンがアルバムに収められています。舞波にも参加してもらいましょう。
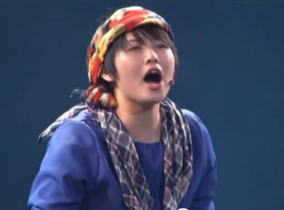 ← Click
← Click
(140) 「やっと会えたね」(2015年 「完熟Berryz工房 The Final Completion Box 通常盤」収録)
劇ハロの曲が2曲続きます。 実は私はまだBerryz工房の舞台劇は見たことがない(舞台劇自体、見るのがちょっと苦手というのがある)のですが、今後ゆっくり過去の作品を見ていこうかと思っています。
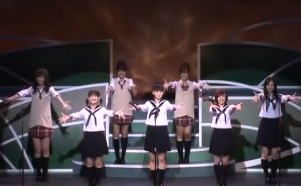 ← Click
← Click
(141) 「Thank You ’Very Berry’」(2015年 「完熟Berryz工房 The Final Completion Box 通常盤」収録)
「完熟Berryz工房」のBOXには新録音のバージョンが入っていて、さすがにそのテイクは最高の仕上がりになってました。この曲を名曲コレクションの最後に持ってこようかと思っていたんですけどね...

↑Click (142) 「CLAP!」(2008年 5thアルバム収録)
あと1曲残っていたんですね、「CLAP!」が。 たまたま残ってしまったんですが、映像見ていたら最後の曲にふさわしいなと思って。Berryzは相当変な曲でもこなせてしまうところが持ち味ですが、「CLAP!」みたいな非常に中庸的な何でもない小曲をやらせると、ホント誰よりも見事にこなしてしまう。
実はここのところが“天才的”なところだと思っています。
この曲は武道館では披露されるかどうかわかりませんが、私はBerryzのこの隠れた特質を忘れたくないですね。
3月1日
有明2日目のセトリです。
第1部
01. Crying/こぶしファクトリー&ハロプロ研修生
02. 念には念/こぶしファクトリー
03. 恋泥棒/カントリー・ガールズ
04. Ca va ? Ca va ?(サヴァ サヴァ)/Juice=Juice
05. 乙女の逆襲/アンジュルム
06. One・Two・Three/モーニング娘。'15
07. The Middle Management~女性中間管理職~/℃-ute ※休憩10分
第2部
01. 超HAPPY SONG/Berryz工房×℃-ute
02. 白いTOKYO/ZYX(清水・嗣永・矢島)
03. 正夢/あぁ!(夏焼・愛理)
04. フォレフォレ ~Forest For Rest~/DIY♡
05. PARTY TIME/ガーディアンズ4(熊井・菅谷・中島)
06. 記憶の迷路/High-King(清水・矢島)
※MC(清水・徳永・須藤)
07. ハピネス~幸福歓迎!~/カントリー・ガールズ
08. TODAY IS MY BIRTHDAY/Juice=Juice
09. Loving you Too much/℃-ute
10. ピリリと行こう!/こぶしファクトリー&ハロプロ研修生
11. ギャグ100回分愛してください/アンジュルム
12. ジンギスカン/モーニング娘。'15
※MC(譜久村・生田・飯窪・石田)
13. ホントのじぶん/Buono!
14. ロッタラ ロッタラ/Buono!
※MC(Buono!)
15. 泣き虫少年/Buono!
16. カタオモイ/Buono!
17. 恋愛ライダー/Buono!
※MC(Buono!)
18. タビダチの歌/Buono! ※休憩30分(歴代MVVTR)
第3部
01. アジアン セレブレイション
02. HAPPY!Stand Up
MC(現ハロのリーダー一同 ゲスト:飯田・吉澤・石川)
03. 恋はひっぱりだこ
04. 安心感
05. 世界で一番大切な人
06. サヨナラ 激しき恋
VTR ※菅谷から熊井、熊井から夏焼、夏焼から須藤についての印象VTR
07. Be 元気<成せば成るっ!>
08. コイセヨ!
09. ヒーロー現る!
MC
10. 桜→入学式
11. VERY BEAUTY
12. ありがとう! おともだち。
VTR ※須藤から徳永、徳永から嗣永、嗣永から清水、清水から菅谷についての印象VTR
13. 恋の呪縛
14. 胸さわぎスカーレット
15. 愛の弾丸
16. ヒロインになろうか!
MC
17. 抱きしめて 抱きしめて
18. 雄叫びボーイ WAO!
19. 友情 純情 oh 青春
アンコール
20. 友達は友達なんだ!
MC
21. そのすべての愛に
![]()
2015年 3月 1日
7の法則 Final Berryz工房

↑Click (134) 「さぼり」(2005年 2ndアルバム収録)
まだまだ終わらないBerryz工房の名曲群です。またまたここへきて屈指の名曲が。
残してあったのです。「さぼり」。
何でこの出だしを千奈美に歌わせるという最高の選択をいともあっさり当たり前のように出せるのか。歌割りの威力のすさまじさを語らずにいられないって、Berryz工房というグループにしか存在しない現象じゃないですかね。
千奈美「このままのまんまでいいの」(!)→ほんわか友理奈→しっとりナチュラル・ヴィブラート桃→必殺の裏声キャプ→シャキンと背筋伸ばすみやちゃん→重量感乗せて加勢に入る茉麻→「すごいデートだわー」がっと場面広げる梨沙子 という絶妙の流れ。
[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]
 ← Click
← Click
(135) 「真っ白いあの雲」(2011年 7thアルバム収録)
これはリーゼント・りーちゃんが歌いだし。レアな曲が来て「おぉっ」とベリヲタからうめきが起きる展開。
Berryz工房の場合、どの曲が来るのか、というのは最早ルーレット回す式に見当がつかないのでヲタも見構える状態です。しかもこんなレア曲までもが結局名曲の始末。
 ← Click
← Click
(136) 「ヒーロー現る!」(2011年 25thシングル「ヒロインになろうか!」B面)
フライング佐紀ちゃんで知られるLive映像。
これで盛り上がるって....と若干覚めた目で見る方もあるかもしれませんが、Berryzの面白いところは基本手作りというところです。誰だって出来るじゃん!みたいな。 でもね、本気でゼロから作ってるからね、そういうのを。
学芸会のレベルっていう言葉? いやいや、じゃあやってみろって、ここまで絶対面白くならない法則。 “本気でふざける”の技術を10年で作っちゃったのがBerryz工房。
しかも本当に 超―イイ感じに力抜けてる。
 ← Click
← Click
(136) 「笑っちゃおうよ BOYFRIEND」(2006年 11thシングル)
この曲はいいLive映像もあるのですが、MVが非常に楽しいのでこのヴァージョンで。
特に千奈美に注目。彼女の節度あるポップさが好きです。

↑Click (137) 「ピリリと行こう!」(2004年 3rdシングル)
茉麻活躍の「ピリリと行こう!」盆踊りヴァージョン。 沖縄ポップが素アレンジの曲なんですけどね。
熊井ちゃんの「いないいない ばぁ~」が、実になんとも。。。。。。。。
このね、盆踊りで回ってるところから、次の立ち位置へ急いだだけなのかもしれないんですけども、メンバーが走り出すところがね、すごい好きですね。回りながら走り出すところが。
これがたぶん子供の頃からずっと変わっていないBerryz工房の姿でしょうね。
2月28日。
初日のセトリが割りと拡散されてていいのかなぁ?と思いましたが、2日目は内容がまたガラリと変わる可能性があるのでしょうか? ま、私のページはこれ以上広まることはまず無いので、申し訳ないとか思いつつ、載せちゃいます。圧巻の4Daysの記録ということになると思います。
第1部
01. Say! Hello!/研修生
02. 念には念/こぶしファクトリー
03. 愛おしくってごめんね/カントリー・ガールズ
04. Wonderful World/Juice=Juice
05. 大器晩成/アンジュルム
06. TIKI BUN/モーニング娘。'15
07. 次の角を曲がれ/℃-ute
第2部
01. 甘酸っぱい春にサクラサク/Berryz工房×℃-ute
02. 白いTOKYO/ZYX(清水・嗣永・矢島)
03. 正夢/あぁ!(夏焼・愛理)
04. フォレフォレ ~Forest For Rest~/DIY♡
05. PARTY TIME/ガーディアンズ4(熊井・菅谷・中島)
06 .記憶の迷路/High-King(清水・矢島)
※MC(清水・徳永・須藤)
07. 笑っちゃおうよ BOYFRIEND/カントリー・ガールズ
08. 告白の噴水広場/Juice=Juice
09. もっとずっと一緒に居たかった/℃-ute
10. MADAYADE/研修生
11. 流星ボーイ/アンジュルム
12. 愛はいつも君の中に/モーニング娘。'15
※MC(譜久村・生田・飯窪・石田)
13. ホントのじぶん/Buono!
14. ロッタラ ロッタラ/Buono!
※MC(Buono!)
15. 泣き虫少年/Buono!
16. カタオモイ/Buono!
17. 恋愛ライダー/Buono!
※MC(Buono!)
18. タビダチの歌/Buono!
第3部 Berryz工房単独
01. アジアン セレブレイション
02. HAPPY!Stand Up
03. マジ グッドチャンス サマー
04. サヨナラ ウソつきの私
05. さぼり
06. 素肌ピチピチ
VTR
07. Be 元気<成せば成るっ!>
08. コイセヨ!
09. ヒーロー現る!
MC
10. 桜→入学式
11. VERY BEAUTY
12. ありがとう! おともだち。
VTR
13. 恋の呪縛
14. 胸さわぎスカーレット
15. 愛の弾丸
16. ヒロインになろうか!
MC
17. 抱きしめて 抱きしめて
18. 雄叫びボーイ WAO!
19. 友情 純情 oh 青春
アンコール
20. 友達は友達なんだ!
MC
21. そのすべての愛に
メインイベントの第3部では「ありがとう!おともだち」の登場が何気にすごいんじゃないでしょうか。10、11、12は、ファンならここで一気に崩れ落ちる流れだと思います。そんなことを言えば13~18の並びも凄過ぎる!と唸るしかありませんが。間にMCが入って一旦切ったのは、むしろほっとするぐらいで、本当に心臓に悪かろうと思います。この勢いでラスト19に入るって...! 13~19をノンストップでやったら死人が出る勢いだったと思います。
しかも初日は「スッペシャル・ジェネレ~ション」も「cha cha SING」も「永久の歌」も無しというのに。
どんだけなんだよ!
![]()
2015年 2月 28日
Berryz工房祭り 開幕
今日からいよいよ本当にBerryz工房のファイナル、「Berryz工房祭り」から3/3「ラスト・コンサート Berryz工房 行くべぇ~!」までの連続4日間イベントが始まります。
2月28日 有明コロシアム
Berryz工房祭り
3月 1日 有明コロシアム Berryz工房祭り
3月 2日 東京プリンスホテル Berryz工房祭り 後夜祭
3月 3日 日本武道館 ラスト・コンサート2015 Berryz工房 行くべぇ~
その前に、今週に入って各メンバーのBlogにて、Berryz活動停止後のメンバーの予定について発表がありました。菅谷梨沙子さんは一旦休養機関に入るということで、今後は未定ですが、残りのメンバーは何らかの形で芸能活動に関わっていく意志があるとのことで嬉しい報告です。特に夏焼 雅さんが歌手活動の継続の意志を表明してくださった事は特別の喜びに感じます。これはかなり重要な朗報です。
さて、菅谷さんですが、しばらくは現在の道重さゆみさんと同様の沈黙期間に入ることが予想されます。
どのような方向へ進むのか全くわかりませんが、ファンとしてはおそらくどんな選択でも受け入れる用意しかないものと思われます。ある意味、特別な存在であり、菅谷梨沙子は菅谷梨沙子であるだけで充分だ、という思いしかファンには無いと思うのです。この人のことは言葉ではなかなか表現が難しく、というより言葉で表現することを拒む何かが彼女にはあり、語らず、とすることがふさわしいような気がするのです。
ただひたすら、ベリのファンにとっては、彼女は全力で守るべき存在である。そうとしか言えないのではないでしょうか?
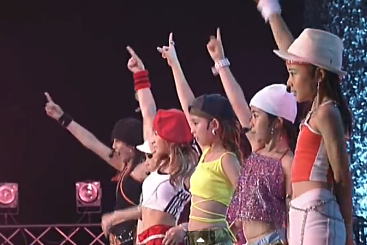
↑Click ZYX 「行くZYX! Fry High」2003年LIVE
こちらは、2003年(Berryz工房 デビュー前) ZYXに村上 愛に代わり梨沙子が出演した時の貴重な映像。メンバーは矢口以外全員小学生であるうえに、他メンバー(梅田、清水、矢島、嗣永)は6年生で全員年長ですが、梨沙子一人3年生でした。
[ 菅谷梨沙子 スッペシャル]
 ← Click
← Click
道重さゆみ、菅谷梨沙子 「やる気! IT’S EASY」(後藤真希 4thシングル 2008年)2014年 Live
ハロコンでは二人で歌う機会もけっこうありました、道重・菅谷コンビ。このコンビは声の相性もいいんです。梨沙子が道重をかなり慕っていたと思います。
 ← Click
← Click
菅谷梨沙子、熊井友理奈、金澤朋子、竹内朱莉、鈴木香音 「君は自転車、私は電車で帰宅」(℃-ute メジャー18thシングル 2012年) 2014年 Live
ハロコンの醍醐味、異色の組み合わせ。熊井ちゃんと梨沙子というのも珍しい。
(かなとも(Juice=Juice)が鈴木愛理の影響をいかに受けているかがこれを見るとよくわかります。)
 ← Click
← Click
「REAL LOVE」(2008年 5thアルバム収録曲)
“Berryz工房のエース” は間違いなく菅谷梨沙子であり、彼女しか考えられないのですが、どうしてそうなるのかと考えるのはよくわからない部分もあるのです。最も正解に近い答えというのは、Berryz工房のメンバー全員が、そう望んだからだというのが正しいところなのではないでしょうか。
梨沙子を守るためにBerryz工房は存在する。ひょっとするとBerryz工房の存在意義は一番にそこにあったのではないか? と考えたりもします。
全員が梨沙子を妹として可愛がったというのは、理屈的には当たり前といえばそうなのですが、かけがえのなさの比がちょっと違ったと思います。
![]()
2015年 2月 26日
こぶしファクトリーに期待感しかない!
ハロプロのファンの間で通称“はまちゃんズ”と呼ばれていた新ユニットの正式名称が“こぶしファクトリー”に決定しました。

“こぶし”は綺麗な花を咲かせる木(辛夷)の名前から。“ファクトリー”は、Berryz工房の意思を継ぐ意味で“工房”からとられた名称だとのこと。
私も実はBerryzの後継は、先日の“はまちゃん大佐”を見て以来、このグループが面白いのではないかと考えていたので、この決定は嬉しいです。


大佐「おい、スタッフ。Berryz工房がひとり混ざっているぞ」 もも「やめてよ!」
あれ以来どうもはまちゃん、たぐっち、れなこの3人で、どういうわけだかマルクス兄弟の姿がだぶって見えてくるようになりまして(本気じゃないですよぉ、冗談ですよー。)、もうこの3人が面白くなるとしか思えないんですよね。さらに加えてここにはリーダー(そのうちキャプテンと名乗るようになるのでしょうか?)の“ジップロック事件”藤井さんも居られるわけで、熊井ちゃんみたいにほわぁ~っとしていじり甲斐のありそうな井上さんもおり、もう期待感しかないです!
*その後、リーダーは広瀬彩海と正式発表がありました。梨央梨央悔しかっただろうけど頑張ってください!
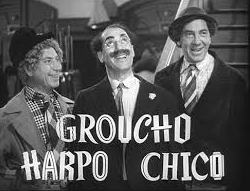

![]()
2015年 2月 23日
残り曲も少なくなってきました

↑Click (130) 「エレガントガール」(2010年 氷室衣舞 名義(菅谷梨沙子) シングルより)
何しろ膨大な映像は残ってはいるのですが、Berryz工房という存在は3月3日をもって居なくなる。
何かこう、いろいろ考えてしまう。考え過ぎて、儚い一生みたいな大袈裟な想像にまで及び、自分を笑うしかありませんが、この7人は本当に替えが効かない。この組み合わせは二度と作れない、作られない。似たものすら想像できない..これが堂々巡りします。
[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]
 ← Click
← Click
(131) 「大人になりたくない 早くおとなになりたいl」(2011年 27thシングル「ああ、夜が明ける」のB面)
勝手な想像ですが、おそらく夏焼さんが「つまらない」と思えば、Berryz工房は早いうちに分解していたんじゃないかな?ということも考えるわけです。いろいろな面で落差があるグループですから、イライラする部分は少なくなかったと思う。
でもね、この人が全部おおらかにOKにしてくれたんじゃないかなぁ。本当はいろいろ言える立場の人だと思うんでね。夏焼さんがBerryzを好きになってくれたというのは本当に大きかったと思う。
 ← Click
← Click
(132) 「ガールズタイムス」(2011年 7thアルバム収録)
ラジオ番組「BZS1422 ベリーズ・ステーション」で、徳永さんが、ももちとのビジネス・パートナーについて語っていました。二人で、カントリー・ガールズでのももちのパートナーには小関 舞ちゃんがいいんじゃないかと話し合ったって。
この二人がBerryzの頭脳ですね。本当にいいコンビ、というか徳永千奈美さんの発想がかなりハイ・レベルだったんではないでしょうか。ディズニー(ピクサーの要素もけっこう重要なのかな?)とおもちゃに囲まれた生活の中で生まれる発想は、単にすっ飛んでるだけではなく、完成度も高いジョークが作れる人だと思います。ももちの突っ込みはその回し方が上手かった。 ももちと熊井ちゃんのコンビもレベルが高かった。
 ← Click
← Click
(133) 「Bomb Bomb Jump」(2011年 7thアルバム収録)
熊井ちゃん、千奈美、茉麻の歌声の貴重さって、どう説明したらいいのだろうか?
千奈美には破壊力という言葉を使ってきましたけども、この人の凄いところは、到達点が揃っているというところだと思います。計算ではないんですよね。この位置が好きなんでしょうねぇ。
茉麻はぬるっと揺れる感じがメロディに乗っかった時にブルドーザーのような重量感で押してくあの塊(かたまり)感が好きです。
熊井ちゃんの歌う「森の熊さん」。 この字の並びを見ただけでその幸福感に涙が出そうです。(沖縄FCで歌ったそうです!) 私、想像だけで、熊井ちゃんの声で完璧に脳内再生できます。ソロ・アルバムを出すべきだと思います。その声に震え上がる人がいっぱい居ると思います。この人の歌手としての可能性は無限。
![]()
2015年 2月 21日
カウント・ダウンに入ってきました
ここへきてさすがにBerryz工房をとりまく動きが賑わしくなってきていますが、世間的には何の波風もたっていなくても、盛り上がっているところではいよいよヒートアップ極まり、箍(たが)が外れかかってきております。
まず、2月28日、3月1日有明コロシアムでの連チャンLIVE、2日のファン感謝祭、3月3日の武道館ラスト・コンサートと続く4日連続の「Berryz工房祭り」と称されるイベントは、今年に入って有明2日間のLIVEの時間変更が発表され、2時間のLIVEが4時間になりました!
2日間で8時間。
当日は3部構成となり、
第1部がBerryzを除くハロプロ所属グループの総出演。
第2部になってBerryzが登場し、過去Berryzのメンバーが参加したハロプロのユニット曲を披露。さらに他のハロプログループによるBerryzトリビュート・カバーがあります。
第3部がBerryz単独のLIVE(約2時間)。NET上では、他のハロメンなど不要、全編Berryzだけを堪能したいというような非難の声もありましたが、4時間連続となれば実質それが無理なのは現実の問題としてあるわけで、文句言う前にもっと違う考え方があるでしょう?と思います。
考えようによっては、これはとんでもない驚愕のイベントです。何しろBerryz自身は2時間がっつりLIVEをする上に、過去のユニット曲も披露するのです。さらにはハロメンがBerryzの曲をカバーするとなると、基本的には本編のセットリストとは被らないように選曲しなければならない(絶対被ってはならない、ということもないですけども)。
しかしファン心理からすると、カバーでBerryzの曲をやられてしまうと、その曲はもう本編ではBerryzはやらないのか?と思い、落胆する羽目となることも考えられます。
例えばトリビュートでモーニング娘。’15が「Loving You To Much」をカバーしてしまったら、本編ではBerryzはこの曲をやらないのではないか?という話になってしまいます。そのように想像すると、本編でBerryzが披露しそうにないとファンが納得できるような曲をハロメンは選ぶということになります。
私が考えるならば、それらは例えば「真っ白いあの雲」、「午後の休憩時間。」、「夢でドゥーアップ」、「サクラハラクサ」、「女の子にしかわかんない丁度があるの」のような曲です。あえてシングル曲にいったとした場合は「サヨナラ ウソつきの私」、「愛の弾丸」といったところでしょうか。
これを℃-uteやANGERMEらがカバーすると考えたらめちゃくちゃレアじゃないですか! これはこれで最高に刺激的ですよ。ベリメンが参加していないとしても十分楽しめる内容です。さらに過去のユニットとなると、今の時点でなら想像し放題ですよ。この想像が幾つ実現されるだろうかと夢想してみたら楽しくてしょうがない筈です。
まずはZYXでしょう。ベリメンのユニットといったらまずはZYXの「白いTOKYO」、「行くZYX! FRY HIGH」は外せません。
しかし、これはまず実現は不可能です。矢口さんが登場したらそれこそ芸能NEWS沙汰の大事件となってしまう(ハロプロならば全然矢口OKだし、援護したい気持ちは十分あると思いますが)。ただ、このユニットは(矢口、梅田、村上の)代役を立ててでも必ずやらなければならないでしょう。ZYX-αなら問題なく可能ですが、ここはやっぱりオリジナルにこだわり、特に清水CAPと舞美リーダーの共演が見たい!
絶対実現してほしい!というのが、あぁ!です。これは出来るでしょ!? 想像しただけでも震えが来そうです。これ1曲だけでも話題性は十分です。11年を経ての田中れいな・夏焼 雅・鈴木愛理!!
田中れいなさえその気になってくれれば問題ありません。
ガーディアンズ4にも期待が掛かります。光井愛佳が帰国してくれさえすれば可能になります。このユニットは楽曲的にも隠れた名曲揃いのユニットですので、馴染みのないファンは聴いたらびっくりすると思います。
さらに注目は、セクシーオトナジャンです。楽曲「オンナ、哀しい、オトナ」が映画「ウルヴァリン:SAMURAI」(2013)にちょい使われたこともあって、話題性としては発表当時よりもあるのではないでしょうか? これを今聴きたいと思っているファンは多いと思います。ただミキティの第2子妊娠のNEWSもありましたし、これも実現が難しい。それでも雅ちゃんソロでもいいから披露を期待したい曲ですね。
 『アイドル最前線2015』(洋泉社)
『アイドル最前線2015』(洋泉社)
、
先日発売されたムック本『アイドル最前線2015』には、“ありがとうBerryz工房大特集!!!!”と銘打って、たくさんのベリファンのタレントや関係者のインタビューが載っていましたが、その中でダンスの振り付け師の夏まゆみさんがBerryz工房CAPの清水佐紀さんのダンスについて語っていたことが話題になっています。
「キッズ時代からダントツ。「なんだ、こいつ!おかしいだろ!」って。だって小学生なのに私の助手より上手いんだもん(笑)。努力はセンスに勝ることがあるけど、センスある人が努力しちゃったら敵わない時もある。それが清水ですね。」
その清水さんのダンスを堪能出来る1曲がHigh-Kingの「C╲C(シンデレラ╲コンプレックス)」です。
これはチームとしてのダンスの難易度も半端ないのでメンバーを集めるのは大変でしょうが、ハロプロ・ダンス部から先鋭を選んで何とか実現できないものか?と思います。ハロヲタのライター:相沢 直さんがTwitterに動画をUPされていましたが、当時あまり注目されなかったユニットでもあり、今、ここで出来るだけ沢山の人に見てもらいたいという気持ちがよくわかります。私も右にならえでUPを。

↑ Click High-King
「C\C(シンデレラ\コンプレックス)」(2008)(高橋 愛、田中れいな、清水佐紀、矢島舞美、前田憂佳)
盛り上がりそうなのは現場だけではありません。ライヴ・ヴューイングが香港、台湾を含め各地25個所ほどで予定されており、さらに場所の追加も発表されたばかりです。
TVでもBSスカパーでラスト・コンサートの生中継放送が決まり、その上、スカパーでは3月2、3、4日の3日間、Berryz工房の特別番組が各2時間30分、合計7時間半!に及ぶプログラムを放送することが決まっております。7時間半!も何をやるつもりなのか?
最後に向けて突っ走る状態に入りました。もう後は、楽しみでしかない!(©譜久村 聖)
![]()
2015年 2月 14日
British Popsの系譜 「チョコレート魂」
ホワイト・プレインズの「Carolina’s Comin’ Home」という曲はヴァニティ・フェアも録音していて、どちらがオリジナルか?というのは自分は知らないのですが、調べてみるとヴァニティ・フェアの方が70年にシングル曲で出していて、ホワイト・プレインズは71年にシングルのB面曲で発表していますので、最初はヴァニティ・フェアだったんじゃないかなと思います。
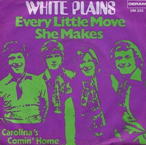 「Carolina's Comin' Home」
「Carolina's Comin' Home」 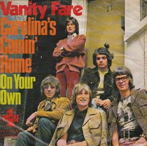
↑Click ↑Click
この曲を聴いていると、どうも松浦亜弥の「チョコレート魂」が浮かんできて、何かしらの影響を受けているような気がして仕方ないのですが、そうはいってもヴァニティ・フェアとホワイト・プレインズでは、現在の作曲家の人からしたらマイナーもマイナー。マニアック過ぎる存在なので、さすがに知らないんじゃないかとも思います。
ただ、このメロディ-・パターンは確かに70年代のポップスとしては広く根を生やしたような、世界中に浸透したメロディ-だとも言えるし、それが時代が変わってもポップスのベーシックな部分として残っているために現在でも甦って来ることがあるのかもしれません。
 ←Click 松浦亜弥 「チョコレート魂」(2009)
←Click 松浦亜弥 「チョコレート魂」(2009)
しかし、こうしたメロディーはあの70年前後の時代、イギリスを中心にして生まれたものが少なくない。当時のイギリスに著名な作曲家、作曲チームが存在していて、今でも本が出たり、雑誌に取り上げられたりすることがありますが、それを演奏したバンドや歌手は案外匿名化し(実際仮空のバンドだったケースもあったため)、知られていないことが多いような気がします。
ところが、意外にも、当時、これらのバンドや歌手は日本でも頻繁にレコードを出していて、洋楽ながらヒットしたりもしているのですけどね。
それが、30年もたって、「チョコレート魂」のようなメロディーとして再生したりする(勝手に影響下にあることを決め付けてしまってるような書き方で済みませんが)のは不思議な感じでもあります。
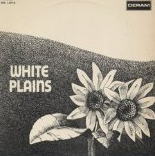
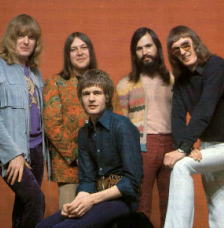
ホワイト・プレインズ 「マイ・ベイビー・ラヴズ・ラヴィン (White Plains)」
先ごろ、ホワイト・プレインズのアルバム「マイ・ベイビー・ラブズ・ラヴィン(WHITE PLAINS)」(1970)が日本でのみ“soft rock BEST COLLECTION 1000”シリーズの1枚として復刻されましたが、イギリスでもチェリー・レッド(またしても!)から、コンピレーションが新たに発売されるようです。
アメリカのポップスに比べると、イギリスに独自のポップスの流れがあることはあまりクローズ・アップされることはありませんが、正直、個人的には日本の音楽においてイギリス(及びヨーロッパ)の当時のポップスが与えた影響は、アメリカのそれより大きいかもしれないとすら思うほど、見過ごせないものだと思っており、ひとつの潮流を成すものだと考えたりもします。
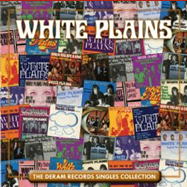
「The Dream Records Singles Collection - White Plains」 (2015年2月23日 発売)
![]()
2015年 2月 13日
Seven の法則 4 Moonriders

ムーンライダーズは6人だろっ!て、勿論そうで、単に書きたいだけで、こじつけでいいからベリと並べてみたかった、という理由しかないのですが、先日出ましたライダーズのムック本『Ciao! ムーンライダーズ・ブック』での各メンバーのソロ・インタビューに“七人目のライダーズ”という話がたびたび出てきたので、これに乗っかっちゃおうという気持ちが起きてしまったわけです。ま、それだけです。
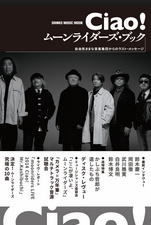

『Ciao! ムーンライダーズ・ブック』 (シンコー ミュージック)
元々は2009年に発表したアルバム「Tokyo 7」が基になっていて、このアルバムにはジャケットの裏面に7人目としてドラムを担当した夏秋文尚の姿も写真におさめられているのですが、当時のインタビューではマネージャーを入れての7人で、”Tokyo7”はMailのやり取りで使っていたNameらしい。ただ、ライダーズはメンバー全員が曲を作るし、音楽の方向性もけっこう違うのでまとめるのが大変らしく、皆が7人目の客観的な存在を仮定して、意識しながら作業していたため、“七人目”という存在は全員が共有していたようです。

森山良子とムーンライダーズ

元メロン記念日・斉藤瞳とBerryz工房
(2014年11月6日 新潟ナルチカ)
この写真、ほんと泣きそうになる
 アグネス・チャンとムーンライダーズ
アグネス・チャンとムーンライダーズ

西川貴教(TMレヴォリューション)とBerryz工房 平家がに・ポーズ
(2015年1月15日 ニコニコ生放送「西川貴教のイエノミ!!」)

小島麻由美とムーンライダーズ
ムーンライダーズは2011年に無期限活動休止を発表しました。当時私はライダーズは永遠に止めないバンドだと考えていたので愕然としましたが、この6人は音楽をやめてしまうことはないのだろうとは思っていて、実際以前にも増す勢いで現在も各々活動継続中ですが、2013年末にかしぶち哲郎が亡くなり、ライダーズは5人となってしまいました。
ただ、去年の年末にはかしぶち哲郎追悼として、ムーンライダーズはトリビュート・アルバムに1曲参加して新曲(かしぶち哲郎の声入り。ドラムは息子の橿渕太久麿が担当)を発表。コンサートも追加公演を加えて2回行いました。


Berryz工房は無期限活動停止で、「休止」と「停止」は字が異なるとともに、意味合いも両者は異なる(Berryzは本当の停止?)のですが、何だか今回のムック本のインタビュー(やっとライダーズが活動休止した時の状況がうっすらとではありますけども初めて本人たちの口から語られたのではないかと思います)を読むと、ムーンライダーズの復活にはまだまだ希望があるのを感じるし(何しろ音楽的にはメンバー全員ばりばりに現在進行形)、そうなるとBerryzだってわからないよな、なんてまだラストコンサートも行われる前から復帰のこと考えたりして...情けない話ですが。

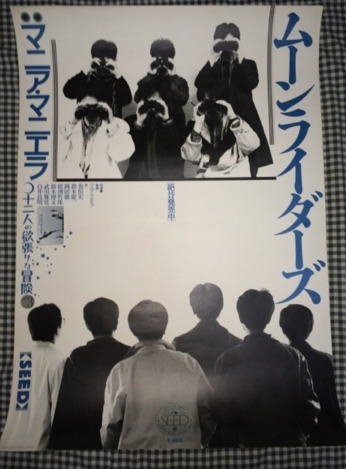


Berryz工房は今月に入って、メンバーが担当していたラジオ番組などの終了がぼちぼち始まっており、私も聞いている(メチャクチャ面白い)「BZS1422ベリーズステーション」(徳永・熊井コンビ)も3月1日ギリギリで最終回が決まっており、雅さんがアシスタント出演していた「爆夜~BAKUNAI」は先日ついに卒業となりました。カウントダウンはもうはっきりと姿を現してきているのですが、昨日たまたまBuono!の曲を聴いてまして、「あ、俺やっぱり雅ちゃんの歌声が好きだったんだな」とつくづく思い、考えるに、ここへきて“迷いがある”としか思えない(と思いたい)夏焼 雅さんのために、Buono!の今後予定だけは、全く何のアナウンスもせず、このまま黙っていてもらいたい!と強く思います。嗣永桃子、夏焼 雅、鈴木愛理のトリオはブランクが空いても直ぐに復帰出来ると思うんですよね。夏焼さんがいつでも帰って来られるようにしておいてほしいというのが正直な気持ちです。 停止後どうされるのか全くわからずに書いておりますが。

![]()
2015年 2月 11日
Berryz 中野区から表彰される

先日、8日。中野サンプラザでファン・イベントを行っていたBerryz工房が、中野区から感謝状を贈られるといういい話がありました。11年間でハロコン、単独合わせると200回ぐらいここでイベントやLIVEを行っているらしいです。ま、Berryzに限らず、ハロプロ全体にとっても中野サンプラザは拠点になっているかというような場所ですが、特別Berryzにというのは粋な計らいですね。

この日のLIVEも大変盛り上がったらしいですが、何かもうね、毎回毎回、何を歌うかわからないという、本当にすごいグループだなと思います。
この日も徳永千奈美さんのソロで「さぼり」が歌われるとか、LAST曲が「VERY BEAUTY」とか、元々ファンの投票結果から選曲するというイベントではありましたが、こうした企画性のあるイベントが何の苦も無く幾らでも実行されるのがBerryz工房の楽しさの根本にもなってます。
http://www.alivem.net/berryz-kobo/3483/
ちょっと気になっているところもあるのですが(私もちょっと雅さんが心配というのはあるんですけどね)、ここまで来たら、ベリメンが最高の状態で3月3日を迎えられるように、ファンはサポートしてあげてほしいなと思います。
![]()
2015年 2月 9日
中山康樹 氏
元『スイングジャーナル』誌編集長で、JAZZ、ROCK音楽評論家の中山康樹氏が、1月28日、悪性リンパ腫で亡くなったと知りました。62歳だったそうです。
ずっと出版される本を読むのを楽しみにしてきました。62歳、まだまだ書きたい事がいっぱいあったと思うのですが、残念です。近年、怒涛のごとく執筆しておられましたが、何か覚悟の部分もあったのでしょうか? 文章からはそんな気配は全く感じられませんでしたが。
私はとにかく中山康樹氏というと1999年に創刊された雑誌『OUT THERE』からが本格的な出会いで、この雑誌は末次安里という方が編集していた雑誌でしたが、ジャンルの横断振りの異様さが半端ではなく、衝撃的でした。極端に言ってしまえば、マイルス・デイヴィスとビーチ・ボーイズを同格に並べる、どころではなく、マイルス・デイヴィスとビーチ・ボーイズに壁など存在しない、とするぐらいに極端で挑発的でした。中山氏は主要執筆者の一人でしたが、以降、全く姿勢を変えないまま、執筆の場を広げていき、読んでいるうちに、私ももはやマイルスとブライアンを語るのに、間に何の障壁も感じないのは当たり前になってしまいました。
こういう視点の氏が、「ジャコ・パストリアスはザ・バンドのリック・ダンコのベースの影響を受けている」などと書いたりすると、本当かどうかはともかくとして、その論考は読み物として非常に面白いのです。
ザ・バーズもブライアン・ウィルソンも聴いたのはイギリス盤の「ラヴァーソウル」ではなく、アメリカ盤の「ラヴァーソウル」(「イッツ・オンリー・ラブ」と「夢の人」が入っている)だったことから考えられるフォーク・ロック誕生への影響であるとか、マイルスとジミ・ヘンドリックスが共演する瞬間まで、どれぐらい近づいたのかの考察など、論の正誤よりも、思いを馳せるその物語性に中山氏の書物の面白さはありました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。

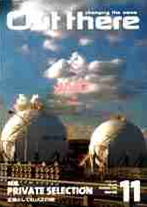
![]()
2015年 2月 7日
真っ当でないものの境界付近
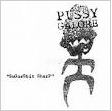
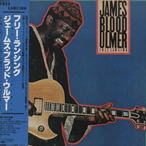
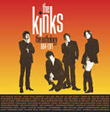
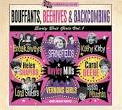
このところ聴いていたのは、PUSSY
GALOREの「SugarShit Sharp」(1988)、James Blood Ulmerの「Free Lancing」(1981)、キンクスの「Anthology
Box 1964-1971」、イギリスのGirls POPを集めたEarly Brit GirlsのVol.1、2。「BOUFFANTS,BEEHIVES
& BACKCOMBING」、「HELEN,DUSTY,SUSAN,CAROL & MORE」。
完全にぶっ壊れるのではなく、何かしらの構築の跡が見られるものを今の自分は好んで聴いている気がします。これは極端なものを対極において受ける「極端なもののインパクト」を受け取るには、現在は“真っ当なもの”の力が弱い。非常に境界が曖昧になってきているので“真っ当でないもの”に平気で“真っ当なもの”が紛れ込んでいる偽物感を燻り出すには、本物の“真っ当でないもの”の“境界”部分を示す必要があるし、そこが一番面白いように感じるからです。
ただ、言っておくと、“真っ当でないものの境界付近”が“完全に真っ当でないもの”に比べ、薄味である、ということにはならない。両者は違うのです。
それに、“真っ当でないものの境界付近”と思う音楽が、本当にそうか?というと、案外“それどころじゃない、真っ当の遥かかなたのもの”である可能性だってあると思うのです。
というわけでジョン・スペンサー・エクスプロージョン的整理が見え始めている「Sugarshit
Sharp」を聴きつつ、NRQについて考えたり、「Johnny Get Angry」のイギリス・カヴァー(Carol Deene)のバッタもん感(これは日本のカヴァー・ポップスにも共通すること)のある種の狂い具合(やっぱりオリジナルであるアメリカの正統性ってあって、イギリスのいかがわしさというのはアメリカのイカれ方とは性質が異なると思います)


NRQ 「Was Here」 (2015)
でね、キンクスのあの異常な音楽バリエーションって、Berryz工房にもあてはまるという気がする。このあたりの壊れてる?壊れてない?の境界部分が気になっているのです。「素肌ピチピチ」があんな風になってしまうというのはネ。
これとは別に、当然ANGERMEの「大器晩成」はヘヴィ・ローテーションで、毎日3回は見てます。聴いてます。ラストあたりのパーカッションの叩きまくり具合が、演奏者は冷静この上ない(配信番組で録音風景が放送されているのを見ています)のはわかっているのですが、出ている音は狂ったように叩きまくっているようにしか聴こえない。ここが境界だと思うのです。冷静に叩いているのだけど、演奏者の魂、高ぶりが曲に乗っかっているのが(つまり、やっぱり演奏者は相当ノッている)びんびん伝わってくるんですよね。
「大器晩成」の凄さはそこ。(是非 太鼓の音を気にしながらPVを見て欲しいです)
![]()
2015年 2月 6日
Berryzを象徴するパフォーマンス

↑Click (125) 「夢を一粒 ~Berryz仮面 ENDINGテーマ~」(2008年 5thアルバム収録)
ベリヲタは「ももち」と呼ばずに頑なに「桃子」コールを守り続けているわけですが、こういう嗣永桃子さんのパフォーマンスを見てしまうとね、やっぱり男にとっては「ももち」じゃないでしょうね。「桃子」ですね。
女子から見てもこの儚い美しさは妖艶に映るのではないでしょうか? バラエティの場ではまず見ることの出来ない姿ですが、Live見れば一発でわかる嗣永桃子の真の魅力。
ん? 曲について全く触れてませんでした。本来ならば茉麻のヴォーカルがフューチャリングされてることを強調しなければならない貴重な1曲だったのですが、済みません。
[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]
 ← Click
← Click
(126)「恋いとしき季節」(2013年 9thアルバム収録)
こちらの「恋いとしき季節」も本当は清水佐紀さんの得がたい声が入っているところがミソなんですが、映ってません! クローズ・アップされるのはBerryz工房のツー・トップ。夏焼雅さんと菅谷梨沙子さんです。
つい古い話を持ち出してしまうと、ちょっとピンク・レディ-のミーちゃんケイちゃんのコンビを思い出させるところがあります。黒とかダーク系の服を殆ど全くというほど着ない雅ちゃんと、割と普段ダーク系を好んで着ることが多いという梨沙子。声の質も初期はそれほどでもなかったのですが、だんだん対称的な声質へと向かい、良いコンビネーションになりました。こういう歌謡曲の伝統的な要素というのをBerryzは本当にたくさん持っています。黄金律の宝庫というか。
 ← Click
← Click
(127)「スプリンター!」(2007年 4thアルバム収録)
佐紀ちゃんの天を仰いでターンする、得意の“歓喜の舞い”を見ることができます。
曲はチャールストンというかデキシーランドみたいなオールドタイム・ミュージックの典型的なアレンジで、Berryzは案外こういうタイプの曲は多いです。キッズ・ミュージックの一つの形で破綻の無い感じ。ただ、こうしたやや典型的なスタイルで膠着したイメージの曲に適度なバラツキ感を加えて退屈はさせません。
 ← Click
← Click
(128)「女子バスケット部 ~朝練あった日の髪型~」(2005年 2ndアルバム収録)
「ハヒホー、ハヒホーフヘホーハヒホー」 ももち=熊井ちゃんの超凸凹コンビによる曲は前にも「男前」という曲を紹介しましたが、こちらは元々は全員で歌う曲。熊井ちゃん大好きなももちがじゃれるのを楽しむという構図になっております。
ももちとの掛け合いで、熊井ちょーが高音でたどたどしく歌う個所がくまくましていてサイコー。
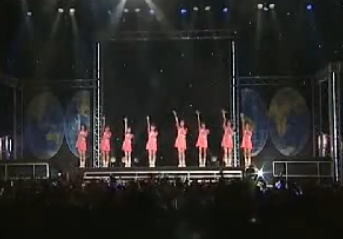 ← Click
← Click
(129)「Bye Bye またね」(2004年 1stアルバム収録)
この曲はLIVEで最後に歌われる事が多く、数々の涙のシーンが映像に残っていますが、ほぼ全員が泣いてしまうこの映像は2005年、グループにとって初の単独コンサートでのアンコール・ラスト曲。
3月3日の武道館でもこの曲が最後になるのか? ま、わかりませんけどね。たぶん、最後の最後はメンバーが曲を選ぶんではないかと思います。
![]()
2015年 2月 6日
大器晩成
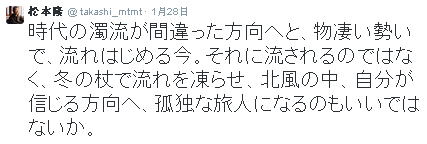
松本隆

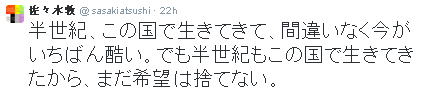
佐々木敦

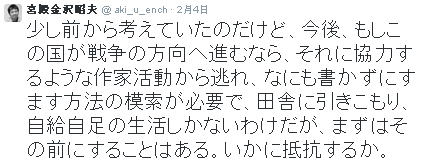
宮沢章夫

めいめい頑張ってるもんなぁ。 地上波TVの番組で歌うのを早く見たい!
何にも惑わされずに どんな時代にも流されずに
![]()
2015年 1月 31日
南海ホークウィンドって何?
![]()
万象亭さんのコラムを更新いたしました。
Berryzと並びって落差あり過ぎー? いえ、そうでもないんじゃないかなぁー
とか言ったりして。
ま、仮にそうだとしても、いいではないですか。 面白ければ。
このあたりの音楽、きっと今の人にだって面白いんじゃないかと思います。
![]()
2015年 1月 31日
初期の隠れ名曲「ファイティングポーズはダテじゃない!」

↑Click (122) 「ファイティングポーズはダテじゃない!」(2004年 2ndシングル)
2014年LIVEで久し振りの披露だったからか、驚きと期待のどよめきが起こった、Berryz最初期2ndシングルの「ファイティングポーズはダテじゃない!」。実は隠れた名曲で、デビュー・シングルがかなり背伸びした感じの作り込んだ曲だったのに対し、この2枚目では当時の年齢に合った等身大のベリメンを見ることが出来るのと同時に、後のコミカルなスタイルに繋がる子供のやんちゃさがステージ上に広がる、本当にナチュラルな姿が非常に印象的だったのではないかと思います。
それが2014年にほぼ再現出来ているというのがBerryz工房の良くも悪くもBerryz工房たる所以。
そしてBerryz工房はこれで正しかったのだと、今、結論は出ているのです。
熊井ちゃんの「このキョイ(恋)の行方だけは」が変更されない奇跡。
[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]
 ← Click
← Click
「女の子にしかわかんない丁度があるの」(2014年 「スッペシャル ベスト Vol.2」収録)
フル・バージョンで。最初からガツンとくるタイプの曲ではないのですが、じわじわきて、今ではたまらん名作やなぁと思うようになりました。つんく♂すごいなぁって。こんな変な曲書く人、日本にいなかったよねぇ。
三木鶏郎、萩原哲晶、宮川泰、小林亜星...etc 過去にいろいろいらっしゃったとは思いますが、この極めて80年代的なメロディ、アレンジでここまで奇怪な曲の完成に達成した人は、他にちょっと思いつかない。こういうそこはかとなく可笑しな曲が何よりも好きです! 私が考える「狂ってる曲」というのは正にこの感覚。
 ← Click
← Click
(123) 「バカにしないで」(2008年 5thアルバム収録)
まだまだとっておきの曲は残ってます。これもアルバム曲ながらファンの間で人気の高い曲。7人で歌う時もありますが、完成度としてはこの4人でのバージョンの方が映えると思います。綺麗どころ4人選抜という感じで(いや、別に残りの3人がそうではないと言ってるわけではありません)。ベリヲタ・コールも一際力が入っている気がします。
重低音ループが格好いいスよね。
 ← Click
← Click
(124) 「我らジャンヌ」(2015年 「完熟Berryz工房 The Final Completion Box 通常盤」収録)
劇ハロからの楽曲。映像は舞台で、スマイレージとの共演です。作曲はつんく♂ではなく、この舞台を演出したチームによるもの。BerryzのBoxに新録音でおさめられましたが、これは吉田 豪氏が1年前にハロプロの楽曲を選曲したコンピレーションを出す際に、劇ハロの曲をリクエストしたのがきっかけで、それまでは舞台の曲をCDにする発想がハロプロ内に無かったという意外な盲点。
しかも、ではこれを機に過去の舞台曲を次々CD化すればよいという問題ではなく、音質的に言って新録音するしかないとのことで、予算を考えると実際は困難。BerryzがBoxに舞台曲の新録を3曲おさめることは出来たのは、吉田 豪氏のおかげで、間にあったのは運が良かったというしかない。
 ← Click
← Click
「六本木心中」(アン・ルイス カヴァー)
Berryzのヴォーカル・コンビネーションをお楽しみください。
![]()
2015年 1月 30日
狂ってる は褒め言葉 2
去年の7月にUSTREAM放送された『南波一海のアイドル三十六房 「ハロー!プロジェクトの全曲から集めちゃいました!」発売記念 5時間あってもまだ語り尽くせない伝説?のハロプロ・スペシャル 第2弾!』は、放送以来もう5回ぐらい見直しちゃってるんですが、この5時間に及ぶ映像を、見る都度にまるまる5時間見尽くしてしまうという、いまだに面白いプログラムで、これを金曜の深夜とかに見始めて殆ど朝になる時間の過ごし方がけっこう至福です。ただもうハロプロ好きの面々が曲のMV流してしゃべっているだけという内容なんですが、ハロプロの“中の人”(UPFRONTの社員)も交えて、このプロダクションの音楽作りの性質的な部分も見えるし、集まってくるファンの気質も(まあ、特別コアなタイプを抽出したものではありますが)浮き彫りになってて最高に気持ち悪くて楽しいです。

↑Click
出演者は、
司会が、2月には佐々木敦と対談する予定もある南波一海氏と、プッシーガロアも好きなベリヲタ。TOWER RECORD社長の嶺脇育夫氏。ゲスト・コメンテイターが、ANGERME「大器晩成/乙女の逆襲」もプロデュースしたUPFRONTの“中の人”、音楽プロデューサーの橋本慎氏、同じく“中の人”で、ハロプロ楽曲をルー・リード「メタルマシン・ミュージック」に例えたりする、EdselやRhinoの仕事に憧れるという西口猛氏。今回、ハロプロ楽曲のコンピレーションを選曲し、その際に劇ハロ楽曲のCD化を希望してUPFRONTのコンピレーションCDに革命を起こしてしまった(その後、劇ハロ楽曲のCD化が出るわ出るわ)吉田豪氏。モーニング娘。「I
WISH」のMVを見て、ルー・リードの「ベルリン」を思い浮かべたりする掟ポルシェ氏。ピンク・フロイド「ザ・ウォール」をコンセプトにハロプロ楽曲のコンピレーションを編纂したら、テーマ曲は℃-uteの「寝る子は℃-ute」になったというBaseball
Bearの小出”小出スロー”佑介氏。ナカGのGはギャング・スターのGだったというマンガ家のナカG氏。一種独特の洋楽志向の持ち主が多いですよね、ハロプロ・ファンって。
![]()
2015年 1月 29日
狂ってる は褒め言葉
だんだん3月3日が来るのが怖くなってまいりました。
まあ、仕方ないのですが..
ANGERME(アンジュルム)の「大器晩成」と並ぶ両A面曲の一方、「乙女の逆襲」。見ました、聴きました、ぶっ飛びました。ハロプロ信じてて良かった!
「乙女の逆襲」は歌詞が最高ですよね。「ズルイほどに 良く」って歌詞がどうやって生まれてくるのか。
すげーって思いました。
「ネイルの拳(こぶし)に 希望 掴みたい」ですよ。
作詞は、コピンクで「カリーナノッテ」とか「最高視感度」(!?)なんて曲の詞を書いてる児玉雨子って人。21歳。 作曲はTOKYO No.1 SOUL SETの川辺ヒロシともう一人、上田 禎という人。編曲はCMJK。元電気グルーヴの人。 Twitterで「間奏にバレエを入れてくれと言われ、この人たち、正気かっ? と思った」と語っている。 確かにバレエが入っている!
最高に狂ってる。
ま、勿論いろいろと批評したくなる部分はあると思いますが、実際、批評する価値のある楽曲だと思います。
ズバリ言わせてもらうと、ハロプロの最も良い点は“オルタナティヴ優等生”にはならないところです。この曲もある意味奇をてらったオルタナティヴ・アイドル曲に陥りそうなところを見事に匂いたつような歌謡曲側へと引き込みに成功している。
“良く出来てるオルタナティヴ”ってやつにはもう飽き飽きしている。今、求めるのは狂った本当の歌謡曲だ、と宣言したい。

![]()
2015年 1月 24日
穴掘りとコンサートどっちが楽しみですか? 穴掘り!!
「完熟 Berryz工房 The Final Completion Box」。とりあえず私は初回限定盤Aと通常盤を買いましたが、完璧な内容で素晴らしい! 買って得した気分にしかならないですね。

「待って、みんな。うちら こんな仲良くなかったじゃん!」「おぉー!?」
↑Click 「ありがとう!おともだち。」(2005年 Bestアルバム「スッペシャル! ベスト・ミニ ~2.5枚目の彼~」収録)
(「完熟・・・・」に入っていないナンバーですが.. 上記のベスト盤にしか入っていない超絶名曲。)
通常盤のCDに入っているレア音源集は、曲数自体は、本当のレア音源は6曲ほどなのですが、最後の最後まで傑作か!! っていう、ほんと、凄いです。 聴きながら呆然としました。
特に太陽とシスコムーンの曲のカバー「丸い太陽」なんて2006年の清水・夏焼・熊井・菅谷で歌っているナンバーですが、自然と涙が出てくるくらい柔らかいユニゾンで美しい。バック・コーラスもいろいろ被さっていますから4人の声だけで成り立っているわけではありませんけど、この柔らかさはBerryz工房のものだと思いますよ。本家やカントリー娘のカヴァーと比べても当然といえば当然ですがイノセント。
「やっと会えたね」、「サンクユーベリーベリー」、「我らジャンヌ」の3曲は劇ハロの劇中歌で、新録なので現在の7人の声です。コーラス、ハモりのポテンシャルが半端ない高さです。高音では清水CAPが屋台骨ですが、千奈美の高音の威力もここへ来て最高潮です。効いてます。

↑Click (119) 「ダーリン I LOVE YOU」(2008年 16thシングル「ジンギスカン」 B面曲)
シングルにはBerryzの単独Ver.が収録されてますが、映像はベリキューVer.で。
℃-uteというと、個人的にはどうしても矢島さんを追ってしまい、他があまり目に入らなくなってしまったりします。今年は矢島さんは本当に正念場というか、大変過ぎますね。ハロ・プロのファンは一枚岩となって守り抜かないとね。
[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]
 ← Click
← Click
(120) 「甘酸っぱい春にサクラサク」(2011年 Berryz工房×℃-uteシングル)
2012年 8thアルバム収録曲
Berryz工房のファンが活動停止後℃-ute推しに変わるかというと、これはそうはならないと思います。それぐらい両者は持っている特色が違う。どうしてこんなに違ってしまったのか、理由はわかりませんが。
でもベリキューの絆というのは間違いなくあると思います。℃-uteが頑張る姿はBerryzファンにも嬉しいだろうし。Berryzのファンは絆を感じるからこそ、℃-uteが℃-uteらしさを貫き、突き進むのを見守りたいと思っているのではないでしょうか。
 ← Click
← Click
「がんばっちゃえ!」(2003年 モーニング娘。とハロー!プロジェクト・キッズ+後藤真希)
映画「仔犬ダンの物語」テーマソング
ハロプロキッズだった時に、最初に参加したデビュー曲だという意識が本人たちにも強いのがこの曲。
Berryz工房と℃-uteはカラーの違うグループですが、結局、最後までハロプロキッズという一つのグループだったともいえる。不思議な関係です。全員小学生からという、世界にも例が無いんじゃないかと思う珍しい歌手グループだし、それが10年以上も続いて、けっこう膨大な量の作品(単独にハロコンの映像作品なども加えれば相当な量ですし、どちらも30枚前後に及ぶシングル作品があるわけで)があるのは驚くべきことだという気がします。
実は、密かに期待しているのは、℃-uteこそは、解散せずにいけるところまで行って欲しいということで。モーニング娘。は老舗として終わらないとしても、メンバーを代えずに継続することが出来るのは、℃-uteだけなんですよね。
 ← Click
← Click
(121) 「幸せの途中」(2012年 Berryz工房×℃-uteシングル「超HAPPY SONG 初回限定盤C」収録) ℃-ute曲のカヴァー
「完熟 Berryz工房 The Final Completion Box」には収録されなかったのですが、℃-uteの曲「幸せの途中」のBerryz工房カヴァーVer.は存在します。
こちらもなかなか良い曲に仕上がっていますが、「超 HAPPY SONG」は、やっぱり性質の異なる二グループが合わさるところが魅力なので、私はベリキューVer.で「超HAPPY SONG」を聴きたいと思いますが、実際のところ、それ以上に「Because Happiness」の単独曲の方が絶対的に好きです。
ファンの間でも「Because Happiness」を未完成曲扱いのように考えている人が多いような気がしますが、全然完成していますからっ!!
![]()
2015年 1月 23日
2015.1.8 K・D JAPON Pirates Canoe LIVE
少し前。1月8日ですが、K・Dハポンでパイレーツ・カヌーというバンドを見に行ってきました。
ハポンはタラ・ジェイン・オニールを見に行って以来の2回目。
初めて3階席(?)で見ましたよ。

このバンドは2009年から活動が始まっているみたいですが、名前も聞いたことがなく知りませんでした。
でも、とてもいいバンドでした。トラッド・ミュージックを基本にしつつも伝統に根ざすというよりは、アメリカのオルタナティヴ・ミュージックなどが向かっている方向と同じく、変化しつづけていく感じですね。
あとで調べたら西村哲也(ex.グランド・ファーザーズ)とも交友があったりするみたいです。
この日はメンバーの一人のヴァイオリニストの女性が出産を控えてお休み中ということで、代わりにギターの人(中井大介)を加えて演奏。澄んだ優しいカントリー調で歌うエリザベス・エタ(ギター)さんと、はきはきした声で唱歌風の朴訥な歌い方をする河野沙羅(マンドリン)さん、タイプの異なる二人のヴォーカルが面白い組み合わせです。
楽器編成やヴォーカル、音楽スタイルの組み合わせでたくさんのバリエーションを持っていて、アメリカのポイ・ドッグ・ポンダリングやラム・チョップを思い出します。(ポイ・ドッグ・ポンダリングってまだ活動してるのかな?) 音楽的に要素が違うものが集まっていても、散漫にはならなくて、むしろそのバリエーションがバンドのカラーを形作っていく方向へと向かっているのが聴いていてよくわかる。
だからカントリーとしてどうだ?とか、ブルーグラスとしてどうだ?という聴き方にはならないんですね。
かなり変態性を極めたラム・チョップ(Lambchop)やカリフォン(Califone)よりもトラッド・ミュージックを大事にしているという芯がある点で、アメリカの主流であるミックスチャーとは違い、ルーツ・ミュージックの異化作用を志向している音楽だというふうに感じました。その点で、ヴァンダイク・パークスに考え方は近いと思う。
だから、エリザベスさんのカントリー・ミュージックの要素を生かしながら、沙羅さんの非常に日本の童謡(日本の童謡、とか言いながら、日本の童謡ってヨーロッパの音楽の影響があるのではないかと感じてしまうのですが)を思わせる部分が入ってきたりすると、すごくコントラストがあっていいなと思いました。
アメリカへツアーに行ったりしてるらしいのですが、このコントラストを頑張ってアピールして欲しいです。


Pirates Canoe 「For The Pain In My Heart」 (2014)
![]()
2015年 1月 17日
Love Together!
Berryz工房のおそらく最終楽曲となる「Love Together!」のPV(Promotion Ver.)がUPされています。

↑Click (116) 「Love Together!」(2015年 アルバム「完熟 Berryz工房 The Final Completion Box」2015年1月21日発売 収録曲)
あまりにもべったべたで、熱心なファンがかえってひくってなぐらい感傷的なPVで、まったくもってBerryzらしくない最終楽曲ですが、ここへきてベリメンよりも周りのスタッフの方が相当まいっちゃってるんじゃないか?という気がします。コンサートでもヲタだけじゃなくスタッフまでが涙顔で、ベリメンがもらい泣きしてるという話なんかも出てきている状態で、じわじわと実感がこみあげてきているのではないでしょうか。
ここまで浸りきって涙、涙のクリップを作ってしまう精神状態。やっぱり平静ではいられないということなのだと思います。
しかし、抑えられなかったスタッフに対して、ファンは結局、感謝の言葉を送るしかないでしょう。最後へ来てこのBerryzへの愛があふれ出しちゃってる、取り乱し感が嬉しいです。
ベリの七人も自分たちに送られたプレゼントに対し、また感謝の気持ちを送り返すような拍手。
私は、このクリップのラストのシーンは、11年のBerryz工房の活動を自ら労(ねぎら)って拍手を送ったというより、ベリメンが最後までサポートしてくれたスタッフに向けてその作品に拍手を送ったということなのではないかなと想像しています。
まったくBerryzらしくない曲ではあるのですが、「Love Together!」。こんな泣きの曲の最後に「!」が付いているところだけに思い切りハロプロ魂が炸裂していて、サイコーだ!というしかありません。

Berryz工房 「完熟Berryz工房 The Final Completion Box」通常盤
(2015年1月21日 発売)
1月21日にBerryz工房のアルバムが発売されます。デビュー曲「あなたなしでは生きてゆけない」からラスト・シングルとなる36枚目の「ロマンスを語って/永久(とわ)の歌」までの44曲のシングル(両A面曲含む)全てと新曲の「Love
Together!」、「あなたなしでは生きてゆけない」(04-13-15 完熟Completion Ver.)が収録されたCD3枚に、MVを集めた2枚がプラスされた初回生産限定盤A(Blue-ray)B(DVD)もお勧めですが、何よりもまず通常盤である6枚組CDが必携です!
シングル曲を集めた3枚に加え、そのシングルのB面曲ばかりを集めたカップリング・コレクション2枚プラスレア・トラック集1枚で全93曲収録されています。
このBoxとBerryzのオリジナルアルバムとBest盤を買えば、Berryz工房の楽曲の殆ど全てが揃うことになります。
先日もNET上でBerryz工房の楽曲の人気投票を行った結果が発表されたのですが、なんとBest100まで公表。曲がたくさんあるグループであれば自然なことといえばそれはそうかもしれませんが、Berryz工房の場合、どうしてもBest100まで見たくなるというぐらい全ての曲が総じてクオリティが高いという評判を表すエピソードだと思います。
http://www.helloproject.com/berryzkobo/10thsp/best/kekka.html
さらにファンの間ではBest100から漏れた曲を列挙し、「漏れた曲だけでも十分セトリ(セットリスト)作れる」とつぶやく人が出てくるぐらい隅から隅まで良い曲が並びます。
因みに100位に漏れた曲の中にあるのが「お昼の休憩時間。」、「夢でドゥーアップ」、「この指とまれ!」、「CLAP!」、「ちょっとさみしいな」、「女子会
The Night」、「ガールズタイムス」、「Because Happiness」、「恋愛模様」、「恋いとしき季節」、「希望の夜」などなど.. 最下位グループがこのレベル。いずれも名曲ばかりで圧巻です。
B面曲だけでも眩暈がするほどバリエーション豊かな絢爛な曲が詰まっているので、興味を持った方は、ちょっとお高いですが6000円で93曲入りと、実際にはお得な商品になっていますから是非チェックしてほしいなと思います。
参考までにBest10を書いておくと
1.Loving you Too much
2.VERY BEAUTY
3.スッペシャル・ジェネレ~ション
4.胸騒ぎスカーレット
5.Be 元気 <成せば成るっ!>
6.すっちゃかめっちゃか~
7.ギャグ100回分愛してください
8.ライバル
9.ヒロインになろうか!
10.付き合ってるのに片思い
となりました。 (「cha cha SING」が11位に!)
[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]
 ← Click
← Click
(117) 「夢でドゥーアップ」(2005年 7thシングル「なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW?」 B面曲)
Berryz楽曲の中では比較的珍しいミドルテンポに近い穏やかでほんわかしたナンバー。これで何度目かってくらい繰り返し書いてますが、Berryzは実は平板な曲を歌わせると滅茶苦茶巧い。ばらけたメンバーの声のバランスが微妙に凸凹を作り、緩やかなメロディも飽きさせないのです。緩やかなナンバーなんですが、その中で細か過ぎるぐらいに意図的に歌割りを細切れにしているのだと思います。このグループはハロプロの中でも一番声の組み合わせのバリエーションが豊富なのは間違いなく、二人で歌う、3人で歌う、4人で歌う、7人で歌うというパターンを1曲の中でめまぐるしく駆使したりもしますからね。
 ← Click
← Click
「ちょっとさみしいな」(2010年 24thシングル「シャイニング・パワー」 B面曲)
以前に一度紹介しましたが、名曲過ぎるこのB面曲を再度。これが人気投票で100位から漏れた曲だっていうんですから。
イントロから既に名曲の予感。本当に痛快なほどに好きなようにメロディをあやつるつんく♂のマジック。
この好き放題ぶりに、聴いたら泣く。本当にハロプロって作曲に全力で遊んでるよね。
確実にピアノの音を聴いただけで泣く。 後半ブレイクするところのピアノで泣く。 楽し過ぎて。
 ← Click
← Click
(118) 「素肌ピチピチ」(2006年 11thシングル「笑っちゃおうよ BOYFRIEND」 B面曲)
どう聴いても、超傑作! 「XTCが作曲した」と言われたら、あっさりそのまま信じてしまうぐらいベースラインのNEW WAVE感から自由過ぎるはっちゃけなノリと、すさまじくテクニカルな転調の連打。
この転調にのけぞるか、気づかずスルーしてしまうか。その差はあまりに大きい。
![]()
2015年 1月 11日
2014年だからって2014年らしさを好むとは限らない2014年の10枚
⑩ Berryz工房
そして最後10枚目はやはりこれしかありません! Berryz工房「コイセヨ!」。特に「The Girls Live」でのスタジオLive映像版で。
2014年3月の終わりでしたか、これを見て自分の中で完全に弾けました。もう全力でいくしかない、と思いましたね。それぐらい衝撃的に素晴らしかった。
今から思えばモーニング娘。‘14 飯窪春菜んの衣装コーディネートも驚くほどフィットしていたと思うのですが、メンバーのレナウン娘感がめちゃくちゃ出ていて、「YeahYeahYeah・Yeah・Yeah・Yeah!」のコーラス入る時にしびれまくりました。
元々好きなグループではありましたが、けっこうぼんやりと見てきていたので、この時になってやっと! 初めて徳永千奈美さんを発見した(なんか凄い人がいる!)という。
このグループの最も大きな特徴が、7人が全員で歌った時の声の“最高”な感じ。声って人それぞれ好みがあるので、Berryzの声に反応しない人がいるとしても、それはそれで十分考えられることだとは思いますけれども、自分の“音楽好き”な感覚(自分で言い切るしかないのですが)からいって、Berryz工房の声は「奇跡」です。この声だけで1冊本が書けそうなくらいとんでもないバランスで出来上がっている。
この「コイセヨ!」でもそれが最上の形で出ています。
以前にも書きましたが、このグループの根幹を成す声は夏焼 雅さんの声です。透明感に最大の特徴があり、驚異的なまでにクセが無い。その為、ソロとしては若干インパクトに欠ける部分はある(私は、今一番好きな歌手だと言ってもいいくらい大好きですが)かもしれませんが、残り6人の個性の強い声に非常によく馴染むわけです。まるで分身の術のようにして、それぞれの声に雅さんの声が溶け込んでいく。実際7人が声を揃えると、6人の声は聴き取れるのに雅さんの声が一番目立たなくなる感じすらあるのです。ところが一方で全員の声が雅さんの声っぽくもなっている。
全員雅さんの声に変化しているという感覚も生まれるのです。その為、ほどよくバラけながらもほどよく一つの声にまとまっている。これが声を揃えたときの最も美しい形だと思います。
これ、波形で調べたら案外ささくれ立ってるところと滑らかに均されてるところと、補完しあっているところが綺麗に視覚化できるんじゃないかなぁ。


「The Girls Live Vol.3」 (DVD 2014 「コイセヨ!」所収)
![]()
2015年 1月 11日
2014年だからって2014年らしさを好むとは限らない2014年の10枚
⑨ 昆虫キッズ
もう1枚はJazzateersのコンピレーション盤にしようかなと思ったのですが、本当に今聴いても80年からずっと続いている現在進行形の音楽として受け入れることが出来るし、恐らくこれから先10年後20年後にも有効な音だと思いました。
しかしここはやはり2014年の新作から選ぼうかと思いまして、昆虫キッズの「Blue Ghost」にします。
昆虫キッズはつい先日の1月7日をもって解散してしまったのですが、もともと何時止めてしまうかわからない、何時でも止めてしまいかねない切羽詰った感じはあったので、驚きもないし、意外に残念という気持ちも起こらないという。
ただ、今までに無いRockを作り出そうとしていたギリギリいっぱいいっぱいな感じが清々しいと思っていて。これだけ苦労して苦労して曲作っているバンドはなかなか居ないんじゃないでしょうか。


昆虫キッズ 「BLUE GHOST」 (2014)
![]()
2015年 1月 11日
2014年だからって2014年らしさを好むとは限らない2014年の10枚
⑧ Norwegian Radio Orchestra (Heiner Goebbels、Frank Zappa)
あまりNEWSにはならないというか、フランク・ザッパのことですが。
ザッパ自身は日本でもいまだ人気のあるアーティストではあると思うのですが、ヨーロッパなどでは現代音楽としてオーケストラなどで演奏される機会も多いのに比べ、日本では殆ど語られることが無いうえに、実際に演奏するオーケストラがいない、というのが現実です。
生前からオーケストラ作品は本人が指揮したものから、本人が参加していないものまで手掛けられており、ザッパの活動のレギュラー的な音楽ジャンルにあたります。
以前、ドイツのアンサンブル・モデルンがザッパの「グレゴリー・ペッカリーの冒険」を中心にオーケストラ作品を発表し、これは国内盤も発売されましたが、日本の現代音楽の領域でこれがどれぐらい話題になったのかは不明ですね。日本のオーケストラが現代音楽をやっているのか?すらよくわからず、ザッパを聴くことなんかあるのかどうかなど予測不能なのですが。
今回ノルウェーのNorwegian Radio Orchestraが、アンサンブル・モデルンも手掛けているハイナー・ゲッベルスとザッパの音楽に挑戦し、作品にしたアルバムが出ました。ハイナー・ゲッベルスも日本ではあまり評価が無いというか、あまり日本では受けが良くないという印象がありますよね、何となくですけど。
現代音楽の文脈には入らない外様(とざま)、本格に対する変格みたいな見下ろした感覚があるのでしょうか?
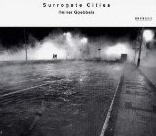
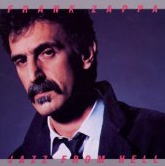
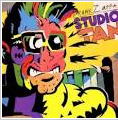
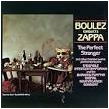
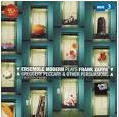
ハイナー・ゲッベルスの方は、2000年に出たECMレーベルからの「サンプラーとオーケストラのための音楽」を演奏しています。ゲッベルス作品の方は私は未聴。ただ初期やチャールズ・ヘイワードらが参加した作品他幾つかは聴いてきているのでゲッベルスについての知識はあります。オーケストラ作品というよりサンプリングやノイジーなギターなども入り、ジョン・ゾーンのネイキッド・シティに近い感覚もあります。
ザッパ作品は6曲ほど(メドレー形式あり)演奏しており、「アンクル・ミート」や件の「グレゴリー・ペッカリーの冒険」(「スタジオ・タン」)など前期のオリジナル・アルバムからの曲もあれば、現代音楽に踏み込んでいく「パーフェクト・ストレンジャー」からの曲もあります。中では「Jazz from Hell」所収の、あの疾走感のある「G-Spot Tornado」をやっていて、オーケストラですけどドラムも思い切り叩いているし、生演奏になることによって(元々ザッパのはシンクラヴィア中心なので)、おもちゃ箱みたいな賑やかさがオリジナルよりもザッパ臭く出てるんじゃないかという会心の出来です。この生演奏、素晴らしい!
これはジャンルが違うように見えて、実はヴァン・ダイク・パークスが試みているアメリカ音楽(アメリカの現代音楽は民俗音楽である)と共通するものがあると思います。ハイナー・ゲッベルスもアメリカ音楽の影響は大きい筈で、都市のイメージが感覚としてネイキッド・シティに近い(あのハードボイルドな感じに到るまで)のもゲッベルスがかなりアメリカを意識している部分がある(ゲッベルスのアルバムは「代理都市」というテーマでイメージされている)からだと思います。
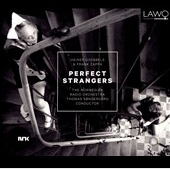

Norwegian Radio Orchestra 「PERFECT STRANGERS」 (2014)
![]()
2015年 1月 10日
2014年だからって2014年らしさを好むとは限らない2014年の10枚
⑦ Sleaford Mods
これは完全にPop
Groupのマーク・スチュワート、ガレス・セイガーが推しているという記事を目にして出会ったアルバムで、それまで全く存在を知りませんでしたがかなり気に入ってます。
ビートが団子状になっているところやヴォーカル・スタイルがザ・フォールを確かに想起させますが、いまどきこのチープなやさぐれ感だけで勝負してくる心意気が好きです。
まあ、それ以上にジャケ写の顔見ただけで決まり!という気分になりましたが。
テクノやグランジ(というよりカウズ的なジャンク)にダブの要素を上手く融合させてますね。元々カウズやYMOにもダブの要素があったんだと、今頃になって気づくという情けなさですが、そこに気づいてみれば、そういえばパンクというのは新しいガレージ・ロックだったと考えるより、レゲエ、ダブが無ければ生まれなかったんじゃないか? (ダブってポスト・パンクになって持ち込まれたものと考えがちだけど、案外パンク自体が影響下から出てきてるのではないかという気がしてきました。NYパンクじゃなくて、イギリスの話ですけど)
このSleaford ModsがPop Groupの原点のようなサウンドなんですよね。順番逆じゃねぇか。
今まではPop Groupやスリッツ、ザ・フォール、ジョイ・ディヴィジョン、イアン・デューリー&ブロック・ヘッズ、ワイヤーなんてパンクから派生もしくはパンクとはちょっと違う流れから出てきたと思ってきたんですけど、案外どちらが先ということはなく、パンクのサウンド自体がダブ要素(ダブ自体を知らなかったとしてもレゲエから汲み取っていた事も考えられる)から発生しているのかもしれない。どうなんでしょうか?
とにかく今更ながら、これは刺激的なダブですよ。
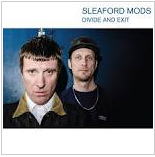

Sleaford Mods 「Divide and Exit」 (2014)
![]()
2015年 1月 9日
2014年だからって2014年らしさを好むとは限らない2014年の10枚
⑥ かしぶち哲郎 トリビュート (アーバンギャルド、佐藤優介、入江 陽 他)
とにかくアーバンギャルドの「スカーレットの誓い」が素晴らしくて泣きました。こういう再生(
甦り)の仕方があったとは。かしぶち哲郎が絶対やらないであろうアレンジでも、こんなにも曲にハマるのかと。びっくりするぐらい退廃の薔薇が前向きソングに変貌してしまい、全く新しい生命をもらったことに感謝の気持ちでいっぱいになりました。いやあ、アーバンギャルドが「スカーレットの誓い」にこんなイメージを持ってくれるとは!
さらに続く曲で、今度は完全なオマージュである佐藤優介の「O・K、パ・ド・ドゥ」でたまらず落涙。若手のミュージシャンがこれほどかしぶち哲郎に対して素敵な解釈をしてくれるとは嬉しい驚きでした。
二人の前の入江陽の「バックシート」も意外性のあるアレンジで(ちょっとピチカート・ファイヴ期の田島貴男を思わせてソウルっぽい)、この3組の並びは感動しました。
しかもその3組の後が鈴木さえ子の「冬のバラ」。がっつり歌ってくれてるし。鈴木さえ子のワールドへと引き込みながら、異化した日本のシャンソン歌謡風の空気をちゃんと表現しえているのがさすが、というか、やっぱりかしぶちの近いところ(ムーン・ライダーズの準メンバー的存在だった時期もありましたから)に居た人なので出せるんだなぁと思いました。
二枚組というヴォリュームで、矢野顕子、細野晴臣、あがた森魚、佐藤奈々子、ピエール・バルーといったファミリーのような存在から柴田聡子、北村早樹子、スカートのような新鋭まで18のミュージシャンが雑多な幅広いタイプの音楽を聴かせてくれるのですが、かしぶち哲郎の曲はかしぶち哲郎ならではの要素を消し去ることは出来ないのですね。面白いことに何度も「薔薇」が飛び出すのは、単に歌詞に「薔薇」の入った曲が多いからというだけでなく、参加した人がかしぶち哲郎の「薔薇」を愛した結果なんだろうなと思うことが出来る、そんな愛情に満ちたトリビュート・アルバムでした。
テンテンコが「ラヴ・フェアー」ではありませんでしたが、岡田有希子の「花のイマージュ」をやってくれたのも嬉しい。
全てのカバーが気に入っている、というわけではありませんが、意図する部分はわかるので、そうしたいろんなタイプが入っているのは良いことだったと思います。
自分としては他に寺尾紗穂(と松井一平)、松尾清憲のカバーが沁みました。細野晴臣の「ハバロフスクを訪ねて」なんて音楽の世界観光たる細野のエキゾ感が噴出している感じで素晴らしかったです。
そしてラストはムーンライダーズがかしぶちの未発表テイクを完成。トリビュートながら本人も演奏に参加ということになりました。
かしぶち哲郎の世界観は特殊で、他に同じようなことをやっている人が日本にはいませんでしたから、実際これを今後実践していける人は、このトリビュートに参加したアーティストの中にもいない(ひょっとしたら山本精一は出来るかもしれない)と思うのですが、ベテラン、若手が偏り無く一同に会し、かしぶち哲郎への深い理解を形にして見せてくれたことは、意義のあるトリビュートだったと思います。
テンテンコも良かったなぁ。
ただ、それにしてもアーバンギャルドには感服。よくこんなメロディライン思いついたね。(ちょっと語尾のメロディをいじってアゲアゲにしてるんだけど、このアガリ具合の気持ちよさが半端ない!) 何度聴いてもこみ上げてくるものがある。「ヤーヤーヤー」の部分を最後だけにしてるところとか、すっげぇ考えてある。
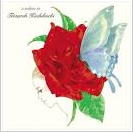

かしぶち哲郎 トリビュート・アルバム 「~ハバロフスクを訪ねて」 (2014) アーバンギャルド
![]()
2015年 1月 9日
2014年だからって2014年らしさを好むとは限らない2014年の10枚
⑤ Nat Johnson
Nat Johnsonの新譜が年末間に合いました。The Figureheadsとのバンドではなく、ソロでの7曲入りアルバム、「Neighbour of the Year」は、本人以外にラップ・スティール、フルート、ヴァイオリン奏者らが参加。また1曲ではコルネット、トロンボーン、チューバなどを擁するブラス・バンドがバックで演奏しています。
振り返ってみれば、マイペースな活動ではありますが2006年から毎年アルバム又はシングルを発表しており(2013年はデジタル配信のみ)、海外のアーティストでは意外に活発に活動している人です。シェフィールドを拠点に自らレーベルを起こし、Facebook等からのプロモーション発信で、名前を広げていくのは容易なことではないと思いますが、素敵な音楽なので、特にイギリスはメディアがメジャーにかまけていて、アンダーグラウンド・シーンを世界に向けて紹介していくという発想が乏しいため、こうした本来イギリスの幅広い音楽の素養を見せ付ける優れた音楽をないがしろにしている状況を打破すべく、もっと日本にも伝えていけるようになればいいなと思います。
最近どうも新しければいい、最新モードであればいいと考えている音楽ライターが多く、日本の音楽雑誌も相当下らなくなっています。もう少し音楽の本質について夫々考えて欲しいというのともっと尖がるとか天邪鬼になるとかの捻くれる反骨精神を持ってもらいたい。年度末のBest10選出などをパラパラと見ても、選ばれているアーティストやアルバム等はそれにふさわしいとしても、選んでいる選者の考え方や方向性(何を求めているのか)、嗜好などが見えてこない。漠然と新しいめのものや2014年にフィットする(周りの目に違和感なく映る感じ?)ものを雑多に選んでいるだけで、毎年選んでいるものがランダムになっているようなライターばかりで面白くもなんとも無い。
もっとジャーナリストとして気概を持ってもらえないだろうか。音楽ライターってそのための専門家ではないのか?
Nat Johnsonは2014年のモードには何の関係もない人だけれども、やっている音楽は流れとしてイギリスの歴史、また80年前後のポスト・パンク(ネオ・アコやアノラックも含む)の影響を本人の幼少からの音楽との付き合いの中で育ててきた、好きな音楽をどのように発展させるかを考えているアーティストです。音楽を“先に進めるという発想”と、“とにかく新しくすること”とは全く違う。新しければ何でもいいという発想が非常に怠惰な発想であると私は思うようになってきていて、現状あるものをきちんと把握して進めていくことの難しさに比べ、流行の先端でさらに新しいものがあればより良いと発想するのは楽なことだと思う。
後者の発想は新しくさえあればOKなので“やってはいけないこと”の意識が低い。
先へ進める中で“やってはいけないこと”も常に意識しないと、“何をやってもいい”では、音楽は音楽である必要性を失っていくのではないか? そこがどうも気になっています。
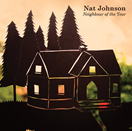

Nat Johnson 「Neighbour of the Year」 (2014)
![]()
2015年 1月 4日
2014年だからって2014年らしさを好むとは限らない2014年の10枚
④ Vic Godard & Subway Sect
これまでのアルバムに比べてモッズ色が濃く出ている新作です。1979年に製作が中途で頓挫したアルバムを現在のメンバーで作り直したもの。おなじみのポール・クックらが今回も参加。エドウィン・コリンズが演奏はしていないようだがプロデュースを勤めている。
ハモンド系のオルガンが良く鳴っているし、タンバリンも常時音をたてている状態でモータウンやビートの強いソウル・ミュージック(ライナー・ノーツによると、79年製作時にゴダードらは、当時イギリスのクラブで流行った“ノーザン・ソウル”というシーンがあり、それを意識していたとのこと)がベースとなったビート・ロックだ。ネオ・モッズには詳しくないので、これが79年当時、どのような位置を占めていた音楽なのかわからないが、少なくともサブウェイセクトが今まで発表してきたアルバムのどれとも似ていない。ここまでソウルに近づいたサウンドは無かったと思う。パンクからJAZZ、ラテンまで意外に節操ない感じでいろいろなジャンルに挑戦してきた人だけど、ある意味、純粋に音楽好きだってことなんでしょうね。だから今日(こんにち)までコツコツ続けてこられたのかもしれない。
モータウン調のアレンジがよりアップ・テンポで疾走する「Holiday Hymn」や、ハモンドオルガンがこれでもかというあくの強さでバック全体を覆う「The Devil's in League with You」など、お馴染みの曲もすっかり様相を変えている。格好いい。
あらためて、ちょっとパンクの文脈とは異なる路線の人なんだなと思う。
全曲、当時作曲した曲なのかも不明ですが、いいメロディが揃ってます。ずっと眠らせてあったのかな?
イギリスのこういう幅の広さが何とか保持され、いっときのブリット・ポップ一色みたいな暗澹たる状況が解消されつつあるのは感じられる。ベテランが頑張っていて、それによって中堅(かつてブリット・ポップやってた人が解散後に幅広い音楽に取り掛かり始めたり)や若手も様々なジャンルに散っていき、横断すれば、イギリスほどの下地があれば絶対また面白くなる。
サブウェイセクトの新譜を聴きながら、まだまだ終わっちゃいない! という思いを強くしました。
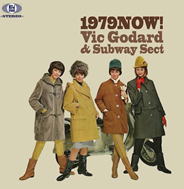

Vic Godard & Subway Sect 「1979 NOW!」 (2014)
![]()
2015年 1月 3日
LAST YEAR
Berryz工房、いよいよLast Year突入となりました。去年夏以降からは怒涛のLIVE活動(神Liveの連続)を続けてきまして、ハロコンのカウントダウンLiveで年を越せば、直ぐに正月明けより既にハロコン・ツアーが始まっており、2月にはタイはバンコクでのナルチカ(ライブハウス・ギグ)、2月28日からは3月3日武道館でのラスト・ライヴまで4日間のまさにラスト・スパートLIVEとなります。最後の4日間では過去の全曲を歌いたい!と年末頃に語っていた彼女たちですが、LASTをベスト・コンディションで、と考えると4日間の構成については、喉への負担も考えて注意が必要だと思います。スタッフはそこを慎重に計画を立ててあげてください。ベリメンはやりきっちゃうつもりで臨むと思うので。

↑Click 「なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW?」(2005年 7thシングル)
2013年の武道館Liveでのアンコール1曲目の「なん恋」。この1曲にBerryzの魅力がどれだけ詰まっていることか。ライヴの猛者として培ってきたものは、例えばとして挙げていけば、細部をあげつらう事にはなってしまうのですが、この規模(1万数千人がMax)で10年以上続けられたのは、ドーム規模に達するキャリアよりも幸福だった、とも言えるかもしれない。メンバーのコンディションに観客がVividに反応して客全体が対応出来る、ベリヲタが大半を占めるLiveは決して悪いものではなかったと思う。BerryzのLiveではつくづくそう思う。
この武道館Liveでの「なん恋」の魅力とは
・バックトラックのオケがほぼオリジナルで、ベース音が異常に大きく、歪みまくっている。とにかくオリジナル・テイクからしてミックスのミスかと思うくらい底部の音が歪み、割れ、でかい。これがLiveでも再現されている。
・梨沙子の「かーなたーっ」では語尾が色っぽくしゃくれる。こういうのも毎回味わえるものというわけではない。Liveの醍醐味。
・キャプ歓喜の時の上を仰いでくるりと回転する仕草。佐紀ちゃんのこの動きは皆知ってるのでスタッフもしっかり映像を抜いていますね。
・ベリメンがこぶしを突き上げながら後姿で階段を駆け上がっていく姿、その全力感。これもいつもの光景。メンバーの後姿が集合していくところがものすごく好きです。
・梨沙子が泣きそうになるやすかさず入るコール。
・雅ちゃんの何しろデビュー時から全く変わらないボーカル・スタイルとその声の透明度。ここまで素直なボーカル・スタイルを貫き通せる歌手ってそうそう居ない。歴代ハロプロの中で最も尊敬できる歌手だと思う。
・のってきたときの桃子の声のスウィング感は手がつけられない状態となる。「じらされるバイオレイション」のところで首が左右上下に揺れるももち特有の動きが出る。
・曲のラストで揺れるというのはベリのダンスの特有な形のひとつ。ラスト・ライヴでも必ず1曲はこの揺れが入る曲をやって下さい。
[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]
 ← Click
← Click
(113) 「愛はいつも君の中に」(2014年 35thシングル「普通、アイドル10年やってらんないでしょ」 両A面曲)
「愛はいつも君の中に」は発表当時、熊井ちゃんがインフルエンザで休んでいたために6人で歌う映像がけっこう残っているのですが、ちょっと物足りない部分があるのですよ。この曲は熊井ちゃんがいないと映えないっていうのは、7人揃った時に感じましたね。
 ← Click
← Click
(114) 「大人なのよ!」(2014年 34thシングル「1億3千万総ダイエット王国」両A面曲)
変な曲しか回ってこない、とは本人たちも思っていたでしょうが、この「大人なのよ!」という大人っぽいのにすっとぼけている感じは、やっぱりBerryzにしか歌えない。あまりに特異なので、モンド曲として後世残るかもしれない。あからさまに変なのではなく、そこはかとなく変なところがモンドマニアにはたまらないと思います。
 ← Click
← Click
(115) 「アジアン・セレブレイション」(2013年 31stシングル)
ここ数年のシングル、確かに全部奇妙だった。この曲もこなせるのはBerryzだけでしょうね。「素晴らしいぜ 近隣国と」なんて歌詞の存在が信じられない。ビューティフルすぎる!
これ、最高ですね。
ttps://www.youtube.com/watch?v=9y-L3SpNdOc
![]()
2015年 1月 3日
2014年だからって2014年らしさを好むとは限らない2014年の10枚
③ Go!Go! Vanillas
Go!Go!Vanillasも影響を受けたバンドの名を聞けば、ギター・ウルフやブランキー、ミシェル・ガン・エレファントらが挙がってきたりはするわけですが、影響力の大きさで言えばリバティーンズやオアシス、アークティック・モンキーズら洋楽の存在の方が大きいという洋楽志向のバンドというか、BAWDIESがソニックスを発見するというような形の、ロックンロール(ガレージ・ロック)のルーツまで遡っていくという接し方の作業を意識しているバンドのようです。(「音楽ナタリー」でのインタビューを参照)
こんなこと好きなことやってりゃ当たり前、と思ったらなかなかそういうわけではなくて、洋楽との距離の取り方は今でも日本のバンドにとって大きな課題だと思います。
『ニッポンの音楽』を読んでも思ったことですが、時間軸というのが大切で、出会った音楽とのリアルタイムでの受けた感覚を大切にして自分が聴いてきた音楽を時間軸でとらえることと、過去の音楽に遡る(自発的に音楽の歴史を探っていく作業)ことを同時に行いながら、修正作業を続けていくのは大事だと思います。
過去の名盤ばかり漁っていればいいわけではなくて、かといって過去の音楽に全く無知というのもこれだけ50年以上もの歴史がある音楽ジャンル(Rock)においては、余っ程の突然変異的天才を除けば、ろくな結果は生まないんじゃないかと思う。流れを学ぶのは意味がある作業だと思います。あくまでも好きなればこその探求ですけどね。 一方で自分がリアルタイムで聴いてきた様々な音楽(それこそ本当にどうでもいいと思うような駄曲まで)の蓄積も無駄ではない。これらを時間軸の中で考えることで音楽というのは出来ていくんじゃないかと私は思っています。
個人的には、オアシスが好きだ、という人は嫌いになれない。リアム・ギャラガーが頭にタンバリンを乗せて「ミュージック・ステーション」に登場したところが格好良かった、という感覚。こういうところがサウンドにきっちりと出ているのがGo!Go!Vanillasの音楽の特徴です。けっこう真面目(90年代にいたスマイルって日本のバンドの生真面目な感じを思い出したりします。あのバンドもけっこう好きだったな)だったりするんですが、悪いことじゃない。 応援したいバンドです。
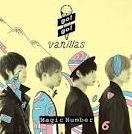

Go!Go!Vanillas 「Magic Number」 (2014)
![]()
2015年 1月 2日
2014年だからって2014年らしさを好むとは限らない2014年の10枚
② 小島麻由美
キンクス、来たぁーーー
ちょー最高! 超気持ちいい! いままでデビュー時からちょいちょいブリティッシュ・ビートへの憧憬を曲に表してくれてはいましたが、今作ほど全開したアルバムはさすがに初めての快挙です。ずっと小島麻由美にはキンクスをやりきって欲しいと願い続けてきましたが、新しく出た「ミュージックマガジン」誌の1月号での小島麻由美へのインタビューを読むと、実はビート系が苦手だったという吃驚の回答があり、意外過ぎて一瞬目を疑った。
キンクスは大好きと常々広言してきていたが、ビートは苦手というか好きな感じでもなかったという..
前作あたりから徐々に開眼したという風に本人は考えているようだが、そんな! とっくにビートとの相性がどんピシャに良い事はわかりきっていたことで、本気になればこんな凄いアルバムはいつでも作ることが出来たはずだ、と思う。
ただ、今回彗眼だったのは、ベースをカジヒデキ(本職ではない)に依頼したこと。このあたりの感覚的な読みがさすが小島麻由美だと敬服します! かっちりいってしまいそうなところを見事に回避している。カジヒデキがヘタウマだというわけではないですが、その意図的なところがバンドの息遣いに出る。かっちりやろうと思えば出来てしまう塚本功もどういう意識を持つべきか、姿勢が明確に伝わるじゃないですか。カジヒデキにベースをやってもらうとはどういうことなのか。
録音もなんか凄いことになっていて、ドラムの音が最早キース・ムーン並みの響き。作為的に音を捜査するということではなくて、気持ちがこのあたりで一つになっているということなのだ。
小島麻由美自身のの声も絶好調で、伸びがとんでもないことになっている。ブランクを感じさせないどころか、ますます伸びているという驚異。 個人的には全ての望みが適った感じです。
今年は、8月頃に出たミニ・アルバムも、ささくれだったビート・ブルース曲「夕陽が泣いている」(スパイダースのカバー)や、ニール・ヤングばりにやさぐれたイノセント・フォーク・ロック曲「渚にて」が入っていて、このミニ・アルバムだけでも2014年BEST級でした。

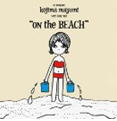

小島麻由美 「On the Road」(2014)、ミニアルバム「on the BEACH」(2014)
![]()
2015年 1月 1日
この本には時間軸が欠けていると思う
佐々木敦の『ニッポンの音楽』を読み終えました。評論家(と書いた場合、本人が許すか又は気に入らないと感じるのかわかりませんが)として、啓蒙したい欲求を表に出すか、または冷徹に分析に徹するか、タイプが幾つかあるのだとして、本書は出来るだけ現象をとらえるにとどめようとした論文であるとは思いました。
60年代末から現在までを分析対象とし、登場させた本書の主人公(筆者がこう呼んでいます)は、はっぴいえんど、YMO、フリッパーズ・ギター、ピチカート・ファイヴ、小室哲哉、中田ヤスタカ です。ポイントとしては、「リスナー型ミュージシャン」であること。「オール・イン・ワン」(作詞・作曲・編曲・演奏・プロデュース、エンジニアリング全てを一人でこなし、完結させてしまう形)へと進む過程(中田ヤスタカにおいて殆ど完成している)が挙げられます。
「外」(洋楽)から見る「内」(ニッポン)、「内」から見る「外」、「内」に「外」を取り込み、もはやクラインの壷のように「内」と「外」が腸捻転を起こしているような「内包」など、ニッポンの音楽が洋楽との関係性の中で作り上げてきたものについての説明は、自分の中でちょっと理解し切れていない部分があるかもしれませんが、一応本書は現象の分析を心がけるとともに基本的には筆者自身がポジティヴ思考であることもあり、上記の音楽を肯定し、才能を評価する姿勢で書かれています。
ただし、筆者が気にしているであろう部分について、“積極的に音楽を探さない一般的リスナー”は増加傾向にあり、彼らに対し、彼らの知らない音楽に耳を傾けさせるのに腐心している中田ヤスタカの努力を擁護したいという気持ちが見え隠れしているのは、読めばわかってしまうと思う。
分析だけでは抑えられず、やはり啓蒙したい気持ちは消し去ることは出来なかったのではないでしょうか?
しかし、基本的に肯定する、という姿勢が果たして本当に良かったのか? 私は少し疑問に思った。
個人的に、はっぴいえんどに対して、私は現在の絶対的な評価というのが納得出来ないところがあって、本書も“はっぴいえんどを前提として肯定する”というところから出発してしまっている。日本語をロックに乗せた、というが、それがどれほど重要なことなのかが私は未だにぴんと来ないし、はっぴいえんどが、ザ・バンドやモビィ・グレイプ、とりわけバッファロー・スプリングフィールドをアイドルとし、この『ニッポンの音楽』でも、“当時の最先端であったバッファロー・スプリングフィールド”と書かれているのだが、正直なところ、今であろうが当時であろうが、バッファロー・スプリングフィールドが最先端の音楽で、ロック史上の重要な音楽であるとする「前提」を、全く怪しまずにはっぴいえんど(又ははちみつぱいも含んでも構わないが)を日本ロックの魁の頂点に持ってくるという発想を認めることが出来ない。
本書もやはり、そのあたりの批評が全く無い!
本書は「ニッポンの音楽」の45年を通覧するとあるが、流れをとらえているように見えて、実はあまりそれは出来ていない。バッファロー・スプリングフィールドに対する考察が無いのと同様に、クラフト・ワークやディーヴォに対する考察も無く、ネオ・アコースティックについても大きく取り上げておきながら、ネオ・アコースティックという現象の価値観については触れていない(ネオ・アコースティックを舐めてかかっているロック・リスナーも多いことなどを踏まえておらず、全肯定である)、ユーロ・ビートとデトロイト・テクノ、アシッド・ハウス、ジャングル(ドラムン・ベース)、これらを評価として並列する人など極めて稀れの筈で、ヒエラルキーや断絶が有り捲くりの筈だが、小室哲哉を無条件に評価していいのか? 同様にボーカロイドの発想から中田ヤスタカの手法を流れとして成功譚のように絶賛するのは事実としてそうかもしれないが、本当にそんなに画期的な音楽なのか?
佐々木氏は恐らくこれらの件に関しては、この本(新書)で対応できるレベルのスケールではないので省略するという考え方でいるのだろうと思うが、やはり現象分析よりも大事なのは考察の方なのではないかという気がする。
本書に欠けているのは、45年間の「ニッポンの音楽」を流れとしてとらえているとしながら、実際には「時間軸が欠落している」ところではないだろうか?
中田ヤスタカ氏にも顕著だが、子供の頃にYMOの「テクノドン」に出会ったのはいいとして、それまでにあまり音楽を聴き込んだ経験がなく、最近では世界中の民俗音楽を聴きまくっているというインタビューの抜粋があるけれども、とにかく今の人に多い傾向として、世界中、現在過去の全ての音楽がいつでも手に入る状況にある中で、たくさん聴くことは出来ても、それらを時間軸でとらえることが出来ない、知ろうとしない場合が多く、全てが時間軸無しに並列してしまう。
そういう方法で新しい音楽が出来るのは、それは出来るのだろうが、本当にそれだけで良いのか?という疑問は無いのか?
佐々木氏が思想書(『ニッポンの思想』)に絡めて、便宜上はっぴいえんどからに区切った(60年代末からの出発点にこだわった)と勘繰りたくもなり、どうしても“何でもはっぴいえんどから”という発想がおかしい気がして仕方がない。音楽評論としても逆行しているように感じる。だって、その前に既にGSも歌謡曲もあるのだからね。それがあっての松本隆、YMOらの歌謡曲進出と、小沢健二、小室、つんく♂、中田ヤスタカらのチャート・ヒット現象でしょう。
省略してはいけない部分が省略されていると思います。

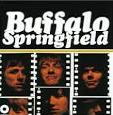 バッファロー・スプリングフィールドって本当に凄いのか?
バッファロー・スプリングフィールドって本当に凄いのか?
佐々木敦 『ニッポンの音楽』 (講談社現代新書)
![]()
2015年 1月 1日
賀正

あけまして おめでとうございます
本年も よろしく お願いします