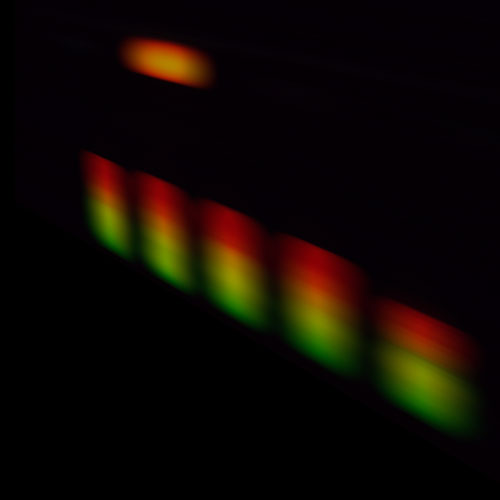
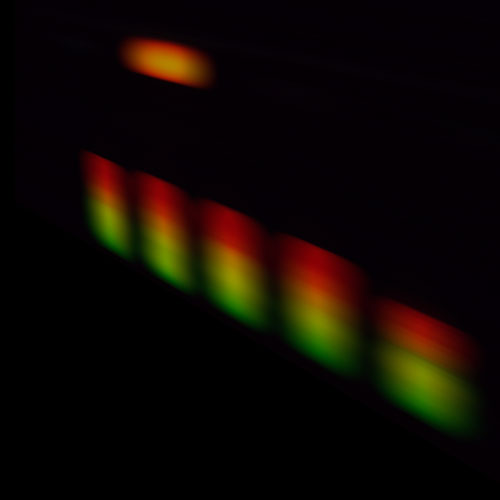
山口富士夫というギタリストの名前を知ったのは、高校生の頃だったと思う。1970年代の終わり、80年代の始め。ポストパンクの時代であったが、そんな言葉は頭の中になく。田舎のティーンネイジャーはラジオで知ったYMOやRCサクセションや、フリクションやフューなんかに夢中なのであった。
その頃レコード盤は特に高価で、一枚2800円はバイトもしていない高校生には辛く、中古レコードショップは都会にしかなく、読みたい小説などを買ってしまうと手も足も出なくなっていた。
しかしいろんな面白いレコードが聴きたい。特に変わったものが聴きたい。TVでいつも歌っているような歌謡曲でもなくて、なにかもっとぐぐっと来るものが。
とそんな思いは皆が持っていたものらしく、なんとその頃レコードをダビングしたカセットテープを交換し合うという、若者の組織がアンダーグラウンドで、ひそかに秘密にひっそりと存在していたのである。
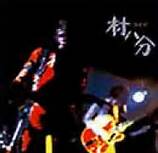
ひょんなことからその会員になって、ダビングできますよっていう、手書きコピーのリストを見たらこれがキャプテンビーフハートやら、ザッパやらに混じってジャックスとか村八分の名前がある。早速ダビングしてもらってジャックスは聴いて感動した。
村八分は聴いたがピンとこなかった。これは別に村八分のせいではなくて、自分がロックンロールやブルースというものをまだよくわかっていなかったということだと思う。
ただ、一曲目の「あっ」。あの印象的なイントロのギターフレーズはずっと頭に残っていた。
その後大学生になって、街の輸入盤屋さんとかレコード屋さんとかウロウロするようになって、とある中古レコード屋さん(たしかバナナレコードだったような。)で山口富士夫の「RIDE ON」というEPを買った。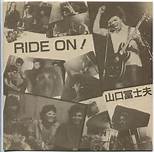
そこは当時で言う自主制作盤を扱っていて、そういうのは壁にディスプレイしてあってカッコ良かったので、けっこう購入した。
他にあったのはスタークラブとか、ミラーズとか、灰野敬二とか。到底売れているようには思えなかったが、そういうことは常に問題ではないので、なにも思わなかった。
この頃になると、ロックンロールといわれる音楽についても、ブルースについても、なんとなく慣れてきて耳に入ってくるようになる。
この耳に入ってくるとか、耳に馴染んでくるとか、なれてくるという感覚は、どういうものなのだろう。最初に聞いたときには、メタルもハードコアもパンクも区別は付かないが、そのうちにちゃんと聞き分けられるようになる。脳の認識能力とかそういったことなんだろうけれども、興味を持ってない人に言わせると、いつまでたってもわからないというのだから、そこには興味という志向性も関係するのであろう。
そこでなぜ山口富士夫を手に取ったのかというと、それはなぜなのだろう。ただ、それを言ったらそこで灰野敬二も買ったしスタークラブも買った。Onna(宮西計三)も買った。
ただ残念なことにまだぴんとこなかったのであった。こうやって考えると自分の感性の低さに驚くものもあるのだが、その頃は読み始めた音楽雑誌(ニューミュージックマガジンとかドールとか、フールズメイトとか)にも影響されて、山口富士夫が伝説的なロッカーだって知識はあったので、こんなものかなとか思っていた。
事態が変わったのはVIVIDから山口富士夫のソロアルバム「ひまつぶし」が復刻されてからで、これを買って聴いたら、もうびっくりした。

そこで聴けたのは、最小限の言葉で真摯に自分を語る男の言葉であり、自分を取り巻く世界についての、自分のとる態度についての決意表明をする言葉であった。
他のやつらがどうあろうとも、俺はこれを信じて、生きてゆくよ、という言葉が気負わずにごく普通に言えていた。
内省的で知性的な、でもことさらに意匠を凝らしたりすることなくごく普通の言葉を使う詩人。
ここから急に好きになって、次に出たカセットテープと、その時期のライブアルバムを買った。カセットテープはアコースティックギターにパーカッションだけという編成で、特に歌を聴かせるものだった。
このあとで山口富士夫はティアドロップスを結成して、メジャーシーンに乗り出してくるのだけれども。
自分にとってはやはり一番好きなのは80年代後半のプライベートカセットを出した頃のものだと思う。
なにがいいのかと考えるに、一人で立っているという感じがいいように思う。人間も大人になって、仕事を通じて世界に対峙するときに、たった一人で自分の仕事をやる、やり遂げるというのはやはり相当の勇気のいるものであると思う。
そのことを考えるに、この人は今まで生きてきて、その道は決して平坦なものではありえず、むしろ険しい道を乗り越えてきたはずなのに、そうであるからなのかすべてを許すかのような佇まいで、穏やかな声で歌ってくれるのだった。
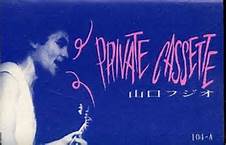
ソロアルバム「ひまつぶし」の「それだけ」という曲ではおまえは 気づいて いるか かわいい俺の狂気にとどこか複雑な攻撃的な感情をこめた声で歌っていたのがカセットの「誰もが誰かに」では
誰もが 誰かに なにか言いたい
だけど どうしても 言葉がみつからねえ
空の つづく限り 飛び続けよう
誰がお前のことなど 知るものか
と歌っていた。立っている位置は変わらないが、この歌を相変わらずのだみ声で、なにか吹っ切れたように明るく軽く歌って見せる。アコースティックギターにパーカッションだけという、シンプルな音の構成のせいもあるだろうけれど、とても心地のよい、音の空間であるのだった。
雑誌で山口富士夫のことを読むと、芸術家肌のギタリスト、ドラッグなどに手を出して何度も刑務所に入っている無軌道なロッカー。というイメージが浮かんでくる。そういった面は確かにあるし、村八分の頃の写真などを見ると、容易に近づきがたい雰囲気の持ち主なのはよくわかる。
ただ、そういうイメージとは違うものをこのカセットの歌から感じたのは事実で、ここには一人で立っている男の人がいると感じたのだった。
ギターを持ち、かき鳴らし、歌を歌う。それで生きていく。別にそれを曲げる必要はないし、そんなことはしない。それを宣言というような勇ましいものでもなく、ごく普通に歌っているところが、すごく好きになってしまった。
ロックンロールってやつはやはり怒りとか喜びとか、悲しみとか、そういう感情の高ぶりが直接表現されているところが、いいんだけれども、だからってそんなことばかりじゃ疲れてしまうし、人間は一種類の陶酔だけじゃ生きていけない贅沢な動物なのだ。
そして山口富士夫はティアドロップスを結成し、シングルを発表する。
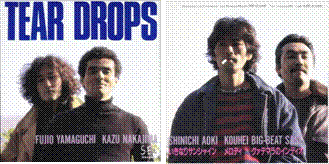 このシングルを見たときに、山口富士夫の表情がとってもよくって、思わず買ってしまったのだった。
このシングルを見たときに、山口富士夫の表情がとってもよくって、思わず買ってしまったのだった。
ティアドロップスはもう一枚シングルを出して、それからメジャーに出て行った。そこからの活躍はもう別にここに書くようなことでもないし、やはり『本物』(これはいやな言い方だが)は売れてくれないといけないと思ったりもしたのだった。
そしてここ数年、村八分の再評価と、昔の音源がCDになって来て、さらに山口富士夫の存在がクローズアップされようとしていたところ、訃報にであった。
人はいつかは死ぬものだから、どうということはないのだけれども、江戸アケミが死んだときも、どんとが死んだときも、たまらない感じがした。
で、カセットの音源をCDに焼いて、通勤の途中で車で聴いている。
2013/10/14 万象亭